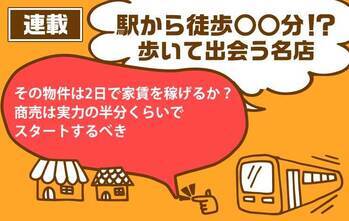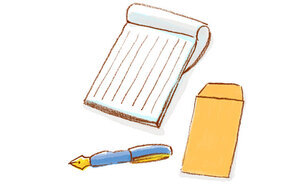- Tweet

個人事業主として開業する際にやるべきことは多岐にわたります。初めて開業される方は、何をすればいいか、何から始めればいいかわからず、戸惑ってしまうことでしょう。
そこでおすすめなのが、開業前に行うことを「開業準備リスト」としてまとめて把握しておくことです。開業に必要な手続きや準備すべきものをリスト化し、順番に進めていけば、開業はそれほど難しくはありません。
この記事では、開業前にすべきことがわかる「開業準備リスト」の一例を示すとともに、開業時に提出する書類や開業準備と並行してやることについて説明します。
関連記事 開業とは?起業・独立との違いは?必要な準備についてもわかりやすく解説
関連記事 個人事業主として起業するには?具体的な手順や手続きを解説
関連記事 開業するにはどうすればいい?個人事業主に必要な手続きと流れを解説目次
個人事業主になる前に「必ずやることリスト」
どのような事業で開業するにしても、この章で紹介する項目は個人事業主が「やらなければいけないこと」に該当します。以下のリストに沿って開業の準備を進めれば、スムーズな事業開始に繋がります。順番に解説していくので、このリストを参考に開業の準備を進めてみてください。
①事業計画書の作成
②健康保険・国民年金の切り替え
③開業準備に必要な資金調達
④開業書類の提出
⑤銀行口座を開設
⑥確定申告の準備をしておく
⑦補助金・助成金の申請準備
⑧商工会議所や商工会への加入
それぞれ詳しく解説していきます。
①事業計画書の作成
開業にあたって、まずは事業の内容を決め、収益を得るためのビジネスプランを練らなければなりません。それらを具体的に記した資料が事業計画書です。
事業計画書には事業の内容や扱う商品・サービスをはじめ、価格設定、ターゲット、販売形態、集客方法などを記載します。事業計画書を作成することによって、事業内容と経営戦略を整理し、想定している計画が実現可能かどうかを今一度判断する材料となります。
事業の概要やビジョン、財務計画などを詳細に明記した事業計画書は、金融機関に融資を申請する際に有利となります。開業後にも経営の指標となるため、事前に事業計画書を作り込んでおくことは非常に重要です。②健康保険・国民年金の切り替え
個人事業主になる場合は国民健康保険に加入するか、もしくは勤めていた会社の健康保険を任意継続する必要があります。
国民健康保険に加入するケースが多いものの、扶養家族がいる場合などは任意継続のほうがお得なこともあるため、どちらのメリットが大きいかを判断して選択しましょう。なお、任意継続には最長2年という制限があります。
保険だけでなく、年金も厚生年金保険から国民年金へと切り替わります。本人確認書類や年金手帳などの必要書類を持参して、市役所や出張所などで手続きを行いましょう。③開業準備に必要な資金調達
開業前に準備する資金には物件取得費や内装工事費などの「開業資金」と開業後の経営に係る諸経費を支払うための「運転資金」があります。それらを自己資金だけでまかなうことが難しい場合には、資金調達を行わなくてはなりません。
資金調達の方法としては金融機関からの融資が一般的です。個人事業主として開業する場合は日本政策金融公庫の融資制度を利用することをおすすめします。日本政策金融公庫が提供する「新規開業資金」は、新たに事業を始める方を主対象とした融資制度で、原則無担保・無保証で自己資金の2~3倍程度の融資を受けることができます。
なお、融資を申し込む際は、創業計画書の提出が必要です。日本政策金融公庫のHPから雛形をダウンロードし、必要事項を記載して作成しましょう。
他には、補助金や助成金、クラウドファンディングなどを利用した資金調達の方法もあります。
補助金や助成金は、融資ではないため返済する必要がないことが大きなメリットです。融資に比べて限度額は低めに設定されていますが、条件を満たしている場合には積極的に活用したい制度です。
クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数の方々から出資による資金調達を行う方法です。ただし、出資者に魅力を感じてもらえる事業でなければ資金を集めることは難しいでしょう。融資や補助金・助成金と同様に、しっかり作り込んだ事業計画書の準備が必須となります。
関連記事 起業・開業の資金調達方法6選と注意すべきポイントを解説④開業書類の提出
個人事業主として開業するためには、さまざまな書類を提出しなくてはなりません。開業時に提出する主な書類は以下のとおりです。
開業書類名 提出要否 公式サイト 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) 必須 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 青色申告承認申請書 青色申告を行う場合のみ https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm 青色専従者給与に関する届出書 配属者や親族に対して支払う給与を経費計上する場合に提出 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 従業員を雇って給与の支払いを行う際に、源泉徴収した所得税を毎月の支払いから年2回まとめての支払いへと変更するための特例を適用したい場合に提出(従業員が10名未満の条件あり) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm 給与支払事務所開設届出書 従業員を雇用して給与を支払う場合に提出 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請書 適格請求書発行事業者に登録する場合に提出 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
従業員を雇わない個人事業主でも「開業届」の提出は必要です。「青色申告承認申請書」は任意提出ですが、多くの個人事業主は税制上の恩恵を受けるために開業届とあわせて提出しています。また、従業員を雇う場合や家族に給与を支払う場合など、状況に応じて提出する書類も存在します。提出が必要な書類を精査して、事前に準備しておきましょう。
関連記事 開業届の必要書類とは?書き方や提出方法をわかりやすく解説⑤銀行口座を開設
開業する際は、プライベートの銀行口座とは別に、事業用の銀行口座を開設しておくことを強くおすすめします。個人事業主になると、個人的な支出と事業の収支を区別する必要があります。別口座を持つことで、収支の管理が簡単になり、確定申告の際にも便利です。
また、事業専用の口座を持つことで、取引先に対するビジネスイメージが良くなります。個人事業主は「○○居酒屋」や「○○商店」といった屋号付きの口座を作ることができ(金融機関によってはできない場合もある)、取引先に事業内容が伝わって信用を得やすくなることも期待できます。⑥確定申告の準備をしておく
確定申告とは、1年間の所得に対する「所得税」を算出して税務署に申告し、納税する手続きを指します。
個人事業主になって初めての確定申告では、不慣れな会計処理を期限ギリギリにまとめて行うのは得策ではありません。確定申告の準備は、なるべく早めに実施しておくのがおすすめです。事業を営んでいると、毎月の売上はもちろん、業務に必要な経費が発生します。経費の管理を怠っていると、どのような使い方をしたかわかりにくくなり、確認する手間が発生します。
このような事態を避けるために、以下の準備を行っておきましょう。
●税金の知識、会計の知識を学ぶ
●会計ソフトの使い方を学ぶ
●請求書や領収書の発行方法を学ぶ
確定申告に関する詳細は以下の記事でも解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
関連記事 事業に必要な支払いは経費!開業前に確定申告を制する!⑦補助金・助成金の申請準備
開業後に補助金、助成金の利用を考えている方は、申請の準備もしておきましょう。
独立したての事業者が利用できる補助金・助成金の代表的なものは「ものづくり補助金」や東京都が実施する「創業助成事業」などが挙げられます。ほかにもさまざまな制度が実施されているので、自分の事業と応募期間など合致するものがあるかチェックしておくとよいでしょう。
補助金・助成金については以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はぜひご一読ください。
関連記事 本当に返済不要?独立支援金として利用できるの補助金 助成金 制度とは?⑧商工会議所や商工会への加入
個人事業主になるタイミングで、商工会議所や商工会への加入も検討しておきましょう。商工会議所や商工会は、個人事業主や中小企業を対象とした経営支援団体。経営・融資に関する相談会や講習会・セミナーを実施して、事業者を支援してくれます。
必ず加入する必要はありませんが、独立したての個人事業主にとって心強い味方になる場面も多いでしょう。商工会議所や商工会は地域ごとに存在するため、加入したい方は自分が事業を営んでいる市区町村を対象にして調べてみてください。
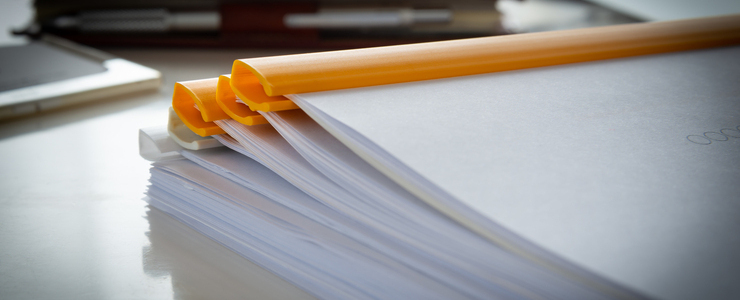
個人事業主が開業時に「準備するものリスト」
ここからは、開業後の事務作業や営業活動を円滑に進めるための「準備するものリスト」を紹介します。
●印鑑
●名刺
●マイナンバーカード
●仕事用のメールアドレス
●クラウド会計ソフト
●プリンター
●Webサイト
●SNSアカウント
開業後はなるべく業務に専念して、効率良く利益を生み出さなければなりません。「事前に準備しておけばよかった」と後悔しないためにも、必要なものは先に準備しておきましょう。
印鑑
印鑑は、会社としての取引を行う上で非常に重要なものなので、必ず準備しておく必要があります。実印・角印・銀行印という3種類の印鑑を作るのが一般的です。
名刺
名刺は、個人事業主としての取引の幅を広げるために重要な役割を果たします。デザインは自由ですが、個性的でわかりやすい名刺にすることで、取引先の方にも覚えてもらいやすくなるでしょう。
最近は名刺にホームページのQRコードを印刷して、認知度向上を図るケースも多いです。デザインなどに自信がなければ、テンプレートを使って作成する方法もあります。マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方は、開業のタイミングで作成しておくのがおすすめです。マイナンバーカードがあれば「e-Tax」を用いて確定申告ができます。e-Taxとは、オンライン上でさまざまな税金に関する手続きができるシステムです。e-Taxを使うとわざわざ税務署に出向く必要がなくなり、自宅で確定申告書を提出できます。(PCの場合別途ICカードリーダが必要です)
仕事用のメールアドレス
事業を営み始めると、業務連絡や請求書の送付など、メールを使う機会が増えてきます。業務連絡に「Slack」や「ChatWork」などのチャットツールを使う企業も増えていますが、まだまだメールが主体のやり取りは多いものです。
プライベートのメールと仕事のメールが混在してしまうと、重要な連絡を見逃してしまう可能性が高まります。近年は個人事業主が増えている背景もあり、「Gmail」や「Yahoo!メール」のような簡単にメールアドレスを取得できるフリーメールでも悪い印象を与えにくくなっているので、事前に準備しておきましょう。クラウド会計ソフト
クラウド会計ソフトは、オンラインで日々の帳簿付けができるサービスです。会計知識が乏しくても、帳簿付けを手軽に行える点がクラウド型会計ソフトを使う最大のメリットです。クラウド型は、税制改正があっても自動的にバージョンアップされるため、いつでも最新の状態で会計業務ができるメリットもあります。
プリンター
プリンターは必須ではありませんが、用意しておくと便利なアイテムの一つです。オンラインのやり取りが主流になっているとはいえ、開業手続きに関する書類や領収書の発行など、印刷が必要になる場面もあるためです。
ただし、コンビニの「ネットプリントサービス」を利用すれば、プリンターを所有していなくても印刷は手軽に行えます。印刷料金は割高になりますが、頻度が低い場合はネットプリントサービスを利用してもよいでしょう。印刷を必要とする場面が多い方は、印刷コストを削減するために早い段階でプリンターの導入を検討してみてください。Webサイト
Webサイトも、個人事業主としての取引の幅を広げるために重要な役割を持っています。名刺は直接会った人にしか渡すことができませんが、ホームページはより多くの人にリーチすることが可能です。
自作することも可能ですが、ホームページは対外的な「顔」の役割も担うので、デザインや技術に自信がない場合は費用を支払って外注することも検討しましょう。SNSアカウント
SNSは宣伝・集客のための必須のツールと言っても過言ではありません。インターネットが普及した現代社会におけるSNSの宣伝効果は絶大です。個人事業主であってもビジネスで十分活用できます。
SNSを活用した宣伝・集客方法を学びたい方は、セミナー参加もおすすめです。「canaeru(カナエル)」では、SNSを活用した宣伝や集客術を学べる無料セミナーも開催されています。興味のある方はふるってご参加ください。
セミナー開催予定一覧個人事業主の開業をより手軽に行うには?
個人事業主として開業を目指す場合、事業計画書の作成や店舗・事務所の取得、開業準備に必要な資金調達など、行わなければならないことは多岐にわたります。また、それらと並行して健康保険や国民年金の切り替えや、名刺・印鑑の準備も行わなくてはなりません。
関連記事 一人で開業できる仕事25選!テーマ別におすすめの仕事をご紹介
これらすべてを抜け漏れなく行うのは大変ですが、開業準備を支援してくれるサービスを活用することで、効果的なサポートも期待できます。
「canaeru(カナエル)」では無料で主に飲食店の開業を支援しており、経験豊富な店舗開業のプロによって、さまざまなサポートを受けることができます。「canaeru」は国から経営革新等支援機関(認定支援機関)と認定された株式会社USENが運営するサービスです。税務、金融および企業財務に関する専門的知識や支援にかかる実務経験が一定レベル以上ある支援機関として国に認められています。
個人事業主として開業に向けてのサポートを必要としている方は、ぜひ「canaeru」の利用をご検討ください。
ご相談はこちらこの記事の監修

USEN開業プランナー
松村俊治
株式会社USEN 開業サポートチームに所属。飲食店経営歴8年。その経験を活かし、開業に関するあらゆる支援を行う。開業に必要なサービスや設備、業者などの紹介のほか、店舗のコンセプト設計、事業計画書の作成サポートにも精通。
【主なサポート内容】
・開業手続きの支援
・開業に必要なサービス、設備、業者を紹介
・創業計画書の作成サポート
・事業計画書の作成サポート
株式会社USEN/canaeru 開業プランナーの詳細はこちら- NEW最新記事
-
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
- おすすめ記事
-
-
2024/07/02
-
2022/12/27
-
2022/04/12
-
2023/08/10
-
2018/05/18
-
2023/12/29
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

※見逃し配信【第4回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|客席…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数8,015件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数690件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数143件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数483件
-