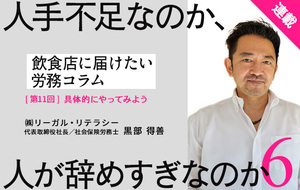- Tweet

初めて事業を開始する方にとって、最初の課題となるのは開業資金の調達です。これまで新規開業に携わった経験がないと、戸惑うことも多いでしょう。
本記事では、以下のような疑問にお答えしていきます。
●開業資金はどのくらい準備するべき?
●開業資金の内訳は?
●開業資金の調達方法は?
開業を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。最後まで読むことで、開業資金に対するイメージが明確になるでしょう。目次
開業資金の平均額は1,027万円
事業者の取り組みを支援する「日本政策金融公庫」の調査によると、2023年度における開業費用の平均値は1,027万円でした。中央値は550万円で、長期的にみると少額化の傾向にあります。
ただし、この数値は「開業費が高額な業種」と「開業費が少額な業種」が混在しているため、どの事業においても1,000万円の開業費が必要であるとは限りません。開業費用を金額別に「500万年未満」「500万〜1,000万円未満」「1,000万〜2,000万円未満」「2,000万円以上」の4つに区分すると、「500万円未満」の割合が全体の約44%。一部の業種が平均値を押し上げているものの、実際は「500万円未満」で開業する層が多いようです。
参照 日本政策金融公庫|2023年度新規開業実態調査
代表的な開業資金の調達方法6選
開業資金の調達方法として代表的なものは、以下の6つです。
●日本政策金融公庫からの融資
●銀行や信用金庫からの融資
●親族や友人からの融資
●民間企業からの融資(ビジネスローン)
●クラウドファンディングでの調達
●補助金・助成金制度の活用
開業資金の内訳や目安額を把握できても、実際に準備できなければ意味がありません。高額な資金が必要になれば、自己資金で賄いきれないケースがほとんどでしょう。この項目を参考に、自分に適した調達方法を考えてみてください。
日本政策金融公庫からの融資
メリット 留意点 ・無担保/無保証の融資制度がある
・民間の金融機関よりも金利が低め
・返済期間が長め
・金利の変動がない
日本政府が出資する「日本政策金融公庫」では、新規開業者を対象とした「新規開業資金」を提供しています。新規開業資金は、担保が原則不要なほか、第三者の保証を付けずに借り入れできる制度です。事業の企画段階でも融資を受けやすく、多くの開業者が利用しています。
日本政策金融公庫の融資は固定金利であることが特徴です。民間の金融機関であれば、財務状況が良い企業に対しては金利を低くし、反対に悪い会社には金利を高く設定します。しかし、日本政策金融公庫の場合、財務内容と利率に相関関係はありません。財務状況の良い会社にとってはデメリットとなることがあります。
融資を申し込む際は、創業計画書の提出が必要です。日本政策金融公庫のHPから雛形をダウンロードし、必要事項を記載して作成しましょう。銀行や信用金庫からの融資(信用保証付き融資)
メリット 留意点 ・市中の金融機関と比較して、長期の借入が可能
・原則連帯保証人は必要ない
・担保がなくても利用可能
・借入申請時には、信用保証協会と金融機関のそれぞれで審査が必要
・信用保証料が発生する
信用保証付き融資とは、信用保証協会が融資の保証を行う融資のことです。信用保証協会とは信用保証協会法に基づき、中小企業や小規模事業者の円滑な資金調達を支援することを目的に設立された公的機関です。
中小企業や小規模事業者が金融機関に借入申込みをする際、大企業と比較して経営リスクが大きいため、返済可能性をはじめ信用面でのハードルが高く、事業者が考えているような資金調達が難しい場合が少なくありません。そこで、公的機関である信用保証協会が事業者の債務保証をすることで、市中の金融機関からの融資を受けやすくなるという仕組みです。
ただし、信用保証協会が保証してくれた融資に対して、毎年信用保証料が発生します。信用保証付き融資を利用する際は、借入金の返済と保証料の支払いがあることも覚えておきましょう。親族や友人からの融資
メリット 留意点 ・審査や面談を行う必要がない
・少ない利率で借り入れできる
・金銭トラブルにつながる恐れがある
親族や友人に借り入れの相談ができる場合は、資金調達における有力な選択肢となります。審査や面談を行わずにスムーズに進行できるだけでなく、低利率で借り入れできる点は大きなメリットです。親族や友人であれば、細かい条件も話し合って決めることができます。
ただし、個人間の借り入れは金銭トラブルにつながりやすいため、必ず契約書を締結しましょう。トラブル防止のために、専門家が作成し、状況に適した書式を用いることがポイントです。
ビジネスローン
メリット 留意点 ・融資実行までの期間が短い
・審査に通りやすい
・金利が高い
・融資限度額が小さい(個人の場合〜1,000万円ほど)
ビジネスローンとは、銀行や消費者金融が提供する金融商品の一つです。「事業用途に利用できるローン」と考えるとわかりやすいでしょう。ビジネスローンは融資実行までの期間が短く、1週間以内に着金されることがほとんどです。審査も比較的ゆるい傾向があり、面談が不要になることもめずらしくありません。
ただし、融資条件がゆるい反面、金利は非常に高額です。消費者金融では、多くの場合、法定金利である年利15〜18%が設定されています。融資限度額も小さく、個人の場合は最大でも1,000万円ほどが一般的な上限額です。
ビジネスローンは、ほかの資金調達がうまくいかない場合の緊急策と考えておくのがよいでしょう。
クラウドファンディングでの調達
メリット 留意点 ・気軽に資金調達を実施できる
・返済が不要(融資型を除く)
・資金調達に時間がかかる
・事業を方向転換するのが難しい
・運営会社に高い手数料を払う必要がある
クラウドファンディングでは、一般個人から出資を募って資金調達を行います。個人規模の資金調達でクラウドファンディングを行う場合は、出資者に対して特別なサービスや割引をリターンに設定する「購入型クラウドファンディング」を実施するのが一般的です。大掛かりな資金調達を行う場合は「融資型」や「投資型」で実施するケースもあります。
クラウドファンディングはリスクが少なく、開業前から一定の宣伝効果が見込めるため、認知度向上やファン作りを目的とした利用のされ方がメインとなっています。事業開始までの期間にゆとりがあり、大衆から支持を得られるような事業プランをお持ちの場合は、クラウドファンディングに登録してみるのもよいでしょう。補助金・助成金制度の活用
メリット 留意点 ・・返済が不要
・諸経費の適用範囲が広い(補助金)
・助成金は一定要件を満たせば必ず支給される
・原則として後払い
・使用用途が限られる
・経費の一部しか補助されない(補助金)
国や自治体は、労働者の環境整備や企業の事業推進を目的として「補助金」や「助成金」を交付しています。これらの制度は基本的に書類のみで審査が行われ、面談は不要です。借り入れではないため、返済がいらない点も心強いポイントです。
代表的な補助金・助成金は以下のものが挙げられます。
●創業助成金(東京都)
●若手・女性リーダー応援プログラム助成事業(東京都)
●地方創生起業支援事業
それぞれ目的が異なっており、交付意図に沿った経費に使用可能です。また、原則として交付は経費を支払った後に行われます。この点を踏まえて、補助金や助成金は二次的な資金調達手段として捉えるとよいでしょう。
関連記事 開業するなら助成金を活用しよう!おすすめの制度や利用する際の注意点など解説
資金調達をする際に注意したいポイント
資金調達の方法はさまざまありますが、その際に注意したいポイントを押さえておきましょう。
調達先・借入先の特徴を理解する
金融機関などから資金調達を行う際は、借入先の特徴をしっかりと理解しておきましょう。上記のように調達方法や借入先によってメリット・デメリットはそれぞれ異なります。希望金額や返済方法など、自身の事業に合ったものを見極めて借入先を選ぶことが大切です。
なお、調達先によって会計上の扱いも異なります。たとえば、金融機関から借入で調達すると「負債」であるのに対し、助成金や補助金は「収入」です。確定申告にも影響する場合があるため、調達資金の出元はちゃんと確認しておきましょう。SNSなどを利用した個人間融資には乗らない
SNSやインターネット掲示板などにおいて、個人間での金銭の貸し借りをうたった書き込みは少なくありません。なかなか審査が通らず融資が下りない状況に陥ると、楽にお金を借りられる手段をとってしまいかねません。
しかし、SNSなどで募集されている個人間融資は、貸金業法の規定に抵触する場合があります。中には個人を装ったヤミ金融業者も隠れており、違法な高金利での貸付けが行われるほか、更なる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性があります。難しい場合は事業の見直しも検討する
資金調達が難しい場合は、事業の見直しも検討しましょう。金融機関から融資が下りない理由は、その事業に将来性がなく、返済できる見込みがないと判断されているからです。
融資が受けられず開業できない場合は、無理せず資金に見合った事業に改める、自己資金を増やすなど、事業計画を練り直しましょう。事業計画のどこに問題があるのか、金融機関に相談してみることも大切です。
関連記事 開業に必要な初期費用とは?お金のトラブルを防ぐために調達方法を知ろう!開業資金の調達を成功させるためのポイント

事業計画書を作り込む
開業資金の調達を成功させるためには、練り上げられた事業計画書が必要不可欠です。特に、金融機関や日本政策金融公庫の融資では、事業内容を厳しくチェックされます。
事業計画書を作成する際は、以下の項目を可能な限り詳しく記載しましょう。
●具体的な事業内容
●顧客ターゲット
●将来的な展開プラン
●市場調査の情報
●考えられるリスク
根拠を添えてしっかり説明できていると、融資担当者の評価を得やすくなります。また、面談に同席していない担当者にも伝わるよう、書面だけで理解できる内容にするのもポイントです。
関連記事 事業計画書とはどんなもの?書き方や作成する目的を解説
開業手続きをキチンと行う
開業資金の調達を行う際は、事前に必要な手続きをすべて済ませておきましょう。
●開業書類の提出
●許認可の取得
●資格の取得
特に、事業開始に必須となる許認可や資格の取得は重要です。融資を申し込む際に取得状況を説明できる状態でなければ、担当者の信頼を大きく損ないます。
各種手続きが進んでいることがマイナス評価になることはないので、可能な限り準備を整えたうえで資金調達に臨みましょう。
関連記事 個人事業主として開業するには?必要な手続きと流れを解説
【無料】開業資金の調達は「canaeru」にご相談ください
開業資金の調達は、どのような業種においても重要度の高い要素です。まずは必要な金額を正確に算出し、目標額を調達するためのプランを綿密に練る必要があります。開業後の運営にも関わることなので、あいまいな計算をせず時間をかけて計画を練りましょう。
なお、「canaeru」では開業に関する無料開業相談を実施しています。canaeruは国から経営革新等支援機関(認定支援機関)と認められた株式会社USENが運営するサービスです。税務、金融および企業財務に関する専門的知識や支援にかかる実務経験が一定レベル以上ある支援機関として国に認められています。
これから開業資金の調達を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な開業コンサルタントがサポートいたします。
無料開業相談はこちら
この記事の監修

USEN開業プランナー
長原雄一
株式会社USEN 開業サポートチームに所属。日本政策金融公庫のほか、地方銀行や都市銀行など複数の金融機関にて融資業務を担当。
資金調達の豊富なノウハウを活かし、店舗開業者のサポートを行っている。
【主なサポート内容】
・開業資金にまつわる相談受付
・事業計画書の作成サポート
・資金調達時の面談アドバイス
株式会社USEN/canaeru 開業プランナーの詳細はこちら- NEW最新記事
-
-
2024/10/23
-
2024/10/18
-
2024/10/11
-
- おすすめ記事
-
-
2023/09/05
-
2022/12/26
-
2020/12/25
-
2024/02/16
-
2022/03/11
-
2022/07/08
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数192件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数128件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数506件
-