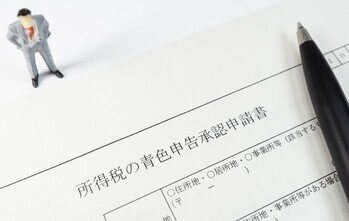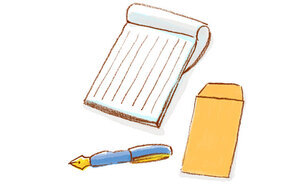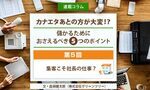- Tweet

開業を目指すためには当然のことながら元手が必要ですが、自力でまとまったお金を用意するのはなかなか難しいでしょう。
それでは、開業資金がほぼゼロの状態で開業はできるのでしょうか。一見すると無謀のように思われるかもしれませんが、本記事で紹介する制度などを活用すれば、開業資金ゼロでの開業が全く不可能というわけではありません。
この記事では、開業資金ゼロで開業する方法や開業資金として必要な金額、自己資金がなくても開業したいときの対策などについて説明します。
参考記事:起業に必要な資金はいくら?使える資金調達方法を紹介
目次
資金ゼロで飲食店を開業するのは難しい
飲食店の開業には、物件取得費や設備投資など多額の資金が必要になります。資金ゼロの状態から飲食店を開業するのは難しいのが現実です。最低でも数百万円ほどの開業資金を手元に用意することが望ましいです。初めての飲食店開業において、数百万円はすぐに捻出できる金額ではないでしょう。
しかし、自己資金が少なくても、設備投資を抑えたり、金融機関から融資を受けたりして開業に至るケースも多々あります。少ない自己資金で開業するためには、まず以下の3点を把握することが重要です。
✔自分の飲食店開業に必要な初期費用
✔設備投資を抑える方法
✔資金調達の方法
必要な知識を身につけて、実現可能な開業計画を立てていきましょう。飲食店の開業に必要な資金の内訳
飲食店を開業する際は、初期費用として「開業資金」と「運転資金」を用意しておく必要があります。
日本政策金融公庫の『2022年度新規開業実態調査』によると、あらゆる業種における開業費用は「250万円未満」(21.7%)と「250万~500万円未満」(21.4%)で4割以上を占めており、「250万円未満」で開業する割合は増加傾向にあります。
飲食店においては、初期費用は店舗の規模によって異なるものの、500〜1,000万円程度が目安となります。居抜き物件を探したり、可能な範囲でDIYしたりすることで、さらに初期費用を抑えることも可能です。
開業資金の調達方法には、自己資金や出資、融資、補助金などがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分の事業に合う方法を選択することが大切です。
引用 2022年度新規開業実態調査
関連記事 飲食店の開業資金はいくら必要?相場や調達方法について解説
①開業資金
開業資金とは、事業を新規開業する上で必要な資金を指します。具体的には、店舗の取得費用(敷金・礼金・仲介手数料など)や内装費、厨房設備費、備品購入費、宣伝費などが挙げられます。なお、すでに内装が整っている居抜き物件を利用する場合は、開業資金を節約できる傾向にあります。
②運転資金
運転資金とは、事業を継続的に運営する上で必要な資金を指します。具体的には、店舗の家賃や光熱費、人件費、仕入原価、宣伝費などが挙げられます。軌道に乗るまではある程度の時間を要することを踏まえ、6~12ヶ月分の運転資金を用意しておくと安心です。
加えて生活費も用意しておきましょう。生活費とは文字通り、事業主とその家族が事業が軌道に乗るまで生活していくのに必要な費用です。開業してもしばらくは売上が安定せず、十分な利益が上げられない場合が考えられます。開業時に住んでいる家の家賃や水道・光熱費、食費などを把握して6~12ヶ月分の生活費も蓄えておきましょう。自己資金なしで飲食店を開業する方法
ここからは本記事の本題である自己資金ゼロで開業する方法について触れていきます。自己資金ゼロ、あるいはわずかな資金で開業を目指す場合、金融機関からの融資や有志による支援金を受ける必要があります。
以下で資金調達の方法をいくつか紹介します。
日本政策金融公庫の制度を活用
飲食店開業を目指すうえで、資金調達の方法として最も一般的なのが日本政策金融公庫の『新規開業資金』を活用することです。新規開業資金は、新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方を対象とした融資です。
自己資金の要件は設けられておらず、条件を満たせば自己資金なし、かつ無担保・無保証人で融資を受けることも可能です。ただし、預金などの金融資産がゼロの場合、開業準備が不十分とみなされ、審査が厳しくなる可能性があります。出資を受ける
これから開業する飲食店が繁盛するという絶対の自信があるのであれば、出資を募ることも選択肢の一つです。具体的な方法としては、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルからの出資が挙げられます。
しかし、投資家や投資ファンドに出資してもらうには、魅力的で成功する見込みの高いビジネスであることをアピールしなければなりません。ある意味、金融機関から融資を受けるより難しいかもしれません。
クラウドファンディングを活用する
クラウドファンディングとは、インターネットを通じて不特定多数の人から資金を募る方法です。新規事業のプランやアイデアを専用のサイト上で公開し、興味を持ったり賛同したりしてくれる人から資金を募ります。
新規事業の内容次第で集められる資金額は大きく異なるため、多くの人から興味を持ってもらえそうな事業の運営を予定している場合には、おすすめの方法です。友人・知人、家族・親戚から資金を借りる
資金調達には上記の公的な方法もあれば、知人や家族からお金を借りる方法も検討できます。すでに信頼関係が築けているため、柔軟な条件で資金を借りられるでしょう。
しかし、開業資金を全て知人や家族から集めるのは容易ではありません。場合によっては何十人もの知り合いから少しずつ借金をすることになり、管理が困難になることも。返済が遅れて信頼関係を損なわないようにするために、開業に対する決意を伝え確実に同意を得ることや、しっかりとした返済計画を立てることが重要です。少ない自己資金で開業する方法
少ない自己資金で開業するためには初期投資を抑えることも重要です。無駄な初期投資をせず、費用をかけるところを吟味したうえで資金調達を行いましょう。
以下の項目では、初期投資を抑える具体的な方法を解説しています。ぜひ参考にしてみてください。居抜き物件を契約する
居抜き物件は、前のテナントが使用していた内装や設備が残っている状態の物件です。特に同業種であれば、残っている設備や内装をそのまま利用できるため、工事費用やテーブルやイスなどの購入費用などの初期費用を抑えられる場合があります。ただし、中古設備のため修理や交換が必要となるケースもあり、場合によっては予想以上の資金を要する可能性もあります。
設備投資を抑える
飲食店の開業時には、冷蔵庫やコンロなどの高額な厨房設備が必要です。これらは新品で数十万~数百万円かかりますが、中古の厨房機器やリース契約を活用することでコストを抑えられます。
リース契約は、リース会社が代理購入した厨房機器を毎月少額の支払いで利用する仕組みです。数百万円かかる厨房機器でも、毎月の支払いは数万円ほど。ただし、契約時の審査が必要な点や、廃業時に残債が発生する可能性は念頭に置く必要があります。
DIYで内装を手がける
DIYで内装を手がけることは、少ない自己資金で飲食店を開業する有効な方法です。自分で壁紙を貼り替えたり、家具を製作したり、塗装を行うことで、専門業者に依頼するよりも大幅にコストを抑えられます。また、自分の理想とする空間を創り出せる点も魅力です。安全面や法規制にも注意を払い、電気や水道工事など専門知識が必要な部分は専門家に依頼することが賢明です。
自己資金がゼロに近い状態で融資を申し込む際の注意点
自己資金は「起業に向けてコツコツと貯めてきたことがわかる」ことが望ましく、その確認のために通帳の記帳もチェックされます。
そのため、「見せ金」や「タンス預金」のように、貯めてきた経過がわからないお金で自己資金を用意したとしても、審査に落ちてしまう可能性があります。
一度審査に落ちると、同じ金融機関に改めて融資の申し込みを行う際のハードルが上がってしまうため、融資審査に通過できるだけの十分な準備をした上で申し込むようにしましょう。
融資を受けないまま開業することも不可能ではありませんが、手元資金が乏しいと経営は不安定になりやすいです。
見せ金を自己資金として提示しない
見せ金とは一時的に知人や他の金融機関からお金を借りて、自己資金を多く持っているかのように見せかけることを指します。金融機関の担当者はプロなので、見せ金を自己資金として提示しても必ず見破られます。
そして、見せ金であることが発覚すると、金融機関のブラックリスト入りしてその後の融資を受けられなくなる可能性があります。金融機関をだまそうとする行為は信用を得られず、リスクの高い行動なので、融資の相談時に見せ金を自己資金として提示するのはやめましょう。タンス預金を自己資金として提示しない
タンス預金とは自宅に保管している現金のことを指します。タンス預金は例え自分で貯めた資金でも、その証拠を提示することが難しい場合がほとんどです。金融機関からは、見せ金と同じく誰かから借り入れた資金としてみなされてしまうため、自己資金として扱えません。
金融機関からの印象が下がる可能性が高いので、自己資金として提示しないようにしましょう。一度審査に落ちると次回以降融資を受けにくくなる
銀行等の金融機関に融資を申し込むと、システムに全ての記録が残ります。審査に落ちてしまった際も記録されてしまうので注意が必要です。
審査に落ちた場合はその原因を解消したり、自己資本比率を上げたりすることで融資を再度受けられる可能性があります。ただ、審査に落ちた原因を解消するのは容易ではありません。
そのため、一度審査に落ちた場合、次回以降の融資を受けるのは難しいと考えておきましょう。融資審査に落ちた場合の資金調達方法
自己資金が少ない場合でも審査に通る可能性はありますが、必ずしも融資を受けられるとは限りません。
審査に落ちてしまった場合は、融資に頼らず開業を目指すしかありませんが、その際に取る方法としては、主に以下のことが挙げられます。
✔ とにかく自己資金を集める
✔ビジネスコンテストに参加する
✔クラウドファンディングを利用する
✔ 不動産を担保にして融資を受ける
✔補助金や助成金を利用する
それぞれの方法について、詳細を説明します。
とにかく自己資金を集める
手元に資金がないのであれば、さまざまな方法を使ってとにかく自己資金を集めるように努めましょう。
たとえば、家族や友人から援助を受けたり、株や持ち家などの資産を売却したりといった方法が考えられます。ただし、援助を受ける場合、金額によっては贈与税が発生する点には注意してください。
開業するまでの期間で必死にアルバイトを行って少しでも稼げるよう努力し、自分なりにできる方法で資金を集めましょう。ビジネスコンテストに参加する
ビジネスコンテストとは、ビジネスに関するアイデアやビジネスプランのコンペのことです。
政府や民間の組織などさまざまなところが主催しているコンペがあり、上位に選ばれると賞金が出るケースや、場合によってはそのまま開業へのサポートを行ってくれる場合もあります。
自己資金がない方にとってはいくつものメリットがあるので、必要に応じて参加を検討するとよいでしょう。不動産を担保にして融資を受ける
一般的に、自己資金がないと融資を受けることが難しいケースもありますが、担保にできる不動産がある場合は話が変わってきます。
不動産は売却して資金にする方法だけでなく、売却は難しくても担保に入れることで融資を受けられる可能性があります。不動産の価値にもよりますが、不動産を担保にすると多額の融資が見込める点がメリットです。
ただし、事業が失敗に終わってしまったら不動産が手元からなくなってしまうことは把握した上で、担保に入れてまで資金を調達すべきか考えなくてはなりません。少ない自己資金で開業する場合の注意点

資金調達に必要な自己資金を準備する
金融機関の信用度を高めて確実に融資を通すためにも、最低限の自己資金を準備しましょう。10坪〜15坪の居抜き物件の場合、500万円〜700万円程度の予算が必要になります。その場合、最低でも予算の10分の1以上の自己資金は確保しておきましょう。
飲食店は工夫を凝らせば自己資金なしでも開業できますが、準備している人の方が金融機関からの信用度が高まります。もし、最低限の自己資金がない場合は、なるべくお金を貯めてから開業の準備を始めましょう。余裕のある事業計画を立てる
倒産するリスクを抑えるためにも、自己資金ゼロで開業する場合、開業後の需要や売り上げ、運転資金も見据えた事業計画を立てましょう。将来を見据えずに開業してしまうと、すぐに赤字に陥り、経営に失敗する可能性があります。
自己資金ゼロで融資を受ける場合、基本的に無担保なので融資の金利が高いうえに、希望よりも融資額が低くなる傾向があります。
融資を受けて開業できても、資金繰りが上手くいかなければ赤字倒産するリスクが高くなります。リスクを抑えた店舗経営を行うためにも、融資を受けた際は返済シミュレーションを行い、長期的な目線で事業計画を立てましょう。飲食店開業後の資金繰りに役立つ知識
資金調達に成功して無事開業に至ったとしても、その後の資金繰りを考える必要があります。特に、少ない資金で開業した場合は、運転資金が心もとないこともあるでしょう。
この項目では、開業後の資金繰りにおいて必要な知識を解説しています。事前に把握することで「このままではまずい」と感じる前に対策できるので、ぜひ参考にしてみてください。

仕入れ金額を交渉する
飲食店で発生する経費において、高い割合を占めるのは「仕入れ」です。仕入れ価格を数百円落とすだけでも、資金繰りに大きな影響を与えます。
そこで、業者に対してある程度仕入れ実績を作れたと感じたら、金額交渉をしてみましょう。業者側も相応の仕入れ量がある事業者を手放したくないため、無理のない範囲であれば交渉に応じてくれるはずです。
また、同じ商品を取り扱う業者がいる場合は、相見積もりを行うのもよいでしょう。相見積もりとは、複数の業者から見積もりを受け取って比較することです。業者側も相見積もりに対して一定の理解があるので、主力商品の原材料だけでも比較するとよいでしょう。うまく交渉できれば、原価率の減少に大きく寄与します。
ただし、ひとつの業者と長く付き合う利点もあるので、相見積もりばかり依頼して困らせないように注意しましょう。仕入れの掛取引を交渉をする
仕入れ実績のない開業初期は、業者側から現金取引を提案されることも多いはずです。しかし、毎回代金を支払う現金取引は、開業直後の資金状況において厳しい決済方法と言わざるを得ません。
そこで、支払い実績を作り業者の信頼を得た段階で「掛取引」の提案をしてみましょう。掛取引とは、仕入れ代金を都度支払わず、後からまとめて精算する取引方法です。具体的には、1ヶ月の仕入れで発生した代金を、翌月15日や末日などに一括で支払います。掛取引で支払いをまとめると、現金が不足していても、材料不足によって営業が滞ることはありません。
ただし、掛取引によって支払いスパンが伸びたとしても、使える資金が増えるわけではないので注意しましょう。期日に支払いができないと業者からの信頼を失うことになります。掛取引を行う際は、納品伝票に記載されている代金を都度記録し、支払額を把握しておくとよいでしょう。オペレーションの効率化を図る
人件費は、仕入れ代金と同様に資金繰りへ大きな影響を与えます。オーナー自ら現場に立つと仮定しても、ほかのスタッフが0人の状況で回していくのは難しいでしょう。
人件費を削減するためには、オペレーションを効率化する必要があります。オペレーションの効率化によって少ない人数で営業できる体制を構築できれば、発生する人件費も比例して少なくなるでしょう。毎日1人分の人件費をカットするだけでも、資金繰りは改善するはずです。
オペレーションを効率化する方法は、以下のようなものがあります。
✔テーブルオーダーシステムを導入する
✔POSレジを導入する
✔料理を提供する順番を変更する
✔座席の配置を変更する
テーブルオーダーシステムやPOSレジの導入には次の項目で解説する「補助金」を利用できるケースもあります。開業初期に大きな出費を避けることも重要なポイントなので、ぜひ活用してみてください。国や自治体の補助金・助成金制度を利用する
運転資金が心もとない場合は、国や自治体が実施する補助金、助成金制度の活用も検討しましょう。
全国各地で、飲食店事業者を支援する補助金、助成金制度を導入しています。一部抜粋したものを以下で取り上げているので、参考にしてみてください。
制度名 内容 働き方改革推進助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 50万円を上限に、POSレジやテーブルオーダーなど、業務効率化ツールの導入費を交付 インバウンド対応力強化支援補助金 300万円を上限に、海外旅行者の受け入れ強化に使用する資金を交付 小規模事業者持続化補助金 50万円を上限に、チラシや看板などの販売促進費を交付
どの制度も無条件で補助金、助成金を受け取れるものではなく、交付要件を満たす必要があります。また、交付要件の多くは開業後でないと満たせないものです。あくまで開業後の運転資金に充てるつもりで考えておきましょう。
関連記事 飲食店開業に使える助成金・補助金まとめ!押さえておきたい基礎知識を解説
開業資金調達には、融資などさまざまな方法が考えられる
自己資金がゼロであっても、いくつかの条件を満たすことで申し込める融資制度を利用すれば、開業に関する資金を調達できる可能性があります。
また、ビジネスコンテストに参加したりクラウドファンディングを活用したりと、開業資金を調達するための方法はいろいろと考えられるため、自分に合う方法を見極めた上で資金調達に励みましょう。
しかし、資金調達に役立つ数々の制度は、そもそも存在を知らなければ利用することができません。
開業にまつわる情報を集めたい方や、開業時に使える資金調達の方法に詳しくなりたい方は、開業準備を支援してくれる「canaeru(カナエル)」のようなサービスを活用するのがおすすめです。制度の利用方法などを理解できれば、無理なく開業準備を進めやすくなるでしょう。
canaeruは、国から経営革新等支援機関(認定支援機関)と認められた株式会社USENが運営する開業支援サービスです。経験豊富な開業プランナーが、開業を多角的にお手伝いします。ご相談の場合は、下記のリンクからお問い合わせください。
無料の開業相談はこちら
この記事の監修

USEN開業プランナー
長原雄一
株式会社USEN 開業サポートチームに所属。日本政策金融公庫のほか、地方銀行や都市銀行など複数の金融機関にて融資業務を担当。
資金調達の豊富なノウハウを活かし、店舗開業者のサポートを行っている。
【主なサポート内容】
・開業資金にまつわる相談受付
・事業計画書の作成サポート
・資金調達時の面談アドバイス
株式会社USEN/canaeru 開業プランナーの詳細はこちら- NEW最新記事
-
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
- おすすめ記事
-
-
2018/04/12
-
2022/09/09
-
2018/03/30
-
2017/11/07
-
2021/07/09
-
2018/02/13
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

※見逃し配信【第4回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|客席…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数8,283件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数687件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数143件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数483件
-