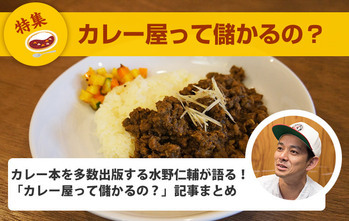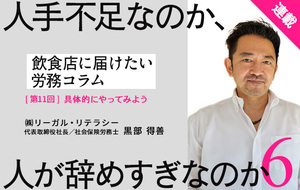- Tweet

本記事では、飲食店の開業に必要な具体的な資金について解説します。開業にはどれぐらいかかるのか、足りない資金はどのように調達すればいいのかなど、開業前に知っておくべきポイントを押さえていきましょう。
参考記事 開業資金はいくら必要?費用の内訳と調達方法を解説
参考記事 飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解説目次
飲食店開業の初期投資に必要な額は?
飲食店を開業する場合、初期投資として必要な金額の目安は1,000万円となります。これは、東京都内で開業する場合の目安です。ただし、店舗の立地や広さ、コンセプトなどの経営計画が変わると、初期投資額も変わるため、あくまでも目安としてください。
なお、すべてを自己資金でカバーしなければならないわけではなく、金融機関による融資を利用するケースが一般的です。融資額は、飲食店の勤務経験の有無、事業計画書の質などによって上下します。言い換えれば、返済能力があるかどうかを上手くアピールすることができれば、融資額も上昇しうるということです。
ただし、1,000万円が調達できれば、必ず開業がうまくいくというわけではありません。物件や備品の具体的なコストを算出し、開業後の利益目標とどのタイミングで達成するかといったことを決め、初期費用となる1,000万円の使い方を考えることが大切です。想定していなかったコストが発生すると、開業後の計画が破綻する恐れがあるため、抜け漏れのないように注意しなければなりません。
そのほかにも、初期投資の内訳を把握することも非常に重要です。内訳を把握することで、何にどのくらいの金額が必要なのか、削減できる箇所はあるのかといったことが理解できるため、投資額を抑えられる可能性があります。初期費用の主な内訳としては、「物件取得費」「内装・設備導入費」「運転資金」「生活資金」の4つが挙げられます。それぞれの概要は以下の通りです。
●物件取得費:前家賃、保証金、礼金、仲介手数料などにかかる費用
●内装・設備導入費:内装工事や、厨房で使用する機器、食器類、各種消耗品などの導入にかかる費用
●運転資金:店舗家賃や人件費、光熱費など、開業後にかかる諸費用
●生活費:自身や家族を養うための費用
引き続き4つの費用について解説します。物件取得費
物件取得費とは、物件の取得に伴い発生する保証金や礼金、仲介手数料などのことです。一般的に物件取得費は、家賃の10倍を目安として考えておきましょう。家賃30万円の物件であれば、物件取得に300万円程度かかるイメージです。
注意しておきたいのは、保証金の金額が物件によって異なるという点です。立地など好条件であるほど高くなる傾向にあるため、立地で勝負したい場合は余裕をもって物件取得費を準備したほうがよいでしょう。内装・設備導入費
物件を契約した後は、店舗を作るための資金を用意しなければなりません。具体的には、内外装費のほか厨房で使用する機器や食器、備品などの準備費用などが該当します。
内装や設備導入にかかるコストは、1坪あたり50〜80万程度を目安としてください。30坪の店舗であれば1,500〜2,400万円程度です。
どのような内装にするか、どういったメニューを提供するかによって投資コストは異なります。内装や設備にこだわればこだわるほど費用は上昇し、開業資金全体の半分以上を占める場合もあります。運転資金
運転資金とは、仕入れ費や人件費などの毎月の支出を賄うために必要な資金を指します。仕入れの支払いに現金が必要となるケースがあるため、手元にある現金を運転資金として用意しておかなければなりません。
開業直後は計画通りに売り上げが伸びないケースが多いため、売上を運転資金に当てるといった考えは大きなリスクを伴います。そのため、売上が少なくても仕入れ対応ができるように、最低でも3ヶ月、できれば6ヶ月分程度の運転資金を確保しておくことをおすすめします。生活資金
飲食店開業時の予算には、自身の生活資金も含める必要があります。開業当初から店舗の利益だけで生活費を賄うのは難しいこともあるため、事前に資金を用意しておくと安心です。家族がいる場合は家庭の生活費を算出し、最低でも3~6ヶ月程度の生活資金を初期投資に組み込んでおきましょう。
なお、生活費は事業資金ではないため、この名目で融資を受けることはできません。あらかじめ自己資金で賄えるようにしておきましょう。飲食店の開業資金をモデルケースで試算
飲食店に必要な資金の内訳を把握できても「具体的な数字を見ないとピンとこない」と感じる方も多いでしょう。そこで、単身者が15坪程度(家賃20万円を想定)の飲食店を開業すると想定したモデルケースで試算してみましょう。都心と郊外で相場が異なるため、2パターンに分けて解説していきます。
【都心で15坪前後(家賃20万円)の飲食店を開業する場合】
項目 金額 内訳 物件取得費 200万円
(20万円×10か月分)・保証金
・礼金
・仲介手数料
・前家賃内装・設備導入費 750万円
(坪数×50万円)・内外装工事
・厨房設備
・その他什器・備品運転資金 200万円
(20万円×10か月分)・人件費
・仕入れ代金
・その他経費生活資金 93万円
(15.5万円×6ヶ月分)経営が安定するまでの生活費 総額 1,243万円
東京都や政令指定都市の中心部は家賃相場が高く、大まかな試算でも1,200万円を超える結果となりました。賑わっている駅前や繁華街の物件は、さらに高額な家賃相場となっています。
【地方都市(郊外)で15坪前後(家賃8万円)の飲食店を開業する場合】
項目 金額 内訳 物件取得費 80万円
(8万円×10か月分)・保証金
・礼金
・仲介手数料
・前家賃内装・設備導入費 750万円
(坪数×50万円・内外装工事
・厨房設備
・その他什器・備品運転資金 80万円
(8万円×10か月分)・人件費
・仕入れ代金
・その他経費生活資金 87万円
(14.5万円×6ヶ月分)経営が安定するまでの生活費 総額 997万円
地方都市や郊外の場合、家賃相場が大きく下がります。それにともなって必要な物件取得費、運転資金が下がり、1,000万円を下回る試算結果となりました。あくまで試算ですが、飲食店の開業資金には家賃が大きく影響することがわかる結果です。自己資金0円でも飲食店開業は可能か?
「自己資金0円でも開業できる」といった謳い文句を耳にすることもありますが、0円開業はほとんど特殊なものだと考えてください。飲食店の開業を目指す場合、どんなに少なくても300万円以上の自己資金が必要です。
自己資金0円開業ができるケースは、飲食店のオーナーや出資者がいる場合であり、そのような人たちがいない場合はほぼ不可能です。強力なバックアップを得ていない場合、0円開業もしくはそれに近い金額での開業は軌道に乗せることが非常に難しく、長続きしない可能性が高くなります。
都内に自己資金180万円で開業したというケースもありますが、都心ではなく郊外での開業であり、開業後しばらくは売り上げが伸びず苦しい時間を過ごしていました。このような点からも0円開業は基本的に不可能であると考え、最低でも自己資金300万円は確保できるようにしておきましょう。
参考記事 開業資金ゼロでも開業できる?主な方法や対策を解説自己資金が少額だと苦しくなる理由
低資金で開業すると、初期の投資で資金のほとんどを使い切ってしまい、その後のキャッシュフローが厳しい状況になる恐れがあります。最悪の場合、廃業に追い込まれるケースもあるでしょう。
これから開業しようとしている人の中には、「開業後は忙しくなるぞ!」と考えている人もいるかもしれません。しかし、実際には開業後は客足が安定しないケースが多く、収入も予想を下回る可能性があります。
一方で、収入が少ないとしても、食料の仕入れや店舗の家賃、融資の返済などは毎月発生します。そのため、自己資金を初期投資の段階で使い切ってしまうと、お店が軌道に乗る前に資金がショートし支払いができず廃業に追い込まれかねません。
自己資金は、飲食店の開業にかかる資金だけでなく、開業後数ヶ月の自身の生活資金や各種支払にかかるコストも含んだものです。この点を踏まえると、少額自己資金では開業時点で資金がほとんど底をついてしまい、開業後の支払いに対応できなくなります。開業後の不安定な時期を乗り越えるためにも、自己資金は多めに用意しておくことが大切です。
以下の記事では金融機関による融資審査について解説しています。自己資金と合わせて開業には融資による資金調達が欠かせないためこちらも合わせてご覧ください。飲食店の開業資金の調達方法
ここからは、開業資金の具体的な調達方法について解説していきます。出店費用を自己資金だけで賄えるのは非常に稀なケース。ほとんどの開業者は金融機関などから資金を調達しています。少しでも選択肢を広げられるように、資金調達の知識を蓄えておきましょう。

融資を受ける
真っ先に検討すべき資金調達方法は、金融機関から融資を受けることです。全国の金融機関や、国が運営する日本政策金融公庫では、創業する方へ向けた融資制度を実施しています。それぞれの詳細を解説していくので、制度を活用できるかチェックしておきましょう。
関連記事 開業資金の融資審査は厳しい?落ちる理由や通るためのポイントについて解説
●日本政策金融公庫「新規開業資金」実施元 日本政策金融公庫 対象者 ・新たに事業を開始する方
・税務申告を2期終えていない方融資限度額 7,200万円
(うち運転資金4,800万円)
担保・保証人 原則不要
「新規開業資金」は、政府系金融機関の日本政策金融公庫が取り扱っている融資制度です。原則、無担保・無保証で融資が受けられることから、独立開業する多くの新規事業者が利用しています。融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円まで)に設定されており、初期投資が大きい飲食店の開業でもしっかりカバーできる金額です。
返済期間は、設備資金は20年以内、運転資金は10年以内と定められています。利率は条件により異なるため、HPで確認しておくようにしましょう。
参考 日本政策金融公庫『新規開業資金』
●銀行/信用金庫の融資制度
全国の銀行や信用金庫でも、新たに開業する方向けの融資制度を導入しています。銀行、信用金庫の融資制度は、大きく分けて金融機関が直接融資する「プロパー融資」、信用保証協会が間に入る「信用保証付き融資」の2種類です。事業実績を作るまではプロパー融資の審査に通りにくいため、信用保証付き融資を検討するとよいでしょう。
創業時に信用保証制度を利用する場合の融資限度額は、最大3,500万円です。信用保証制度の利用にも一定の審査は必要ですが、プロパー融資と比較すると金融機関側の審査は通りやすくなります。ただし、融資で発生する利息に加えて「信用保証料」と呼ばれる費用が加算される点は念頭に置いておきましょう。信用保証料は、実績が少ない事業者の融資を担保するための対価として支払うものです。家族や親戚から借りる
融資を受けるための自己資金が不足している場合は、家族や親戚から借りる方法も検討しましょう。
通常、金融機関が自己資金と認定するのは地道に積み上げられたことがわかる資産です。一時的に借り入れたと思われるものは自己資金とは認められません。しかし、親族からの借り入れに限っては自己資金として認められる場合があります。融資の自己資金要件を満たせない場合は、一度親族に相談してみるとよいでしょう。
また、親族からの借り入れであれば金融機関からの融資ほど利息はかからないはずです。少額の資金調達で開店費用を賄える場合は、金融機関より先に親族を頼るのも一案です。クラウドファンディングで調達する
クラウドファンディングとは、資金調達が必要な起案者に対して、不特定多数の人が少額ずつ出資する仕組みです。クラウドファンディングサイトを介して実施するのが一般的で、日本では「CAMPFIRE」や「READFOR」といったサイトでクラウドファンディングを実施できます。
クラウドファンディングにおいて重要視されるのは、事業に対する熱意です。出資者は「この人と、この事業を応援したい」と感じて出資するため、心を動かす熱意を伝える必要があります。
また、起案者から出資者に対するリターンも重要視される要素の一つです。リターンとは、資金調達が完了した際に、起案者が出資の見返りとして提供するモノやサービスを指します。飲食店の場合は「食べ飲み放題券」や「オリジナルグッズ」をリターンに設定するケースが一般的です。冷蔵、冷凍で遠方に食品を届ける場合は「看板メニューの送付」を設定するのもよいでしょう。
参考記事 話題の「クラウドファンディング」って何?投資家から調達する
投資家とコネクションを持っている場合は、開業時に出資してもらう方法もあります。投資家からの資金調達は出資形態を取ることが多く、条件次第では返済義務のない資金調達が可能です。
ただし、利益が出た後に永続的なリターンを求められることが多い点は覚えておきましょう。投資家も慈善事業ではないので、出資するリスクに見合ったリターンが必要です。トラブルを避けるためにも、投資家に出資してもらう際は入念な打ち合わせを行っておきましょう。飲食店の開業資金を抑えるためのポイント
飲食店の初期投資において、もっとも大きい割合を占めるのは「内装・設備導入費」です。店舗の設備や内装にかかる費用を抑えると、必要な開業資金が大きく減少します。
この項目では内装・設備導入費を抑えるためのポイントを解説していくので、資金計画を立てる際は参考にしてみてください。

居抜き物件を借りる
内装・設備導入費を大幅に削減する現実的な方法は、居抜き物件を借りることです。居抜き物件とは、過去に入居していたテナントの内装や設備がそのまま残っている物件を指します。以前のテナントと開業したい飲食店が同じ業態の場合は、かかる費用を大幅に削減できるでしょう。
ただし、居酒屋やカフェの居抜き物件は人気が高く、すぐに入居者が決まってしまいます。居抜き物件を狙う場合は、複数の不動産会社に問い合わせて、めぼしい物件が見つかったらすぐ内覧できるようにしておきましょう。
小さい物件を借りる
小さい物件を借りることも、内装・設備導入費を抑える結果につながります。保証金や礼金、仲介手数料はすべて「家賃」をベースに設定される項目です。小さな物件を借りて家賃を下げることで、初期投資にかかる費用も抑えられます。
また、家賃は毎月発生する固定費です。固定費は開業後のランニングコストにも影響を及ぼします。家賃が下がると必要な運転資金も減少し、資金繰りもしやすくなるでしょう。
開店計画を立てる際は、必要な売上と確保したい席数を計算し、最小の坪数で物件を探してみてください。中には小さい坪数でも席数を多めに取れる構造の物件もあるので、内覧時にしっかり調査しておきましょう。中古の備品を購入する
厨房機器を中古品で揃えることも、内装・設備導入費を抑えるポイントになります。開店時に揃える備品の中でも、厨房機器は高額です。中には数百万円を超える備品もあるため、購入金額を下げられれば初期投資額が大幅に抑えられます。「テンポスバスターズ」などの専門業者では、全国の店舗やオンラインで、飲食店向けの中古厨房機器を購入できます。新品が望ましいもの、中古で問題ないものをあらかじめ決めておくとよいでしょう。
リース契約を活用する
リース契約とは、リース会社が代理購入した機材を店舗で利用する仕組みです。店舗オーナーが支払うのは毎月のリース代金のみ。機材購入のための高額な初期投資は不要になります。また、機材の納入やアフターサービスは販売したメーカーが行うため、トラブルに関する心配もありません。とにかく内装・設備導入費を抑えたい方にとっては、魅力的なサービスと言えるでしょう。
ただし、リース契約の利用にはデメリットもあります。主なデメリットは以下の通りです。
●廃業しても残債が残る
●購入よりも割高になる
●所有者はリース会社になる(契約終了後に買い取り可)
初期投資を抑えられる点は魅力的ですが、デメリットを把握したうえで利用することが重要です。とくに高額な機材だけリース契約を締結する、など特性を考えた活用法を検討しましょう。
開業後は助成金や補助金も活用しよう
国や自治体は、飲食店オーナーに向けた数多くの助成金、補助金制度を実施しています。要件を満たして交付が受けられれば、資金繰り計画の一助となるでしょう。
飲食店で活用できる代表的な助成金、補助金は以下の通りです。
制度名 内容 IT導入補助金(全国) 中小企業・小規模事業者などの労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金。 小規模事業者持続化補助金(全国) 持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓や業務効率化などの取り組みを支援する補助金。 キャリアアップ助成金(全国) 非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するもの。
どの助成金、補助金も、無条件で交付されるものではありません。しかし、詳細を把握していないと「条件を満たしていたのに申請していなかった」という事態が起こりかねません。ほかの助成金や補助金は以下の記事内でまとめているので、詳細をチェックしてみてください。
参考記事 飲食店が利用できるコロナ対応の助成金・補助金・融資まとめ!自治体ごとの支援も紹介飲食店開業に必要な資格
開業にあたっては、物件の取得や内外装工事、備品の購入などの準備が必要であり、それに伴いコストも発生します。また、開業資金の把握や融資を受ける際に必要となる事業計画所の作成、資金調達の手続きなども必要です。
さらに、開業時には以下の資格を取得していなければなりません。
●食品衛生責任者:都道府県の食品衛生協会が行う講習を受講する
●防火管理者:日本防火・防災協会が行う講習を受講する
開業までにやることは多いため、抜け漏れのないように注意してください。
以下の記事では、飲食店の中でもカフェの開業について必要な資金や資格について詳しく解説しています。カフェの開業を検討している方はこちらもご覧ください。
参考記事 飲食店開業に必要な資格は2つ!取得方法や届出についても解説開業資金の調達はcanaeruにご相談ください
『canaeru(カナエル)』では、開業資金に関するお悩み相談を無料で承っています。金融機関や銀行出身の経験豊富な開業プランナーが、丁寧にヒアリングを行い、資金面の課題解決をサポートします。
canaeruの運営元である株式会社USENは、国が定める経営革新等支援機関(認定支援機関)です。税務、金融および企業財務に関する専門的知識や支援にかかる実務経験が一定レベル以上ある支援機関として国に認められています。
canaeruでは、開業のエキスパートによる無料サポートをご利用いただけます。開業にあたってお困りのことがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらまとめ
飲食店を開業するにはまとまった資金が必要となります。本記事で紹介している1,000万円はあくまで目安ですが、個人資産のみで開業できるケースはめったにありません。
資金調達は金融機関から融資を受ける方法が一般的です。クラウドファンディングや投資家からの投資は調達できる見込みがあれば利用したい方法です。また、開業資金を抑える方法や、補助金や助成金を活用して金銭面の負担を軽減する方法をあらためて確認し、開業前の準備は万全にしておきましょう。この記事の監修

USEN開業プランナー
長原雄一
株式会社USEN 開業サポートチームに所属。日本政策金融公庫のほか、地方銀行や都市銀行など複数の金融機関にて融資業務を担当。
資金調達の豊富なノウハウを活かし、店舗開業者のサポートを行っている。
【主なサポート内容】
・開業資金にまつわる相談受付
・事業計画書の作成サポート
・資金調達時の面談アドバイス
株式会社USEN/canaeru 開業プランナーの詳細はこちら- NEW最新記事
-
-
2024/10/23
-
2024/10/18
-
2024/10/11
-
- おすすめ記事
-
-
2017/12/28
-
2017/11/27
-
2018/02/01
-
2024/10/23
-
2022/10/20
-
2023/10/02
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数192件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数128件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数506件
-