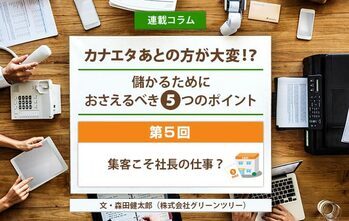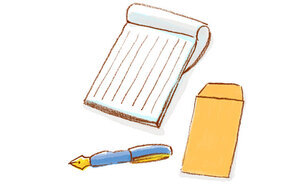- Tweet

「会社を辞めて個人事業主になることを考えているけど、何から着手すべきか悩んでいる」
「起業にあたって、必要な手順を知りたい」
個人事業主として起業するにあたって、何から始めるべきか悩んでいる方もいるでしょう。起業前に必要な手続きや手順を把握しておくことで、事業の成功率は大きく上がります。
この記事では、起業するために必要な手続きや手順、学ぶべき知識などについて解説します。ぜひ最後まで読み進めて、起業を始める参考としてください。
目次
個人事業主として起業するために必要な手続き
会社を辞め、個人事業主として起業するために必要な手続きは、下記の4つです。
- 開業届の提出
- 保険・年金の切り替え
- 退職の手続き
- 許認可の取得
一つひとつ解説します。

開業届の提出
個人事業主として起業する際は、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署に提出しましょう。未提出のまま事業を始めても罰則はありませんが、所得税法によって提出が義務づけられています。
開業届を提出すると、確定申告で青色申告特別控除を利用でき最大65万円の税額控除が受けられる、社会的な信用を得やすくなるなど多くのメリットを得られるため、起業したら特別な理由がない限り提出することをおすすめします。
開業届を提出する際は、必要に応じて以下の書類も提出しましょう。
- 青色申告承認申請書
- 個人事業税の事業開始等申告書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 適格請求書発行事業者の登録申請書
- 消費税簡易課税制度選択届出手続
いずれの書類も、国税庁公式ホームページから入手可能です。
関連記事:開業届の必要書類とは?書き方や提出方法をわかりやすく解説
保険・年金の切り替え
個人事業主として起業する際には、保険・年金の切り替え手続きを行いましょう。個人事業主が健康保険に加入するときの具体的な選択肢は下記の2つです。
- 国民健康保険への加入
- 退職した会社の健康保険の任意継続(最長2年間)
年金についても、厚生年金の脱退手続きと国民年金の加入手続きが必要です。それぞれ、市役所や支所などで切り替え手続きを行いましょう。
退職の手続き
個人事業主として独立する意思が固まったら、勤めている会社を退職する手続きを進めましょう。
まずやるべきことは、退職する旨を適切なタイミングで会社に伝えることです。民法上は退職の2週間前までに伝えていれば問題ないとされています。しかし、引き継ぎをする業務が多い場合や繁忙期などは、2週間前に伝えられると会社が困る可能性があります。
スムーズかつ円満に退職するためには、伝えるタイミングを図る配慮が大切です。
許認可の取得
起業する業種によっては、許認可の申請が必要となるケースがあります。
たとえば、飲食店や美容院を開く際には保健所の許認可が、酒屋を開く際には税務署の許認可が必要です。起業する業種が、許認可を必要とするのか否かについてあらかじめ確認をしておきましょう。
すぐに申請が通らないケースも想定し、時間に余裕があるうちに申請手続きを進めることをおすすめします。
【4段階】個人事業主として起業するための手順
個人事業主として起業する際には、下記に挙げる4つの手順を踏みましょう。
- 事業計画を策定する
- 資金計画を策定する
- 資金調達の段取りを行う
- 起業準備を行う
手順を一つひとつ解説します。
事業計画を策定する
個人事業主として起業する際には、まず事業計画を策定しましょう。事業計画を立てるためには、事業内容や想定顧客、提供できる価値などを具体的に「事業計画書」にして落とし込む必要があります。
事業計画書には、下記の項目を盛り込みましょう。
- 事業内容
- 想定顧客
- 提供できる価値(サービス・製品の詳細)
- 市場規模
- 競合情報
- 販売戦略・マーケティング戦略
- 生産方法・仕入先
- 生産方法・仕入先
- 売上目標
事業計画を立てることで、起業後にどのようなアクションを取っていくべきかが明確になります。事業計画書は金融機関からの融資を受けるための説得材料ともなるため、細部まで内容を固めておきましょう。
関連記事 事業計画書の書き方とは?目的やメリットについて解説資金計画を策定する
事業計画を策定したら、資金繰りについての計画を立てましょう。策定した事業計画を実現させるためには資金がどれほど必要なのか、どのように資金を調達するのかを明確にする作業が必要です。
貯金などの自己資金から起業資金をまかなえれば理想的ですが、業種・業態によっては必要資金が多額になるため難しい場合があります。その際は、金融機関からの融資や補助金・助成金を活用して資金を用意する必要があるでしょう。
資金調達の段取りを行う
資金計画を策定したら、資金調達の段取りを具体的に組みましょう。起業時に考えられる代表的な資金調達方法は、下記のとおりです。
- 銀行からの融資
- 日本政策金融公庫からの融資
- 各自治体からの制度融資
- 補助金・助成金の利用
- ビジネスローンの利用
- 親族からの借り入れ
- 投資家からの出資
- クラウドファンディング
上記に挙げた資金調達方法の中でおすすめの方法は「融資」です。まずは、銀行や日本政策金融公庫に融資の相談をしてみましょう。
融資を受ける場合は、金融機関からの信用を得るために「最低限の自己資金」が必要です。最低でも、融資を受ける金額の30%程度の自己資金を用意しておきましょう。自己資金が足りない場合には、家族や親族、知人から援助を受けるのも選択肢の1つです。
関連記事 開業資金の調達方法をご紹介!自己資金と6つの集め方
起業準備を行う
資金調達の段取りを組んだら、起業する業種・業態に応じて具体的な起業準備を進めます。店舗の取得や設備の導入、取引先への営業など、必要な準備を整えていきましょう。
先のことを見据えたうえで、経営・融資に関する相談会やセミナー、講習会への参加を検討することも大切です。起業直後はわからないことが多いため、相談できる相手や場所を見つけておきましょう。
税金や法律に関する悩みは、司法書士や税理士、社会保険労務士への相談もおすすめです。
個人事業主として起業したときに必要な知識
個人事業主として起業したときに身につけるべき知識は、下記の3つです。
- マーケティング&ブランディングの知識
- 税務の知識
- 法務の知識
一つひとつ解説します。
マーケティング&ブランディングの知識
事業を軌道に乗せるために、個人事業主は継続的に売上を立てる、あるいは集客を安定化させる必要があります。たとえば店舗ビジネスにおいては、お客さんをいかに途切れさせないかがカギとなるでしょう。
そのためには、マーケティングやブランディングの知識を学ばなければなりません。マーケティングとブランディングは数多くの手法があるため、どの内容が事業に適しているのかを見極める力も養いましょう。
オーソドックスな手法だけでなく、競合に負けないためにいま話題の手法を得る努力も重要です。
税務の知識
個人事業主になると、税務知識の有無で毎年の納税額に大きな差が生まれます。個人事業主は確定申告を行う必要があるため、税務に関する知識は必須です。
確定申告では、自ら所得税の納税額を算出しなければなりません。支払う税金を抑えるためにも、何を経費として計上できるのか、控除になる項目はなにかを知識として押さえておきましょう。
仮に税理士に確定申告を依頼する場合でも、経営を行う以上は、税金の知識は持っておくべきです。事業の財務状況を把握するためにも、基礎的な内容は起業前に学んでおきましょう。
法務の知識
個人事業主として起業する際には、法務(法律)に関する知識も身につけておく必要があります。取引先と個人で契約して業務を行うことになるため、最低限の法務知識は必須です。
たとえば店舗ビジネスの場合、万引きなどの迷惑行為を受ける、仕入れた商品に不具合があったなどのトラブルが起こる可能性があるでしょう。その際も知識を身につけておけば、店舗を守る一助となります。
個人事業主として起業する際はリスクを抑えることが重要!
個人事業主が起業する際に、なるべく回避したいリスクは金銭面のリスクです。多額の初期投資はリスクが高いため、なるべく資金を抑えて起業することを心掛けましょう。店舗を構える場合は多額の資金を必要とするケースもありますが、融資を受ける際は返済できる金額を申し込むことが大前提です。
最初は小規模から始め、軌道に乗ったら少しずつ規模を拡大していく方法がおすすめです。会社員の場合は、まずは副業として事業を始めて感触を掴むのも有効な手法です。
個人事業主として動き出す前に必要な手順を把握しておきましょう
新たな生き方として起業を考えている方は、独立前に必要な手順や知識を一通り押さえておきましょう。綿密な計画づくりと、事業に関する知識を取得してから起業することで、事業の成功率は大きく変わってきます。
「canaeru」では、個人事業主として起業をしたい方向けに無料相談を実施しています。起業にあたり、悩み事を抱えている方はぜひお問い合わせください。
開業の無料相談はこちら
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- NEW最新記事
-
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
- おすすめ記事
-
-
2019/09/27
-
2017/10/20
-
2018/03/02
-
2021/07/26
-
2021/12/03
-
2018/08/03
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

※見逃し配信【第4回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|客席…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数8,015件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数690件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数143件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数483件
-