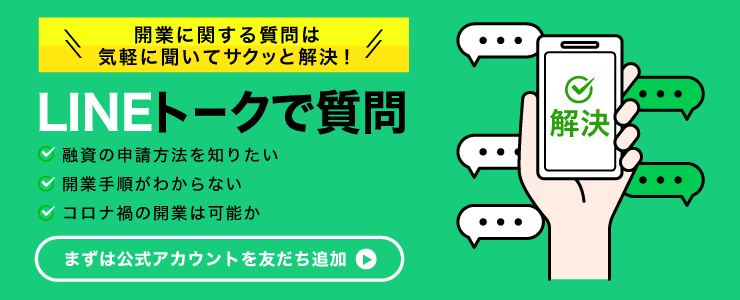多様な働き方が認められるようになってきた昨今では、サラリーマンとして企業に勤めながら、それとは別に副業を行っている方も少なくありません。
中には、いっそのこと脱サラして開業を目指そうと考えている方も多いのではないでしょうか。しかし脱サラして開業するというのは人生における一大決心なので、判断は難しく、いざ脱サラして開業する場合の仕事の選び方や、おすすめの業種などについても知っておきたいところです。
この記事では、脱サラして開業することのメリット・デメリットや、脱サラして開業する仕事の選び方、必要な事前準備などについて説明します。脱サラして開業を目指している方は参考にしてください。
関連記事 会社員が開業するには?会社にバレる?メリットや開業届の書き方をご紹介
関連記事 脱サラとは?メリットやデメリット、成功のポイントを解説
関連記事 脱サラしたい人が知っておくべき知識を総まとめ!注意点やおすすめの職種とは?
目次
そもそも脱サラとは何のこと?
脱サラとは「脱サラリーマン」の略で、勤めている会社を辞めて自分で事業を行うことを指す言葉です。
自分で事業を行う際の形態としては、個人事業主やフリーランスとして働く、自分で法人を設立するなどのパターンが考えられます。
ただ単に会社を辞めるだけでは「脱サラ」とは言わず、一般的には「自分で事業を行う」までがセットであると定義されています。
脱サラと言うと、ただ単純に退職するのではなく「自分の意思で辞めた」というような、前向きなニュアンスを持つことが多い概念だと言えるでしょう。
脱サラして開業することのメリット&デメリット
脱サラして開業することに夢を持つ方は多いと思いますが、脱サラしての開業にはメリットもデメリットもあります。
メリット
脱サラして開業することのメリットとしては、主に以下のことが挙げられます。
●自由に仕事ができる
●やりがいがある
●収入アップが見込める
●人間関係に悩まされにくくなる
●自分が本当にやりたいことができる
勤めている会社を辞めて自分で仕事を選べるため、自分が本当にやりたいことを自由に行うことができるところは大きな魅力です。
押し付けられた仕事ではなく自分で選んだ仕事なのでやりがいはありますし、決められた枠や範囲の中でしか昇給しないサラリーマンとは異なり、自分の頑張りに応じた分だけ収入アップが見込めるというのも、脱サラ開業のメリットの一つです。
また仕事をする上で付き合う人をある程度は自分でコントロールできるので、人間関係に悩まされにくくなるということも、このストレス社会においては重要なことかもしれません。
デメリット
反対に脱サラして開業することのデメリットとしては、主に以下のことが挙げられます。
●経済的に不安定になる可能性がある
●基本的にすべて自己責任
●最初は社会的な信用がない
●休みが不規則
脱サラして開業すると、仕事をしていれば毎月必ず決められた給料を得ることができるサラリーマンとは異なり、仕事の有無によって収入が大きく変動するため、経済的な不安定さは増すことになるでしょう。
基本的にすべて自己責任のもと判断しなければならないのも、サラリーマン時代とは大きく異なります。
また、事業を始めたばかりのころは社会的な信用がないため、各種ローンやクレジットカードなどに申し込んでも、審査落ちになる可能性が高く、納期に追われて働き詰めになり、休みが不規則になるなど体を壊してしまう可能性も考えられます。
関連記事 脱サラの失敗例3選!起業失敗の原因や成功するためのポイントを解説
脱サラして開業する仕事の選び方
●これまで(サラリーマン時代)の経験を活かした仕事を選ぶ
●資金面を考えて選ぶ
●副業から始めて脱サラに繋げられる仕事を選ぶ
これまで(サラリーマン時代)の経験を活かした仕事を選ぶ
まったく知識がなく門外漢のことを事業として行うより、多少なりとも経験のあることを行ったほうが、成功確率は高くなると考えられます。
つまり、サラリーマン時代の経験を活かせるような仕事や事業を選ぶという観点が重要だと言えるでしょう。
たとえば、サラリーマンのときはSEとして働いていたのであれば、フリーランスのプログラマーとして働くなどの方法がおすすめです。
ただし、基本的に元勤務先で得た人脈などは使えない「競業避止義務」があるため、あくまでも経験が活かせるに過ぎないという点は覚えておいてください。
資金面を考えて選ぶ
開業するには資金が必要なので、用意できる資金という観点から考えることも大切だと言えます。
ここで注意すべきなのが、「単純に初期費用を少なく抑えられるから選ぶ」のではなく、資金の回収期間も考慮して選ぶべきだということです。
資金を早めに回収できる事業であれば、金融機関からの融資金額が多少大きくても返済に関して問題なくカバーできる可能性があるでしょう。
また、今ある貯金額によっても、とれるリスクとリターンのバランスは変わってくるので、資金面に関してGOサインを出すべきかどうかのラインは人により異なります。
副業から始めて脱サラに繋げられる仕事を選ぶ
経験がないことをいきなり仕事として選ぶのは、不安なものです。
未経験のことを今後の事業として検討しているのであれば、サラリーマン時代から副業として挑戦してみて、上手くできそうかを判断するとよいでしょう。
本業にしても問題なさそう、ある程度収入を伸ばせそうと思えるのであれば、脱サラ後にそれを本業として仕事にするというステップを踏むのが、ある意味では理想的な流れです。
なお、本業にする以上、今後はそれをメインにして生計を立てることになります。自分に適しており、この先も長く継続していけそうな仕事かどうかは、しっかり見極めなくてはなりません。
関連記事 サラリーマンにおすすめの副業10選!タイプ別の副業を一覧でご紹介
脱サラして開業するのにおすすめの業種
脱サラを成功させるためには、どの業種を選んで開業するかも重要なポイントです。おすすめの業種としては、主に以下のものが挙げられます。
●パソコンを使う業種
●Web関連の制作職
●スキルを活かす業種
●第一次産業
●フランチャイズ
それぞれの業種について、具体的な内容を説明します。
パソコンを使う業種
パソコンひとつあればできる仕事は、自宅やコワーキングスペースなど働く場所を自由に選びやすく、開業時に必要な資金を抑えやすいというメリットもあります。
主な仕事として挙げられるのは、以下の通りです。
●ライター
●データ入力
●イラストレーター
●アフィリエイト
この業種で開業する場合は一人で仕事を行うケースも多いため、最初は個人事業主かフリーランスとして働くのが一般的です。
Web関連の制作職
オンライン上で何かしらの制作を行う仕事も、パソコンやタブレットなどがあれば以下のような仕事を行うことが可能です。
●プログラマー
●Webデザイナー
●Webエンジニア
●動画編集
これらの仕事には専門的な知識が必要となるため、サラリーマン時代に同様の仕事をしていた方には、とくにおすすめです。
スキルを活かす業種
資格や何かしらのスキルを持っている場合は、そちらを活かした仕事で開業を目指すのもよいでしょう。
●ネイリスト
●美容師
●弁護士
●コンサルタント
●講師
全国どこでも一定の需要があるため、場所を選ばずに仕事ができるところが大きな強みです。
必ずしも資格が必要ではない場合もありますが、資格を持っていることで有利に働くケースもあるため、必要に応じて資格の取得や更なるスキルアップに努めることもおすすめします。
第一次産業
以下のような第一次産業の仕事も、各種セミナーに参加して情報を集めたり、開業の支援を行う各種センターなどのサポートを利用したりすることで、まったくの未経験でも参入可能なケースは多いです。
●農業
●林業
●漁業
ただし、第一次産業の仕事は体力がないと厳しかったり、周囲の同業者とのやり取りが必須であったりすることが多いため、注意しておきましょう。
フランチャイズ
フランチャイズ展開はさまざまな業種で行われていますが、本部のノウハウを利用することができるため、未経験でも開業しやすいというのが大きなメリットです。
フランチャイズ展開を行っている店舗が多い業種としては、主に以下のものが挙げられます。
●飲食店
●コンビニ
●学習塾
●ハウスクリーニング
●マッサージ店
フランチャイズへの加盟を行うと、一定額のロイヤリティを支払う必要があることや、契約期間中は基本的に解約が難しいことなどは念頭に置いた上で、フランチャイズに加盟するべきかどうかを判断しましょう。
脱サラして開業するための事前準備
脱サラして開業を目指す場合、勤めている会社を辞めてすぐに開業するというわけにはいきません。
脱サラして開業する際には、主に以下のような準備を行う必要があります。
●事業計画を練る
●必要な費用を計算する
●資金調達を行う
それぞれについて、詳しい内容を説明します。

事業計画を練る
サラリーマンとして会社勤めをしている間に、脱サラして行う事業についての計画を練っておきましょう。
最初はアイデアベースから始めますが、なるべく具体的な計画を作成するよう心がけ、この段階で詳細な計画を練ることができていれば、今後の段取りが楽になります。
必要な費用を計算する
開業に必要となる費用は、事業内容や事業形態によって変わります。
店舗をどこに構えるか、従業員は雇うか、フランチャイズに加入するかなど、開業に必要な費用に関わってくる要素は、挙げていけばキリがありません。
事業計画をしっかりと練ることができていれば、費用も詳細に見積もることができるでしょう。
資金調達を行う
必要な費用の目安がわかったら、算出した費用をいかにして調達するかを考えます。
自己資金だけで賄えない場合は、金融機関からの融資や補助金・助成金、クラウドファンディングなどを利用することになるでしょう。
金融機関からの融資に関しては、一般の金融機関からの融資と日本政策金融公庫からの融資の2つに大きく分けられますが、開業時には後者を利用するメリットが大きいです。
一般の金融機関の場合、売上などの実績がなければ融資が難しいケースも多いですが、日本政策金融公庫では実績がない場合でも積極的に融資を行ってくれます。
いずれの場合でも比較的低金利で資金を調達することができますが、融資である以上必ず返済しなければならないことは、念頭に置いておきましょう。
補助金や助成金による資金の調達は、融資とは違って返済の必要がないということが非常に大きなメリットです。
補助金や助成金には各々条件が設けられているので、それらをクリアしなければ利用することはできませんが、条件を満たしている場合には積極的に活用するとよいでしょう。
クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数の人から出資による資金調達を行える方法で、こちらも融資ではないので調達した資金に関する返済義務はありません。
ただし、多くの方に魅力を感じてもらえるような事業内容でなければ出資を集めることは難しいので、始める予定の事業内容を客観的に判断し、利用すべきかどうかを検討しましょう。
なお、金融機関から融資を受ける場合は事業計画書が必要になるので、この点においても最初の段階で事業計画をしっかり立てておくことが重要です。
脱サラの心構えと成功するために必要なこと
脱サラすることで成功する人もいれば、会社員時代よりも厳しい生活に陥る人もいます。ひとつだけ言えることは後悔しない選択をすることが大切です。
脱サラ開業するときは、ネガティブな感情や勢いで行うのではなく何をしたくて会社員を辞めるのか、開業する理由を明確すると良いでしょう。開業してすぐに経営が軌道に乗るとは限らないため、運転資金や生活費を蓄えておく必要があります。自分だけが得するような目的を優先するよりも、ターゲット層のニーズに合う事業を行うことが脱サラ開業には大切です。
一度はサラリーマンの経験があるからこそ、開業した際に活かせる場面が多くあると思います。現在、会社員として働いている人は、会社員にしかできない経験や学びをたくさん行っておきましょう。
脱サラして開業するのは、夢を仕事にするためにおすすめの方法
脱サラして開業することには、自分の好きなことややりがいのある仕事ができて、収入も増やせる見込みがあるという大きな魅力があります。
その一方で、経済的に不安定になる可能性があることや、サラリーマンと比べると社会的な信用という点で劣ることは否定できません。
ただし、夢として描いていることがあるのであれば、脱サラして開業することはそれを実現できる可能性のある方法とも言えます。
脱サラしての開業を目指している場合には、開業準備の支援を行ってくれるサービスを利用するのもひとつの方法です。
飲食店や美容院などの開業支援をサポートしている「canaeru(カナエル)」では、起業経験者にさまざまな悩みを相談することができます。
不安を解消して前向きな気持ちで開業を目指したい方は、ぜひ「canaeru(カナエル)」の利用をご検討ください。
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。