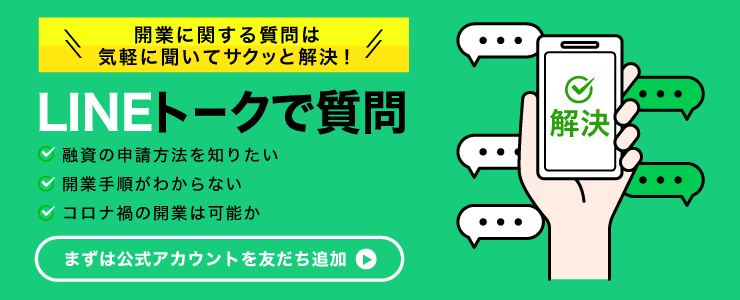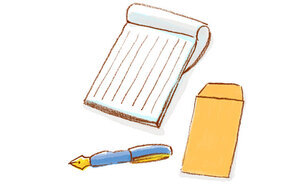- Tweet

自宅の一部を店舗などとして利用する自宅開業。
また、物件を借りないで開業する、プチカフェや週末だけのお店。
自宅開業や、プチカフェ、週末カフェなどは自分の時間を確保しやすいこともあり、開業を志す男性だけでなく子育て中の主婦などからも注目されています。
物件を借りないため、少ない資金で開業できるのが何よりの魅力です。
ここでは、自宅などを利用して開業する時に知っておきたいことなどをまとめてみました。
参考記事:開業とは?起業・独立との違いは?必要な準備についてもわかりやすく解説目次
自宅で開業するメリットとは?
低予算でスタートできる
自宅開業ができるビジネスは、初期費用や維持費を抑えられるものが多く、低予算でのスタートが可能です。資金を準備する必要がないため、初心者でも安心して始められるでしょう。
オフィスの賃料がかからない
自宅で開業できるビジネスは自宅やオンラインで仕事をするため、オフィスを借りる必要がありません。しかし、自宅が賃貸住宅の場合は事務所利用できないこともあるので、家主や管理会社に確認したほうがよいでしょう。
移動時間がかからない
自宅でビジネスができれば、通勤する手間がなくなります。通勤時間を節約できるうえに、満員電車に乗るストレスからも解放されます。交通費もかからないので経済的です。
家事や育児と両立できる
自宅で開業できるビジネスであれば、家事や育児との両立が可能です。家事や育児にも力を入れたい方でもビジネスを続けられます。
落ち着いて働ける
自宅で開業すると、落ち着いて働けるのもメリットの1つです。とくに、1人で黙々と作業することが好きな方にはベストな環境でしょう。最近ではメールやチャット、ビデオ通話ツールで完結できる仕事も多いので、人と対面しなくてもビジネスが成り立ちます。
自宅で開業するデメリットとは?
店舗業の場合、改装が必要になる
もし、飲食店や美容院などの店舗業を始める場合、自宅を改装する必要が出てきます。費用が掛かるのはもちろん、近隣に迷惑をかけないか考えましょう。
例え一軒家であっても、自宅で飲食店を開業する場合、人の出入りやにおいが出るため苦情が入る可能性があります。自宅で店舗業を行うことはリスクが伴うので、あらかじめ把握しておきましょう。
プライバシー対策をする必要がある
自宅で開業する場合、名刺やメールの署名などに自宅の住所を載せる場合があります。もし住所を明かしたくないのであれば、バーチャルオフィスを契約するのも1つの手段です。
バーチャルオフィスのサービスには、住所や電話番号の提供、郵便物の受取・転送などがあるため、個人情報を明かすことなくビジネスができます。
プライベートで人を招きづらくなる場合がある
自宅で習い事教室やエステサロンを開く場合、人の出入りが多く、備品などもあることから、プライベートで人を招きづらくなる可能性があります。同居している家族がいる場合、家族も気苦労する面があるかもしれません。
自宅の雰囲気を壊したくない方はオンラインで開講できる事業にするか、Web、ECサイトの運営やWebライターなど自宅を改装しなくても始められるビジネスを選びましょう。
情報セキュリティが不安
自宅開業は、情報セキュリティが強化された会社勤めと比べると、セキュリティが万全ではないのが難点です。仕事場とプライベートスペースを分けていないと、家族や子どもがパソコンや資料に触ってしまう可能性があります。
家族であっても、ビジネスの情報を漏らすことはご法度。トラブルにつながることもあるのでパソコンや仕事に関わるもののセキュリティは強化しておくとよいでしょう。仕事とプライベートの区別が難しくなる
昼夜や曜日を問わず好きな時間に、好きなだけ仕事ができるため、プライベートの区別がつきづらくなります。仕事場と自宅が同じだとメリハリがつかず、仕事がなかなか終わらないことも。自宅開業をする際は、セルフマネジメントも大切です。
自宅開業におすすめの業種5選
自宅開業におすすめの業種として、以下の5つが挙げられます。
・エステサロン
・学習塾・習い事教室
・Web、ECサイトの運営
・ライター
・家事代行
中でもエステサロンや家事代行は女性におすすめできる業種です。スキルや趣味を活かしながら、自分の裁量で働く時間や場所をマネジメントできるため、上述のように家事や育児との両立や、通勤ストレスの軽減など様々な利点を得られます。
いずれも初期費用を抑えて始められるビジネスです。それぞれの特徴を見ていきましょう。
関連記事:女性の起業におすすめの職種10選!見つける方法や起業方法も解説

1.エステサロン
女性に人気があるエステサロンやネイルサロンといった美容系の事業は、自宅でも開業できます。知識や技術があり、接客できる部屋と施術用のベッドやソファなどの設備を用意できれば開業することが可能です。
知識・技術がない場合でも、スクールを受講する、フランチャイズに加盟する、資格を取得するなどしてスキルを身に付けることができます。
自宅の一室を使用するプライベートサロンのような店舗だと、内装工事をせず設備や備品への投資だけでも開業できるので費用を最小限に抑えることができます。
その他、開業にかかる費用の詳細は以下の記事をご覧ください。
関連記事:開業資金はいくら必要?費用の内訳と調達方法を解説2.学習塾・習い事教室
書道や英語学習などの習い事教室は、人に教えられるスキルとスペースさえあれば自宅で開業できます。好きなことや得意なことをそのまま仕事にできるため、高いモチベーションで働けるでしょう。
最近では、ZoomやGoogle Meetなどを使ってオンラインでも開講できます。自宅に人を入れたくないという方にもおすすめのビジネスです。
3.Web、ECサイトの運営
Web、ECサイトの運営はオンライン上でビジネスを行うので、自宅でも開業できます。サイトの開設や維持費などがかかりますが、比較的費用を抑えて始められるのもうれしいポイント。
「オンライン上で何か販売したい」「Web系の知識やスキルを活かしたい」という方におすすめのビジネスです。
4.ライター
Webライターであれば、パソコンとネット環境さえあればすぐに事業を開始できます。資格も必要ないため、手軽に自宅開業をしたい方におすすめです。
自宅以外でもパソコンとネット環境があれば、カフェや旅行先でも仕事ができます。さまざまな場所で自由に働きたいという方にも向いているでしょう。
5.家事代行
家事代行は、お客様の自宅に訪問して家事全般を代行するサービスです。テナントを借りる必要がなく、近年では共働き世帯や高齢者世帯からの需要が高まっています。
特別な資格や経験がなくても始められるうえに、初期費用もほとんどかからないのがメリットです。手軽に始められるビジネスで開業したい方は、ぜひ検討してみましょう。
開業までに必要な手続・資格
開業するには必要な届出の提出や、業種に応じた資格を取得する必要があります。
業種によっては手続きが煩雑になる場合もありますが、順番にやればとりわけ難しい作業ではありません。
以下の項目を読んで開業までにやるべきことを整理しましょう。
個人事業主の開業は1ヵ月以内に「開業届」を提出する
「開業届」とは、「個人事業の開業・廃業等届出書」の一般的な呼び方です。自宅開業のみならず、開業する際には納税地の税務署への提出が必須となります。
提出は開業から1ヵ月以内と定められており、書類には開業者の氏名や生年月日、個人番号などを記入するほか、屋号や青色申告の承認申請の有無を記載する項目もあります。
開業届の書き方は以下の記事で詳細に説明しています。
関連記事:開業届の必要書類とは?書き方や提出方法をわかりやすく解説
屋号については以下で決める際のポイントを押さえておきましょう。
●屋号を決める際のポイントとは
屋号はお客さまの第一印象を大きく左右するものです。
名前のインパクトが集客にも影響を与えるため、安易な名前づけで簡単には決められません。
では、どのようなポイントに気を付けて決めればいいのでしょうか?ポイントは以下の4つです。
1,事業内容が分かりやすい
看板にお店の名前が書いてあったとしても、何のお店か分からなければお客さまがすぐに足を運んでくれません。カフェであれば「○○カフェ」、美容院であれば「○○美容院」など、事業内容を含む方がより足を運んでもらいやすくなります。
2,覚えやすい
インパクトを与えるためにかっこいい英語の名前を付けても、覚えてもらうことができなければ意味がありません。良いお店と思われても、名前が思い出されないと多くの人へ周知しづらくなります。短くて覚えやすい店名が良いでしょう。
3,言いやすく書きやすい
SNSなどで情報が拡散されやすい時代になっているため、入力しやすい文字、文字数を心がけることも重要です。長すぎる文字やアルファベットとひらがなを両方使う店名は、SNSでの周知に影響します。
4,個性的である
他店と同じ名前では差別化を図ることができません。ネット検索では、同じ名称でもアクセス数の多い店の方が上位に表示されます。自分のお店が他店に埋もれてしまう場合があるのです。個性的でオリジナリティ溢れる店名をつけましょう。
青色申告と白色申告、どちらがいいの?
「開業届」提出時に、確定申告方法も決めておきましょう。
青色申告では、帳簿のレベルに応じて最大55万円の特別控除が得られ、条件次第では65万円の控除も可能です。
青色申告を選ぶ場合は、税務署に開業から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。開業準備で忘れがちになるため、開業届と一緒に提出することをおすすめします。
白色申告は控除などはありませんが、利点がないわけではありません。双方のメリットとデメリットを理解し、確定申告を検討することが重要です。
白色申告のメリットとデメリット
白色申告は以前は帳簿の義務がなく、業務負担を軽減するために選ばれていましたが、現在は帳簿が必要となっています。それでも白色申告は簡単な簡易簿記を使用し、複式簿記である青色申告より業務負担が少ないというメリットは健在です。また、青色申告のような事前の申請手続きが不要で、柔軟な申告が可能です。
一方、白色申告のデメリットは特別控除の適用ができないことと、赤字の繰越ができないことなどが挙げられます。赤字を黒字に転換した際や交互に赤字と黒字を繰り返す場合には、青色申告よりも税負担が増える可能性があることは留意しておきましょう。
青色申告のメリットとデメリット
青色申告の最大のメリットは冒頭でも触れた特別控除が受けられることにあります。確定申告書と貸借対照表、損益計算書を提出することで最大55万円の特別控除が受けられ、電子帳簿保存やe-Taxによる電子申告を行うと最大65万円の控除を受けられます。その他にも、家族への給与を全額経費として計上できる、30万円未満の減価償却資産を経費として計上できる、赤字を3年間繰り越せるなどといったメリットもあります。
デメリットとしては、事前の届け出や、最大65万円の特別控除を受けるには複式簿記での記帳が必要な点が挙げられます。複式簿記は初心者には難しいかもしれませんが、その場合は会計ソフトを使用したり、税理士に依頼したりして対処しましょう。なお、提出期限内に申告しなければ、特別控除は最大10万円に制限されます。
例えば、雑貨屋を開業する際に、特に注意したい届け出とは?
●中古品やアンティーク雑貨を扱う場合に必要な「古物商許可申請」
アンティーク雑貨や古着、古本、リサイクル品などを販売する場合は「古物商許可申請」の手続きが必要です。
申請はお店の所在地を管轄する警察署の防犯係で行います。
申請費用は1万9千円で、許可をもらうのに40日程かかります。
また、申請の際には身分証明書や住民票などさまざまな書類の提出も必要です。無許可で古物の売買を行うと「懲役3年または100万円以下の罰金」が課せられます。簡単そうに見えて課題も多い、自宅を利用したカフェ開業
自宅の一角を利用して飲食店を開く方が増えています。その中でもカフェは特に人気が高く、初期費用を抑えられる点や、営業時間を柔軟に決められることが理由として挙げられます。
また、テイクアウト主体の専門店もコロナ禍を経て需要が高まっている業態です。小規模スペースで始められ、内装や席数にかかる設備費用や備品購入費用が比較的安価であるという利点があります。
ただし、個人で飲食店を始めるには、開業届の提出に加え、飲食店営業許可や食品衛生責任者の資格を得なければなりません。これらの資格を得るにはいくつかの基準と手順を満たす必要があります。それぞれ以下で解説していきます。
●自宅カフェ開業には地域の保健所の許可が必要
カフェの開業には「飲食店営業許可」が必要です。
地域の保健所で申請しますが、まず店舗が許可の基準に達しているか、保健所の調査があります。
保健所によって違いがありますが、主な基準は以下の通り。
・調理場が仕切られていること
・シンクが2槽以上あること
・給湯設備があること
・食器棚に扉がついていること
●「食品衛生責任者」の資格は講習で取得できる
営業許可を申請するには、お店の衛生面を管理する責任者、「食品衛生責任者」の資格を持つ人が1名必要です。
調理師や栄養士の資格がなくても、食品衛生協会が行っている講習を修了すれば1日で取得できます。
また、「食品衛生責任者」とよく似た「食品衛生管理者」という資格もあります。
こちらは、「特に衛生上の考慮を必要とする食品」の製造・加工の過程において、全ての施設に配置しなければならない国家資格です。
取得は食品衛生責任者よりはるかに難易度が高いですが、飲食店経営に必ず必要な資格ではありません。
関連記事:飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解説
関連記事:資金ゼロからのカフェ開業!ゼロから資金を集める方法を徹底解説
自宅で開業する際はメリットとデメリットを必ず把握しましょう
自宅で開業する最大のメリットは、コストを安く抑えられることです。物件探し、内装工事などの時間・費用も節約できるので、準備を始めてから開業までの時間も短縮できます。
その一方で、仕事とプライベートの境界があいまいになり、モチベーションの維持が難しくなる可能性も。また、改装した部分を元に戻すことが難しい点や、場合によってはご近所トラブルを招いてしまう恐れも考慮しておかなければなりません。
もし、自宅開業の事業計画や内装など開業までの流れで不安がある方は『canaeru』の無料開業相談をご利用ください。事業計画書の作成サポートや内装業者の紹介を無料で実施しています。
開業の無料相談はこちら
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- Tweet
-

- NEW最新記事
-
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
- おすすめ記事
-
-
2016/12/21
-
2022/04/12
-
2016/12/01
-
2017/08/24
-
2019/01/15
-
2018/08/24
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

※見逃し配信【第4回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|客席…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数8,015件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数690件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数143件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数483件
-