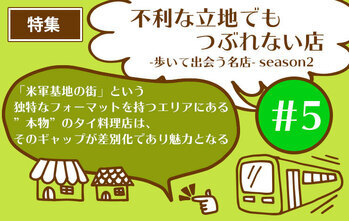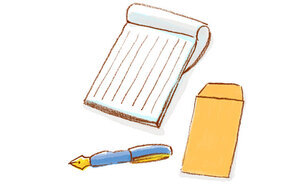- Tweet

個人事業主として事業を行うためには開業届を提出する必要がありますが、事業を行っている間に引越しを行うことも考えられます。
開業届には事業を開始した時点での住所を記載して提出しているため、引越したあとには記載されている内容と実態が食い違ってしまうこともあるでしょう。
このようなケースにおいて、「住所変更した開業届を改めて変更すべきなのか?」と迷っている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、引越しを行った際に開業届を再提出する必要があるのかについて、ケースごとに紹介します。開業届以外に提出が必要になる書類やそれらの提出方法についても説明するので、引越し予定がある個人事業主の方はぜひ参考にしてください。
※記事上の「開業届」とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、開業時に提出したものと同一の様式のものです。目次
個人事業主の引越し・住所変更・転居に必要な手続き
個人事業主の引越し・住所変更・転居に必要な手続きには、主に以下のようなものがあります。
①税務関連の手続き
●開業届の提出
●所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書(必要な場合)
②社会保険関連の手続き
●国民年金の住所変更
●健康保険、労働保険など各種保険の住所変更
③その他の手続き
●各種許認可申請書の所在地変更
●取引先への住所変更の連絡
●名刺や広告媒体等での住所変更
ただし、上記はあくまで一般的なケースです。必要な手続きは、どのような引越しや住所変更なのかによって少しずつ異なります。以下では引越しや住所変更をケースごとに分けて、それぞれで必要な手続きを解説していきます。個人事業主の納税地に異動又は変更があった場合の手続き
個人事業主の納税地に異動又は変更があった場合とは、具体的に以下のケースなどがあります。
●引越しなどで、納税地の住所地が異動になる場合
●納税地を住所地から居所地に変更する場合
●住所地とは別に事業所等を構えて、そこを納税地に変更する場合
●居所地もしくは事業所等から住所地に納税地を変更する場合
など
【手続き】
納税地の異動又は変更があった年分の確定申告書に異動又は変更後の納税地を記載します。
(令和5(2023)年1月1日以後に異動又は変更がある場合は「納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出は不要となりました。)
送付物などを変更後の納税地に送付してもらう場合は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を税務署に提出することで、年の途中でも送付物先を異動又は変更後にすることができます。引続き振替納税を利用したい場合
納税地を異動又は変更した年分の確定申告書の第1表にある「振替継続希望」に○を付けると、引続き振替納税を利用することができます。
個人事業主の納税地について
納税地は以下のようなケースが挙げられます。
1.住所地である自宅を納税地とする
2.住所地以外の居所地を納税地とする
3.住所地や居所地があるが、他に事業所等がある場合に事業所等を納税地とする
個人事業主の納税地は、原則住民票のある住所地ですが、上記のように任意の所在地を納税地にすることが可能です。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の提出は必要?
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出は、給与等の支払いを行う事務所等を移転(または廃止)した場合に、提出が必要な書類です。給与支払事務所等の所在地の所轄税務署に、事務所を移転してから1ヶ月以内に提出する必要があります。ただし、開業届に給与の支払い状況などを記載した場合は、提出する必要はありません。
個人事業主の住所変更の年金・保険に関する手続きについて
健康保険や厚生年金、労働保険といった社会保険についても、事務所等の所在地を移す場合には、手続きが必要です。各機関に定められた期間内に各届出書等の提出をしてください。
個人事業主が海外へ引越し・住所変更・転居する場合の税務手続き
海外に引越して、生活の拠点が海外となり、引越し後に日本に税金を払う必要がない場合については、次の手続きが必要になります。
●個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
●所得税の青色申告の取りやめ届出書
●出国をする年の1月1日から出国時までの期間について、確定申告の必要がある場合には、準確定申告書の提出
※詳細については、税務署等にお問い合わせ下さい。
提出場所はいずれも、納税地を所轄する税務署です。《事業状況別》必要な手続き一覧
この項目では、主な手続きについて、ケースに分けて紹介します。

1:自宅(住所地)を納税地としている場合
●自宅を引越しなどで異動した場合は『開業届』を提出
2:事業所等を納税地としている場合
●事業所の移転などで異動した場合は『開業届』を提出
●事業所の住所は変わらず、自宅のみの引越の場合は一般的な転出入届のみ行う
以下は1と2のケースを踏まえての具体例です。
例①)事業所等が移転するが住所地は変わらない場合
●住所地を納税地としている場合は手続き不要
●事業所等を納税地としている場合は『開業届』を提出
例②)住所地は移転するが事業所等は変わらない場合
●住所地を納税地としている場合は『開業届』を提出
●事業所等を納税地としている場合は手続き不要3:振替納税を利用している場合
●引続き振替納税を利用したい場合は、変更等のあった年分の確定申告書の第1表の「振替継続希望」に○を付けて提出
●口座の変更等をする場合は、改めて「預金口座振替依頼書」を提出4:海外に引越し日本で納税しない場合
●『個人事業の開業・廃業等届出書』を提出
●『所得税の青色申告の取りやめ届出書』の提出
●出国をする年の1月1日から出国時までの期間について、確定申告の必要がある場合には、納税地の所轄の税務署に準確定申告書の提出
●そのほか、状況に応じて『事業廃止届出書』などを提出。健康保険・厚生年金保険などの資格喪失手続きも必要個人事業主が開業後に開業届を提出する場合の注意点
個人事業主が開業後に開業届を提出する必要がある場合はどのようなケースでしょうか。
●納税地の異動又は変更の場合
●事業所等の新設・増設・移転・廃止があった場合
●所得の種類(不動産所得、事業所得など)に変更があった場合
●事業を廃業した場合
など
一方で、以下のような場合は開業届の提出は不要です。
●個人の氏名変更(結婚・離婚など)
●開業時に記載した所得の種類(事業所得、不動産所得など)内での新規事業を始める場合
例)事業所得である建設業を営んでいたが、新規事業として飲食業であるカフェをはじめた場合
など
個人の住所変更のみや新規事業の開始では、開業届の提出は不要となります。
このように、事業活動に影響のある変更があった場合にのみ、開業届の提出が必要になるのが一般的です。個人事業主が引越しを行う際、事業所等がある場合は、納税地を自宅(住所地)にするか事業所等にするかは、事業上都合の良い場所を選択し、適切な手続きをするようにしましょう。
開業届の再提出期限を過ぎても提出できる?
開業届の提出の期限は、異動又は変更から1ヶ月以内と定められていますが、期限を過ぎたからといって罰則はなく、提出はいつでも可能です。 提出を忘れていた場合は、速やかに所轄の税務署に提出をしましょう。
個人事業主の引越し代は経費にできる?
業者に依頼して引越しを行う際には引越し代がかかりますが、この引越し代を経費にできるかについては、個人事業主が納税を考える上での大きな問題です。
事業に関わる支出は経費計上できるので、住居と事務所が独立しておりその事務所が引越しを行う場合には、すべて経費計上することができます。住居兼事務所から事務所だけが引越すという場合も同様です。
住居兼事務所のまま引越しをするケースでは、引越し代全額を経費計上するわけにはいかず、家事按分して事業部分について経費計上しなくてはなりません。
引越しにかかった費用をどのような勘定科目として計上するかに関しては、引越し業者に支払った費用は雑費、不動産会社に支払った仲介手数料は支払手数料とするのが一般的です。
起業のお悩み相談はcanaeruへ
個人事業主の住所変更に伴う必要な手続きについて解説してきましたが、手続きのタイミングや手順を把握するのは簡単ではありません。
必要な手続きを忘れてしまうと、その後の経営にも影響を与える可能性があるため、手続き面に不安がある方は、開業支援サービスを利用してみるのはいかがでしょうか。
無料で開業や経営に関する相談を行える『canaeru(カナエル)』では、開業時や住所変更時に必要な手続きなどに関するサポートを受けることもできます。
開業に向けて心強いサポートをお求めの方は、ぜひcanaeruの利用を検討してみてください。まとめ
個人事業主が引越しや住所変更をする場合、状況に応じて開業届など必要な書類を所轄の税務署に提出する必要があります。移転などの際には事業のことばかりに目が向いてしまい、書類などの届出を怠ってしまうことも珍しくありません。
しかし、必要な手続きをしないままでいると、確定申告が正しく行えない可能性があるほか、従業員にも悪影響を及ぼしかねません。
店舗や事業所の住所が変わる際には、余裕を持って必要な届出を準備し、ゆとりをもって手続きを行うことを心がけましょう。
- NEW最新記事
-
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
- おすすめ記事
-
-
2024/04/25
-
2022/03/30
-
2022/08/16
-
2023/02/07
-
2017/11/14
-
2021/05/10
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

※見逃し配信【第4回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|客席…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数8,283件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数687件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数143件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数483件
-