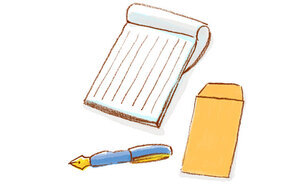- Tweet

「売上を上げるために努力しているけど、思うように利益率が伸びない。」飲食店を経営されている方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
売上高に対して利益が占める割合を示す「利益率」は、飲食店経営の成否を分ける重要な指標です。いかに利益率を上げられるかによって、経営者としての手腕が問われると言えるかもしれません。
この記事では、利益率の相場や計算方法、効率よく利益率を向上させる方法など、飲食店の経営における基礎やノウハウについて詳しく解説します。
これから飲食店を開業しようと考えている方や、利益率が伸びずに悩んでいる経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事:居酒屋の利益率とは?利益率の計算方法や居酒屋の平均利益率、利益率の高いメニューを解説!
目次
飲食店の利益率の相場は?
最初に、飲食業界全体の利益率の相場について紹介します。
経済産業省が発表した「商工業実態基本調査」によると、飲食業界全体における利益率の平均は「8.6%」です。
また、飲食店の利益率は10%〜15%あるのが理想とされますが、繁盛店の中には利益率が30%を超えているところもあります。
これから飲食店を開業する方は、まずは平均値である利益率8.6%を目安に営業をするとよいでしょう。利益率が安定して8.6%を超えるようになってきたら、次は目標値とされる10%〜15%を目指すといったように、段階的に目標を引き上げていきましょう。
ただし、ひと口に飲食店といっても、レストランやカフェ、バーや居酒屋など、業態によって利益率の目安が多少異なることを覚えておいてください。
引用:経済産業省「商工業実態基本調査」業態別の利益率の相場は?
大企業を含めた飲食店全体の利益率の平均は8.6%ですが、次に小企業の業態別利益率の相場を見てみましょう。日本政策金融公庫が2020年に発表した「小企業の経営指標調査」の飲食店・宿泊業版によると、飲食業態の業態別利益率は以下の通りです。
業態 利益率 一般飲食店 3.2% 食堂・レストラン 3.0% 日本料理店 3.2% 西洋料理店 2.9% 中華料理店 3.2% 韓国料理店 2.8% カレー料理店 1.7% そば・うどん店 6.0% すし店 3.1% 喫茶店 2.7% スナック 5.2% 酒場・ビヤホール 2.9%
※売上高営業利益率から抜粋
※利益率は黒字かつ自己資本プラス企業の平均です
回転率の高い「そば・うどん店」は利益率が6%と高く、輸入食材の多いカレーや韓国料理店は1~2%台と低い水準であることがわかります。
参考:小企業の経営指標調査|日本政策金融公庫
関連記事:ラーメン屋の利益率とは?原価率や経費についても解説!
飲食店にかかる経費の内訳
飲食店経営にかかる経費は「変動費」と「固定費」の2種類に分けられます。変動費と
は売上の変動によって金額が変わる経費、固定費とは売上の変動にかかわらず金額が変わらない経費をいいます。
具体的な経費項目の一例と、割合の目安は以下のとおりです。内訳 目安
変動費 原材料費 30%
人件費(パート・アルバイト) 10%
水道光熱費 5%
販売促進費 2%
消耗品費 3%
固定費 家賃 15% 人件費(正社員) 20%
償却費・借入返済 5%
利益 10%
これらの経費は飲食店を経営していく上で必要なランニングコストです。営業利益は10%以上を確保するのが理想とされているため、その点を意識しながら経費の割合を組み立てていくことをおすすめします。目安として、原材料費(FOOD)と人件費(LABOR)を合わせたFL比率を60%程度に抑えることを目指しましょう。
飲食店の利益率の計算方法
そもそも利益率とは、売上高に対して利益がどのくらいの割合を占めるのかを表す指標で、別名「営業利益率」とも呼ばれます。
利益率を算出するには、まず「粗利(売上総利益)」と「営業利益」という2つのワードについて知る必要があります。
利益率の計算方法
売上高に対する営業利益の割合を示す「利益率」は、計算式で表すと以下のようになります。
【営業利益率(%) = 営業利益 ÷ 売上高 × 100】
たとえばひと月の売上高が500万円で、売上高から家賃や食材費などのコストを差し引いた営業利益が50万円だった場合、利益率は「50 ÷ 500 × 100 = 10」で10%となります。
月に500万円の売上があっても、手元には50万円の利益しか残らないということに驚く方もいるかもしれません。しかし、飲食業界では10%という利益率は平均(8.6%)を超えており、実際にはそれよりも低い利益率のお店のほうが多くなっています。
一般的に、飲食業は他の業種よりもランニングコストがかかりやすいため、利益が出にくい(利益率が低い)といわれています。
こうした現状があり、飲食店の経営者は売上アップの施策を考えて競合店と差別化を図ったり、徹底した経費削減を実施するなどして、少しでも利益率を伸ばす努力を行っているのです。
利益が出ない場合に考えられる要因
飲食店経営においてなかなか利益が出ない場合は、以下のような要因があると考えられます。
回転率が悪い
飲食店における回転率とは、お客様の人数を客席数で割った比率をいいます。基本的に回転率が上がるほど売上も高くなるため、利益が出ない場合は回転率が悪いことが一つの要因として考えられます。飲食店で回転率を上げるには、料理の提供時間を短くする、注文や会計をスムーズに行うなどの工夫が必要です。
原価(食材費)が高い
利益が出ない場合は、原価(食材費)を見直していく必要があります。開業当初は原価率を上げてでもコストパフォーマンスを重視する傾向がありますが、すべての商品を高原価率にすると経営が立ち行かなくなってしまいます。お客様を呼び込むための集客商品を設定するのであれば、それと合わせて注文していただける高収益商品(=原価の低い商品)も考えておくことが大切です。
人件費をかけすぎている
原価と同様に、人件費も高くなりやすい経費項目の一つです。飲食店に適正な従業員の人数を把握するには、売上高を総労働時間で割った「人時売上」を用いるとよいでしょう。人時売上とは従業員1人あたりが1時間にどのくらい売り上げたか表す指標であり、飲食店の場合は4,000〜5,000円程度が目安となります。目標とする金額を割り込んだ場合は、労働時間の見直しやシフトの調整を検討しましょう。
飲食店の利益率を上げる5つの方法
飲食店の利益率を上げるには、主に以下5つの方法があります。
①食材費を見直す
②食品ロスを減らす
③高利益メニューを考案する
④回転率を上げる
⑤人件費を抑える
それぞれどのような内容なのか、順番に説明していきます。

利益率を上げる方法①「食材費を見直す」
高額な食材費が原因で売上が伸びないとしたら、仕入先を変えることで問題が解決する可能性があります。
たとえば食材の仕入先を、近所のスーパーからより安く購入できる業務用食材店に変えることで、仕入れ原価は抑えられるでしょう。
食材費は毎日かかる費用なだけに、できるかぎり安く抑えたいところです。食材費の高さが経営を圧迫していると感じたら、一度仕入先を見直してみるとよいかもしれません。
利益率を上げる方法②「食品ロスを減らす」
料理の食べ残しが多かったり、食材を仕入れすぎて消費期限内に処理できなかったりすると、その分経費が増えて利益率の低下につながります。
まだ食べられる食品を無駄にしてしまうことを「食品ロス」といいます。農林水産省の発表によると、平成30年度の日本の食品ロスは推計600万トンで、そのうちの19%にあたる116万トンが外食産業による廃棄とされています。
こうした食品ロスを減らすには、「在庫管理を定期的に行う」、「オーダーミスをなくす」、「ロスの出にくい冷凍食品を活用する」などの方法が効果的です。
出典:農林水産省「食品ロスとは」
利益率を上げる方法③「高利益メニューを増やす」
原価が低く、利益を出しやすいメニューを増やすことも利益率の向上に効果的です。
売値に対する原価の割合を示す「原価率」は、低ければ低いほど一品あたりの利益が大きくなります。メニューを考案する際は、原価率が低いフライドポテト・枝豆・ポテトサラダ・サワー系の酒類などの商品を増やすことで、利益率を上げられるでしょう。
ただし、メニューに原価率が低い商品しかないと、お客様から「このお店はコスパが悪い」と思われてしまい、お店の評価が下がってしまう危険もあります。
そうした事態を避けるためにも、高利益メニューだけでなく、儲けにつながりにくくても集客効果が高い「目玉商品」をバランスよく混ぜることが大切です。
利益率を上げる方法④「飲食店の回転率を上げる」
客単価が高い高級店は別ですが、一般的な飲食店では、回転率を上げることも利益率を上げるために欠かせません。
回転率を効率よく上げるには、客層に合わせて店内のレイアウトを変えることがおすすめです。
たとえば、1人での来店者が多い飲食店はテーブル席を少なくし、代わりにカウンター席を増やすことで店内のスペースを有効活用できて、回転率のアップにつながります。
利益率を上げる方法⑤「人件費を抑える」
飲食店を経営するうえで、食材費と並んでコストがかかるのが人件費です。利益率を上げるには、人件費を抑えることも重要になります。
ただし、人件費を抑えるために従業員の給与を下げるのは得策とはいえません。飲食業界は、ただでさえ人手不足が深刻といわれています。給与の低下などの待遇面の悪化は、人材流出の原因になりやすいため注意が必要です。
人件費を削減させるには、お店が空いているアイドルタイムは従業員を少なくするなど、時間帯に合わせてシフトを調整するのが有効です。
損益分岐点の計算も重要
飲食店の売上を黒字化させるには、利益率以外にも覚えておくべき指標があります。
その中でも代表的な指標である「損益分岐点」と「FL比率」について解説しましょう。
損益分岐点の計算方法
損益分岐点とは、「売上と費用がちょうど等しくなる点」を指します。
つまり損益の分岐となるポイントのことで、売上が損益分岐点を上回れば黒字、下回れば赤字となります。
飲食店のオーナーは、最低でも売上が損益分岐点を下回らないように経営しなくてはいけません。毎月のように売上が損益分岐点を下回るようであれば、いずれお店は閉店へと追い込まれてしまうでしょう。
損益分岐点は、以下の計算式で求められます。
【損益分岐点 = 固定費 ÷{ 1 − (変動費 ÷ 売上高)}】
たとえば、ひと月の売上高が400万円、固定費が120万円、変動費が100万円の場合、損益分岐点は以下の計算式となり、その月は160万円以上を売り上げないと赤字ということになります。
120 ÷ { 1 – (100 ÷ 400) } = 160万円
計算式からもわかる通り、損益分岐点を下げるには固定費を抑えるのが効果的です。先ほどのケースでは、固定費が90万円であれば損益分岐点は120万円まで下がります。
固定費の中でも、とくに大きなウエイトを占めるのが「家賃」です。飲食店にとって立地は重要ですが、家賃が高額であればそれだけ損益分岐点が高くなるため注意が必要です。
飲食店の中には固定費を削減するために、住居の空いているスペースを活用して営業を行うところもあります。そうすることで、毎月の家賃が発生せず損益分岐点が低くなり、売上高が通常より低くても黒字化できるのです。
家賃を抑える
経費を抑えて利益を確保するためには、「固定費」を安く抑えることが重要です。なかでも家賃は固定費の大半を占めるため、開業時の物件選びは利益率を大きく左右する事項といえます。飲食店は一度開業してしまうと、物件を変えることは難しい業種です。開業前の物件選びでは、お店の業態・コンセプト・ターゲットにあわせて、経費を圧迫しない物件を選ぶようにしましょう。開業後に家賃を抑えたいと考えた場合は、家賃交渉をする、営業時間を伸ばす、店舗の間貸しをして家賃比率を下げるなどの工夫を行ってみましょう。
関連記事:飲食店の家賃相場はどのくらい?開業するなら知っておくべき売上との関係性
FL比率
FL比率は、売上高に占める食材費(Food)と人件費(Labor)の割合を示す指標です。食材費と人件費を合わせたコストのことを、「FLコスト」と呼びます。
飲食店の経営を成功させるには、食材費と人件費を安く抑えなくてはいけません。FL比率は、この2つの費用が売上高に対してどのくらいの比重を占めるのかを確認する際に使用します。
計算式で表すと、以下のようになります。
【FL比率(%) = (食材費 + 人件費) ÷ 売上高 × 100】
たとえば、売上高が300万円、食材費が100万円、人件費が50万円のお店の場合、FL比率は次のようになります。
(100 + 50) ÷ 300 ×100 = 50(%)
一般的に、FL比率は60%未満に抑えるのがよいとされているようです。このお店の場合、FL比率が50%なので、FLコストは低く抑えられているといえるでしょう。
参考記事:飲食店のFL比率(FLコスト)とは?計算方法や数値の目安を解説
飲食店経営を成功させるには利益率アップが必須
どのくらいの利益率があれば飲食店の経営がうまくいくのか、きちんと把握することはとても重要です。
利益率を上げるには、売上を上げるのはもちろん、余計なコストを減らせるよう心掛けましょう。とくに、費用の中でも高額になりやすい家賃・原材料費・人件費の3つをいかに抑えられるかがポイントになってきます。
この記事で紹介した5つの方法は、お金をかけずに今すぐ実践できるものばかりです。利益率が伸びずに悩んでいる飲食店オーナーの方はもちろん、これから開業しようとしている方も、ぜひ参考にしてください。
関連記事「オーバーポーション」が原価率に影響?原価率の知識不足で閉店も!
関連記事:焼肉屋の利益率はどう上げればいい?儲けるためのポイント、利益の事例も解説経費の削減・利益率アップの相談はcanaeruへ
canaeruでは、日本政策金融公庫や銀行出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーなど、飲食店経営に関する経験を積んだ開業コンサルタントが無料開業相談を実施しています。経費の削減・利益率アップにお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。担当コンサルタントが誠心誠意アドバイスいたします。
無料開業相談はこちら
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- Tweet
-

- NEW最新記事
-
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
- おすすめ記事
-
-
2022/01/30
-
2017/10/30
-
2019/07/26
-
2018/08/03
-
2024/05/20
-
2018/11/30
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

※見逃し配信【第4回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|客席…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数8,015件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数690件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数143件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数483件
-