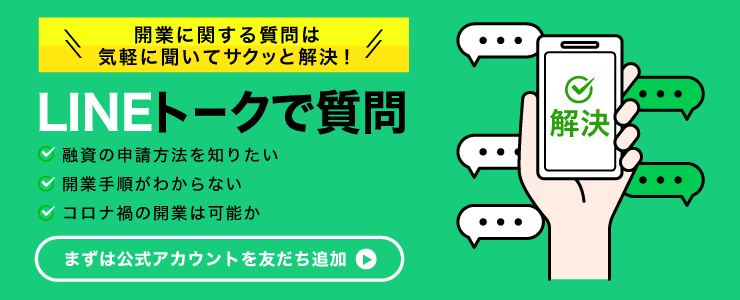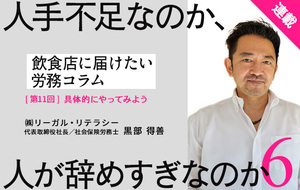- Tweet

お弁当販売を取り入れる飲食店が近年増えています。新規顧客の獲得、利益アップなど十分なメリットが期待できるお弁当販売を今回は徹底解説。どのような営業形態があるのか、許可や資格、食品表示など事業を新たに始めたい方向けにお弁当販売の基礎知識をご紹介します。
目次
お弁当を販売する営業形態3つ
お弁当を販売するための営業形態には大きく分けて3つ。「店舗型」「宅配型」「移動販売型」があり、それぞれには次のような特徴があります。

店舗型
特定の場所に店舗を構え、お弁当を調理、販売するスタイル。調理施設を別に持ち、店舗では販売のみのスタイルもあります。
店舗型では直接お客様に足を運んでもらう必要があるため立地が重要です。ただし、人通りが多い路面の店舗を借りようとすると家賃が高くなる傾向にあり、初期費用もそれだけ高額になる場合もあります。
開業時の準備や物件選びの詳細については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解説
宅配型
注文を受け、弁当を直接お客様に届けるスタイルです。販売スペースが不要で、店舗型よりも省スペースで開業できるのがメリット。さらに、店舗への集客が不要で、立地を気にする必要もないため、家賃などを抑えられます。しかし一方で、宅配のための車両や、宅配業者との提携のための手数料といった費用がかかってくるので注意しましょう。
キッチンカー型(移動販売型)
キッチンカーなど、調理設備を整えた車でお弁当の販売を行うスタイルです。固定の店舗が不要なので、初期費用を安く抑えられます。イベントへの出店やオフィス街での販売など、好きに販売場所を変えられるので、新規客を獲得しやすいのが特徴です。
キッチンカーでの開業について、一から知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
関連記事キッチンカー(移動販売)で開業するには?資格や許可・費用をまとめて解説!
お弁当を販売するには許可が必要
お弁当を販売するには、保健所などから許可を得なければなりません。お弁当販売に必要な許可は、営業形態によって異なります。
お店が取り組む形態に応じて、必要な許可を取得しましょう。代表的なものは「飲食店営業許可」や「そうざい製造業」「食品の冷凍業又は冷蔵業」などです。
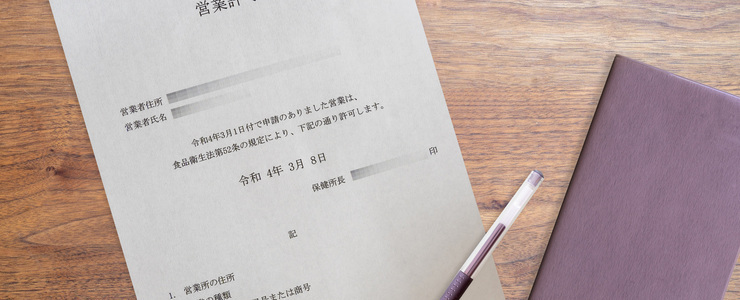
飲食店営業許可
お弁当販売のみを行う店舗でも、飲食店に分類されるため飲食店営業許可が必要になります。以下の手順を参考に、飲食店営業許可を取得しましょう。
1. 営業する地域の保健所を訪問し、必要な書類や手続きについての詳細情報を入手する
2. 店舗が決まったら、保健所の定めた衛生的な要件を満たせる店舗設計を行う
3. 店舗が完成する10日前までに、担当の保健所へ必要な書類を提出する
4. 書類が受理されると、保健所の職員による施設の立入り検査が行われる
5. 立入り検査で問題がなければ、飲食店営業許可が交付される
保健所への書類提出から営業許可の交付までは約3週間ほどですが、保健所の要件をクリアする店舗を設計するところから考えると数か月かかることも。物件を決めた段階で保健所に相談へ行くとスムーズに進むので、前もって準備を始めましょう。
お弁当をネットで販売する際に必要な許可
お弁当をネットで販売する際には、飲食店営業許可に加え、食品衛生法に基づく食品製造業の許可が必要です。お弁当は食品であり、その製造・販売を行う際には食品の安全性を確保するための基準が求められます。販売するお弁当の内容に応じて、「そうざい製造業」や「食品の冷凍業又は冷蔵業」などの資格を取得しましょう。
また、ネット販売の際は食品表示基準に定められた項目の表示が義務付けられているため、ラベルに商品の情報を記載し、外袋等に貼り付けて販売する必要があります。
<ラベル表示の例>
・名称
・原産地
・原材料名
・アレルゲン
・遺伝子組み換え表示
・内容量
・賞味期限
・事業者の名称及び所在地
栄養表示は任意となっていますが、可能であれば表記したほうが信頼性の向上に役立つでしょう。
キッチンカー型の場合チェック項目が異なる
キッチンカーで開業する場合も、飲食店営業許可の申請手順は店舗と同様です。しかし、チェックされる項目が異なるため、事前に違いを把握しておいたほうがよいでしょう。
キッチンカー型の場合に、主にチェックされる項目を以下の表にまとめました。キッチンカーで開業する場合は参考にしてください。
衛生環境 ・キッチンカー内が清潔に保たれているか
・床、壁、天井などの材質が食品を取り扱うのに適切で、清掃しやすいか食材の保管 ・冷蔵/冷凍設備が適切に備えられているか
・食材の保存方法や取り扱いが適切であるか換気設備 調理時の煙や臭いを適切に排出できる設備があるか 水道・排水設備 ・十分な量の清潔な水を確保できる設備があるか
・使用済みの水を適切に排水できるシステムがあるか手洗い設備 ・調理者が手を適切に洗える設備が整っているか。
・手洗い設備の近くに石鹸や消毒液、ペーパータオルなどが置かれているか廃棄物の処理 調理廃棄物やゴミを適切に保管・処分できる設備や方法が確立されているか 調理器具・機器の管理 ・調理器具や機器が清潔に保たれているか
・使用後の洗浄方法が適切であるか
自宅をお弁当屋にする場合、保健所の審査が厳しい
自宅でお弁当屋を開業する場合、自宅が住居専用地域だと、店舗の床面積に制限が生じるケースがあります。また、一般家庭用のキッチンでは保健所の基準をクリアできない可能性が高いため、飲食店営業許可やその他の食品製造業許可を取得するのは困難です。
新たに手洗い場や、水洗いができる床の設置、居住区域と店舗の間に仕切りを作るなど大規模なリフォームが必要になることもあるので注意しましょう。
お弁当を販売するのに必要な資格
お弁当販売を始めるにあたり、営業許可以外にも資格を取得しなければなりません。どちらも前もって準備しなければなりませんが、特に資格に関しては早めに取得しておいた方が安心です。
お弁当の販売には、一般的な飲食店と同様に食品衛生責任者の設置が義務付けられています。一方で、飲食店と同じく調理師免許の取得は必須ではありません。これらの点について、それぞれ解説していきます。
食品衛生責任者
お弁当を販売する店舗には、食品衛生責任者の資格を有した人を必ず1人は配置しなければなりません。食品衛生責任者の資格は、各地域の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者講習会」に参加すれば取得できます。
また、お弁当の販売だけを行う場合でも、食料品等販売業の資格も必要です。食品の種類に応じて必要な資格が異なるのでしっかり確認しておきましょう。
食品衛生責任者や調理師免許についてはこちらの記事でも解説しています。
関連記事カフェ開業に調理師免許はいらない…必要な免許2点と手続き6点
調理師免許は必須ではない
お弁当を販売する上で、調理師免許は不要です。そもそも調理師免許は、食品や栄養、衛生に関する知識を有することを証明する国家資格です。
食品衛生責任者のように、事業所ごとに設置を義務付けられているわけではないため、調理師免許がないからといって罰則を受けることはありません。
しかし、調理師免許をもっている「調理師」がお弁当を作れば安全性や信頼性が高まり、ブランディング効果も見込めます。調理師免許は必須ではないが、あったほうが良いものと解釈すれば良いでしょう。
お弁当販売に必要な準備
お弁当の販売を始めるには、営業許可や資格のほかに、設備や備品の準備も必要です。ここからは、お弁当屋を開業するのに必要な設備や備品のほか、設置するうえで気を付けることを解説します。
お弁当販売に必要な準備の例
営業に必要な許可や資格の準備とともに店舗を整えていきます。調理設備や器具、冷蔵・冷凍庫などを購入し、適切な位置に設置します。飲食店営業許可を得るために必要な要件を満たせるように、設置箇所を確認しておくとよいでしょう。
店舗が整い始めたら、材料を仕入れるルートやメニューの開発、スタッフの確保にも着手します。どうやってお店を宣伝するか、認知度を上げていくかの広告戦略も考えていきましょう。
お弁当用の容器を購入する
調理した食材を詰めるための容器、割りばしやお手拭きの購入が必要です。容器は料理がこぼれないよう、内容に合わせて選ぶ必要があります。ただし、コスト増につながるため、「容器はなるべく安いものを」という意識も大切です。
容器や割りばしなどの値段についてはこちらの記事で紹介しています。お弁当販売のメリットとは
お弁当販売にはさまざまなメリットがあります。主なメリットとしては次のようなものがあります。
省スペースで営業できる
調理スペース、販売スペースのみで営業ができるので、省スペースで済みます。客席を必要としないので、広い店舗を借りなくて済みます。また弁当宅配をする場合、立地すらも気にする必要がありません。好立地を狙う必要がなくなることで、結果的に家賃を安く抑えられます。
コストカットできる
調理スタッフと販売スタッフのみで営業できるため、通常の飲食店より人件費が安く済みます。お弁当のメニュー数を絞れば、仕入れる食材数も少なくて済むので、食材のロスも減らせるでしょう。加えて、一度に大量の調理をこなせるので光熱費などを抑えることもできます。
座席数に関係なく売上が伸ばせる
飲食店であれば座席数と回転数は売上に直結します。しかしお弁当の販売であれば売上を伸ばす上で、座席数も回転数も気にする必要がありません。一度に受けられる注文数に限界がなく、やり方によっては大幅に売上を伸ばせる可能性があります。
軽減税率の対象となる
通常の店内飲食には10%の消費税がかかりますが、持ち帰り弁当の販売であれば軽減税率の対象となり、消費税率は8%になります。店内飲食よりも安く販売できるので、食事を安く済ませたいと考えているお客様の集客が期待できます。
お弁当を販売する際の注意点とは
メリットも多いお弁当販売ですが、事業を始める際には気をつけるべきポイントがいくつかあります。主な注意点も併せて確認しておきましょう。
衛生管理を徹底する
お弁当販売は店内調理に比べて食中毒のリスクが高い傾向に。そのため、店内調理の時以上に衛生管理に気を配る必要があります。
食中毒予防3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」に加えて「持ち込ませない」という意識を持って細菌の増殖を予防しましょう。
ただ、お店側がどんなに気をつけても、食中毒が発生するリスクはゼロにはなりません。食中毒が一度発生すると、倒産しかねないダメージを負ってしまうかもしれません。食中毒が発生した場合の賠償責任の補償に備えて、保険加入を検討するのもいいかもしれません。
飲食店の衛生管理についてはこちらの記事でも解説しています表示義務を守る
弁当・総菜を容器包装に入れて販売する場合、原則として「名称」「原材料名(食品添加物以外)」、「食品添加物」、「アレルギー物質(遺伝子組み換え食品である旨)」、「内容量」、「消費期限」、「保存方法」、「製造者」を見えやすい場所に表示しなければいけません。ただし、店内調理したものをその場で販売する場合、原材料名等の表示を省略することが可能になります。
表示義務の有無に関わらず、アレルギー食材、消費期限や保存方法について記載する配慮は大切です。大きなトラブルになりかねないリスクを少しでも減らしておきましょう。メニュー価格とコストに注意する
お弁当は割安で済ませたいと考えるお客様が多いため、価格設定が重要になってきます。あまり高い料金にすると売れない可能性もありますが、お弁当には容器代などもかかるもの。それらも加味して上手く価格設定する必要があります。
レジ袋有料化に対応する
2020年7月1日より、「レジ袋有料義務化(無料配布禁止等)」が施行され、レジ袋を有料で販売することが義務付けられました。持ち手のついたプラスチック製の袋が対象で、価格については各事業者に任されていますが、1枚1円以上で販売することが求められています。レジ袋有料化に伴い、お客に対して持ち帰りのビニール袋が有料であると告知をしっかりとしなければいけません。
原則、レジ袋は有料で販売する必要がありますが、植物性由来のプラスチック「バイオマス素材」を25%以上配合しているものや、プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの、海洋生分解性プラスチックの配合率が100%のもの、厚手で繰り返し使える袋、紙袋等の場合、有料化の対象外となり、無料で配布が可能です。レジ袋の販売で小銭のやり取りが手間になるなど、どうしても無料でつけたい理由があるなら、先に上げたような素材のビニール袋に変更するのも一つの手です。お弁当販売の開業資金に使える支援策
お弁当の販売業を始めるには多額の開業資金が必要です。自己資金で足りない場合は、以下のような制度を活用してみるといいかもしれません。

国・地方自治体の補助金
近年、国や地方自治体がテイクアウトやデリバリーを推奨しており、移行する飲食店を対象に補助金を出しています。金額や申請内容、期間は各地方自治体のよって異なるので、店舗が所在する地方自治体のHPを確認してみてください。
その他自治体などの融資制度についてはこちらの記事で解説しています。
関連記事飲食店開業の流れ「自治体の制度融資や補助金・助成金もチェックしておこう」日本政策金融公庫の融資を受ける
新たに事業を開始する方を対象に設備資金と運転資金の融資を受けられる制度です。融資限度額が高く、審査も信用金庫などに比べ緩いので借りやすいのが特徴です。年齢や性別などにより受けられる融資制度の種類が異なるので、興味のある方は日本政策金融公庫のHPを確認してみてください。
日本政策金融公庫についてはこちらの記事で紹介しています。
関連記事飲食店開業の流れ「開業融資の定番!日本政策金融公庫の『新創業融資制度』」
開業資金については、調達方法や金額相場、主な内訳などを以下の記事で解説しています。
関連記事飲食店の開業資金はいくら必要?相場や調達方法について解説
まとめ
お弁当販売はコストを抑えて、利益を伸ばせる可能性がある近年人気の販売形態です。お弁当販売が気になっているという方は、営業形態によって必要な届出や資格取得などが異なるので注意しましょう。
また、食べ物を販売する場合、常に注意しなければならないのが「食中毒」です。季節に応じてメニューを変更するなど、衛生管理をしっかりと行うことが大切です。
準備に必要な資金が足りない場合、地方自治体や国の支援策をうまく活用することで、初期投資を抑えてお弁当販売を始められることもあります。「店舗型」「宅配型」「移動販売型」とお弁当販売は販売スタイルがさまざまなので、自分に合ったスタイルを見つけてみましょう。
canaeruでは、飲食店開業に役立つセミナーを開催。物件探し、資金集め、集客や内装といった開業に必要なノウハウを公開しています。
また、各分野のプロが、基本的な内容からここでしか聞けないリアルな実情まで、わかりやすく解説する無料セミナーを定期的に開催中です。飲食店の開業を検討している方はぜひご参加ください。
無料のセミナーに参加する
無料の開業相談はこちらこの記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- NEW最新記事
-
-
2024/10/23
-
2024/10/18
-
2024/10/11
-
- おすすめ記事
-
-
2017/12/26
-
2017/01/05
-
2017/06/19
-
2018/11/30
-
2022/02/21
-
2017/12/07
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数192件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数128件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数506件
-