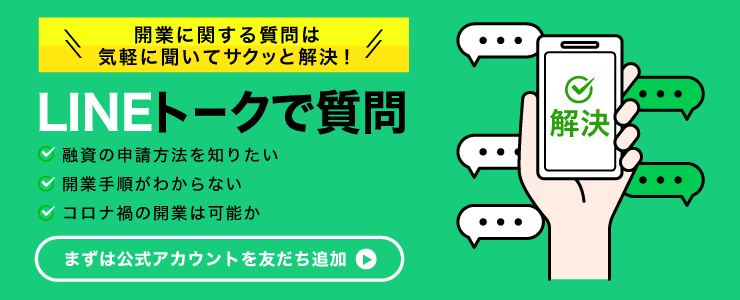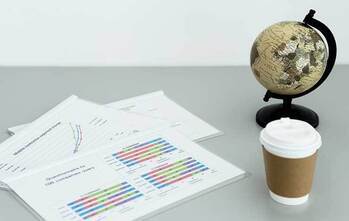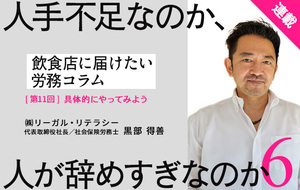- Tweet

オフィスビルが立ち並ぶビジネス街や、大型のショッピングモールなどで人気のキッチンカー。今では全国から人気のキッチンカーを集めたフェスや、キッチンカーと出店場所をマッチングさせるサービスなども登場し、キッチンカーを取り巻く環境が様変わりしています。
キッチンカーは初期費用が安く、開業しやすいと人気の業態ですが、開業にあたり資格取得や許可の申請が必要不可欠です。この記事では、キッチンカーの開業に必要な許可や資格の取得方法、開業までの流れについて解説します。目次
移動販売が今流行っている?
まずは、消費者の視点を交えてキッチンカーをはじめとした移動販売がなぜ流行っているのかについて深掘りしていきます。

消費者のライフスタイルが変化した
キッチンカー業界が活気づいている主な理由として、ライフスタイルの変化が挙げられます。
コロナ禍では“三密の回避”により、多人数での飲食が避けられるようになり、お弁当需要が増したことで移動販売のキッチンカーに注目が集まりました。加えて、飲食店や新規開業者がキッチンカー事業へ積極的に参入し、さまざまなメニューを提供するキッチンカーが増えたことも人気が上昇した要因の一つです。
その潮流は現在も続いており、キッチンカーの利用が日本人の生活に根付いてきたといえます。開業時の初期費用や固定費を抑えられる
初期費用や固定費が安く済むのは、開業資金を抑えたいと考える開業希望者にとって大きな魅力です。キッチンカーの初期費用の相場は約250~300万円であり、店舗型飲食店の初期費用の相場の約1,000万円と比べると、およそ1/4の費用で済みます。
また、キッチンカーの事業は駐車場代と年間の車両保険料を合算した固定費がかかりますが、費用相場は年間約30~80万円ほどです。このほか、人件費や光熱費、イベント出店費などもかかりますが、全体的に店舗経営よりも固定費を安く抑えられる傾向にあります。参入しやすい飲食業態
客席のある飲食店を開業するには、規模に応じて多額の資金が必要です。また、開業後の業態やコンセプトの変更も容易ではありません。さらに、移動販売とは異なり店舗は動かせないため、立地で失敗したと気付いても後の祭りです。
キッチンカーでの飲食事業はメニューやコンセプトを変更しやすく、いずれ店舗での開業を目指しているのであれば候補地をキッチンカーで試験営業して事業と商圏がマッチしているかテストできます。キッチンカーでの移動販売で、飲食店経営のノウハウを身につけつつ、実店舗開業に向け資金を貯めることは実店舗開業のリスク軽減に繋がります。移動販売の主な業態・開業タイプ
移動販売は、キッチンカー以外にもさまざまな業態で使われています。代表的な「生活必需品販売型」「イベント販売型」「ファッション・小物販売」の3つのタイプを解説します。
1:生活必需品販売型
生活必需品販売型は、近くにスーパーマーケットやコンビニエンスストアがなく、車がないと買い物が困難であったり、公共交通機関が十分に整備されていない地域を対象に、野菜や卵、魚類、肉類などの食材など生活必需品を売る移動販売を指します。
開業場所は公共施設の駐車スペースや道端など決まった場所で週1〜2回、同じ曜日に販売されるのが一般的です。顧客が定着するまでに時間を要しますが、軌道に乗ると安定した売上が確保できます。2:イベント販売型
イベント販売型は、ランチタイムのオフィス街や繁華街、ショピングモールやスーパーの軒先、イベント会場などで食品を販売する移動販売のことで、本記事で紹介しているキッチンカーでの移動販売はこちらに該当します。
オフィス街ではランチタイムでの需要が高いためコストパフォーマンスの良い弁当やドリンク、ショッピングモールやスーパーでは家族へのお土産需要を考えた焼き鳥やスイーツなど、立地や時間帯によって最適なメニューが異なります。
売上は販売する場所や天候に大きく左右されるため、状況に応じて製造数等を調整するなど臨機応変に対応することが重要です。3:ファッション・小物販売
こちらは食品とは関係のない移動販売です。主に洋服や和服、カバンや財布などのファッション小物、貴金属などのアクセサリーを移動販売で取り扱っています。ショッピングモールやスーパーの軒先、商店街、イベント会場などに出店しているのが一般的です。
食品販売のように、衛生面に気を遣わないため参入のハードルは低く、イベント会場などではハンドメイドのグッズを販売している方も多く見られます。キャリーケースに商品を詰め、徒歩で移動する方から自家用車や専用トラックまで輸送手段の自由度が高いのも特徴です。キッチンカーでの移動販売の開業のステップ
キッチンカーでの移動販売を始めるには、次の流れで手続きを行う必要がります。
ステップ1:キッチンカーの購入/レンタル
移動販売に使用するキッチンカー、フードトラックを購入、またはレンタルします。すでにキッチンカーとして売り出されている車を購入・レンタルする場合もあれば、軽トラックなどを購入し、キッチンカーへ改造する場合もあります。車両を改造してキッチンカーにする場合、車体の高さや幅、長さに上限があるので注意が必要です。
ステップ2:メニューの開発
キッチンカー開業において、早期の段階でメニューの開発に取り掛かる必要があります。その理由は、メニューによって売上が大きく変動するためです。売上が大きい傾向にある食べ物を提供すれば、その分だけ売り上げを伸ばせるチャンスがあります。
また、販売しやすい商品であることも重要であり、仮に売れやすいメニューであっても提供時間がかかると回転率が落ちてしまう恐れがあり、売上に影響するリスクがあります。食材や扱う料理によって難易度や費用が変化する点にも注意が必要であり、その点でも早期なメニュー開発は重要です。
さらに、商品によっては特別な営業許可が必要になることもあり、どのようなメニューを提供するのかは早期に決定してください。ステップ3:資格、許可の取得
営業に必要な資格や許可を取得します。まずは食品衛生責任者養成講習会を受講して食品衛生責任者の資格を取得します。そのうえで、出店予定先の保健所にて営業許可の申請を行いましょう。
必要書類に不備がなければ、キッチンカーを持ち込み、保健所職員による確認検査が行われます。保健所の要件を満たしていれば、晴れて営業許可証が交付されます。ステップ4:販売
保健所からの営業許可が下りたら実際に営業を開始します。販売するメニューを決め、仕入れを行い、実際に調理・販売を行います。オフィス街やイベント会場など人が多い場所を狙って販売場所は決めるとよいでしょう。
キッチンカーでの移動販売の開業資金はいくらかかる?
キッチンカーの開業資金の相場は250〜300万円と言われています。内訳は以下の通りです。
●キッチンカーの購入費・レンタル費
●調理器具の購入費
●容器や販促品にかかる費用
それぞれ具体的な金額を提示しながら解説します。キッチンカーの購入費・レンタル費
キッチンカーを用意する方法は、主に以下の4つの方法があります。
【新車のキッチンカーを購入する】
250~600万円
【中古のキッチンカーを購入する】
100~500万円
【キッチンカーをレンタルする】
5万円/日、15万円/週、30万円未満/月
【自分の車を自力で改造する】
約50万円
キッチンカーの入手方法については下記の『キッチンカーの購入方法』で説明していますので、そちらも参考にしてみてください。調理器具の購入費
キッチンカーに必要な調理器具は主にグリドルと言われる業務用の鉄板です。新品であれば7~10万円、中古であれば5万円以下で購入できます。
ポテトやからあげ、ドーナツなどを調理するフライヤーは、卓上型か据え置き型かによって価格は異なります。新品で用意する場合、小型の卓上型は20万円以下で購入可能です。フライヤーをメインで利用するキッチンカーであれば、中型~大型のもので30万円~50万円ほどかかります。容器・消耗品や販促品にかかる費用
キッチンカーで食べ物を販売する際は、トレー、スプーン、コップなどの使い捨て容器が必要です。例えば、透明カップ100個は400円、焼きそばやたこ焼きを入れる透明なプラスチックの容器は100個で600円、400mlのプラスチックコップは50個で1,000円程度です。
さらに、チラシや看板、広告費などの販促活動にも費用がかかります。立て看板の相場はサイズにもよりますが1万円〜3万円ほどです。のぼりは1,000円台から制作でき、ポールと台のセットを含めても3,000円程度で準備できます。
このように、使用する容器や販促方法によってかかる費用は異なりますが、必要な経費をしっかりと見積もり、適切なアイテムを選ぶことが重要です。また、販促品に投資することで宣伝効果が高まり、売上の増加が期待できます。
調理器具を準備するのにかかる費用
食べ物を販売する場合は、調理器具の費用もかかります。たとえば、焼きそばやお好み焼きの場合は鉄板7~10万円、ケバブを販売する場合は専用マシーン7~8万円程度必要です。ただし、調理器具はモノによってピンキリです。クオリティの高い物や業務用マシーンを購入する場合は、30万円かかることもあります。
保健所の許可取得にかかる費用
食品を調理して販売する店舗に対しては、どのような販売方法であっても保健所の許可が必要です。キッチンカーも例外ではなく、保健所の許可を得てお客様が見やすい位置に掲示する義務があります。
保健所の許可を取得するためには、食品衛生法の条例を満たし、食品衛生責任者1名を配置しなければなりません。かつ複数の自治体で出店する場合は、各自治体で保健所の許可を得る必要があります。
1ヶ所に固定して保健所の許可を得る場合、申請費用として10,000円程度かかります。さらに食品衛生責任者の資格において講習費用10,000円ほどかかり、もし許可を得るためにキッチンカーの業者や行政書士のサポートを受ける場合、別途費用がかかります。月に必要な運転資金
キッチンカーで営業を続けるためには、初期費用のほか、以下の費用がかかります。
●キッチンカーの維持費
駐車場代(月2~6万円)、保険料(年間4~7万円)、車検代(2年で4~7万円)
●消耗品や販促費用
使い捨て容器(100個400円)、チラシなど(2~3万円)
●出店料
平日2,500円~、土日祝日1万円~
営業を続けるためには、キッチンカーや食材以外にもさまざまな費用がかかります。無理なく続けられるように、必要な物を入念にチェックしておきましょう。キッチンカーでの移動販売に必要な資格・許可・手続き
キッチンカー開業には、必要な資格や許可があります。主なものは次の5つです。
関連記事飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解説
食品衛生責任者
食品衛生責任者とは、食品の製造や販売を行う場合に必要な資格のことです。自治体により規定が若干異なりますが、小さな個人店舗や大規模チェーンであっても、飲食の営業を行う場合は最低でも1店舗に一人は食品衛生責任者を配置しなければなりません。
当然、キッチンカーによる営業であっても、食品の製造と販売を行うため食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者の資格を取得する場合、各自治体において以下の食品衛生責任者養成講習を受講しなければなりません。
●衛生法規(約2時間)
●公衆衛生学(約1時間)
●食品衛生学(約3時間)
受講費用は自己負担しなければならず、概ね10,000円程度かかります。講習受講後は、出店したいエリアの保健所に申請することで資格取得可能です。
なお、以下の資格を持つ人の場合は、講習が免除となり窓口に申請するだけで資格取得できます。
●栄養士
●調理師
●製菓衛生師
●食鳥処理衛生管理者
●船舶料理士
●食品衛生管理者等の有資格者
●その他医師
●薬剤師営業許可(自動車営業)
キッチンカーでの移動販売で必要な営業許可(自動車営業)は取り扱うメニューによって異なります。車内で調理をして販売をする場合、基本的に必要なのは「飲食店営業」の許可です。
スイーツなどを販売する場合は「菓子製造業」、ドリンクなどを販売する場合は「喫茶店営業」の許可が必要です。
もし、ランチメニューと菓子を同時に販売する際には「飲食店営業」と「菓子製造業」、それぞれの許可を取得しなければなりません。
ただし、保健所によってはどちらか1つの許可しか取得できないなどの制限を設けている場合がありますので、出店先の保健所の規則を事前に確かめておきましょう。
一方、車内で調理をせず、販売のみを行う場合は、取り扱う料理や食材に応じて「食料品等販売業」「食肉販売業」「乳類販売業」「魚介類販売業」の営業許可を取得する必要があります。
保健所での手続きに関しては、以下の記事を参考にしてください。
関連記事意外な盲点あり…飲食店開業における保健所での手続き、何をすればよい?
特殊用途自動車用の8ナンバー登録
キッチンカーは特殊用途自動車である8ナンバー登録が絶対必要というわけではありません。普通貨物車ナンバーや小型貨物車ナンバーでも登録は可能です。ただし、普通貨物車や小型貨物車で登録をしていると、車検の際に車内の設備を一度全て取り外さなければいけなくなります。8ナンバーであればキッチンカーの設備を外さず車検を受けられるので、長い目で見て8ナンバーを取得するほうが得策です。
販売場所の使用許可
キッチンカーでの営業許可が下りたからといって、どこでも好き勝手に移動販売をしていいというわけではありません。営業を行う際は、営業場所の使用許可が必要なことがほとんどです。
使用許可の申請先は販売場所を管理する会社です。ショッピングモールの敷地ならショッピングモールの運営会社、大学のキャンパスなら大学が申請先になります。
また、道路を使って路上販売を行う際は、その場所を管轄する警察署にて「道路使用許可」の申請を行います。無断で販売をすると、駐車違反で反則金が発生するので気をつけてください。運転免許
キッチンカーを運転するための特別な免許はなく、車種によっては普通免許だけで運転可能です。ただし、免許を取得した時期によって普通免許で運転できる車両の総重量が変化する点には注意が必要です。
具体的には、道路交通法の改正に伴って中型車の運転区分が追加された2007年以降と、準中型車が追加された2017年以降に免許取得された人は、運転できる車両総重量が異なります。
2007年6月2日以降に普通免許を取得した方は、以下の条件を確認してください。
●2007年6月1日までに取得した場合:車両総重量:8t未満
●2007年6月2日~2017年3月11日までに取得した場合:車両総重量:5t未満
●2017年3月12日以降に取得した場合:車両総重量:3.5t未満
キッチンカーの車両総重量の計算式は、以下の通りです。
<車両総重量 = 車両重量 + (乗車定員×55kg) + 最大積載量>
また、最大積載量の計算式は以下となります。
<車両総重量 - ( 車両重量 + 乗車定員 × 55kg ) = 最大積載量>
以上より、一般的なキッチンカーのサイズとなる2tトラックを運転するためには、準中型免許が必要です。
牽引タイプのキッチンカーの場合、750kg以下の車両を牽引する場合は普通免許で対応できます。車両総重量750kgを超える車を牽引する場合は牽引免許が必要となるため、注意してください。キッチンカーの購入方法
キッチンカーを用意するには、以下の4つの方法があります。
新車のキッチンカーを専門業者に制作してもらう
専門の業者に依頼して、新しくキッチンカーを制作してもらう方法です。新車キッチンカーは、理想のデザインを手に入れられる、中古車よりも長く使えるといったメリットがあります。調理に適した内装や、集客力のある外装など、好みや機能性をとことん突き詰めることができます。
中古のキッチンカーを購入する
中古のキッチンカーを購入し、そのまま使う、または一部を変更して使うという方法です。中古車は、新車を購入するよりも費用を抑えられるというメリットがあります。ただし、購入してから不備に気付き、修理をするのに思わぬ出費が発生してしまう場合も。あまりに安い中古車には注意が必要です。
キッチンカーをレンタルする
まだ購入には踏み出せない、とりあえず始めてみたいという人には、レンタルもおすすめです。面倒な手続きがなく初期費用もかからないため、精神的な不安も少ないでしょう。ただし、月額費用としては割高になってしまうため、長期的に使う場合は注意が必要です。
自分で車をキッチンカーに改造する
自分で購入した軽トラックやバンを、キッチンカーに改造するという方法もあります。自作する場合は時間と手間がかかりますが、費用を安く抑えながら自分仕様に作れます。保健所の許可が取れるように、あらかじめ要件を確認しておきましょう。知識や技術に自信がない場合は、業者に依頼して改造するのがおすすめです。
キッチンカーでの移動販売に必要な設備
保健所に営業許可を申請する際には、保健所が求める設備がキッチンカーに整っている必要があります。必要な設備は取得する営業許可の種類によって異なりますが、車内で調理を行う飲食、菓子、喫茶営業許可において必要な設備は同じで、以下のものになります。
●流水式またはアルコール式の手洗い設備
●2槽以上の洗浄施設
●給湯設備
●給水量200L以上の給水タンク
●給水タンクの容量以上の排水設備
●冷蔵庫
●密閉できる合成樹脂の食品保管設備
●密閉できる合成樹脂の食器器具保管設備
●蓋付きゴミ箱
キッチンカーでの移動販売におすすめのアイテム
キッチンカーでは、如何にお客様にインパクトを残せる集客ができるかが鍵です。主に、集客時におすすめしたいアイテムとして、以下があります。
●タペストリー
●のぼり
●黒板
●看板
タペストリーは、主にキッチンカーの販売面や側面で使用することが多いアイテムです。なお、運転席などの側面に設置すれば車内を目隠しできます。
のぼりは、キッチンカー周辺に設置してどのようなお店なのかを知らせることが可能なアイテムです。インパクトに残るフレーズを使用すれば、お客様の目に留まり来店してもらえるきっかけとなります。
黒板はメニューやおすすめ商品をアピールする際に役立ち、看板は店舗名をアピールする際に最適です。キッチンカーでの移動販売をした場合の損益モデル
キッチンカーでの移動販売は、低コストで始められる魅力的なビジネスモデルですが、収支バランスの把握が重要です。ここでは、キッチンカーを開業する際の初期費用や月額運営費用、損益のモデルを紹介します。
下記のモデルは、車両を購入し、個人によるイベント販売型の営業を想定した数値です。
【初期費用】
項目 費用 車両購入・改造費 250万円〜300万円 設備費 10万円〜100万円 営業許可申請費 約3万円 合計 263万円〜403万円
【月々の運営費用】
項目 費用/月 食材費 20万円〜30万円 人件費 15万円〜25万円 燃料・維持費 5万円〜10万円 販促費 2万円〜5万円 合計 42万円〜70万円
【売上と収益】
出店場所 1日の売上予想 オフィス街 3万円〜5万円 ショッピングモールやスーパーの軒先 3万円〜5万円 イベント会場 8万円〜10万円
上記の表からオフィス街の月間損益を予想してみましょう。1日の売上が3万円、営業日は平日の23日と仮定します。
項目 金額 売上 69万円 食材費 20万円 人件費 20万円 燃料・維持費 7万円 販促費 3万円 利益 19万円
キッチンカー開業時における注意点
キッチンカーで移動販売を始めるにあたって注意しなければいけないことがいくつかあります。主な注意点は次の5つです。
扱える食材が異なる
食品衛生上の関係で、キッチンカーで扱える食品は限定的です。車内の設備によって扱える食品や種類が異なるうえ、販売を予定しているメニューに合わせて営業許可を取得しなければいけません。また、いかなる場合であっても生ものを扱うのはNGです。
別途仕込み場所が必要な場合もある
自治体によっては、キッチンカー以外で仕込み場所を別途確保する必要があります。既製品を盛り付けるだけの場合は不要ですが、切る・混ぜるなどの下準備が発生する場合は仕込み場所が必要なことが多いです。仕込み場所が必要かは出店予定先の保健所に事前に確認しておきましょう。仕込み場所が必要な場合は、キッチンカーとは別に仕込み場所の営業許可も取得しなければいけないので注意が必要です。
衛生管理を徹底する
キッチンカーは通常の飲食店に比べ、設備が乏しく、場所も狭いです。加えて、屋外に近い状態での調理になるため、季節によっては菌が繁殖しやすい傾向にあります。そのため、食材の取り扱いは慎重に行うことが求められます。もし食中毒などを出してしまえば、営業停止命令を受けるだけではなく、損害賠償請求をされる可能性もあります。手洗いや設備の除菌はこまめに行うようにしましょう。
営業許可は出店する都道府県や地域ごとに申請が必要
食品衛生責任者の資格は全国共通ですが、一方、保健所の営業許可は出店先の都道府県や地域ごとに必要です。そのため、販売地域を変える場合は、新たに出店予定先の保健所にて営業許可の申請を忘れずにしておきましょう。
営業許可の有効期限は5年
保健所の営業許可の有効期限は5年です。有効期限を越えて営業を続ける場合は、有効期限満了日の約1ヶ月前に更新手続きを行う必要があります。もし更新手続きをせずに有効期限を越えて営業すると、食品衛生法違反になり、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金が課せられる可能性があります。さらに、営業停止命令を受け、2年間営業許可の取得ができなくなる場合もあります。
《失敗例から学ぶ》移動販売を成功させるためのポイント
成功と失敗はほんのちょっとの工夫で逆転することがあります。ここでは、よくある失敗を例に挙げながら、どのようにすれば成功の可能性が高まるのかを解説していきます。
《失敗例》SNSを活用しなかった
特定の場所で営業していないキッチンカーは、自ら営業時間や場所を発信しないとお店のファンはつきません。そのため、多くの人に向けて情報発信が可能なSNSを活用すれば、来店したい方を取りこぼさずに済みますが、SNSの更新を面倒くさがって投げ出してしまう方は多いものです。
キッチンカーでの営業こそ、いかにSNSを駆使して効率よく集客できるかが重要です。ここからは、キッチンカーの集客に活用すべきSNSを紹介します。
LINE
LINEは日本で最もアクティブなSNSです。LINE公式アカウントを活用して「おともだち」登録してもらえば、営業時間や場所の情報をダイレクトに届けることができます。さらに、ショップカード機能やクーポン機能があったり、1対1でのコミュニケーションも可能です。自動返信機能もあるので、忙しいタイミングでも対応できます。さまざまな料金プランが用意されているので、必要に応じてオプションをつけるとよいでしょう。
X(旧Twitter)
X(旧Twitter)はLINEに次いでアクティブなSNSです。いいね機能やRT機能があるので、不特定多数に店舗の情報を発信できます。また、Xにはダイレクトメッセージ機能があるため、使い方によっては商品の取り置きや予約を受け付けることもできます。他にも、つぶやいた場所を追加できる機能があり、今どこで営業しているのかを知らせることが可能です。
Instagram
Instagramは、写真と動画が中心のSNSです。シズル感溢れるメニュー写真は多くの人を惹きつけます。最近では「リール動画」機能が注目されていて、30秒~1分程度のショート動画が人気コンテンツとなっています。お店の情報はもちろん、スタッフやオーナーの人柄がわかる動画を投稿すれば、お店のファンの増加が期待できます。営業時間やメニューなどは「ハイライト」機能を活用し、過不足のない情報発信を目指しましょう。
Facebook
文字数や画像の枚数に制限がなく、しっかりとお店の良さをアピールできるSNSを使いたいならFacebookがおすすめです。いいね!機能によって情報が拡散される可能性があり、またコメント機能があるためお客様とコミュニケーションできる点も評価できます。
関連記事 SNSフォロワー数10K超え!バズってるお店のSNS使い方のコツ《失敗例》顧客ニーズを正しく認識していない
顧客のニーズを正しく汲み取れていないのは、ありがちな失敗例です。自身のやりたいことを優先するあまり、顧客の求めるものに考えが至らないケースはよくあります。
顧客ニーズの把握には市場調査が欠かせません。具体的には、アンケート調査やインターネットの口コミ調査などが有効です。例えば、出店予定地やイベント会場でアンケートを実施し、人気の商品や新しいニーズを把握します。
インターネットの口コミ調査は、競合になりそうなお店の口コミやSNSを徹底的にチェックする方法が有効です。需要が高い商品を中心にラインナップを揃え、常に顧客の期待に応える品揃えを提供しましょう。《失敗例》営業時間と場所が適切でない
顧客が利用しやすい時間帯と場所を選ぶことは、移動販売の成功に直結する重要な要素です。例えば、お昼時に高齢者が集まる公民館前や住宅地内の広場などで、「メガ盛りカツ丼」を販売しても、売れ行きは厳しいでしょう。一方、大学のキャンパス周辺や工業団地などでは人気がありそうです。
しかし、売れ行きが良好な地域でも「メガ盛りカツ丼」のようなヘビーな食べ物は、早朝からの販売には向いていません。お店のメニューとコンセプトが営業時間と場所にマッチしないまま営業すると「流行っていないのかな?」と悪い印象を与えてしまう可能性もあります。失敗しないためには、ターゲット層が買いやすい時間と場所に出店することが重要です。《失敗例》宣伝が不足している
h3 新規 《失敗例》宣伝が不足している
宣伝不足も飲食店経営者が陥りやすい失敗の一つとして挙げられます。 すばらしい商品を用意しても、顧客に気付いてもらえないと経営は成り立ちません。宣伝方法は、チラシ配布や地域の掲示板、先ほど紹介したSNSの活用も有効です。地元のフリーペーパーやグルメ雑誌等での広告も効果があります。
また、グルメ雑誌の編集部にプレスリリースを送付すると、無料で掲載してくれるケースもあります。これらの施策により、潜在的な顧客層へのリーチが可能になるでしょう。《失敗例》商品の品質に問題がある
商品の品質に問題がある場合、顧客満足度に直結するため早急に改善する必要があります。平時ならおいしい料理でも、忙しくなると品質が大きく落ちる可能性がある場合も放置は厳禁です。オペレーションや人員配置などを見直し、ベストな商品のみ提供できる環境を整えましょう。
また、食品を提供する場合、適切な温度管理が求められます。必要に応じて、冷蔵・冷凍設備を導入し、商品が劣化しないように管理しましょう。こうした徹底した品質管理により、顧客の信頼度が向上し、再購入へと繋がっていきます。《失敗例》サービスが一貫性に欠ける
サービスの一貫性はどの業種でも大切ですが、移動販売は店舗がないため、特に注意する必要があります。告知もせずに、いつもの場所・時間に出店しないことが頻発すれば顧客の信用を失い、リピーターの獲得が困難になるでしょう。
そのような事態を避けるためにも、毎週同じ曜日に決まった場所で営業するなど、顧客が安心して利用できるように努めることが大切です。また、商品のラインナップや価格設定も安定させることで、お店に対する信頼度の向上も期待できます。開業に関するお悩みは「canaeru」にご相談ください
キッチンカーでの開業をご検討の方は、「canaeru(カナエル)」の『無料開業相談』をご利用ください。飲食店開業経験者や元金融機関出身者が、事業計画書の作成や資金調達などトータルでサポートいたします。
「canaeru」の運営元である株式会社USENは、国が定める経営革新等支援機関(認定支援機関)です。税務、金融および企業財務に関する専門的知識や支援にかかる実務経験が一定レベル以上ある支援機関として国に認められています。
キッチンカー開業にあたってご不明点やお困りのことがあれば、ぜひご利用ください。
無料開業相談はこちらからまとめ
食品衛生責任者の資格と営業許可があれば、キッチンカーでの移動販売はすぐに始められます。複数の地域で自由に販売できる強みを生かせれば、大きな集客・売上が期待できます。ただし、キッチンカーは販売先を変えるたびに出店先の都道府県や地域の保健所の許可が必要になるため注意しましょう。
キッチンカーの開業に融資を希望している方は、canaeruにご相談ください。canaeruでは飲食店の開業に関する相談を無料で承っています。金融機関や銀行出身の経験豊富な開業プランナーが、丁寧にヒアリングを行い、資金面の課題解決をサポートします。
canaeruの運営元である株式会社USENは、国が定める経営革新等支援機関(認定支援機関)です。税務、金融および企業財務に関する専門的知識や支援にかかる実務経験が一定レベル以上ある支援機関として国に認められています。
canaeruでは、開業のエキスパートによる無料サポートをご利用いただけます。開業にあたってお困りのことがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
- NEW最新記事
-
-
2024/10/23
-
2024/10/18
-
2024/10/11
-
- おすすめ記事
-
-
2022/10/21
-
2024/05/01
-
2017/11/01
-
2019/09/06
-
2021/02/02
-
2022/02/10
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数192件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数128件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数506件
-