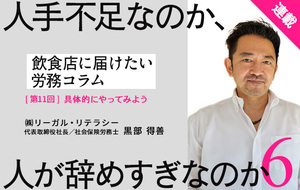- Tweet

起業には、個人事業主として起業するか、法人を設立するかの2通りがあります。それぞれ異なるメリットとデメリットがあり、場合によっては個人事業主として起業した後しかるべきタイミングで法人化するというパターンもあり得るでしょう。
個人事業主と法人のどちらで起業するにしても、そのために必要な準備と手続きについては事前に把握しておかなければなりません。たとえば青色申告を行う事業者は、事業開始から2ヶ月以内に申告する必要があります。
この記事では、個人事業主と法人のそれぞれのメリット・デメリットや起業時の手続き、起業する前に行っておくべきことなどについて説明します。起業する方法が知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
起業方法には2つの選択肢がある
冒頭でも触れたように、起業する際の選択肢には個人事業主と法人があります。それぞれ手続き方法に違いがあるため、概要を把握した上で検討しましょう。
個人事業主
個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営む人のことです。税務署に「開業届」を提出すれば、誰でも個人事業主となることができます。会社に勤めていても、副業で事業所得が生じ、青色申告による確定申告をしたい場合は、開業届を提出する必要があります。
法人
法人とは、法律によって人と同じ権利や義務を認められた組織のことで、大きく「営利目的の私法人」「非営利目的の私法人」「公法人」の3種類に分かれます。起業においては営利法人を指し、具体的には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社がこれに該当します。
「法人成り」という選択肢もある
最初は個人事業主として起業した場合でも、状況に応じて事業を法人に変更する「法人成り」という選択肢もあります。法人成りのタイミングを考える上で重要なポイントは利益や売上高です。
これまで、目安とされてきたのは「課税事業者になるタイミング」です。個人事業主は2年前の消費税課税売上高が1,000万円を超える場合、または2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても前年の前半6ヶ月の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者となります。
上述した条件に該当するタイミングに合わせて法人成りすることで、新しくできた法人と個人事業主は別人格と判断されるため、個人事業主としての過去の売上高に対する納税義務はなくなるのです。また、新しく設立された法人については、設立1期目および2期目分について、原則として納税義務が免除されます(資本金の額が1,000万円未満の場合)。
ただし、インボイス制度を導入する場合は注意が必要です。インボイス制度は、免税事業者である個人事業主を対象に特定の期間に限り消費税の税負担を軽減できる特例措置があります。法人成りするとこの特例措置は受けられないため、事業内容に応じて「個人事業主のままインボイス制度に登録申請する」「インボイス制度のタイミングで法人成りする」など、最も負担を軽減できるタイミングを見極めるようにしましょう。
関連記事 個人事業主は消費税を納める?仕組みや計算方法をわかりやすく解説
個人事業主と法人のメリット・デメリット
ここからは、個人事業主と法人のメリット、デメリットを比較していきます。両者の違いを踏まえて、より具体的な利点を把握していきましょう。
個人事業主のメリット・デメリット
個人事業主のメリット・デメリットには以下のようなものが挙げられます。
メリット デメリット ・開業手続きが簡単
・初期費用がかからず、すぐに事業を開始できる
・税務処理が法人よりも簡単
・経費にできる範囲が狭い
・所得が大きいと税負担が大きくなる
個人事業主のメリットの一つは、開業までが法人よりスムーズであることです。法人設立よりも提出書類や手続きが少なく、開業のための設立費用はかかりません。複雑な税務処理も必要ないため、小規模のビジネスに適した開業方法と言えます。
ただし、個人事業主の場合、相手によっては取引に応じてくれない可能性があることも留意しておきましょう。また、個人事業主にかかる所得税は累進課税のため、所得が大きくなるほど、税率も上がってしまうデメリットがあります。法人に比べて経費にできる範囲が狭く、自宅を事務所と兼用している場合、家賃や水道光熱費などはプライベートで使用した分と事業で使用した分の線引きが曖昧になるため、「家事按分」をして事業にかかった費用を算出する必要があります。
法人のメリット・デメリット
法人のメリット・デメリットは以下のようなものがあります。
メリット デメリット ・節税対策の範囲が広い
・一定の所得を超えたら、所得税よりも節税になる
・赤字を長く繰り越せる
・事業開始までの手続きが多く、設立費用もかかる
・赤字でも税金が発生する
・社会保険の加入によるコストがかかる
法人を設立する主なメリットは、節税できる範囲が広がることです。法人は個人事業主に比べて計上できる経費が多いことが特徴です。たとえば、役員に対する給与は「役員報酬」や「役員給与」として経費計上が可能です。
また、法人に課される法人税は比例課税方式が採用されており税率は15%〜20%前半と、個人事業主の所得税と比べて所得にかかる税率が穏やかです。赤字についても、繰越控除が3年の個人事業主に対して、法人の場合は、10年間赤字を繰り越すことができ、個人事業主に比べてより長く繰越控除ができるメリットがあります。
一方で、法人設立には個人事業主よりもはるかに複雑な手続きが必要になるほか、高額な設立費用もかかります。株式会社の場合、最低でも25万円程度は見込んでおく必要があります。また、法人は赤字の場合でも「法人住民税」を支払う必要があり、社会保険の加入も義務付けられています。
法人設立、または法人成りは十分な利益を見込める状態で行うことをおすすめします。設立費用や運営費用を支払ってもメリットを活かせると感じたら、法人設立を視野に入れてみましょう。
個人事業主として起業する際の手続き
起業後、スムーズに事業を行っていくためにも、起業する際に必要な手続きを知っておくことが重要です。個人事業主として起業する際に必要な手続きは、以下の通りです。
●個人事業の開業・廃業等届出書を提出する
●青色申告承認申請書を提出する
●必要に応じて各種書類を提出する
それぞれの手続きについて、以下で詳しく説明します。
関連記事 開業に必要な手続きが知りたい方は必見!書類の提出方法や期限など解説
個人事業の開業・廃業等届出書を提出する
個人事業主として開業するためには、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出する必要があります。開業届は、税務署の窓口で受け取るか、国税庁のサイトよりPDFで取得してから提出しましょう。
また、開業届を提出する際は、マイナンバーが確認できる書類・本人確認書類・印鑑が必要です。マイナンバーが確認できる書類は住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書、本人確認書類は運転免許証や健康保険証などが該当します。
なお、マイナンバーカードは1枚でマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類の役割を果たすことができるため、マイナンバーカードを持っている方はそちらを利用すると便利でしょう。
提出先は店舗や事業所の所在地を管轄する税務署で、提出期間は起業してから1ヶ月以内です。
関連記事 個人事業主として開業するには?必要な手続きと流れを解説青色申告承認申請書を提出する
確定申告時に青色申告を行うためには「青色申告承認申請書」を提出する必要があり、こちらの書類を提出しない場合は、白色申告になります。
提出は必須ではありませんが、青色申告を行うことで、白色申告よりも多くの控除を受けられたり、家族の給与を経費にできたりするなど(諸条件あり)多くのメリットがあるため、青色申告のほうが賢明でしょう。
青色申告承認申請書は、税務署の窓口で受け取るか国税庁のサイトからPDFで取得した上で、提出してください。提出先は店舗や事業所の所在地を管轄する税務署で、提出期間は起業してから2ヶ月以内です。必要に応じて各種書類を提出する
開業届や青色申告承認申請書以外にも、必要に応じて提出が必要な書類は下記になります。
●所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
●青色専従者給与に関する届出書
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
● 給与支払事務所開設届出書
「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」は、起業にあたって引っ越しを行い、納税地が変わる場合に提出が必要な書類です。
「青色専従者給与に関する届出書」は、確定申告で青色申告を行う場合に、配属者や親族に対して支払う給与を経費計上するために必要となります。確定申告を青色申告で行わない場合や、配属者や親族を従業員として雇わない場合には、提出する必要はありません。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、従業員を雇って給与の支払いを行う際に、源泉徴収した所得税を、毎月の支払いから年2回のまとめた支払へ変更するために提出が必要な書類です。
この特例が適用されるのは、常時雇用する従業員が10人未満の場合のみなので、従業員を雇わずに自分だけで事業を行う、または常時10人以上の従業員の雇用を予定している場合は、提出の必要はありません。
「給与支払事務所開設届出書」は、従業員を雇用して給与を支払う場合に提出が必要となります。
状況によって必要な書類は異なるため、どの書類を提出しなくてはならないか判断し、忘れずに手続きを行いましょう。個人事業主と法人の違いまとめ
個人事業主と法人の主な違いは以下の通りです。
個人事業主 法人(株式会社の場合) 設立に必要な手続き 開業届の提出 法人登記(定款の作成、資本金の準備など) 設立にかかる費用 0円 約25万円(株式会社の場合) 納める税金の種類 ・所得税
・住民税
・消費税(課税事業者の場合)
・個人事業税・法人税
・法人住民税
・消費税
・法人事業税など社会的信用度の違い 低い(法人と比べて信用度は劣る) 高い(個人事業主よりも取引や融資で有利に) 会計・申告制度の違い 確定申告を提出 法人決算書を提出 経費の違い 事業に必要なものは経費として認められる、だたし自分への給与や生命保険料は経費にできない 事業にかかる費用の他にも自分の給与や退職金も経費として計上できる 赤字の繰越 3年(青色申告の場合) 10年
個人事業主と法人、どうやって選択する?
上記の通り、個人事業主と法人は手続きや税金、経費の範囲など多くの面で違いがあるため、しっかりと違いを理解したうえでどちらを選択するか検討しなくてはなりません。ここでは、3つのポイントをピックアップして解説します。
従業員数から考える
個人事業主と法人では、どちらも従業員の給与(人件費)を経費として計上できる点では同じですが、雇用する従業員の数によって雇用側が負担する経費の内容が異なります。
法人の場合は従業員数に関わらず社会保険の加入義務があり、会社が保険料の半分を負担しなければなりません。一方、個人事業主が従業員を雇用する場合は原則社会保険の加入義務がなく、法人に比べて人件費の負担は少ないといえます。ただし、2022年(令和4年)10月から常時5人以上の従業員数を雇用する個人事業所は社会保険の加入が義務となったため、雇用人数に注意が必要です。
事業を拡大させるためには従業員の雇用が必要ですが、従業員数が増えればその分雇用側の負担が大きくなることを踏まえて、個人事業主か法人かを検討する必要があります。また、家族を従業員として雇う場合も個人事業主か法人かで条件が異なるため、それぞれのメリット・デメリットを把握しておきましょう。取引先の条件から考える
事業開始前から取引見込みのある取引先や取引したい企業がある場合は、事前に取引先の契約条件を確認するほうがベターです。なぜなら、取引先や仕入れ先によっては法人としか契約を結ばないケースがあるためです。
ビジネスにおいては、個人事業主よりも法人の方が信用度が高いという事実は否めません。個人事業主は「トラブルがあっても保証されない」といった印象を持たれ、取引対象にならない可能性があります。個人事業主か法人かを検討する際は、どのような企業と取引したいのかをあらかじめ考えておきましょう。
特に取引先に制限がなければ、個人事業主として開業しても問題ありません。資金調達方法から考える
起業に資金が必要な業種を選択した場合、起業の際どのような方法で資金を調達するかも、個人事業主か法人かを決める判断基準となります。個人事業主と法人のいずれも融資を受けることは可能ですが、個人事業主よりも社会的信用がある法人の方が資金調達の選択肢が豊富で、株式や債券などを用いた大規模な資金調達が可能です。
個人事業主として起業する際に資金が必要な場合は日本政策金融公庫の融資の利用がおすすめです。日本政策金融公庫は中小企業・小規模事業者を対象に融資を行っており、担保・保証人が原則不要というメリットがあります。起業する前にやるべきこと
個人事業主や法人として起業するために必要な手続きは上述した通りですが、起業前にはほかにもさまざまな準備を行わなくてはなりません。
●家族・知人や会社に報告する
●起業する理由を明確にして事業計画書を作成する
● 資金を調達する
● 宣伝広告を行う
●人材の採用や育成
ここからは、それぞれの内容について詳しく解説します。
家族・知人や会社に報告する
起業や店舗の開業にあたって、家族や知人に協力や援助を依頼することも考えられます。起業についてあらかじめ報告しておくと、相手も事態を把握しやすくなる上に、何かと協力も得やすくなるでしょう。
また、勤めている会社を辞めて独立する場合は、後任者へ引き継ぎを行わなくてはなりません。上司やチームメンバーには適切な順序でなるべく早めに報告し、業務を引き継ぐ時間を確保することで、会社に迷惑をかける心配が少なくなります。起業する理由を明確にして事業計画書を作成する
起業後や店舗オープン後の展望・資金計画といった道筋や見通しを明確にするために、事業計画書を作成しておきましょう。事業計画書は金融機関から融資を受ける際にも必要です。重要な書類のため、必要に応じて専門家からアドバイスを受けるとよいでしょう。
事業計画書の書き方については以下の記事で解説していますので、あわせてチェックしてみてください。
関連記事 事業計画書とはどんなもの?書き方や作成する目的を解説
資金を調達する
起業や店舗オープンに必要な資金を自己資金だけでまかなえない場合は、資金調達を行う必要があります。
資金調達の方法として代表的なものは、金融機関から融資を受ける方法です。一般の金融機関からの融資と日本政策金融公庫からの融資の2つに大きく分けられますが、開業時には後者を利用するほうがメリットは大きいと言えます。
その理由は、創業初期でも融資の審査が通りやすい」「無担保・無保証人でも融資を受けやすい」「金利が低い」といったメリットが享受できるからです。一般の金融機関の場合、売上などの実績がなければ融資が難しいケースもありますが、日本政策金融公庫は中小企業や小規模事業者の資金調達に力を入れている国の政策金融機関のため、民間の銀行より支援に積極的な傾向があります。「
いずれの場合でも比較的低金利で資金を調達できますが、融資である以上必ず返済する必要があることを念頭に置いておきましょう。
また、金融機関からの融資だけでなく、補助金・助成金、クラウドファンディングを活用する方法も選択肢のひとつです。補助金や助成金は、返済の必要がないことが非常に大きなメリットです。各々条件が設けられているため、条件を満たしている場合は積極的に活用するとよいでしょう。
クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数の人から出資を募って資金調達を行う方法で、こちらも融資ではないので調達した資金に関する返済義務はありません。ただし、出資に対する返礼品を用意したり、クラウドファンディングのプラットフォームに手数料を支払ったりする必要があります。
それぞれの資金調達方法のメリット・デメリットを理解して、資金調達の方法を検討しましょう。
また、資金調達の前に開業資金はいくらかかるのか、金額や内訳を知っておく必要があります。以下の記事で開業資金について深堀りしていますので、参考にしてみてください。
関連記事 起業・開業の資金調達方法6選と注意すべきポイントを解説
宣伝広告を行う
事業の開始日や店舗のオープン日が近づいてきたら、近隣の方に知ってもらえるように宣伝を行いましょう。宣伝方法は多岐にわたり、チラシ・タウン誌の出稿・SNSの利用などが代表例です。働きかけられる層は宣伝方法によって異なるため、ターゲット層によって方法を決めましょう。
たとえばSNSでは、いわゆるインスタ映えのような写真を投稿することで、より魅力的な店舗や企業として宣伝効果が見込めます。宣伝に必要な費用は採用する方法によって異なりますが、宣伝広告は起業後も必須のため、費用対効果を確認しながら最適な方法を選びましょう。
人材の採用や育成
場合によっては、起業や店舗運営に必要な人材を採用して育成する必要もあります。起業や店舗オープンまでにあまり時間がなく、育成に時間をかけられなさそうな場合は、必要な経験をすでに有している人を中心に採用することで、育成の手間を省きやすくなるでしょう。今後さらに人を増やす場合に備えて、人材育成の流れやフォーマットは早めに固めておくことをおすすめします。
関連記事 起業準備としてやっておくべきこととは?必要なものや具体的行動について解説!
まとめ
起業には、個人事業主と法人の2つの選択肢があります。どちらにもメリットとデメリットがあり、事業内容に応じて適切な起業方法を選びましょう。
もし判断に迷った際は、ぜひ「canaeru(カナエル)」の利用をご検討ください。canaeruは、経営革新等支援機関(認定支援機関)として国が認めた株式会社USENが運営する開業支援サービスです。税務、金融および企業財務に関する専門的知識や支援にかかる実務経験が一定レベル以上ある支援機関として国に認められています。
canaeruでは経験豊富な開業コンサルタントによる無料開業相談を実施しています。開業のお悩みについて、担当コンサルタントがアドバイスいたします。起業に必須の事業計画書の作成サポートも無料で承っています。
ご相談はこちら
この記事の監修

USEN開業プランナー
長原雄一
株式会社USEN 開業サポートチームに所属。日本政策金融公庫のほか、地方銀行や都市銀行など複数の金融機関にて融資業務を担当。
資金調達の豊富なノウハウを活かし、店舗開業者のサポートを行っている。
【主なサポート内容】
・開業資金にまつわる相談受付
・事業計画書の作成サポート
・資金調達時の面談アドバイス
株式会社USEN/canaeru 開業プランナーの詳細はこちら- NEW最新記事
-
-
2024/10/23
-
2024/10/18
-
2024/10/11
-
- おすすめ記事
-
-
2020/03/12
-
2024/02/01
-
2020/06/10
-
2023/10/31
-
2024/04/03
-
2019/10/28
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数192件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数128件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数506件
-