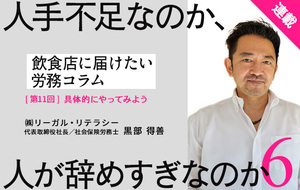- Tweet

焼き鳥屋は大規模な店舗を必要とせず、利益率が高いと言われていることから、飲食店の中でも比較的開業が容易であるという話を耳にしたことがあるかもしれません。
実際に新規開店数も多い業態ですが、開業にはメニューの開発や資金調達など、さまざまな準備が必要です。
たとえ「焼き鳥が好物」や「焼き鳥屋の雰囲気が好き」といった理由から、自分でも焼き鳥屋を開業したいという夢を抱く方でも、開業までに必要な手順を知り、スムーズに進めることが重要です。
この記事では、焼き鳥屋を開業するメリット・デメリットや、焼き鳥屋をオープンするために必要な開業資金、行うべき準備などについて、わかりやすく説明します。
目次
焼き鳥屋を開業する前に必要な準備
焼き鳥屋を始めようと思ってすぐに始められるわけではなく、開業に向けてさまざまな準備が必要です。
● コンセプトやターゲットを決定
● 店舗の取得
● 資金調達
● 従業員の採用と教育
● 資格の取得と関係各所への届け出
● 店舗の準備と仕入れ先の決定
● 店舗オープンの宣伝
以下でそれぞれについて説明します。
コンセプトやターゲットを決定
「焼き鳥屋」と一口に言っても、店舗ごとにコンセプトはさまざまです。
価格設定を低めに抑えて気軽に足を運べるお店にするのか、ブランド鶏にこだわった高級感あるお店にするのかによって、仕入れの方向性なども大きく変わります。
店舗出店を予定しているエリアの市場調査を行い、受け入れられやすいコンセプトにすることが重要です。店舗の取得
店舗を取得したとしてもすぐに開業できるわけではなく、オープンに向けて工事が必要になります。内外装にこだわりがあるのであれば、より時間や手間を要する工程だと言えるでしょう。
また、希望している条件に近い物件がすぐ見つかるとは限りません。
焼き鳥屋の開業を意識したのであれば、しかるべきタイミングでオープンできるように、なるべく早めから物件探しを行うよう心がけましょう。
資金調達
開業に必要な資金を自己資金だけでまかなえない場合は、何らかの方法で資金調達を行う必要があります。
自己資金を調達するためには、金融機関から融資を受ける方法や補助金・助成金を活用する方法が一般的です。
金融機関からの融資は、一般の金融機関からの融資と日本政策金融公庫からの融資の2つに大きく分けられ、開業時には後者を利用するのが有利と言えます。
一般の金融機関の場合、売上などの実績がなければ融資が難しいことも多いですが、日本政策金融公庫は中小企業や個人事業主の支援を主な目的として設立されている金融機関なので、新規事業立ち上げ時などにも積極的に融資を行ってくれます。
申し込みを行って審査に通ることで、いずれの場合でも比較的低金利で資金を調達できますが、融資である以上必ず返済しなければならないため、きちんと返済計画を立てることが重要です。
一方で、補助金・助成金は国や地方自治体で設けられている制度であり、融資ではないので返済の必要がありません。
それぞれの補助金や助成金で設けられている条件をクリアしなければ申請できませんが、条件を満たしている場合には積極的に活用したい方法です。
開業に必要な費用をきちんと把握していなければ適切な資金調達は行えないため、開業に必要な費用を算出した上でどの資金調達方法を活用するか検討しておきましょう。
従業員の採用と教育
焼き鳥屋は一人でオープンすることも可能ですが、スタッフを雇う必要があるのであれば採用活動を行い、きちんと働ける状態でオープンできるように教育しておく必要があります。
フランチャイズに加入した上で開業する場合は、一からマニュアルづくりをする必要がないため、その分の手間が省けます。
資格の取得と関係各所への届け出
焼き鳥屋を開業するためには「食品衛生責任者」の取得が必要ですが、「防火管理者」の取得も必要となるケースもあります。
食品衛生責任者は、焼き鳥屋に限らず飲食店を開業するために必須となる資格です。
各都道府県の食品衛生協会が開催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで取得でき、受講料は都道府県によって若干異なるものの、おおむね1万円程度となっています。
なお、栄養士や調理師などの資格を有している方は、食品衛生責任者養成講習会の受講が免除されます。防火管理者は、収容人数が30名以上の飲食店を開業する場合に必要となる資格で、日本防火・防災協会開催の講習を受講することで取得できます。
店舗の延べ面積によって取得すべき資格が甲種と乙種に分けられており、それぞれ講習の時間や費用が異なるため、取得が必要な種別の講習を受けるようにしてください。
どちらの資格も取得するだけでは意味がなく、食品衛生責任者は管轄の保健所、防火管理者は管轄の消防本部あるいは消防署に届け出を行わなければなりません。
店舗の準備と仕入れ先の決定
店舗となる物件が決まり工事が終わった後は、オープン日に間に合うように備品を購入し、営業に使う備品の配置なども行う必要があります。
たとえば、アルコール用のグラスをしまう場所や、メニューを設置する場所、調理器具を保管する場所などを検討しなくてはなりません。
また、料理に用いる材料の仕入れ先も、なるべく早めに決めておいたほうがよいでしょう。
店舗オープンの宣伝
オープン時期が近づいてきたら、実際にオープンする前に近隣の方に知ってもらえるように宣伝を行いましょう。
宣伝方法としては、チラシ、タウン誌への広告出稿、SNSの利用などが考えられます。チラシは高齢者層の方が目にすることが多く、SNSは若年層が目にする傾向にあるため、店舗のターゲット層に合わせた方法で宣伝を行ってください。
宣伝方法によって必要な費用は異なるので、資金と相談しながら宣伝方法を決めることをおすすめします。焼き鳥屋をオープンするために必要な開業資金
焼き鳥屋をオープンするために必要な開業資金の内訳として、主に以下のものが挙げられます。
● 物件取得費
● 内外装費
● 設備導入・備品購入費
● 広告宣伝費
● 運転資金
物件取得費は立地や店舗の大きさにもよりますが、おおむね300万円~500万円程度を見ておくとよいでしょう。首都圏や大都市圏の一等地に関してはこれ以上かかる場合もあります。
そのほかの費用に関しては、内外装費は200万円~1,000万円程度、設備導入・備品購入費は50万円~100万円程度、広告宣伝費は50万円~100万円程度、運転資金は300万円程度が平均的な金額です。
全体的なイメージとしては800万円~1,500万円程度あれば、焼き鳥屋をオープンできると考えられます。
なお、フランチャイズに加盟する場合は別途フランチャイズ関連の費用も必要なので、そちらも合算して考えてください。
参考記事 飲食店の開業に必要な資金はいくら?開業に必要な資金や資格
焼き鳥屋は比較的開業しやすい?業務内容について
このように開業前にも多くの準備が必要となる焼き鳥屋ですが、本当に開業しやすい業種なのでしょうか?今度は具体的な業務内容を確認しておきましょう。
調理と料理の提供
焼き鳥屋の業務内容は第一に調理と料理の提供があります。食材を下ごしらえし、様々な部位や種類を炭火やガスコンロを使用して焼き上げます。焼き鳥の調理には部位に応じた串打ちや火入れの高い技術が必要です。
串焼きでの提供が一般的ですが、宮崎風とも言われる鉄板をお皿代わりにしてお客様へ提供するスタイルもあります。
在庫/設備管理
焼き鳥屋では鶏肉や調味料などの食材を定期的に仕入れ、新鮮さを確保するための徹底的な管理が必要となります。さらに、需要予測に基づいた適切な仕入れと在庫管理で食材ロスを最低限に抑えなければなりません。
また、毎日使う焼き場や調理場などを清潔に保つことで、食材や料理の品質維持にも繋がるでしょう。メニュー開発
メニュー開発は、焼き鳥屋が新たな魅力を発信し続けるための要素です。季節や顧客の嗜好に合わせて新しいメニューを開発することで、得難い食体験を提供し、顧客の期待に応えることが大切です。
集客
インスタグラムやTikTokをはじめとする写真・動画共有SNSのほか、グーグルマップを活用した集客方法が近年の主流です。こうしたデジタルマーケティング力を身につけておくことは、焼き鳥屋に限らず飲食店の成功に欠かせないポイントとなっています。
焼き鳥屋を開業する3つのメリット
焼き鳥屋を開業するにあたって以下のようなメリットが挙げられます。
● 初期費用やランニングコストを抑えやすい
● 高い利益率が見込める
● メニューがシンプルで特別な資格も必要ない
それぞれのメリットについて、詳細を説明します。
初期費用やランニングコストを抑えやすい
焼き鳥屋は小規模店舗での開業が可能なため、物件取得費や内装費など、物件にかかる初期費用を抑えやすいというメリットがあります。小規模店舗であれば家賃も下がり、ランニングコストも節約できます。
また、焼き鳥屋でメインとなる材料の鶏肉は、牛肉や豚肉などよりも安価で仕入れやすい上に、時期による価格の変動もほとんどないため、仕入費用を抑えやすいです。
高い利益率が見込める
焼き鳥屋ではメインで取り扱う焼き鳥と一緒に、ビールやハイボールといったアルコールの注文も入りやすい業態です。
アルコールは飲食店において利益率が高い商品です。そのため、客単価自体がそこまで上がらなくても高い利益率が見込めるところが、焼き鳥屋の大きな強みでもあります。メニューがシンプルで特別な資格も必要ない
焼き鳥屋のメニューはほかの飲食店に比べると比較的シンプルなことが多いので、スタッフに調理工程を覚えさせるための教育に、膨大な手間や時間を割かなくてもよい傾向があります。
また、焼き鳥を焼くために特別な資格も必要ありません。
開業前に時間をかけて資格を取得する必要もないので、開業を目指しやすい業種と考えられているのかもしれません。焼き鳥屋を開業する2つのデメリット
開業しやすい業種を探している方にとって焼き鳥屋は魅力的ですが、焼き鳥屋の開業にはデメリットも存在します。
ここでは、焼き鳥屋を開業する際の2つのデメリットについて説明します。
競合が多い
開業しやすいことが焼き鳥屋のメリットではありますが、それは同時にライバルの多さにも繋がる要因です。
同業者の中で個性や特徴を上手く押し出すことができなければ、継続して営業することは難しくなるでしょう。
「同業者」のくくりを同じ焼き鳥屋だけではなく、「鶏をメインに扱う料理店」や「仕事帰りに一杯飲むために立ち寄る店」などまで広げて考えれば、競争はより厳しいものになります。
売上が立地に左右されやすい
焼き鳥屋は、「仕事帰りにちょっと一杯」という形で利用されるケースが多いため、ビジネス街や駅・繁華街の近くでは売上が伸びやすい傾向があります。
その一方、そういった目的での流入が見込みにくい人通りが少ない場所は、客足が伸びにくいです。
これは焼き鳥屋に限らず飲食店全般に言えることではありますが、売上が立地に左右されることには十分注意しておく必要があります。
焼き鳥屋の開業を成功させるためのポイント
ここまで開業までの準備と開業後の業務内容について押さえてきましたが、開業することがゴールではありません。
長期的な視点で経営を考え、お店を成長させていくためには、効果的な経営戦略を練ることが重要です。他店と被らない、明確なコンセプトを考える
焼き鳥屋は競合が非常に多い業態です。その中で勝ち抜くためには、他店にはない特徴や強みが不可欠です。
例えば、鶏肉の仕入れにおいて一羽丸ごと仕入れる方法があります。これには『食鳥処理衛生管理者』という資格が必要ですが、取得のハードルが高いため他店との差別化を図ることができます。また、「希少部位や市場に出回らない部位が楽しめる」という独自の強みが生まれ、かつ大きな宣伝効果も期待できます。
ただし、重要なのは価格競争に巻き込まれないことです。安価で提供している店はその理由があるため、価格で勝負するのではなく、少々高額でもお客様が通いたくなるようなこだわりを持つことが重要です。
コストパフォーマンスのいい料理を提供する
コストパフォーマンスは、提供される料理の品質や味わいがその価格に見合ったものであるかどうかを指します。特に焼き鳥屋をはじめ飲食業界は競争が激しいため、お客様はよりリーズナブルでありながらも美味しい料理を求める傾向があります。
ただし、価格を無制限に下げることは利益に繋がりません。お客様にとって納得のいく価格でありながら、良質な料理を提供することが重要です。料理の品質と価格のバランスを見極め、お客様に支払いたいと感じていただけるクオリティを提供することが成功の鍵となります。
コンセプトにあった集客の見込める場所で開業する
コンセプト設定は、開業エリアの選定に直結します。例えば、大衆向けの焼き鳥屋を展開する場合、オフィス街や学生街、商店街などが最適です。一方で、高級な焼き鳥屋を展開する場合は、東京ならば銀座や麻布、広尾など、その高級感を漂わせるエリアを選ぶことが必要です。コンセプトとエリアの調和が、成功の鍵となります。
フランチャイズで開業するメリット・デメリット
焼き鳥屋の開業はフランチャイズを利用する方法もあります。この項目ではそのメリットとデメリットをそれぞれ確認しましょう。
フランチャイズで開業するメリット
①経営サポートとトレーニングを受けられる
フランチャイズに加盟すると、本部からマニュアルやトレーニングプログラムが提供され、経営や運営に関するノウハウを学ぶことができます。飲食店経営や調理の経験が少ない方にとっては独立開業よりも成功しやすい開業方法と言えるかもしれません。
焼き鳥屋のフランチャイズにおいては、難しいとされる串打ちや焼きの技術に関してもマニュアル化されていることが多いため、未経験でも始めやすいことが大きな特徴です。ただし、フランチャイズによっては調理技術が必要な場合もあるので事前に確認しておきましょう。
②決まった仕入れルートがある
焼き鳥屋を開業する際、最も難しい課題の一つは仕入れ先を確保することと言われています。もし有名店で修業を積んだ経験があれば、そのネットワークを活かしたり、既に仕入れ先との関係を築いているかもしれませんが、まったくのゼロから始める場合、仕入れ先を見つけるだけでも相当な労力がかかります。
一方で、フランチャイズを利用すれば、既に確立された仕入れルートが存在するため、新たに見つける必要がありません。
③開業資金が借りやすい
個人で飲食店を開業する際、経験が浅く実績がない場合、融資を受けるのが難しいこともあります。一方でフランチャイズを活用すれば、そのブランドに対する信用があるため融資が受けやすいと言われています。
しかし、あまりにもブランドの信頼性に依存しすぎると、資金を借りる際に自主性が疑われてしまう可能性があることも注意しておきましょう。
フランチャイズで開業するデメリット
①オリジナルのメニュー開発が難しい
フランチャイズを利用する場合、既にメニューが確定しているため、新しい商品を開発することは難しいとされています。フランチャイズを利用して経営や調理のノウハウを学び、将来的な独立開業を目指す方にとって、メニュー開発の制限はその足枷になってしまう可能性があるため、契約する前に確認しておきましょう。
②競合と差別化しにくい
フランチャイズは同一ブランドの他店と直接的な競合が生じる可能性があり、他店との差別化が難しくなることがあります。オリジナルのメニュー開発など、同じフランチャイズ内での差別化を図る方法があるかどうかも考慮すべき点です。
③初期投資やロイヤリティの発生
どのフランチャイズにも言えることですが、フランチャイズを利用する際には、基本的に特定のブランドやノウハウを使用するための初期費用やロイヤリティが発生します。これが独立開業に比べて費用がかさむ可能性があるため、利益を生みづらいかもしれません。
軽トラや屋台で焼き鳥屋を開業するには?
焼き鳥屋は実際に店舗を構えるのではなく、軽トラをキッチンカーに改造したり屋台を利用したりする形でも開業できます。
軽トラや屋台を利用して焼き鳥屋を開業する際の方法や必要資金、注意点について説明します。
開業方法
軽トラや屋台で焼き鳥屋を開業するためには、物件を取得する代わりに軽トラや屋台を購入する必要があります。
それ以外に必要な準備や手続きに関しては、店舗で焼き鳥屋を開業する場合とおおむね変わりませんが、取得する資格に関しては食品衛生責任者のみで営業できるため、防火管理者は必要ありません。
また、出店地を管轄する保健所に営業許可を申請する必要があることや、焼き鳥を調理できるように車両を改造した場合は、その旨を申請して登録しなくてはならない点は覚えておきましょう。
開業資金
開業資金に関しては、物件取得費用や内外装費が必要ない代わりに、車両の購入費用や改造費用などがかかります。
設備導入・備品購入費や広告宣伝費、運転資金などには大きな違いはありませんが、店舗を購入したり家賃を支払ったりする必要がない分、店舗を取得して営業する場合よりも開業資金は安くなる傾向にあります。
また、車両を用意しなくてよいことから、テントで出店する屋台形式のほうが費用を抑えやすいと言えるでしょう。
軽トラや屋台で焼き鳥屋を開業する際の資金の目安としては、20万円~500万円程度を想定しておくとよいでしょう。
注意点
軽トラや屋台は自由に移動できるため、人通りの多いところで営業できるところは大きなメリットですが、営業を行う場所に応じて事前に営業許可を取得しておかなければなりません。
また、軽トラや屋台の中で仕込みを行うことはできないため、仕込みを行うための場所をどこかに確保しておく必要があります。
なお、仕込み場所に関しても許可申請が必要となるため注意してください。
参考記事 キッチンカーの開業に必要な資金って?開業準備に必要なものも紹介
必要な手続きや段取りを踏まえて焼き鳥屋の開業を目指そう
焼き鳥屋は飲食店の中でも、コストを抑えながら高い利益率が見込みやすい業種です。
開業資金として800万円~1,500万円ほど必要となるので、自己資金だけで調達するのが難しそうな場合は、金融機関からの融資や補助金・助成金などを利用しましょう。
そこで焼き鳥屋の開業準備を支援してくれるサービスを利用すれば、開業にあたって活用できる制度についても教えてもらえるため、最適な形で資金調達に臨めるでしょう。
飲食店の開業支援を行う「canaeru(カナエル)」では無料で開業相談を受け付けているので、開業に向けての悩みや疑問を払拭でき、資金調達方法についてのセミナーなどに参加することも可能です。
焼き鳥屋を開業するにあたって不安がある方は、ぜひcanaeruの無料開業相談サービスを利用してみてください。
ご相談はこちらこの記事の監修

USEN開業プランナー
松村俊治
株式会社USEN 開業サポートチームに所属。飲食店経営歴8年。その経験を活かし、開業に関するあらゆる支援を行う。開業に必要なサービスや設備、業者などの紹介のほか、店舗のコンセプト設計、事業計画書の作成サポートにも精通。
【主なサポート内容】
・開業手続きの支援
・開業に必要なサービス、設備、業者を紹介
・創業計画書の作成サポート
・事業計画書の作成サポート
株式会社USEN/canaeru 開業プランナーの詳細はこちら- NEW最新記事
-
-
2024/10/23
-
2024/10/18
-
2024/10/11
-
- おすすめ記事
-
-
2018/03/20
-
2024/07/11
-
2018/09/07
-
2024/04/03
-
2022/01/30
-
2017/06/28
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数192件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数128件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数506件
-