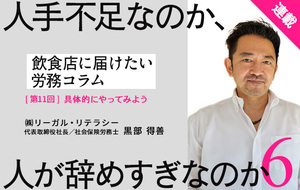- Tweet

サラリーマンにとって確定申告を行う機会はそう多くはないかもしれません。しかし、副業による損失が生じた場合に、確定申告で損益通算をすることで得られるメリットがあります。
この記事では、サラリーマンが確定申告で損益通算を行うための条件や、確定申告で損をしないための方法をご紹介していきます。目次
- 確定申告の損益通算とは?
- 確定申告で損益通算する際の注意点
- 事業所得と判断される場合
- サラリーマンが確定申告で損益通算をするデメリットは?
- ①手間と時間の負担
- ②申告書の複雑性
- ③損益通算の効果が限定的
- サラリーマンが確定申告で損益通算をするメリットは?
- 副業について事業所得や雑所得として確定申告すると負担が増えることがある?
- 確定申告の必要が無い場合
- 損益通算の手順は?
- ①書類を準備する
- ②所得を計算する
- ③損益通算を行う
- ④納付すべき所得税を計算する
- ⑤確定申告書に必要事項を記入し提出する
- サラリーマンが副業で開業する場合、青色申告がおすすめ!
- 青色申告のメリット
- 確定申告が必要な場合とは
- サラリーマンが損をしないための確定申告は?
- 1年間で10万円以上の医療費を支払った人(医療費控除)
- 寄付を行った人(寄付金控除)
- 途中退職し、年末調整のタイミングで未就職の人
- 年末調整で考慮されなかったものがある場合
- 社会保険や税金のポイント
- サラリーマンが開業する場合には確定申告や税金に関する注意点を押さえておきましょう
確定申告の損益通算とは?
確定申告の損益通算とは、事業などで生じた損失と、給与所得など他の所得がある場合に、これらを相殺して所得を計算すること
を言います。この損益通算を行うと、所得が減少するため、税金の支払を少なくすることができます。
確定申告で損益通算する際の注意点
損益通算は、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得(総合)から生じた損失からでしか、他の所得と相殺することはできません。
一般的には、サラリーマンが副業で得た所得は雑所得となりますので、副業で損失が出ても損益通算することはできません。
しかし、次の要件を満たす場合は雑所得ではなく、事業所得となる場合があるので、事業所得で損失が出た場合は、損益通算が可能になります。事業所得と判断される場合
●副業に係る取引を記録した帳簿書類の保存があること
●副業が社会通念上事業と称するに至る程度で行っていること
ただし次の場合には、事業所得かどうかの判断は、個別の判断となります。
●収入金額が毎年(3年間ぐらい)300万円以下で、給料など本業の収入の10%未満
●毎年(3年間ぐらい)赤字で、かつ、収入を増加させる又は黒字にするための営業活動等をしていない場合
社会通念上によるところなどから、事業所得と雑所得の境界線は曖昧なため、どちらに該当するのか不安な方は、税務署に確認するとよいでしょう。
なお、株式等の損失、不動産の譲渡損失、国内FXによる損失などは、給与所得などの所得と損益通算できません。サラリーマンが確定申告で損益通算をするデメリットは?
サラリーマンが赤字の副業を事業所得として、他の所得と損益通算する場合には、いくつかのデメリットが考えられます。
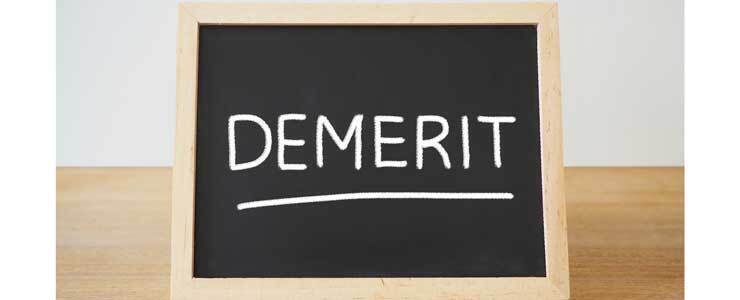
①手間と時間の負担
確定申告で損益通算を行うには、詳細な帳簿をつけたり、取引履歴を整理したりしなければなりません。これには手間や時間がかかり、煩雑な作業となる可能性があります。
②申告書の複雑性
サラリーマンは通常、会社が年末調整をやってくれるので、自分が税金等の計算をする必要はありません。しかし、副業で赤字が出たため、確定申告で損益通算をする場合は、一般の事業所得と同様の処理が必要になります。
また、誤りや不備があると税務署からの問合せや追徴課税のリスクなどが生じる恐れもあります。
③損益通算の効果が限定的
サラリーマンの場合、給与所得控除額や所得控除、住宅ローン控除などの税額控除などが既に適用されていることが多いため、損益通算による恩恵が限定的な場合があります。そのため、手間と時間に見合った利益を得られないかもしれません。
サラリーマンが確定申告で損益通算をするメリットは?
サラリーマンが確定申告で損益通算を行うメリットは、副業での事業所得に赤字が生じた際、それを給与所得と相殺し、最終的な所得を引き下げることができる点にあります。所得が小さくなれば所得税も少なくなり、結果として年末調整で負担した所得税が還付されます。
副業について事業所得や雑所得として確定申告すると負担が増えることがある?
副業で赤字が出た場合は、事業所得として損益通算をすれば、税金が安くなることがありますが、副業で黒字となった場合で、以下のように確定申告をする必要が無い場合に確定申告をすると税金の負担が増える可能性があります。
確定申告の必要が無い場合
※給与所得と副業の所得(事業所得か雑所得)のみがあるケース
●給与を1か所から受けている場合で、副業で得た所得(収入-経費)が20万円以下の
場合
●給与を2か所以上から受けている場合は、年末調整をされなかった給与の収入金額と副業で得た所得との合計額が20万円以下の場合
●給与を2か所以上から受けており、その給与所得の収入金額の合計額から一定の所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万円以下、さらに副業で得た所得の合計額が20万円以下の場合
など…
損益通算の手順は?
確定申告で損益通算を行うには、確定申告書の用紙に記載するほか、専用のソフトやアプリ、国税庁のホームページに設けられている「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、必要な手順を踏んでいきます。
副業で事業所得を得ているサラリーマンを一例として、手順を確認しましょう。①書類を準備する
まずは提出書類の準備です。確定申告書等の用紙(専用のソフトやアプリ、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用する場合は不要)や給与の源泉徴収票などの準備をしましょう。源泉徴収票は給与の支払を受けている会社から受取りましょう。
【準備するもの】
●確定申告書の用紙(第一表、第二表)
●給与の源泉徴収票
●各種所得控除などの添付書類
●青色申告決算書又は収支計算書の用紙
●マイナンバーカードまたは通知カード(コピー)②所得を計算する
次は収入と経費から所得を計算します。所得とは収入から経費を差し引いた金額です。収入とは事業により得た売上を指し、経費とはその事業で使った支払金額を指します。
これらを元に青色申告決算書や収支内訳書を作成します。③損益通算を行う
事業所得が算出できたら、事業所得と給与所得を相殺し、損益通算を行います。
給与所得と相殺することで所得金額が減少します。④納付すべき所得税を計算する
事業所得と給与所得の損益通算を行ったあとの所得金額と各種所得控除等を元に所得税を計算します。還付されるべき金額が生じた場合には、指定した還付口座へ後日還付額が振り込まれます。
⑤確定申告書に必要事項を記入し提出する
①~④のステップに従い、確定申告書を完成させます。
確定申告書の提出方法はe-Tax、郵送、税務署への持ち込みが選べます。e-Taxの場合は、確定申告ソフト、確定申告アプリなどから提出できます。
ただし、e-Taxの場合は、マイナンバーカードとPCで行う場合はカードリーダー、スマートフォンで行う場合はカード読み込みに対応しているスマーフォンが必要です。サラリーマンが副業で開業する場合、青色申告がおすすめ!
副業で事業所得となる要件(上記の「確定申告で損益通算する際の注意点」 参照)を満たすようであれば、損益通算ができ、青色申告で確定申告を行えば、主に次のようなメリットが受けられます。
青色申告のメリット
●最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
●赤字を最長で3年間繰り越せる
●家族への給与を経費にできる
●取得価額が30万円未満の減価償却資産を一度に費用計上できる
など…
白色申告でも、損益通算は可能ですが、青色申告にすることで、多くのメリットが受けられます。
副業で事業所得となる際は、ぜひ青色申告での提出を検討してみて下さい。確定申告が必要な場合とは
サラリーマンで確定申告が必要となるケースは主に以下の2つです。
●給与の収入金額が2,000万円を超える場合
●給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える場合
など…
会社からの給与が2,000万円を超えている場合や、複数の会社から給与の支払いがあったり、給与以外の所得が20万円を超えたりする場合は、確定申告が必要です。
サラリーマンをしながら副業をしていても、その副業部分の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。
しかし、副業が事業所得で赤字がある場合は、損益通算できる可能性がありますので、確定申告の必要がなくても、確定申告をする場合のデメリットも考慮して検討しましょう。
サラリーマンが損をしないための確定申告は?
1年間で10万円以上の医療費を支払った人(医療費控除)
申告者自身と生計一の家族の分を合わせて、年間の医療費を10万円以上支払った場合は、10万円を超える部分が医療費控除の対象となります。
なお、医療費が10万円に満たない場合でも、所得が200万円以下の場合は医療費控除の対象となります。寄付を行った人(寄付金控除)
ふるさと納税により、任意の自治体に寄付を行った場合、2,000円を超える金額を所得税・住民税から控除できます。寄付金控除は年末調整で手続きできないため、サラリーマンであっても確定申告が必要です。
ただし、ふるさと納税の寄付先が5自治体以内ならば、「ワンストップ制度」を利用することで確定申告することなく控除が受けられます。
しかし、副業による事業所得又は雑所得がある場合など、確定申告をする場合は、確定申告で「寄付金控除」の処理をしなければなりません。途中退職し、年末調整のタイミングで未就職の人
年末調整は、毎年の年末時点(12月31日時点)に会社に在籍している方に対して行われます。もし年の途中で会社を退職し、年末までに再就職していない場合は、会社で年末調整が行われないため、確定申告が必要になります。
給与が1年間で103万円以下の場合は確定申告が不要ですが、退職前の給与から源泉徴収された所得税がある場合は、確定申告することで納めすぎた所得税が還付される可能性があります。年末調整で考慮されなかったものがある場合
年末調整で生命保険料控除などの所得控除、初年度の住宅ローン控除などがある場合は、確定申告することにより所得税が還付される可能性があります。
社会保険や税金のポイント
サラリーマンが開業する場合は、社会保険や税金でいくつか気を付けるべきポイントがあります。
在職中は保険や年金に関しては、会社の健康保険・厚生年金に加入している場合は、特別な手続きは必要ありません。扶養家族がいる場合も同様です。しかし、退職をして健康保険・厚生年金の資格を喪失した場合は、国民健康保険・国民年金に加入する義務があります。
退職をしても、会社で加入していた健康保険を2年間任意継続できることもあるので、該当するか確認するとよいでしょう。国民健康保険より保険料が安くなる可能性があります。
なお、年の途中で開業した場合の社会保険料や所得税、住民税は、その年の給与所得と開業に係る事業所得や雑所得を合算した所得で計算されます。サラリーマンが開業する場合には確定申告や税金に関する注意点を押さえておきましょう
サラリーマンが開業すると、メリットだけではなくデメリットも多く存在します。それぞれのポイントを押さえておくことで、開業する際に動きやすくなるでしょう。
ただ、自分の力のみで開業する自信がない方は、canaeruの無料開業相談を受けるのがおすすめです。
日本政策金融公庫・銀行出身者など実績を積んだプロが、相談をお受けします。無料で相談できるので、これから開業したいと考えているサラリーマンの方は、以下のリンクからぜひご相談ください。
開業の無料相談はこちら- NEW最新記事
-
-
2024/10/23
-
2024/10/18
-
2024/10/11
-
- おすすめ記事
-
-
2018/11/30
-
2017/11/20
-
2018/07/13
-
2022/09/30
-
2020/04/13
-
2024/05/20
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数192件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数128件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数506件
-