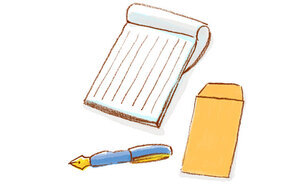- Tweet

2023年10月から導入されたインボイス制度(適格請求書保存方式)。個人事業主として飲食店を経営するオーナーの中には、まだ具体的な対応を考えていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、インボイス制度は飲食店にとっても無視できない税制変更です。
制度の詳細を知らずに従来通りの請求書やレシートを発行していると、知らぬ間に客足が遠のいたり、得意先から取引の停止を求められることも。
この記事では、インボイス制度が飲食店に与える影響や、具体的な対策について解説しています。インボイス制度への対応を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。目次
- インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
- インボイス制度を導入する目的・背景
- インボイス制度導入による飲食店への影響とは?
- 飲食店経営者が免税事業者の場合の影響
- 飲食店経営者が課税事業者の場合の影響
- インボイス制度の導入で飲食店がすべき準備は?
- 適格請求書発行事業者の登録をする
- レシート・領収書の表記を適格簡易請求書に合わせる
- インボイス制度に対応したレジ・システムを導入する
- クラウド請求サービスを利用する
- 【対象別】インボイス制度導入後に飲食店が行う対応
- 顧客への対応
- 仕入れ先への対応
- 取引先への対応
- インボイス制度導入後も利用できる補助制度はある?
- IT導入補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 要注意!補助金は誰もが受け取れるものではない
- まとめ
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
「インボイス」とは、日本語にすれば「適格請求書」のこと。それでは「適格請求書」とは何か?というと、売り手が買い手に対して発行する請求書のうち、適用税率や消費税額等を正確に記載している請求書のことです。では、何のためにインボイスが必要なのでしょうか?
一つ、わかりやすい例を挙げましょう。
例えば、あなたが1,000円の商品を売り上げた場合、通常、顧客からは商品代金の1,000円+消費税100円の支払いを受けます。課税事業者の場合、この消費税100円は「顧客から預かった税金」として税務署に納付しなければいけません。
しかし、この1000円の商品を700円で仕入れていた場合、あなたは仕入れ業者に代金700円+消費税額70円を既に支払っているはずです。となれば、納付すべき消費税額は100円-70円の30円で構いません。
つまり、利益額である300円(1,000円-700円)に対する消費税額のみを納めればよいのです。
このように、売り上げ時に受け取った税額から仕入れの際に支払い済みの税額を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。
しかし、仕入れ時に「買い手」が支払った消費税額や適用税率(8%か10%か)を、仕入れ業者等の「売り手」から正確に伝えられていなければ、当然この仕入税額控除を正しく行うことができません。
そして仕入税額控除が行えない場合、消費税額を過剰に支払ってしまうことになります。
これを防ぐために導入されるのがインボイス制度。正式名称は「適格請求書等保存方式」であり、インボイスとは「商品に課税されている消費税率・消費税額が明記されている請求書、及びそれに類するレシートや領収書、納品書」のことなのです。インボイス制度を導入する目的・背景
インボイス制度とは、一言で言うと「適格請求書などの保存を、仕入税額控除の新たな要件とする」制度。ごくごく砕いて言えば「仕入れの際に、従来とは違う特別な請求書(=適格請求書、インボイス)を受け取らないと、仕入税額控除が行えない」、その場合「納付する消費税が増えてしまう」制度のことです。
パッと見た限り、事業者にとっては面倒でデメリットばかりの制度に見えてしまいませんか?仕入税額控除は従来も行えていたはずなのに、なぜそんな制度が導入されるのでしょう?
大きな理由の一つが、2019年10月に導入された軽減税率です。消費税率が10%に上がるのに伴い、お酒や外食を除いた食料品全般や定期購読の新聞など、生活に必須の特定品目のみが消費税8%に据え置きになったことは、みなさんの記憶にも新しいでしょう。
結果として、請求書にも8%と10%の品目が混在することになり、消費税額の計算が以前よりも煩雑になりました。そのため、それぞれの品目に対する消費税率(8%か10%か)と、適用税率ごとに区分した合計額・消費税額を明記させることで、正確な税額を確認する必要が出てきたのです。
もう一つが事業者における益税、すなわち「消費税のもらい得」を防止することです。
例えば一般の消費者が事業者に物品を売却して利益を得た場合、当然ながら消費者に消費税を納める義務はありません。しかし、事業者の側が消費税込みで購入したことにしてしまえば、商品代金に消費税額を加えた金額を仕入れ額として計上することができます。
つまり、支払ってもいない消費税を支払ったことにして、仕入税額控除を受ける。そのような不正の是正もインボイス制度の目的なのです。
上記のような複数税率の混在に加えて、現行制度では請求書の発行が売り手の義務とはなっていないために、事業者が支払った消費税額を正確に算出するのが非常に困難になっています。
そこで仕入税額控除を受けるために必要な請求書の基準を厳密に定め、消費税納税の透明性を図ろうというのが、インボイス制度導入の根本的な理由なのです。インボイス制度導入による飲食店への影響とは?
インボイス制度は飲食店にどのような影響を与えるのでしょうか?
その影響についてお伝えする前に、前提の知識として以下の用語について解説します。これらを知っておくことでインボイス制度について理解しやすくなり、どのような影響が発生し、どのような対応をしていけばよいのかが見えてきます。
●免税事業者と課税事業者
●原則課税と簡易課税
インボイス基礎知識①免税事業者と課税事業者
インボイス制度は消費税にまつわる仕組みですが、税の観点から見ると事業者は免税事業者と課税事業者に分類することができます。
免税事業者とは、消費税の納税が免除される事業者です。具体的には、基準期間(前々年度)の年間売上高が1,000円以下の事業者は消費税の納税が免除されます。なお、開業して間もない事業者は売上の実績がないため、免税事業者となります。
一方で、消費税の納税対象となる事業者を課税事業者といいます。基準期間の年間売上高が1,000万円を越えると、消費税の納税義務が発生し、課税事業者となります。納税期限は年によって細かな日程で変わりますが、概ね3月末〜4月初旬に設けられています。
なお、消費税は国税と地方税の2つに分けられているため、課税事業者はそれぞれを集計して納税しなければなりません。
この免税事業者と課税事業者の違いは、インボイス制度に対してどのような対応をしていくべきかを考える上で基礎的な知識となります。しっかりと理解しておきましょう。
インボイス基礎知識②原則課税と簡易課税
消費税には原則課税と簡易課税という2種類の方式があります。原則課税は一般的な集計方法で消費税を集計するもので、それを簡略化させたものが簡易課税です。
そもそも消費税はどのように集計されるのでしょうか?一般的に消費税は以下の計算で導き出すことができます。
消費税=売上×消費税率 - 仕入れなどで支払った消費税額
これがいわゆる、原則課税です。
式はシンプルですが、売上といっても課税・非課税のものがあり、計算する上でまず分類しなければなりません。また、消費税は国税と地方税に分かれており、それぞれを計算しなければならず、手間がかかります。
この煩雑な作業を大幅に簡略化できるのが簡易課税です。その集計方法は以下の通りです。
消費税=A(売上×消費税率) - (A × みなし仕入れ率)
みなし仕入れ率とは、6つに分類された業種ごとに設定された割合です。国税庁によって業種と割合の分類が定められています。
簡易課税は集計がシンプルになるため、業務負担の軽減に繋がります。また、原則課税よりも簡易課税の方が税額が安くなる場合もあります。節税を考えたい場合は、税額が低いのはどちらかを見極めた上で申告した方がよいでしょう。
ただ、簡易課税は全ての事業者が導入できるものではなく、基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者が対象となっているので要注意です。
いかがでしたでしょうか?以上の用語をご理解いただいた上で、インボイス制度が免税事業者と課税事業者にどのような影響を及ぼすのか、次項から解説していきます。
飲食店経営者が免税事業者の場合の影響
インボイス制度導入後、免税事業者の飲食店には以下のような2つの影響が発生すると考えられます。
●顧客が離れてしまう可能性
●消費税分を乗せた価格での提供がしづらくなる
それぞれ解説します。
顧客が離れてしまう可能性
免税事業者の飲食店は、レシートや領収書が必要な顧客が離れてしまう可能性があります。
顧客がレシートや領収書が適格請求書として受け取れない場合、仕入れ額控除が適用されません。そうなると、飲食店に消費税を払いながら事業の売上にかかる消費税を全額納めなければなりません。
つまり、支払う消費税の額が増えてしまうということです。
顧客がこの消費税の増税を免れるためには、仕入れ額控除が適用される飲食店=課税事業者の飲食店を選ぶ必要があります。
この動きが加速すると、免税事業者の飲食店は集客に影響が及ぶでしょう。特に接待など経費が伴う会食が多いレストランなどは注意が必要です。
消費税分を乗せた価格で提供がしづらくなる
仕入れ額控除が適用されないにも関わらず、免税事業者が消費税を商品価格に乗せて請求する点に疑問を持つ顧客もいるでしょう。
免税事業者が商品に消費税を乗せて請求する行為は、違法ではありません。実際に今まで免税事業者が受け取った消費税は、国や地方へ納めずにそのまま受け取ることが認められていました。(これを「益税」といいます。)
今後はインボイス制度によって免税事業者と課税事業者の立場がより明確になり、益税を得ることがイメージの悪化に繋がる可能性も高まっています。飲食店経営者が課税事業者の場合の影響
一方で課税事業者の飲食店にはどのような影響が発生するのでしょうか?主に考えられる影響は、以下の2点です。
●適格請求書発行の申請や領収書の準備が必要
●仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうかを確認する
それぞれ解説します。
適格請求書発行の申請や領収書の準備が必要
適格請求書を発行するには「適格請求書発行事業者」にならなければなりません。適格請求書発行事業者になるためには申請が必要です。
また、レシートや領収書のフォーマットも今までのものではなく、インボイス制度に則った書式に変更します。適格請求書は掲載しなければならない項目が定められており、それらの項目がないと適格請求書として認められないので要注意です。
具体的な申請方法や作成方法は後ほど詳しく解説します。
仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうかを確認する
レシートや領収書の変更は顧客に対する準備ですが、食材やドリンクなどの仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうかを確認しておくことも大切です。
仕入れ先が適格請求書発行事業者であれば今まで通りで問題ありませんが、免税事業者の場合は仕入れ額控除が適用されません。つまり、今までは仕入れ先に支払う消費税の分が税額控除されていましたが、その控除が無くなり、消費税の増税に繋がるということです。
増税を避けるためには、今まで請求されていた消費税分を引いた商品価格にしてもらうなどの価格交渉を行うか、適格請求書発行事業者になってもらうよう相談する必要があります。インボイス制度の導入で飲食店がすべき準備は?

適格請求書発行事業者の登録をする
適格請求書発行事業者としての登録を受けるためには、登録申請書を提出しなければなりません。申請書提出の方法には、
●所轄の税務署へ持参
●所轄の税務署へ郵送
●e-Taxを利用した電子提出
の3つがあり、税務署による審査を経て、登録番号が通知されます。
登録番号のほか、適格請求書発行事業者の氏名又は名称、登録年月日などの情報も、登録次第インターネットを通じて公表されます。レシート・領収書の表記を適格簡易請求書に合わせる
適格請求書発行事業者になったら、レシートや領収書を定められた書式に変えなければなりません。適格請求書に必要な項目は下記の通りです。
(引用:「適格請求書等保存方式の概要」国税庁)①求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
これは一般的な適格請求書ですが不特定多数の人を顧客とする飲食店は、⑥を省略することができます。この一部簡略化した適格請求書を「適格簡易請求書」といいます。
つまり飲食店の場合、適格請求書発行事業者になったら①〜⑤までを記載したレシートや領収書を用意すればよいのです。
POSレジやキャッシュレス決済を導入している場合、端末の設定変更が必要となるかもしれません。提供元に確認するなどして対応するようにしましょう。
手書きで対応している場合は、店舗の印鑑に登録番号を刻印しておけば領収書に押すだけで済みます。ただ、今まで不要だった税率の記載をしなければならないため、その対応も忘れないように注意しましょう。インボイス制度に対応したレジ・システムを導入する
自身でレシートや請求書のフォーマットを用意するのが難しい場合は、インボイス制度に対応したPOSレジを導入するのがおすすめです。POSレジは自動的に必要項目を網羅したレシートを出力できるため、インボイス制度導入後のレジ業務を大幅に効率化できるでしょう。スタッフのオペレーション改善にもつながるため、ぜひこのタイミングで導入を検討してみてください。
クラウド請求サービスを利用する
現状Excelなどの表計算ソフトで会計管理を行っている場合は、インボイス制度に対応した会計ソフトの導入を検討してみてください。飲食店が注力すべき点は、おいしいメニューの提供と心地よい接客、そして集客の強化。インボイス制度導入により事務作業の負担が増えてしまうと、本来注力すべきところが疎かになりかねません。
この機会に、利用者が多いクラウド会計ソフトや税理士指定の会計ソフトの契約を検討してみるとよいでしょう。顧問税理士と契約している場合は、一度相談してみるのがおすすめです。【対象別】インボイス制度導入後に飲食店が行う対応
インボイス制度の導入後、飲食店が行う対応は以下の3つに大別されます。
●顧客への対応
●仕入先への対応
●取引先への対応
なお、いずれも「適格請求書発行事業者=課税事業者」であることが前提の内容です。それぞれ詳しく解説していくので、参考にしてみてください。顧客への対応
インボイスの記載条件には「書類の交付を受ける事業者」、つまり「買い手」の「氏名または名称」が含まれていますが、「不特定多数に対して営業を行う一定の業種」は事実上不可能として、これらを省略した「簡易インボイス」の発行が認められています。飲食業もこちらに含まれますので、まずは既存のレシートを簡易インボイスに変更しましょう。簡易インボイスに記載すべき項目は以下の5つです。
●インボイス発行事業者の名称(店名)および登録番号
●取引年月日
●取引内容(品目、軽減税率の対象品目の場合は、その旨も)
●税率ごとに区分して合計した料金額
●「税率ごとに区分した適用税率」もしくは「税率ごとに区分した消費税額等」のどちらか
上記の要件を満たせば、手書きの領収書も簡易インボイスとして認められます。特に領収書を求められるということは、接待等の利用で経費として計上する目的である可能性が高いため、インボイスとしての体裁を整えることは非常に重要です。仕入れ先への対応
仕入れ先が免税事業者である等の理由で、インボイスを発行しない/できない場合、こちらは仕入税額控除が受けられないというデメリットを被ることになります。
そのデメリットを受け入れるか、そうでなければ課税事業者になってもらう、もしくは消費税分を減額してもらう等の交渉をするか、対応を検討しなければなりません。
解決策や妥協案が見いだせない場合、可能であれば仕入れ先を変えるのも一つの手でしょう。取引先への対応
こちらが売り手となって取引をする相手が来店する客以外にもいる場合、そして、それが課税事業者である場合は、買い手側に対して簡易インボイスではなく、正式な「適格請求書」を発行しなければなりません。
適格請求書に記載すべき項目は、以下の通りです。
●適格請求書発行事業者の名称(店名)および登録番号
●取引年月日
●取引内容(品目、軽減税率の対象品目の場合は、その旨も)
●税率ごとに区分して合計した金額、及び適用税率
●税率ごとに区分した消費税額
●書類の交付を受ける事業者(買い手)の氏名または名称
簡易インボイスとの違いは、適用税率と消費税額の両方を記載することと、相手事業者の氏名または名称が必要なことなので、注意してください。インボイス制度導入後も利用できる補助制度はある?
インボイス制度は、免税事業者から課税事業者へ転身することによって発生する消費税の納税や、レシートや領収書の変更に伴うデジタルツールの導入コストなど経済的な負担も発生します。
それらの負担を軽減できるのが、補助金です。インボイス制度導入にはぜひ活用したいところです。ここでは代表的な補助金を二つ紹介します。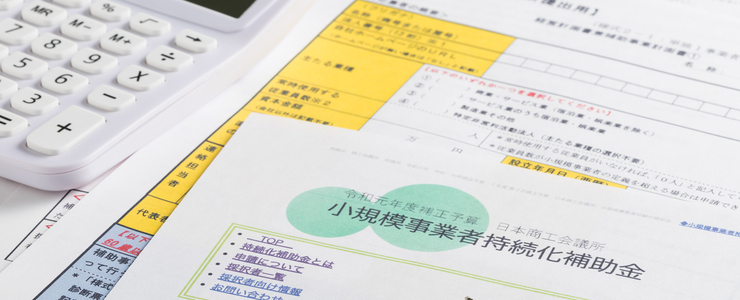
IT導入補助金
IT導入補助金は、デジタルツールの導入にかかる費用を一部負担してくれる補助金です。インボイス制度開始に伴い、手書きの領収書からPOSレジやキャッシュレス決済への変更を検討する飲食店も少なくありません。
デジタルツールは業務効率を格段にアップさせてくれる貴重なアイテムです。低コストで導入できればハードルも下がるのではないでしょうか。
IT導入補助金は中小企業でも申請が可能で、最大350万円までの補助が用意されています。小規模事業者持続化補助金
免税事業者から課税事業者になることで消費税分、増税となる。そんな飲食店に役立つのが小規模事業者持続化補助金です。
小規模事業者持続化補助金は、事業継続のために行われる販路拡大を支援する補助金制度です。インボイス制度開始に伴い、課税対象へと転換する事業者に対しては通常枠+50万円の限度額上乗せが設けられました。
新たな施策に取り組みつつ消費税増税分の負担を軽減できるので、今まで免税事業者だった飲食店にとって大きなサポートとなります。要注意!補助金は誰もが受け取れるものではない
補助金は経済的な負担を減らす便利な制度ですが、申請すれば誰でも受けられるものではありません。綿密な事業計画書などの準備した上で申請をし、採択されたあとに実際に行動をして発生した経費に対して補助金をもらうことができます。
募集時期も決められているので、申請の際には商工会議所や税理士に前もって相談しておくとスムーズに進めることができるでしょう。まとめ
インボイス制度は適切な対応をしないと納める消費税が増税になったり、顧客が離れて売上の減少に繋がるなど、大きな損害を被る可能性があります。
特に現在、免税事業者の飲食店は注意が必要です。現状の免税事業者ままでいる場合、そして課税事業者となった場合の各パターンを想定し、今後どのような対応が最適なのかを見極めなければなりません。
インボイス制度は既に始まっており、早急な対応が求められています。どうすべきかわからない場合は、専門家に相談するのもおすすめです。
canaeruでは、これから飲食店を開業する方に向けた無料開業相談を承っております。経験豊富なコンサルタントが、インボイス制度に関する疑問にもお答えしているので、ぜひご相談ください。
無料の開業相談はこちらこの記事の監修

現役飲食業13年兼WEBライター
S.kado
飲食業界歴13年。ホールからキッチンまで全ての場を経験し、複数店舗のサービスマネージャーに就任した経歴もあり。現在は独立し、時折店舗に立ちながら、レストランメニューのコンサルティングや制作、飲食業界関連のSEOライティングを請け負う。また、これまでの経験や知識をもとに著書も執筆。
- NEW最新記事
-
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
- おすすめ記事
-
-
2024/06/24
-
2022/08/30
-
2023/04/06
-
2023/10/02
-
2017/03/24
-
2023/04/24
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

※見逃し配信【第4回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|客席…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数8,015件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数687件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数143件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数483件
-