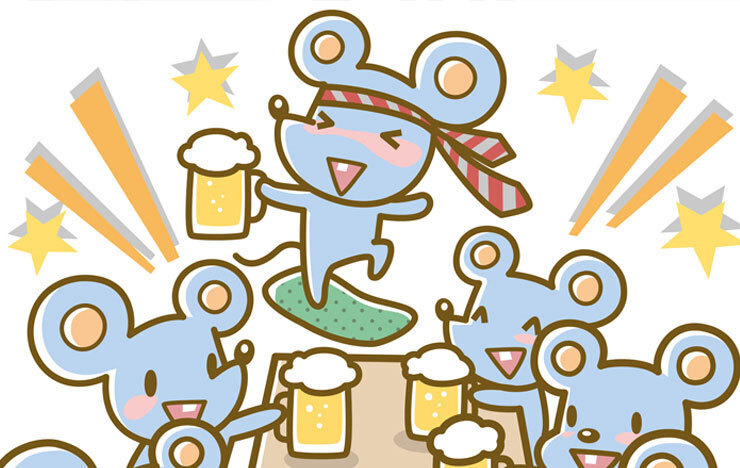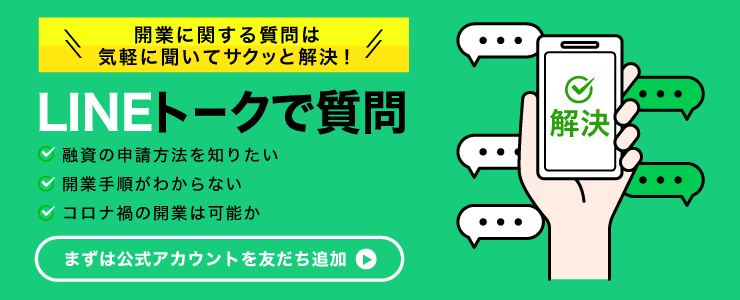飲食店において、ネズミ、ゴキブリなどの害獣・害虫は、残念ながら切っても切れない縁にあります。とはいえ、極力出会わないようにしたいものです。自分のお店でネズミやゴキブリを発見してしまった場合の対策と、それ以前の予防策、事後対策などについて説明していきます。
目次
店舗の掃除や食材の保管場所を見直す
お店でゴキブリやネズミと遭遇したら、まずは清掃を徹底的に見直しましょう。ゴキブリは水一滴、髪の毛一本で何週間も生き延びられるとても生命力の強い生き物。終業時の掃除は徹底的に行うことが重要です。また、ゴキブリやねずみのエサとなるような残飯やゴミはシンクやゴミ箱などに放置せず、できるだけこまめに捨てましょう。ランチ終了時、仕込み後、ディナータイム中に一回、営業が終了後と、とにかくこまめに。
2つ目は食材を厨房内などに放置しないこと。パントリーや収納庫などにきちんとしまっておきましょう。包装されているから大丈夫という油断禁物。ネズミは袋をかじります。ひとつでもかじられた形跡があったら、その付近の食材はすべて廃棄しましょう。
「侵入口」を徹底的にふさぐ
掃除を見直したあとに取る対策は、ゴキブリやネズミの侵入経路を絶つこと。飲食店は人の出入りが激しく、さらに閉店後に鍵やシャッターを閉めても完全な密閉は困難。どうしても少しの隙間は空いてしまいます。ネズミはともかく、ゴキブリはたった1ミリの隙間でも侵入します。壁のヒビなどはすぐ埋めるなど、外部との隙間は徹底的にふさぐようにしましょう。また、換気扇や通風孔換気扇、エアコンの排水ホースの隙間には、目の細かいフィルターをするとよいです。ネズミに食いちぎられないような鉄板や目の細かい金網、コンクリートなどで穴をふさぎましょう。さらにキッチンやパントリー、バーカウンターなどの排水溝は絶好の侵入経路となるので、閉店後には必ずフタをして帰るなどの対策を取りましょう。
撃退用品を置いて駆除する
ゴキブリとネズミの侵入経路を立ったら、次は寄せつけないようにします。ホウ酸団子や、ゴキブリの嫌うハーブやかんきつ類のニオイなどを利用した防虫シートを置く、ネズミを捕らえるための粘着シートや殺鼠剤(毒入りのエサ)の使用が有効です。ただし、殺鼠剤は効果が出るまでが遅く、どこで死ぬか分からないというデメリットがあります。ネズミ対策専門のクリーニング業者は「殺鼠剤を持ち帰ったネズミが、エアコン内部で死んでしまい、腐敗臭が客席に放出される」という可能性も指摘していますので利用は慎重に。またゴキブリ対策には、閉店後でも換気扇をつけっぱなしにしておくことがおすすめ。ゴキブリは換気扇の音を嫌います。キッチンの換気扇はもちろん、トイレの換気扇も常時回すようにしておきましょう。
専門の駆除業者に頼む
被害の状況、自店で行なった処置策・対応策などをきちんと業者に説明。費用面でも、定額払いの年間契約にすることで、効率良く、割安にネズミや害虫を駆除してもらえます。どこにしたらいいか悩んでしまうような場合は、飲食店専門の経営コンサルタントに聞いてみるのもよいでしょう。信頼のおける業者を紹介してくれるはずです。
万が一客席に出てしまったら
万が一、店内に出現してしまった場合、対応はお店側の判断に任されます。すでにお客様が完食済みの場合は丁寧に謝罪をし、代金は頂くというところもあれば、不快な思いをさせてしまったということで代金を受け取らない、もしくは割引にするというところもあります。ただし、ゴキブリなどが料理に混入してしまった場合は全額返金するのが常識です。後々、それが原因で体調不良に陥り、病院にいかなければならなくなった場合は治療費も全額負担しなければなりません。お店の信用を失わないためにも、ゴキブリが料理に混入するというのは、絶対に避けなければいけません。
ネズミの場合は特に注意
害虫であるゴキブリは、大量発生する、汚いといった印象があることから、飲食店にとって天敵と言えますが、ゴキブリよりネズミが発生した方が危険ということを知っている人は意外と少ないのではないでしょうか?飲食店にとってネズミが危険と言われている理由について見ていきましょう。
サルモネラ菌を媒介する
飲食店にとって最も怖いのは食中毒です。サルモネラ菌などは、テレビでも取り上げられたことがあるため、知っている人も多いと思いますが、食中毒の1種です。ネズミは、様々な病原菌を体内に媒介していて、サルモネラ菌もその中に含まれています。厨房に誰もいない無人の時間帯の厨房に現れて病原菌を拡散していくので、閉店時に店舗内の清掃を入念に行っても食中毒が発生する可能性があるので、飲食店ではネズミが天敵と言われています。飲食店に生息しているネズミのほとんどは、クマネズミと呼ばれる種類のネズミです。クマネズミは臆病な性格であるため、人間の前に出てくることはほとんどありません。一方で、地階や路面階といった場合には、性格が獰猛なドブネズミが現れる可能性があります。ドブネズミは獰猛な性格からお客さんに噛みつく可能性があるので、クマネズミ以上に注意が必要です。噛んだクマネズミがモニリフォルミスといった病原菌に感染している場合には、5日~2週間後に発熱や頭痛を伴う鼠咬症になる可能性もあります。また、噛まれたことに対してアナフィラキシーショックを起こして、死に至ってしまう可能性もあるので注意が必要です。
糞にも高いリスクがある
ネズミの姿が見えないからといって安心してはいけません。ネズミのリスクは、尿や糞にもあります。ネズミの糞にはレプストスピラ菌と呼ばれる病原体が含まれています。基本的に人間の体内に入ることはありませんが、体内に入った場合には、黄疸や高熱、筋肉痛などを引き起こす可能性があるため注意が必要です。糞や尿に触れていない場合でも、調理器具に何らかの理由によって付着する可能性があります。そのような場合には、見た目上は清潔であるため、なおさら危険性が高まるので注意が必要です。また、糞には上述したサルモネラ菌が大量に含まれています。体内に入った場合は、食中毒の症状として、下痢、嘔吐、急性胃腸炎、高熱などの症状を引き起こしてしまい、場合によっては死に至るケースもあります。店内でネズミの糞や尿を見つけた場合は、直接手を触れてしまうと、自身がサルモネラ菌に感染するリスクがあるだけでなく、自分を中心にサルモネラ菌が広まってしまう可能性があります。被害が拡大しないようにするためにも、素手で触らないようにするなど注意しておきましょう。
火災の原因にもなる
「ネズミの姿や糞・尿を見かけていないから問題ない」と思って油断していてはいけません。確かにネズミが姿を見せたり、糞・尿があったりした場合は、風評被害によって店舗経営に大きな影響がでるだけでなく、食中毒による損害賠償や営業停止に追い込まれる可能性があります。しかし、ネズミの被害は他にもあります。例えば、ネズミが電気ケーブルを噛み切った場合には、停電によって営業を続けることができません。また、電気ケーブルを噛み切ったことで停電するだけであれば被害は最小限で済みますが、それが原因で火災が発生した場合には、停電どころの被害では済まなくなります。そのため、店舗経営を行う際には、ネズミを見た・見ていないに関わらず、一度チェックした方が良いと言えるでしょう。
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。
【特集:トラブルシューティング】の記事