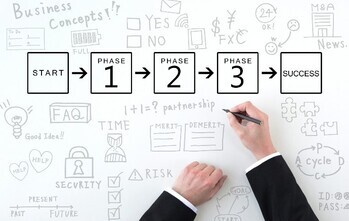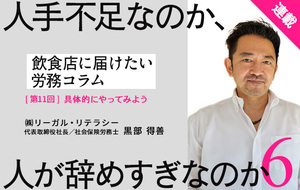- Tweet

いろいろな業種・業態の飲食店がある中で、需要が高く開業しやすいとも言われている居酒屋。しかし、開業のハードルが低い分、競合店が多いのも事実です。
本記事では、居酒屋経営を成功に導くためのヒントとなるポイントをご紹介。開業のための資金調達や必要な手続きについても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。目次
居酒屋開業をするメリット・デメリット
まずは、居酒屋を開業するとどのようなメリットがあるのか、反対にデメリット、注意すべき点は何か、把握しておきましょう。
居酒屋開業をするメリット
利益率が高い
居酒屋は料理だけでなくお酒を提供するため、客単価が高くなる傾向にあります。また、お酒のお供として定番の焼鳥やお刺身などは、仕入れ原価の2倍近い価格で販売ができるため利益率も高くなります。
原価率が低いこと、そして、利益率が高いことは経営の面から見て大きなメリットです。
初期費用を抑えやすい
居酒屋というと大きな店舗をイメージするかもしれませんが、コンパクトな居酒屋であれば初期費用を抑えて開業できます。
カウンターのみの営業もできるので、開業がしやすく、初期費用を抑えてスタートすることも可能です。
「お一人様」需要がある
大人数で利用することもありますが、最近ではひとり飲みの需要も増えてきています。仕事帰りにちょっと飲んで帰りたい・・・というお一人様需要に対応するコンパクトな居酒屋の開業も検討してみましょう。居酒屋開業をするデメリット
競合店が多い
居酒屋は利益率の高さなど、魅力がある業種です。開業費用が抑えられる小規模開業でも、工夫次第で利益を上げられる可能性があるため、参入のしやすさもメリットと言えます。
しかし、その分、既存のライバル店が多いというデメリットがあります。特に、駅から近い場所や繁華街などは居酒屋がひしめき合っており、すでに「飽和状態」になっていることも珍しくありません。
このようなことから、他店との差別化がしっかりできるように、開業するエリアのリサーチや効率的なプロモーションなど、戦略的な経営計画を綿密に立てる必要があります。居酒屋開業に必要な手順
居酒屋開業のための手順は、大きく5つに分けられます。
① 事業計画の作成
② 物件の契約と資金調達
③ 工事
④ 許可申請
⑤ 開店準備
以下でそれぞれ詳しく解説します。
関連記事 飲食店を開業するまでに必要な準備や開業資金を解説① 事業計画の作成
居酒屋を開業する前に、まずは事業計画を立てます。事業計画とは、ターゲットとする客層、店舗のコンセプト、メニュー構成、利益計画、経費予算などを詳細に決めることです。また、競合他店との差別化を図るための戦略や、リスク管理のための対策も含まれます。
それらをまとめたものを事業計画書と言いますが、事業計画は開業だけでなく、資金調達の際の銀行や投資家への説明資料としても使用します。② 物件の契約と資金調達
事業計画書が完成したら、物件探しと資金調達に移ります。物件選びは立地や規模、賃料などに注意しながら行い、最適なものを見つけて契約しましょう。希望を満たす居抜き物件を見つけることができれば、費用を抑えることも可能です。
開業に必要な資金は、物件の賃料や内装工事費などによって変動しますが、自己資金のみで足りない場合は資金調達する必要があります。資金調達は日本政策金融公庫や銀行などの金融機関からの融資、投資家からの出資などが考えられます。資金調達の際には、事業計画書が必須となります。③ 内装工事
店舗の内装は、お店の印象を大きく左右します。最初に決めたコンセプトをもとに、店舗の設計やレイアウト、必要な設備の導入、装飾、家具の配置などを計画しましょう。
居抜き物件の場合は内装工事を抑えることも可能です。特に前の店舗が同業種だった場合、厨房設備がすでに整っているケースがあるため、時間とお金を大幅に節約できます。④ 許可申請
営業開始前には、営業許可を取得したり、届出を行う必要があります。居酒屋を経営する場合は主に「飲食店営業許可」「食品衛生責任者資格」「防火管理者資格」の取得・申請が必要です。所轄の保健所や消防署などのHPを確認し、必要な書類を揃えましょう。
これらの資格や許可を取得しないまま居酒屋を経営することは違法です。申請には時間がかかることもあるため、早めに手続きを始めましょう。⑤ 開店準備
許可が下りたらいよいよ開店目前です。開店の1~2ヶ月前から、人材の募集や研修、広告・宣伝活動を行います。従業員は収容人数やテーブル数など店舗の規模によって変動します。雇用する人数が増えれば募集や研修に要する時間も増えるので、ホールやキッチンに何人必要か検討し、余裕のあるスケジュールを立てましょう。
広告・宣伝としては、グルメサイトへの掲載や周辺地域へのチラシ配り、SNSへの投稿などさまざまな手段があります。ターゲットとなる層に合わせた宣伝を行い、より効果的な集客を実現しましょう。開店からしばらくの間は、値引きクーポンの配布なども顧客をお店に誘う強力な手段となるでしょう。さらに、SNSを使ってお店の魅力を発信すれば、若い世代からの注目を集める可能性もあります。居酒屋開業に必要な資格や手続き
居酒屋を開業する場合に必要な資格や許可は以下の通りです.
食品衛生責任者の資格
飲食店営業許可
防火管理者
このうち「食品衛生責任者の資格」と「飲食店営業許可」は必須です。「防火管理者」については、オープンさせる居酒屋の収容人数が30名を超える場合に必要な資格となります。なお、居酒屋などの飲食店営業をする際に調理師の資格はなくてもかまいません。
また、上記にはありませんが、午前0時~午前6時の間に営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の許可を取る必要があります。この手続きは、開業の10日前までに行っておきましょう。食品衛生責任者
居酒屋だけでなく、すべての飲食店で必要なのが、食品衛生責任者です。食品衛生責任者とは、食品衛生法第51条に基づく義務でひとつの店舗に必ずひとりの食品衛生責任者が必要です。
食品衛生責任者の役割は「食品衛生上の管理運営」、「食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が必要な場合は、営業者に対し改善を進言し、その促進」です。
食品衛生責任者の資格は、指定された講座を受講することで取得できます。講習は1日で終了し、費用はおおよそ10,000円程度です。特に難関資格ということもなく誰でも取得できます。
なお、以下の資格を持っている人は資格を取得せずに食品衛生責任者となることができます。
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師ならびに大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
栄養士
調理師
船舶料理士
製菓衛生師
食鳥処理衛生管理者
食品衛生管理者
ふぐ調理師
食品衛生指導員もしくはその経験者
食品衛生監視員
食品衛生責任者の資格がなければ、飲食店営業許可を取ることができませんので必ず取得しましょう。飲食店営業許可
居酒屋の開業には、地域の保健所に申請をして「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
飲食店営業許可を取得する際は、実際に保健所の担当者が店舗に立ち入り調査をして必要な設備が揃っているかなどをチェックします。この必要な設備に関してはすべて指定されていますので、居酒屋の内装工事や機材の購入の前に必ず確認しておく必要があります。
必要書類は、以下の通りです。
営業許可申請書
店舗の図面
食品衛生責任者の資格
また、水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合は水質調査の成績表も合わせて提出します。申請から立ち入り調査までの日程は、保健所や時期によって異なります。余裕を持って申請しておきましょう。防火管理者
開業する居酒屋の収容人数が30名を超える場合は、防火管理者の資格も必要です。防火管理者は、たくさんの人が利用する建物などの火災による被害を防止するための資格で、「防火管理に係る消防計画」の作成や「防火管理上必要な業務」を行う人のことです。
この資格は防火管理講習を受けることで取得可能で、講習は1日で終了します。居酒屋開業に必要な資金
当然ですが、居酒屋の開業にはまとまった資金が必要です。物件・設備の取得費用や工事費用等の初期費用と、開業から数ヶ月分の運転資金が必要となります。
居酒屋開業に必要な資金は600~1000万円といわれていますが、店舗の場所や規模によってはよりコストがかかるケースもあります。初期費用の平均
居酒屋を開業させるための費用の平均は、以下のようになります。
物件の取得費用・・・250万円
内装・外装工事費用・・・居抜き:10~20万円/坪 スケルトン:20~50万円/坪
厨房機器・・・中古100万円、新品250万円
レジ・・・10万円
その他の用品・・・10万円~
ただし、これはあくまでも平均値ですので、規模や提供するメニューによって費用は大きく変わります。
日本政策金融公庫によると、初期費用の全体の62.7%(内外装工事41.7%・機械・什器
・備品等21.1%)を内装工事、機械・備品費用が占めており、物件の取得費用が全体の17.5%となっています。どのような飲食店かによって割合は変化しますが、物件の取得費用だけでなく設備にかけるお金も大きなウェイトを占めていることがわかります。
設備資金を「少しでも抑えたい」という場合は、新品ではなく中古品を積極的に利用したり、場合によってはリースで初期費用を抑えるといった工夫もできます。また、スケルトンの物件ではなく居抜きの物件で営業することで内装工事費を削減できるケースもあります。運転資金の平均
運転資金とは、事業を日常的に運営するために必要な資金のことを指します。居酒屋を開店する際に必要な運転資金は主に以下のようなもので、これらを支払うための資金が必要となります。
原材料費
人件費
家賃・水道光熱費
広告・宣伝費
など
売上から運転資金を賄うことが理想ですが、開業からすぐに経営が軌道に乗るとは限りません。
日本政策金融公庫によると、飲食店を開業してから軌道に乗り始めるまで3ヶ月以内という回答が26.1%、3~6ヶ月という回答が10.1%、6ヶ月~1年という回答が28.2%、1~2年が19.1%です。つまり、3ヶ月で軌道に乗る店舗がある一方で、半数以上の飲食店が経営を軌道にのせるまで半年程度の時間を要しているということになります。
この期間も運営資金は必要ですので、あらかじめ運転資金を準備しておくと安心です。運転資金の平均は初期費用全体の約2割と言われています。初期費用が600万円だとすれば、120万円程度が運転資金の目安になりそうです。居酒屋の開業に必要な設備
居酒屋を開業するために必要な設備は、以下が挙げられます。
厨房設備
空調設備
音響設備
照明設備
テーブル
イス
食器
調理道具
看板
おしぼりなどの小物類
特に厨房設備に関しては、料理の作りやすさはもちろんのこと食材の管理や収納などを考慮した設備の導入が必要です。また、お客様が触れることになる食器や椅子なども素材感や使用感も含めて厳選しましょう。居酒屋開業の成功に必要なポイント
居酒屋開業の成功に必要なポイントは主に6つあります。
✔コンセプトを明確にする
✔出店場所の調査
✔さまざまな人の意見を聞く
✔資金計画をしっかり立てる
✔新規オープンの周知徹底
✔支払方法のバリエーション
それぞれを詳しく説明していきます。コンセプトを明確にする
居酒屋を開業する際には、どんな居酒屋にするのか、メインターゲットの客層をしっかりと設定したうえで事業計画を立てる必要があります。コンセプトに沿ったサービスや内装は成功への鍵となりますし、メインターゲットの客層の心を掴む内装やBGMといった演出もできます。なんとなく「誰でもいいから来てくれれば良い」という居酒屋より、コンセプトがはっきりしている居酒屋の方が口コミで広がりやすくインパクトがあります。
出店場所の調査
出店場所がコンセプトに合っているのか、メインターゲットにしたい客層の利用が見込める場所なのかを地図で確認したり、実際に現地に行って確かめたりして調査をしましょう。出店場所の選定は費用面など、シビアな判断が必要になる場面でもありますが、居酒屋経営で成功するための大きな要素となりますので妥協することなく理想の出店場所を探しましょう。
さまざまな人の意見を聞く
居酒屋開業の際にどうしても「自分がしたいこと」が最優先になってしまうのは仕方のないことですが、実際に店舗を利用するのは自分ではなくお客様です。お客様目線になり、周囲のさまざまな意見を取り入れることで、お客様から愛される人気店に近づくことができるのではないでしょうか。
資金計画をしっかり立てる
成功のために最も重要と言っても過言ではないのが資金計画です。収支の計画はできるだけ綿密に立てておくことが必要です。
開業後にどんなリスクがあるのかは誰にも予想がつかないもの。予定通りに集客できないケースや営業できないケースもあるので、資金計画をしっかりと立ててリスクにも対応できるようにしておきましょう。
資金計画が甘いと開店早々に「こんなはずではなかった」と経営難に陥ってしまう可能性もあります。
新規オープンの周知徹底
新規オープン時は「誰もここに居酒屋があることを知らない」という前提でプロモーションを行いましょう。看板を設置したり、グルメサイトの利用や、ホームページの作成、ポイントカードやクーポンを作って集客を促すなどさまざまな工夫ができます。さらに、SNSなどをできるだけ駆使し、たくさんの人に「お店の存在を知ってもらうこと」を目的に実践してみてください。
支払い方法のバリエーション
顧客目線で考えたときに、利用できる支払い方法はできるだけ多い方がいいでしょう。クレジットカード決済はもちろん、キャッシュレス決済にも対応して顧客が支払いをしやすい対応を心がけましょう。経済的な視点で見れば現金収入は魅力がありますが、現金決済のみの居酒屋よりさまざまな支払い方法に対応しているほうがより集客を見込むことができます。
居酒屋開業の失敗パターン
居酒屋開業で陥ってしまいやすい失敗例をここで3つ紹介します。
ひとりよがりの居酒屋
誰もが独立開業するときに陥りやすいのが「ひとりよがり」です。コンセプト作成から実際にオープンさせるまでさまざまな道のりがあり、資金調達も乗り越えてとなれば当然「自分はこうしたいんだ」とか「これはやらない」といったこだわりが出てくるものです。もちろん、そうしたこだわりや個性はあっていいのですが、あまりにもひとりよがりになりすぎると「誰も理解してくれない」風変わりな居酒屋になってしまい顧客がなかなかつかないというケースがあります。
オーナーの理想はあって当然ですが、利用者の視点に立つことや、他の人の意見も柔軟に取り入れて「人に愛される店舗づくり」をしなければ売上に影響します。資金計画がない
「なんとかなる」「営業すれば収入ができる」と計画性のないままで開業まで突き進んでしまうと、失敗する可能性が高くなります。オープン直後にどのくらいの売上があるかは「営業してみるまでわからない」のです。ですが、固定費や人件費はたとえ売上が0円でも必ずかかります。設備や内装にお金をかけ過ぎて運転資金がなくなってしまわないように注意しましょう。
集客ための工夫がない
居酒屋はライバルが多く、場所によってはすでに飽和状態ということも珍しくありません。いかにして「知ってもらうか」は非常に重要な要素です。メニュー開発やサービスの工夫などももちろん大切ですが、お店を知ってもらわないことには経営は成り立ちません。看板やポスター、SNSを使った宣伝などさまざまな方法を駆使して目的に応じた集客戦略を立てましょう。
まとめ
コロナ禍以降、激化する居酒屋業界において、成功させるためには、従来の常識にとらわれない新しい視点と戦略が必要です。さらなる衛生面への配慮や空間デザイン、SNSや口コミサイトなどでのデジタルマーケティングの活用がますます重要になるでしょう。
開業にあたっては、食品衛生責任者の資格取得や飲食店営業許可の取得などが必要となります。資金調達や物件の取得など時間を要する工程もあり、コンセプト作成から1年程度かかるケースもあります。居酒屋開業は時間にゆとりをもって計画を進めましょう。
一人での居酒屋開業に不安な点やわからないことがあれば、開業支援サービスを利用してみるのはいかがでしょうか。株式会社USENが運営する『canaeru(カナエル)』では、居酒屋をはじめとした飲食店の開業のご相談を承っています。USENは国から経営革新等支援機関(認定支援機関)と認定されています。元居酒屋経営者や金融機関出身者といったさまざまな経歴を持つ開業プランナーのサポートが無料で受けられますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。この記事の監修

USEN開業プランナー
松村俊治
株式会社USEN 開業サポートチームに所属。飲食店経営歴8年。その経験を活かし、開業に関するあらゆる支援を行う。開業に必要なサービスや設備、業者などの紹介のほか、店舗のコンセプト設計、事業計画書の作成サポートにも精通。
【主なサポート内容】
・開業手続きの支援
・開業に必要なサービス、設備、業者を紹介
・創業計画書の作成サポート
・事業計画書の作成サポート
株式会社USEN/canaeru 開業プランナーの詳細はこちら- NEW最新記事
-
-
2024/10/23
-
2024/10/18
-
2024/10/11
-
- おすすめ記事
-
-
2020/03/05
-
2024/02/16
-
2024/02/19
-
2023/10/02
-
2021/05/31
-
2017/12/22
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数192件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数128件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数506件
-