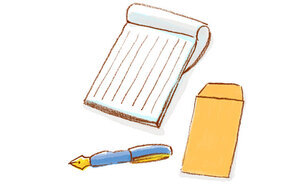- Tweet

飲食店を起業するためには、各種資格や手続きを行う必要があります。
では、飲食店を起業するために必要な手続きや書類にはどのようなものがあるのでしょうか。
この記事では、必要な手続きや書類について解説します。
関連記事:飲食店の開業に必要な資格は2つ!開業に必要な届出についても解説
関連記事:開業届の必要書類とは?書き方や提出方法をわかりやすく解説
関連記事:飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解説
目次
税務署で必要な手続き
個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業の開業・廃業等届出書とは、一般的に開業届と言われるもので、個人が事業を始めたときに提出する書類です。
特に開業届を提出していない場合であっても特に罰則は設定されていませんが、開業した日から1ヵ月以内が提出期限となっており、開業届をまだ提出していない場合は、速やかに提出するのがベターです。
開業届に必要事項を記入して提出する形となりますが、開業届作成時に必要なものには以下があります。
個人事業の開業届出・廃業届出 税務署の窓口または国税庁のホームページからダウンロードして入手 個人番号が把握できるもの 個人番号の証明に「通知カード」または「住民票の写し」を提出する場合、本人確認書類が必要となる 本人確認書類 運転免許証、パスポート、在留カード、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳などのうち1つが必要 印鑑 シャチハタは不可能 青色申告承認申請書 青色申告をおこないたい場合に必要。顧問税理士や公認会計士がいる場合、その方の署名の用意が必要となる
開業届は、基本的に税務署の窓口に提出するとその場で確認され、承認されれば税務署の印鑑が押印され返却されます。
なお、開業届は法人口座や法人クレジットカード作成時などで必要となる場合があるため、紙または電子データ上で保管してください。
開業届と併せて青色申告承認申請書を申請すれば、毎年の確定申告時に青色申告制度によって節税対策を測ることが可能です。
青色申告の承認申請は、個人事業主にとって重要になるため、忘れず申請を行ってください。
開業届の書き方
開業届は、1枚で構成されており決して記入が難しいものではありません。
具体的な記入項目と記入内容は、次の通りです。
納税地の税務署名、提出日 開業届を提出する所轄の税務署の名称と提出する日付を記入。税務署の名称は国税庁の公式ホームページで確認できる。提出する日付は、開業日から1ヵ月以内である必要があるが、仮に超えていても罰則などはない。 納税地/上記以外の住所地・事業所等 住所地、居所地、事業所等のいずれかを選択し、納税地の住所を記入する。電話番号は携帯電話の番号でも問題ない。納税地は、基本的には生活の拠点となる自宅の場所を示す住所地のことを指す。住所地以外で事業を営むための店舗や事務所がある場合、事業所等を選んで納税地としても問題ない。居所地は、海外に居住して日本に住所はないものの、活動場所は日本にある場合に選択する。 氏名/印/生年月日 フルネームで氏名を記入して押印する。印鑑は個人印でも屋号印でも問題ない。 個人番号 マイナンバーカードまたは通知カードに記載されているマイナンバーを記入する。 職業 職業の欄には明確な記入ルールはなく、客観的に分かる名称であれば問題ない。飲食店の場合は「飲食業」と記載するのが一般的。ただ、業種によって個人事業税の税率が異なるため注意が必要。
屋号 屋号がある場合は、屋号を記入する。屋号がない場合は、空欄のままとする。 届出の区分 新規開業の場合は「開業」にのみ○を記入して、その他は空欄とする。もし、事業を引き継いだ場合は住所、氏名を記入する。 所得の種類 不動産による所得、山林による所得以外は事業所得を選択する。 開業・廃業等日 開業日は、提出日から1ヵ月以内が原則となるが、開業日といつにするかは細かなルールはない。自分が開業したと宣言する日や、開業届を出した日でも問題ない。もし、開業した年から青色申告を適用する場合、開業日から2ヵ月以内に行う必要がある。開業日から2ヵ月を過ぎて申請した場合、翌年分の確定申告から適用されるので注意が必要。 事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合 新規開業の場合は記入不要。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業届に伴い青色申告に関連する書類や消費税に関連する書類を提出する場合は、チェックを入れる。 事業の概要 職業欄に記入した内容を具体的に記載する。職業欄を「飲食業」とした場合、事業の概要として「宅配弁当の調理と販売」などのように、誰が見ても客観的に分かるように表記する。 給与等の支払いの状況 家族従業員や、家族以外の従業員を雇用する予定がある場合に記入する。
・従事者数:専従者、使用人それぞれ雇用する人数を記入する。
・給与の定め方:月給や日給、月給と賞与などの具体的な給与の支払い方法を記入する。
・税額の有無:源泉徴収する場合は「有」、しない場合は「無」にチェックを入れる。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期となる。ただ、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、申請をすれば年2回にまとめて納めることが可能である。申請書を提出する場合は「有」をチェックする。 給与支払を開始する年月日 従業員に対して給与を支払う場合にのみ記入する。すでに支払っている場合、その日付を記入し、予定の場合は支払いを開始する予定日を記入する。
もし、作成時に不明な点がある場合は最寄りの税務署で確認してください。保健所で必要な手続き
飲食店の営業許可申請・取得方法
飲食店を開業する際には、管轄の保健所で必ず営業許可を取らなければなりません。
飲食店営業許可を取得するには、食品衛生責任者を設置していることが条件となります。
食品衛生責任者とは、食品を扱う店舗で食品の衛生管理を行う責任者のことを指します。
1人の食品衛生責任者が担当できるのは1店舗のみとなり、複数店舗で開業する場合はそれぞれの店舗に責任者が必要です。
食品衛生責任者は、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有していること、または保健所長が実施する食品衛生責任者になるための講習会や、知事の指定した講習会の受講を修了することで取得できます。
大まかな流れとしては、まずは保健所に事前相談した上で営業許可の申請を行います。
その後、保健所の施設検査が行われて、審査を通過すれば営業許可書が交付されます。
なお、飲食店営業許可と似た許可申請として喫茶店営業許可申請があります。
飲食店営業許可と喫茶店営業許可申請の違いは、喫茶店営業許可では設備規定が飲食店営業許可と比較して緩い反面、アルコール類全般や手を加えない既製品以外の食品が提供できないことです。
よって、基本的には飲食店営業許可の取得をおすすめします。
申請前に保健所に事前相談を!
飲食店営業許可申請を行うステップとして、保健所に事前相談が必要です。
申請書類の準備や実際の設備準備などができているのに、保健所にお伺いを立てるのは面倒に感じるかもしれません。
ただ、事前相談は絶対に欠かしてはいけない手順なのです。
その理由としては、保健所職員の立会い検査を受ける際、規定通りの設備が適切に揃えられているかという点を実際にチェックされますが、もし規定を外れていれば再検査となるためです。
主な、保健所の立ち会い検査では以下のようなポイントがチェックされます。
・シンクの種類
・食器棚に戸は設置されているか
・網戸が設置されているか
保健所の検査を通過できるように、内装工事を行う際は業者側が配慮して設計するのが一般的です。
ただ、内装業者が営業許可を出すわけではなく、抜け漏れがあった場合に責任を負う事はありません。
内装の図面が完成した時点で、本当に保健所の検査に適合しているかどうかを保健所でよく確認してください。
なお、事前確認を受ける際には実際に検査を受ける保健所で行うことが重要です。
それは、保健所によってチェック項目や書類などが微妙に異なる場合があるためです。
無駄な費用が発生しないように、手間がかかりますが保健所への事前相談は欠かさず行ってください。
飲食店営業許可申請に必要な書類
飲食店営業許可申請時には、各種書類の提出が必要です。
提出する保健所によって必要な書類が異なりますが、東京都の場合は以下6つの書類を施設が完成する10日ほど前に提出しなければなりません。
・営業許可申請書(法許可業種、条例許可業種)
・営業設備の大要・配置図(2通)
・許可申請手数料
・登記事項証明書(法人の場合のみ)
・水質検査成績書(貯水槽使用水や井戸水使用の場合のみ)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
各書類は、作成までにとても手間がかかるものです。
また、営業設備の大要・配置図は自分で作成するのは困難で、施工業者などに作成を依頼することになります。
他にも、書類仕事をまとめて行政書士にお願いすればすべての書類を手際よく準備できるのでおすすめです。
なお、水質検査成績書は業者に水質検査を依頼して、その結果を添付しなければなりません。
当然、検査費用がかかるためにその分の費用を見込んでおく必要があります。
また、検査結果が判明して書類を受け取るまでに時間がかかるため、早めに手配して施設完成に間に合わせることが重要です。
消防署で必要な手続き
防火対象物使用開始届
防火対象物使用開始届は、建物の安全性を確保する目的があるため、火を扱うことが多い飲食店では、開業の際に必要となる手続きです。
防火対象物使用開始届は、消防が防火対象物の使用状況を把握した上で、防火の専門家の立場から届出内容の確認や消防用設備の設置状況などを事前に審査、指導を行います。
物件を使用する7日前までに、最寄りの消防署に提出しなければなりません。
火を使用する設備等の設置届け
火を使用する設備またはその使用に対して、火災の発生のリスクがある設備の中で、以下を設置する場合、事前にその旨を消防長に届け出る必要があります。
・炉
・温風暖房機
・厨房設備
・ボイラー
・乾燥設備
・給湯湯沸設備
・ヒートポンプ冷暖房機
・火花を生ずる設備
・放電加工機
設備設置前までに、最寄りの消防署に提出しなければなりません。
防火管理者選任(解任)届
防火管理者専任(解任)届は、消防法8条に基づいて、防火管理者の選任、解任した際に、消防署長に届け出る書類です。
営業開始までに、最寄りの消防署に提出しなければなりません。
防火管理者とは、多くの人が集まる施設において、火災を予防するための必要な措置を講じる責任を経営者に進言する責任がある人のことを指します。
店舗の収容人員が30人未満の場合、防火管理者の設置は不要です。
なお、延べ床面積が300平方メートル以上の場合は甲種防火管理者、300平方メートル未満の場合は乙種防火管理者となります。
防火管理者の資格を取得するためには、防火管理者講習を受講して効果測定試験に合格しなければなりません。
警察署で必要な手続き
届け出の前に確認
実際に警察に対して届出を行う前に調査しておくべき点があります。
それは、開業予定地の用途です。
普段生活している土地では、都市計画法に従って用途地域が定められているのです。
用途地域の中には、深夜酒類提供や風俗営業許可がそもそも下りない地域があります。
もし、深夜酒類提供や風俗営業許可を取りたい場合、許可が下りるかどうかを事前リサーチしてください。
深夜酒類提供飲食店営業開始届書
深夜酒類提供飲食店営業開始届書とは、午前0時から日の出までの時間において、酒類を提供する飲食店が申請しなければならない届出です。
管轄の警察署に対して、営業開始の10日前までに届け出る必要があります。
風俗営業許可申請
従業員に客を接待させたり、スナックやキャバクラを開業したい場合に必要となる届出です。
バーのように、カウンター越しでお酒を提供する程度では、本申請の届出は不要です。
管轄の警察署に対して、営業開始の約2か月前に届け出る必要があります。
従業員を雇用する上で必要な手続き
労災保険の加入手続き
労災保険とは、労働者が業務上の事由や通勤が原因となって負傷したり疾病や障害、死亡した場合、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度です。
最寄りの労働基準監督署に対して、雇用日の翌日から10日以内に届け出る必要があります。
雇用保険の加入手続き
雇用保険とは、失業に備える公的保険であり、失業などによって労働者の収入が途絶えた場合、生活や再就職を支援する目的で給付される制度です。
最寄りの公共職業安定所に対して、雇用日の翌日から10日以内に届け出る必要があります。
その他営業内容に応じて必要な手続き
社会保険の加入手続き
社会保険は、広い意味では健康保険や厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険を総称したものであり、一定の条件を満たしている事業所とその従業員が加入する公的保険となります。
場合によっては、健康保険と厚生年金保険だけを社会保険と総称し、労災保険と雇用保険は労働保険と分類するケースもあります。
2020年5月の法改正によって、要件を満たすパートやアルバイトの場合でも、社会保険の被保険者となりました。
従業員が入社して5日以内に被保険者資格取得届を作成し、事業所を管轄する年金事務所に提出する必要があります。
酒類販売の許可
飲食店でお酒を提供するだけでなく、お酒を販売する場合には酒類販売の許可が必要です。
お酒を開栓して提供する場合には該当しませんが、未開栓のボトルや樽をそのまま販売する場合、酒税法上の酒類の小売業に該当し、酒類販売業免許が別途必要となります。
免許取得する場合、まずは酒類指導官設置税務署で事前相談を受けて、要件の確認や提出書類などについて相談してください。
そして、書類の作成をおこなって申請者が署名押印し、 所在地管轄の税務署にて申請します。
動物の取扱の許可
猫カフェなど動物を飼育したり展示したりする場合、第一種動物取扱業の登録申請が必要です。
新たに第一種動物取扱業をスタートさせる場合、営業開始前に登録を受ける必要があります。
第一種動物取扱業の登録申請をする場合、事業所ごとに常勤の従業員の中から専属の動物取扱責任者を選任しなければなりません。
申請は、第一種動物取扱業登録申請書に必要事項を記入して、添付書類をそろえて管轄の保健所又は動物保護管理センターへの提出が必要です。個人で飲食店を開業する時に必要な手続き
個人での開業の場合に必要な届出として、青色申告承認申請書があります。
先に解説した通り、青色申告承認申請書は開業する上で必須の届け出ではなく、届け出て青色申告で確定申告すれば以下のメリットを受けられます。
・青色申告特別控除で10万円または65万円の税制優遇を受けられる
・大きな赤字が発生した場合に3年間繰り越し可能となり、2年目以降黒字になっても税金を抑えることができる
・親族への給与を支払う場合に専従者給与として経費に計上できる
・30万円未満のものを購入した場合、合計金額が300万円までは一括でその年度の経費とできる
個人事業で確定申告をする場合、青色申告の他に白色申告があります。
青色申告は、白色申告よりも複式簿記という複雑な帳簿付けをする必要がありますが、税制優遇という観点では大きなメリットがあるのです。
青色申告で確定申告をするためには、所轄の税務署に対して所得税の青色申告承認申請書を届け出る必要があります。
法人として飲食店を開業する時に必要な手続き
法人設立届出書
会社を設立した場合、税務署に税金を納める必要がありますが、会社を設立した事実と会社の概要を通知するためにM法人設立届出書を所轄の税務署に提出します。
法人設立届出書の提出は、会社の設立にあたり法務局で法人登記を終えた後の税務関係の手続きとなります。
なお、届出書は以下3箇所に提出しなければなりません。
・税務署に届け出る届出書
・都道府県税事務所に届け出る届出書
・市町村役場に届け出る届出書
基本的に、提出する内容は同じですが若干異なるケースもあるためよく確認してください。
青色申告承認申請書
個人事業主と同様に、法人でも青色申告によって税制優遇を受けることが可能です。
青色申告承認申請書を作成し、開業後3ヶ月以内または第一期終了日のいずれか早い日までに所管の税務署に提出する必要があります。
給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等の開設届出書とは、従業員を雇い入れて給与を支払うことになる場合に提出が必要な書類です。
申請書は、最寄りの税務署または国税庁のホームページからダウンロードして入手します。
従業員を雇用してから1ヶ月以内に、所管の税務署に提出する必要があります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉徴収税は、原則として翌月の10日までに納付する必要がありますが、給与を支払う従業員が10人未満の小規模な飲食店の場合、半年に1回まとめて納付できる特例が用意されています。
まとめて納付するためには、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を所管の税務署に提出する必要があります。
提出期限は特にありませんが、本特例が適用されるのは届出書を提出した翌月となるため、特例を受ける月の初日の前日までに提出してください。
まとめ
飲食店開業に必要な資格や手続きは、多岐にわたります。
特に、営業許可を得る際には時間がかかり、また施設検査は厳しい基準が求められていることから、念入りな準備が必要です。
もし、不明な点があれば最寄りの行政機関に相談して、準備をしっかり行う必要があります。
また、青色申告のように税制優遇を受けられる制度もあるため、手間がかかりますが漏れなく申請してください。
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- NEW最新記事
-
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
- おすすめ記事
-
-
2020/03/19
-
2022/08/30
-
2017/03/24
-
2022/02/25
-
2021/12/23
-
2024/04/16
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

※見逃し配信【第4回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|客席…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数8,283件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数687件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数143件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数483件
-