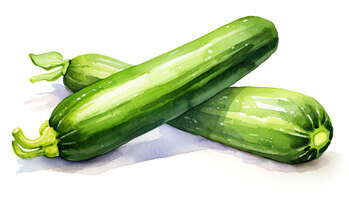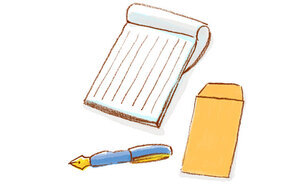- Tweet

飲食店の人手不足は、コロナ禍以降さらに深刻さを増しています。人手不足によりお店が回らないとお客様へ影響が出るだけでなく、経営難につながる可能性があります。また、働いているスタッフにもきつい思いをさせることになり、スタッフが辞めてしまう原因にもなりかねません。
この記事では、人手不足の解消方法をご提案していきます。「人手不足をなんとかしたい」「効果的な求人施策とスタッフを定着させる術を知りたい」「いま話題のDXで人手不足の悩みを解消したい」とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事 スキマバイトの活用で求人コストを削減!人手不足の改善に取り組もう
目次
コロナ渦で深刻さを増した飲食店の人手不足
コロナ禍で一時営業停止・時間短縮に追い込まれた飲食店界隈は、苦渋の決断で働き手の解雇やシフトの削減などを進めた結果、働き手が戻らないまま働き手離れが進み深刻な人手不足に陥りました。2023年5月現在、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザと同等の5類感染症へ移行し、マスクの着用も個人の判断に変わるなど、コロナによる規制が緩和。インバウンド需要も回復の兆しを見せ、飲食店にも活気が戻っています。
コロナ前の営業状態に戻りつつある飲食業界ですが、それに逆行するかのように人手不足はコロナの影響を引きずっています。
2022年10月に帝国データバンクが行った「人手不足に対する企業の動向調査」では、飲食店の76.3%が非正社員の人手不足を実感しているという結果が出ています。2020年は36.4%、2021年は63.3%だったことから、人手不足が年々深刻化している状況です。〔※1〕
〔※1〕
帝国データバンク|人手不足に対する企業の動向調査(2022年10月)
飲食店が人手不足を引き起こす5つの原因
飲食店の人手不足はコロナの影響だけでなく、飲食店の労働環境ならではの事情も関係しています。
- 飲食店は「きつい」イメージがある
- 給与や待遇に魅力を感じられない
- 求人広告が高額である
- 新人教育に手が回らなくて人材が定着しない
- 「飲食店経営は不安定」というイメージを拭いきれない
これらについて、それぞれ詳しく解説していきます。
1.飲食店は「きつい」イメージがある
飲食店のアルバイトは基本的に立ち仕事であり、お客様とのコミュニケーションが発生する仕事です。体力的にもきついイメージがあるうえ、お客様への気遣いやクレーム対応、近年SNSで露呈される飲食店への迷惑行為などのせいでマイナスイメージを持つ人もいます。
また、ランチどきやディナー帯などに客として飲食店を利用した際、あまりに忙しそうな店員の姿を見て敬遠してしまっている可能性もあります。少なからず体力のいる仕事ですが、必要以上にきついイメージがついてしまっている現状から、働き手が集まりにくく人手不足が起こっていると考えられます。
2.給与や待遇に魅力を感じられない
飲食業界の人手不足には、業務内容に対して給与が低いことや、待遇に魅力を感じられないといった意見もあります。
そもそも飲食業界は材料費や諸経費などで、利益率が低いと言われています。利益の中から給与や福利厚生などの整備に関する費用が捻出されるため、必然的に給与を上げられない、待遇に費用をかけられないといった状況が引き起こされます。
給与や待遇に魅力を感じられないのであれば、飲食店で働こうと考える人は少ないでしょう。
3.求人広告が高額である
求人広告は媒体によりさまざまな料金形態がありますが、一週間の出稿で1万円前後~数十万円の広告掲載費用がかかります。
費用をかけるほど求人の露出度があがり、求職者の目につきやすくなるといったメディアもあり、実質的に求人広告は高額になりがちです。
また、上記にプラスして、採用した人数に対してマージンを支払う場合もあります。求人広告費用を確保できないと、そもそも求人すらままならないといった状況になり、人手不足を引き起こすのです。
4.新人教育に手が回らなくて人材が定着しない
慢性的な人手不足に陥ると、日々の営業をやりくりするだけで精一杯になりがちではないでしょうか。目の前の業務にいっぱいいっぱいになってしまうと、新たなスタッフを雇用しても、新人教育の時間を満足に取れない状況が続きます。
新人スタッフは新しい仕事先で緊張しているうえ、仕事を教えてもらえないのなら何をすればよいかわからないのは当たり前です。新人教育に手が回らないと、せっかくの新人スタッフも疎外感ややりづらさを感じてしまうでしょう。
新人スタッフが定着するかは、店舗の責任者や先輩スタッフのケアにかかっています。新人教育に人や時間を割けないのであれば、どうすればリソースをかけずに教育できるかを考える必要があります。
5.「飲食店経営は不安定」というイメージを拭いきれない
コロナ禍では、飲食店の経営危機に関するニュースが飛び交いました。そのため、社会情勢に左右されやすい飲食店の経営は、不安定で何が起こるかわからないといったイメージがつき、現在もそのイメージを拭いきれていない状況が考えられます。
仕事をするならば、安定して働ける職に就きたいと考える人がほとんどです。突然仕事がなくなってしまうかもしれない恐怖心を抱かせてしまったことも、人材が集まらない原因の一つでしょう。
人手不足は負の連鎖を生む
しかし、人材が集まらないからといって、人手不足のままで店を回そうとするのは非常に危険です。人手不足の状態では
スタッフ一人ひとりの業務負担が増える
↓
手が回らないことで不満が募り、スタッフが離職する
↓
さらに人手が減少したことで、サービス品質が低下
↓
お客様からのクレームが発生。客離れが進む
といった負の連鎖を生みます。
途中で新しいスタッフを雇えたとしても、スタッフ教育の時間が取れない状況であれば、サービス品質を上げることは難しくなります。その結果、新人スタッフの未熟な接客によって店の評判を下げてしまう可能性もあるのです。
飲食店の人手不足の対策アイデア5選
飲食店の人手不足を対策するには、飲食店での仕事のイメージや待遇を改善する、人間じゃなくてもできることはデジタル化するなどが挙げられます。
- 労働環境の改善
- 評価制度の見直し
- SNSの活用
- DXの活用
- ロボティクスの導入
これらは、人手不足の原因を根本的に見直す施策と、人手に頼らず業務を効率化するアイデアです。それぞれ詳しく解説していきます。
労働環境の改善
飲食業界は拘束時間が長い傾向にあり、一般的な企業と比べて年間休日が少ないなど、労働環境面の悪さから敬遠されがちです。有給休暇や連続休暇を取りやすい環境を整え、アピールするだけでも人が集まりやすくなり、人材の定着にもつながります。
その他にも、飲食店では珍しい退職金制度の整備、住宅手当の支給など、福利厚生を充実させることも有効とされます。事例として、大手うどんチェーン店の「はなまるうどん」は、福利厚生面が充実した企業として有名です。夏季休暇、冬季休暇として7連休を取得する制度や、単身赴任の場合に支給される帰省手当などが整えられています。
評価制度の見直し
働き手に対する「評価制度の見直し」は、スタッフのモチベーションを向上させ、人材の定着につながる施策です。評価制度のほかにも、教育制度・シフト制度などを見直すことで、スタッフにやりがいと働きやすさを感じてもらうことは昨今の雇用において重要な課題となっています。
スタッフのホスピタリティの高さに定評があるディズニーリゾートを運営する、株式会社オリエンタルランドでは、“アワード”と呼ばれる「優れたパフォーマンスや長年の貢献に応える表彰制度」があります。また、グレードアップ制度といった昇格の仕組みを構築し、スタッフの頑張りや評価を“見える化”して昇給につながるようになっています。
仕事にやりがいを見出し、雇用主から賃上げで還元されれば、モチベーションが上がるでしょう。その際、評価には一貫性を持たせること、評価する担当者によって差異が出ないことが重要です。
SNSの活用
近年、SNSを活用してプロモーションする飲食店が増えてきました。その投稿内容は、シズル感溢れる料理や、内装・ロケーションなどの宣伝に留まらず、和気あいあいと働くスタッフたちをフォーカスしている動画も見受けられます。
SNSで“バズる”飲食店の中には、愉快で明るい店長とスタッフとの「飲食店あるある」の寸劇を投稿しているものもあり、店の雰囲気の良さを伝えています。このようなSNSの使い方は、飲食店の偏ったイメージを払拭し、「この店で働いてみたい」「この店に行ってみたい」という求人効果・来店効果が見込めます。
SNSの認知度を上げるには時間がかかりますが、お店の良さやイメージが伝わりやすくなります。SNSを見た採用希望者なら、採用後の離職率低下にもつなげられるでしょう。
DXの活用
「DX」とは、Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略です。よく似た言葉として「IT」が挙げられますが、ITとは情報技術のこと。インターネットなどのネットワークを駆使してさまざまな物事を便利に、効率的に進めるための「技術」を指します。一方のDXは、こうした情報技術を手段として、製品やサービス、企業活動の「変革」を進めることを意味します。
飲食店におけるDX化事例として挙げられるのは、セルフオーダーシステムやキャッシュレス決済、WEBでの予約受付の導入など。業務のDX化によって業務の効率化やコスト削減といったメリットが期待できます。
また、DXを活用することで、お客様の注文内容や滞在時間、客単価といったデータの蓄積が可能に。顧客や売上のデータ分析・管理が容易になり、より効果的なマーケティング施策を打てるようになります。
・セルフオーダーシステムの導入
オーダー業務の効率化のため券売機を導入する手もありますが、券売機で対応できるのは、ラーメン屋や牛丼店といったメニュー数が少ない飲食店に限定されます。しかし、スマホやタブレットによるセルフオーダーシステムであれば、メニュー数の多い居酒屋やレストランでも対応が可能に。
オーダー業務を省人化する分、厨房での調理や接客に集中できるようになり、業務効率化と同時に、結果的に顧客満足度のアップにつながります。
・キャッシュレス決済の導入
会計業務の効率化に有効なのがキャッシュレス決済です。現金での会計とは異なり、お釣りの受け渡しが発生しないだけでなく、渡し間違いのトラブルも防ぐことができます。また、売上が全てデータ化されるため、レジ締め作業や経理処理も楽に行えます。
・スタッフ間の業務連絡もデジタル化
ビジネスチャットツールを導入することで、スタッフ間の業務連絡や引き継ぎ事項もよりスムーズに伝達できます。また、昔は手書きが当たり前だったシフト表も、デジタル管理することで利便性が高まり、急なシフト変更も即座に全スタッフに共有可能。その後の給与計算も楽になるなど、メリットづくしです。
このように、人材不足解消のためには、省人化・デジタル化できる業務と、人を手をかけるべき業務とを上手く切り分けていく必要があります。
関連記事 【飲食店のDX】デジタルを取り入れたスタッフ教育でモチベーションを変える
ロボティクスの導入
「ロボティクス」とは、ロボットの設計、製作、コントロールを行う「ロボット工学」のことです。ロボティクスもDXの1つであり、飲食店においては、人手不足の解消策として配膳・運搬ロボットが注目を集めています。
配膳・運搬ロボットは人手不足を補うだけでなく、スタッフとお客様の接触機会を減らす意味でも有効で、ニューノーマル時代の需要にもマッチ。大手外食チェーンが続々と導入し、話題になっています。
3Dカメラや高性能のセンサーを備えた配膳・運搬ロボットは、タッチパネルなどの簡単な操作で目的の場所まで自走し、料理や食器などを安定的に運びます。障害物の回避が可能な上に、自動で客席から厨房へと戻る機能も。
料理や食器をロボットに乗せる作業は人が行うことになりますが、配膳やバッシング業務の一部をロボットに任せられるというのは非常に画期的です。
そんな飲食業界が注目する配膳・運搬ロボットのメリットとデメリットは、以下の通りです。
▼メリット
- 一度にたくさんの料理や食器を運ぶことができ、人材不足の解消と業務の効率化につながる
- 省人化によって人件費を削減できる
- コロナ禍における非対面・非接触のニーズに応えられる
▼デメリット
- 1台あたり300万円程度〜と非常に高価である
- 段差があったり、通路の幅が狭かったりする場合は導入が難しい
- ロボットで運ぶと無機質で冷たい印象になりがちで、人による温かみが薄れる
費用面や導入時の課題はあるものの、人材不足の解消と業務効率化のためには非常に有効な選択肢であるといえます。また、配膳・運搬ロボットそのものがまだまだ物珍しい存在であるため、配膳・運搬ロボットを導入していることが話題性や来客のきっかけにもつながるでしょう。
飲食店の人手不足は対策できる
飲食店の人手不足は、コロナ禍以降、年々深刻になっています。人手不足の解消方法として、労働環境や制度の見直し・SNSの活用・DXやロボティクスの導入といった対策をご紹介しました。
しかし、方法はわかっても実際にどう行動すればいいのかわからない、もっと具体的な内容を知りたいという方も多いのではないでしょうか。
USENの開業支援サイト「canaeru(カナエル)」では、飲食店に関するさまざまなセミナーや講座をオンラインで行っています。飲食店にとって役に立つノウハウを徹底的にレクチャーしているため、ぜひお店をよりよくするための参考にしてみてはいかがでしょうか。
セミナーの詳細はこちら
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。- NEW最新記事
-
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
2024/07/26
-
- おすすめ記事
-
-
2022/05/16
-
2023/03/03
-
2023/05/10
-
2023/11/17
-
2023/09/08
-
2023/05/19
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

※見逃し配信【第4回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|客席…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数8,015件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数690件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数143件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数483件
-