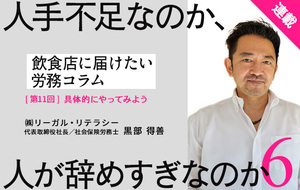- Tweet

最近、配膳ロボットやコーヒーを淹れるロボットなど、飲食店で活躍するユニークなロボットを見かける機会が増えたと感じる方も多いのではないでしょうか。
ロボットの需要が拡大し、導入が進む理由とは何なのか?そもそも、飲食店用のロボットにはどのような種類があるのか?ロボット導入のメリットやデメリットも交えて詳しく解説します。
目次
配膳ロボットとは?飲食店での需要拡大の背景
配膳ロボットとは、レストランや喫茶店など飲食店で自動的に料理や飲み物をを運ぶ機能を持つロボットです。
外食業界では慢性的な人手不足と人件費高騰が深刻な課題となっています。調理や接客など、人の手によるサービスが主体の外食産業ですが、労働人口の減少と人件費の高騰により、飲食店運営のハードルは年々高くなっています。これらの問題を解決しうるのではないかと考えられるようになりました。
そのような課題を解決するソリューションとして、配膳ロボットが飲食店に導入され始めたのは2010年代後半頃から。特に2020年からの新型コロナウイルス感染症の流行によって、人と人との接触を減らすニーズが高まったことも、配膳ロボットの普及を後押ししました。
人手不足と人件費高騰、そしてコロナによる非接触推奨の意見が強まったことから、配膳ロボットが外食店舗で徐々に普及していったと言えるでしょう。飲食店での導入が進むロボットの種類
昨今の飲食店では、配膳ロボットのほかにも様々なロボットが活躍しています。
代表的なものは調理ロボットです。調理ロボットとは、調理の各工程を自動化するロボットを指し、食材を切る、混ぜる、煮る、焼くなど、調理の基本的な動作を行います。一部の調理行程を自動化することで、調理時間の短縮や調理精度の向上を実現でき、省人化や品質の安定化を図ることができます。
近年では、センサー技術の進歩により、味付けなどより高度な調理動作にも対応できるようになってきています。某中華料理チェーンでは、20種類のメニューで調理ロボットを活用する試みを開始するなど、ますます需要が高まっています。
そのほか、清掃ロボットも飲食店での導入が広がりつつあるロボットの一つです。店内の掃除や除菌作業を自動化することで、清掃作業の迅速化と衛生管理の向上が可能。人手不足解消と人件費削減にもつながるため、注目されています。配膳ロボットの主な役割・機能は?
配膳ロボットの主な役割や機能として、「配膳」「下げ膳」「接客・巡回」などが挙げられます。それぞれ詳しく解説します。
配膳
座席やテーブルの位置を登録しておくと、指示に応じてロボットがその場所まで自動で配膳を行います。ロボットにもよりますが、積載量は30kg~40kg。複数のトレイが設置されているため、数人分の料理を一度に運ぶことができます。
下げ膳
配膳ロボットは下げ膳でも活躍します。スタッフがお皿をロボットに載せる作業は発生しますが、大量のお皿を一度に下げることが可能です。また、ロボットがお皿を下げてくれている間に、スタッフはテーブル付近の清掃やテーブルセットに専念でき、回転率向上にも寄与します。
接客・案内
配膳ロボットは多くのモデルで言語機能が搭載されており、接客向けの会話コンテンツが充実しています。そのため、簡単な接客であれば来店客を座席まで案内することも可能。さらに、多言語対応のモデルもあるため、訪日外国人客の接客にも対応できます。
配膳ロボット導入のメリットとは?
人手不足の改善と人件費削減
従来は人の手で行われていた配膳業務を自動化することで、深刻化する人手不足の問題に対応できます。配膳人員の確保が不要となるため最低限の人員でお店を回すことができ、人員を抑えられることで人件費削減にも寄与。人手不足と人件費高騰の問題の解消につながるメリットがあります。
業務効率向上と業務負担軽減
配膳や下げ膳をロボットに任せることで、スタッフは接客、バッシング対応、電話対応などその他の業務に集中することができ、全体的な業務効率を向上させることができます。ロボットによる配膳ミスもなく、正確かつ迅速な配膳が実現できます。
また、十分な積載量を備えたロボットであれば、一度に複数人分の料理を配膳することも可能です。重たい物を代わりに運ぶこともできるため、スタッフの業務負担を大幅に軽減することができます。顧客満足度の向上
配膳や下げ膳作業の自動化により、スタッフはその他サービスや接客業務などに専念できるようになります。接客などの「人にしかできないサービス」に注力できることで、来店客とのコミュニケーション時間が増えてサービス品質も高まります。それは結果的に、顧客満足度の向上にもつながることになるでしょう。
話題性による集客効果
飲食店用ロボットの認知度は年々高まっているものの、実際に導入している飲食店はまだまだ少ない状況です。そのため、ロボットを導入していること自体が話題を呼び、来店につながる可能性も。来店したお客様がロボットの様子を撮影し、SNS等で発信してくれることで、次のお客様を呼ぶ高い宣伝効果も見込めます。
感染症のリスクを低減できる
配膳ロボットは非接触で配膳と下げ膳が可能なため、感染症対策にも効果的です。コロナが落ち着いてきた現在でも感染症対策は当たり前の時代。人同士の接触を極力減らし感染リスクを低減しておけば、来店客にとっても安心です。
配膳ロボットを導入するデメリットはある?
導入時にコストがかかる
年間費用で考えると、スタッフを雇う人件費よりコストを抑えられるものの、導入時にはある程度の費用が発生します。例えば、配膳ロボットの導入費用(販売価格)の相場は、1台あたり150〜500万円程度と高価です。レンタルやリース契約で導入する場合も、月5〜10万程度の費用がかかります。
無機質で温かみがない
飲食店はサービス業であり、人的サービス(接客)も魅力の一つ。ロボットが席案内や配膳を行うと、無機質で人による温かみが薄れると捉えられる可能性もあります。簡単なコミュニケーションであればロボットにもできますが、お客様が何を求めているかを察して自ら行動することは人が接客をする良いところでもあります。
しかし、配膳ロボットに一部業務を任せることで時間や余裕が生まれ、その分を接客に充てることができれば、それまで以上にお客様に寄り添ったサービスを提供できるようになるかもしれません。完全な無人化は難しい
配膳ロボットも調理ロボットも人のサポートがある程度必要であり、完全な無人化は難しいのが現状です。ロボットはあくまで人間の助手であり、人に取って代わることは困難です。
店舗環境によっては導入が難しい
飲食店の店内環境によっては、配膳ロボットを導入できないケースもあります。たとえば「通路が狭い」「段差がある」「スロープがある」などといった店舗では、配膳ロボットが店内を巡回できないかもしれません。
また、配膳ロボットの運用にはインターネット環境も必要です。システムのバージョンアップや稼働状況ログのアップデートに無線のインターネットを利用するため、配膳ロボットの導入の際には店舗のインターネット環境も整備する必要があります。配膳ロボット導入の流れについて
飲食店が配膳ロボットを導入する際の主な流れは以下のようになります。
1.導入の目的やゴールを定める
2.店舗の環境調査を行う
3.トライアル
4.フィードバック
配膳ロボットを導入する際にまず考えるべきことは、配膳ロボットによってどのような課題を解決したいのかという目的やゴールを明確にすることです。そのうえで、上述した店舗環境の調査を専門家と行い、トライアルを実施します。
フィードバックの段階では、トライアルの結果をもとに課題を解決できるか、満足できる費用対効果が期待できるかなどを確認。業務と経営の視点から配膳ロボット導入を最大限活用できるかどうかを検討しましょう。飲食店で配膳ロボットを導入した事例
飲食店の中には、すでに配膳ロボットが活躍している企業や店舗があります。代表的な事例をいくつか紹介します。
■日高屋
日高屋では、コロナ後の人手不足と採用および新人の教育時間の確保が困難となっていた課題を解決するため、配膳ロボットを導入。トライアルで大幅な業務効率化が見られたことから、2022年に50店舗に1台ずつ、計50台を導入することを決定しました。日高屋は特に配膳・下膳の両方で即戦力として活躍したとしており、スタッフの労働負担の軽減に貢献したとのことです。
参考 PR TIMES『日高屋に見習いスタッフとして配膳・運搬ロボット50台入社決定 2022年3月より順次配属開始!』
■すかいらーくホールディングス
すかいらーくホールディングスは、2021年11月頃から全国のガストやしゃぶ葉、バーミヤンなど約2100店舗に配膳ロボットの導入を開始し、1年間で導入台数は3000台に達しました。当時はその話題性から集客効果に注目が集まりましたが、業務効率化にも貢献。同社によると、片付け時間が35%削減、スタッフの歩行数も42%削減したといいます。
参考 Skylark Career『すかいらーく「ネコ型配膳ロボ」3000台導入を成功させた「特命チーム」に迫る』
■ワタミ株式会社
ワタミ株式会社が展開する『焼肉の和民』では、配膳ロボット「KettyBot(ケティーボット)のスマート案内機能を活用し、ロボットに搭載された大画面のサイネージ越しに接客を行う「バーチャル店員」サービスを実施しました。 バーチャル店員にはバーチャルライブ配信アプリ「REALITY」の配信者を起用。当初は限定店舗のみでの実施でしたが、全国での実施を求める声が多かったことから、全店舗に拡大した第2弾も行われました。
参考 焼肉の和民『日本初「焼肉の和民」配膳ロボットバーチャル店員』配膳ロボット導入時の注意点と考えるべきポイント
配膳ロボット導入は人手不足の改善や人件費削減などさまざまなメリットがありますが、導入の前に以下のような注意点やポイントを考える必要があります。

アフターサポートがしっかりしているか
配膳ロボットは日々の運用の中で、メンテナンスや修理が必要になることがあります。迅速かつ適切なサポートがなくロボットが動かなくなってしまうと、業務効率や生産性の低下につながりかねません。問題が発生した際に素早く修理に駆けつけてもらえるサポート体制が整っているかを確認しておきましょう。
店舗の環境に合っているかどうか
配膳ロボットの導入にあたっては、店舗の広さや席数、スタッフ数など店舗環境への適合性の十分な検討が必要です。店舗の実態に合わないロボットを導入すると、オペレーションの障害となったり、お客様に迷惑をかけてしまったり、かえって経営に悪影響を及ぼす可能性があります。
配膳ロボットは異なるモデルやサイズが揃っており、さまざまな店舗に対応しています。導入する際は店舗の規模やレイアウトに沿った適切なものを選びましょう。目的やゴールを明確にする
配膳ロボットを導入する具体的な目的やゴールを明確にします。「人手不足への対策」「業務効率向上」「衛生管理の強化」など、自店舗の課題に基づくゴールを設定しましょう。明確な目的とゴールがあれば、トライアルの結果を適切に評価でき、ロボット活用の意義を客観的に判断できます。
費用対効果を見極める
配膳ロボットの導入には初期費用と運用費用を考慮しなければなりません。人手不足改善や人件費削減の効果を金銭的に換算し、費用対効果として算出しましょう。投資に見合った収益が得られるかどうかを総合的に判断することが重要です。
活用できる補助金・助成金の確認
配膳ロボットの導入には補助金や助成金も活用できます。代表的なものとして以下の3つが挙げられます。
●ものづくり補助金
●事業再構築補助金
●労働業務改善助成金
活用すれば導入コストの負担を抑えることができます。ただし、補助金や助成金の申請には決算書の準備や事業計画書の作成などが必要です。まとめ
ロボットは人の仕事を奪うのでは?と言われることもありますが、お客様の要望や困りごとを察知して自ら行動に移すのは、人だからこそできること。人間とロボットそれぞれの長所と短所を理解し、人でなければならない業務と、ロボットに任せられる業務をうまく棲み分けることで、業務効率や顧客満足度を高めていくことが可能です。
労働人口が減少傾向にある日本において、ロボット活用の重要性は今後一層高まると予想されます。これまでの店舗運営のあり方を見直し、ぜひロボットの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
株式会社USENでは、配膳ロボットを豊富なラインナップからご提案しています。多くの飲食法人様へ配膳ロボット導入を支援した実績をもとに、お客様の業態に合わせた活用方法をご提案します。資料請求から見積り、トライアルまで無料で承っているので、お気軽にご相談ください。
USENの配膳ロボット 詳細はこちらからこの記事の執筆

株式会社USEN canaeru編集部
飲食店をはじめ、小売店や美容室などの開業を支援する『canaeru』の運営を行う。店舗開業や経営に役立つ情報を日々提供し、開業者と経営者に向けた無料セミナーの企画・運営も担当。
- NEW最新記事
-
-
2024/10/23
-
2024/10/18
-
2024/10/11
-
- おすすめ記事
-
-
2017/10/17
-
2017/10/18
-
2021/11/24
-
2021/03/15
-
2021/06/29
-
2018/09/18
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数192件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数128件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数506件
-