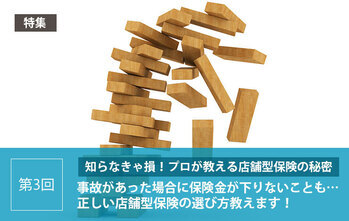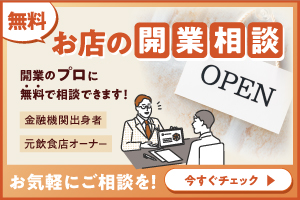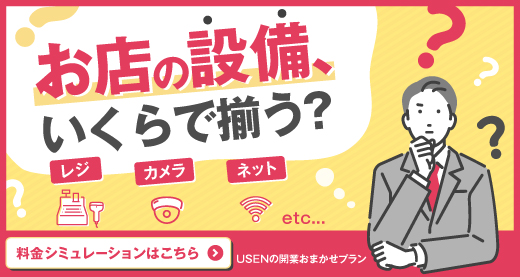更新日:
開業とは?起業・独立との違いや必要な準備・手続きを徹底解説!

- Tweet
-
働き方の多様化が進む中、「自分で事業を始めてみたい」と考え、実際に行動に移す人が増えています。しかし、開業と一口に言ってもさまざまな事業内容・形式があり「どのように進めればよいのかわからない」とお悩みの人も多いのではないでしょうか。
この記事では、開業にまつわる基礎知識や開業までの流れ、開業におすすめの業種について解説します。初めて開業する人、自分が開業に向いているかどうかを判断したい人はぜひ参考にしてください。
目次
開業とは?
開業とは、新たに事業や商売を始めること、あるいはしていることです。一般的に、個人が「開業届」を提出し、個人事業主として事業をスタートすることを指します。また、飲食店や美容室、病院など、店舗やクリニック、事務所を開いた場合にもよく用いられる言葉です。
開業届の提出方法はこちらを参考にしましょう。
参考記事 開業届に必要なものは?提出するメリットや書き方を解説!
国税庁サイト A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
法人を立ち上げて事業を始める場合は「法人を設立した」「起業した」と表現されることから、一般的に「開業」という言葉は個人に対して用いられる傾向があります。
また、開業と似た言葉に、起業や独立があります。「新しく事業を始める」という基本的な意味は同じですが、立場やタイミングによって意味合いが異なるため、これから開業をする人はその違いについても知っておきましょう。

開業と起業の違いは?
起業は、新しく事業を始めるという意味に加えて「それまでに世の中になかった新たな事業を起こす」「初めて会社を立ち上げる」といったニュアンスが含まれており、最近ではベンチャーやスタートアップ企業に対して使われることが多くなりました。そういった傾向から、「起業」は「開業」よりも法人や新事業に対して使われることが多い言葉です。
開業と独立の違いは?
独立は日常生活の中で多用される言葉ですが、ビジネスにおいては「会社に頼らず自分の力で生計を立てる」ということ。つまり、会社を辞めて個人で事業を始める、いわゆる「脱サラ」を意味します。開業は開業前の経歴に関係なく使用できる言葉ですが、独立は何らかの組織に所属していた人が離職し、事業を始める場合に使われます。
開業と創業の違いは?
創業とは、一般的に企業や事業を「新しく作り出すこと」を意味し、開業よりも大規模な印象があります。創業は事業の「初めて」を強調する表現で、会社設立時や事業の歴史的起点を指します。開業が営業の開始に重点を置くのに対し、創業は組織や事業の基礎づくりにフォーカスしています。また、「創業者」という言葉が示すように、長期的な事業展開の起点となる意味合いが含まれています。
開業するメリット・デメリットは?
個人で開業するということは、働き方の自由度が高い一方で、収入や社会的信用が不安定になるリスクも背負うことになります。あらかじめメリット・デメリットの双方を理解した上で判断するようにしましょう。
開業するメリット
■働き方の自由度が高まる
会社員から独立して開業する場合、働く場所や時間を自分で選択できることを魅力的に感じる人は多くいるでしょう。やりたい仕事を自分で選択し、好きな時間に取り組む、ワークライフバランスを重視した生活を送ることも可能です。通勤や人間関係のストレスから離れられる、という利点も大きいでしょう。
■開業届を出すと青色申告を選択できる
開業届を出して個人事業主として開業する場合、確定申告で青色申告を選択できるようになります。そうすることで最大65万円「青色申告特別控除」という税制上の優遇を受けることができるのです。
開業届や青色申告については以下の記事で詳しく解説をしています。
関連記事 開業届の必要書類とは?書き方や提出方法をわかりやすく解説
関連記事 青色申告を行う方法は?気になる書き方や提出期限を解説
■■収入が高くなる可能性がある
開業することで、会社員時代の給与の枠を超えた収入を得られる可能性があります。自分のスキルや専門性を直接収益に結びつけることができ、顧客や取引先を増やすことで収入の上限がなくなります。特に自分の得意分野で開業すれば、高い報酬を得られるプロジェクトを選択できるようになります。
また、複数の収入源を持つことで安定性と成長性を両立させることも可能です。事業が軌道に乗れば、会社員時代には考えられなかった収入水準に到達できるケースも少なくありません。開業するデメリット
■収入が不安定になるリスクが高い
自ら事業を営む場合、会社員と違って毎月同じ額の収入が得られるわけではありません。
また、会社を辞めて開業する場合、失業保険を受けられません。この失業保険の受給期間は通常、離職してから1年間と定められていますが、離職後に事業を開始した方に向けて2022年から特例を申請できるようになりました。
この特例は、離職後に事業を開始した方がやむを得ず事業を休廃業し、再就職することになった場合に失業保険が受けやすくなるものです。
事業を行っている期間は最大3年間受給期間にカウントされなくなるというもので、もし2年で事業を畳むことになった場合はその際に失業保険を申請することができます。
もちろん事業が続くことが一番ですが、どんな外的要因があるかわかりません。リスクヘッジとして認識しておくとよいでしょう。
参考 雇用保険受給期間の特例を申請できます|厚生労働省
また、仕事を得るためには自ら営業活動を行い、取引先と信頼を築いていく必要があります。収入を増やそうと仕事を詰め込みすぎて体調を崩してしまわないように、健康管理も大切です。
■自ら責任を負う必要がある
責任や役割が分散されている会社組織とは違い、個人事業主は自分で判断し、責任を負います。事業を始める際の資金調達から設備の手配、行政への申請や納税関係など、会社員とは比にならないほど管理する領域が広がります。
個人事業主は働き方の自由度が高まるメリットがある一方で、やりたい仕事ばかりに時間を割けなくなるという点も理解しておきましょう。
■資金集めに苦労する場合もある
開業時には初期投資や運転資金が必要となりますが、資金調達が大きな壁になることがあります。会社員と違い、安定した収入実績がないため、銀行からの融資審査が厳しくなることが多いです。自己資金だけでは足りない場合、公的融資や創業支援制度を利用する方法もありますが、申請手続きや審査に時間がかかります。
また、親族や知人からの借入を検討する場合も、人間関係に影響を及ぼす可能性があります。資金不足は事業継続の大きなリスクとなるため、開業前に十分な資金計画を立て、複数の調達手段を検討しておくことが重要です。開業する方法
実際に開業する方法として、主に以下の3つが挙げられます。
個人事業主になる
法人を設立する
フランチャイズ契約を結ぶ
それぞれ、どのようなメリットや注意点があるのか、確認しておきましょう。
個人事業主になる
個人事業主としての開業は、手続きがシンプルで初期費用も比較的少額で済むため、ハードルが低いのが特徴です。必要な手続きは、開業届の提出、青色申告承認申請書の提出(青色申告を希望する場合)、事業の種類によっては許認可の取得や保健所への届出などがあります。
経営判断の自由度が高く、事業収入をすべて自分のもにできるのも魅力ですが、一方で、社会的信用が法人より低い、社会保険は国民健康保険・国民年金となり、給付水準が会社員より低いなどの面もあるため、注意が必要です。
法人を設立する
株式会社や合同会社などの法人格を持つ組織を作ることを法人設立と言います。資本金や登記費用など、個人事業主より初期コストがかかりますが、法人格を持つことで社会的信用が高まり、融資や取引先の獲得がしやすくなります。
また、経営者個人の資産と会社の資産が分離されるため、事業上のリスクから個人財産を守りやすい特徴があります。節税効果や将来的な事業拡大、事業承継のしやすさなども法人化のメリットとして挙げられます。フランチャイズ契約を結ぶ
フランチャイズは、確立されたビジネスモデルやブランド力を持つ本部(フランチャイザー)と契約を結び、そのノウハウやシステムを使って事業を行う方法です。開業時には加盟金やロイヤリティが必要になりますが、独自で事業を立ち上げるよりも成功率が高いとされています。本部からの研修やマニュアル提供、経営指導があり、初心者でも比較的安定して事業を始められます。店舗デザインや仕入れルート、広告宣伝なども本部の支援を受けられるため、開業準備の負担が軽減されます。
ただし、本部のルールに従う必要があり、自由度は低くなる点や、契約内容によっては撤退時の制約もある点に注意が必要です。
【4ステップ】実際に開業するまでの流れ
開業を決意してから実際に開業するまでには、さまざまな手続きや準備が必要です。事業内容や状況によって必要な項目や順番が変わることもありますが、ここでは基本的な4つのステップを解説します。
どのような手続きや準備が必要なのか、まずは全体の概要を把握しましょう。

1.事業計画を立てる
開業を進めるにあたって最初に取り組むべきステップは「事業計画を立てる」です。事業計画とは、事業の内容や目標、収益や経費の予測、雇用のプランなど、どのように事業を進めていくかを示したものです。
事業計画を立てるときは、「事業計画書」にまとめていくとよいでしょう。事業計画書は、誰が読んでも事業計画の内容をわかりやすく可視化したもので、融資の申し込みや出資を募る際にも必要な資料です。頭の中にある事業プランに根拠となる数値をしっかりと記載し、説得力のある事業計画書を作成しましょう。
融資の返済期間にもよりますが、一般的には開業後3〜5年分の事業計画書を作成します。事業計画書は開業後の経営指針となるため、入念に作り込んでおくことが大切です。事業計画書の書き方について知りたい場合は以下の関連記事もご覧ください。
関連記事 事業計画書の書き方とは?目的やメリットについて解説
2.資金計画を立てる
資金計画は新しく始める事業にどれくらいの収益が発生し、どれくらいの経費がかかるのかを把握し、事業の継続性や信頼性を高めるために必要なステップです。
まずは、開業前後に必要となる開業資金と運転資金を算出し、収支計画書に落とし込みます。開業に向けては物件の取得、設備購入、広告・宣伝などが必要になりますが、開業当初は売上が不安定になりやすいため、初期投資は必要最低限に抑えておきましょう。
資金の調達方法は自己資金を準備し不足分は融資を申し込むケースが一般的です。融資にはさまざまな方法があり、日本政策金融公庫やメガバンクからの融資や、自治体による融資制度もあります。家族や親族からの借り入れも一つの選択肢として挙げられます。
融資によって借り入れ可能額や必要な自己資金額、入金のタイミングなどが異なるため、それぞれを比較して無理のない返済計画を検討しましょう。
関連記事 開業資金の調達方法をご紹介!自己資金と6つの集め方[人気記事]
3.備品の準備や手続きを行う
事務作業で最低限必要となるものは、事業用口座・クレジットカードや名刺、印鑑、電話番号、メールアドレスなど。インターネット回線やWi-Fiの準備も必須です。
飲食店や物販店舗の場合は、開業準備として設備や器具、什器などを用意するほか、仕入れ先の選定や見積り依頼、決済端末の手配などを行います。大型の家電や家具は高額なため、リース契約や中古品の購入を検討するのも一案です。広告・宣伝のためのショップカードやSNSアカウントの準備は早めにしておくとよいでしょう。
また、個人事業主になれば「確定申告」を行わなければなりません。申告は一年に一度ですが、一年間の収支をすべて洗い出す作業は予想以上に時間と労力のかかるもの。予め会計ソフトを導入して経理を効率よく進めることをおすすめします。
開業に必要な準備や手続きについては以下の関連記事で詳しく解説しています。
関連記事 個人事業主の開業でやるべきことはたった4つ!やることリストまとめ
開業するにはどうすればいい?個人事業主に必要な手続きと流れを解説4.開業届を提出
開業届とは、個人事業主として新たに事業を開始する際に税務署へ届け出る書類のこと。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。店舗や事務所を新設せず自宅で開業する際にも届け出は必要です。
開業届は開業日から1ヶ月以内の提出が義務付けられています。融資審査や子どもの保育園申請時など開業届の提出が求められる場面は意外と多く、開業届は個人事業主である事実を公的に証明するツールとなっています。
さらに、「青色申告承認申請書」も一緒に提出すれば税制上の優遇措置を受けることができるため、開業届を提出するメリットは大きいと言えるでしょう。
関連記事 開業届を出すメリットとは?具体的な書き方や提出方法も解説開業する際に必要な手続きとは?
個人で開業する場合、事業に応じた認可証の取得のみで開業することが可能です。たとえば飲食店を開業する場合は、保健所から営業許可証を得られれば、開業のための最低基準は満たしたことになります。
しかし、事業を開始する前に適切な手続きを行うことで、開業後にさまざまなメリットが得られたり、不利益を避けることができます。ここでは、事業開始時の重要な4つの手続きについて解説します。1:認可証の取得
まずは、事業形態に応じて保健所や税務署などで必要な認可を取得します。業種によっては不要な場合もありますが、許認可が必要な業種であるにもかかわらず、手続きを行わないまま事業を行うと、罰則を受けることがあります。
個人で開業するケースの多い業種において、認可証の申請先と必要な概要は以下の通りです。
業種 申請先 条件 飲食業 保健所 営業許可が必要 理容業・美容業 保健所 免許が必要 クリーニング業 保健所 営業許可が必要 不動産業 都道府県庁 免許が必要 2:開業届の提出
認可証を取得したら次は開業届の提出です。開業届は、所得税法で事業開始から1ヶ月以内に提出しなければならないと定められています。提出することで以下のようなメリットがあるため、忘れずに期日内に提出しましょう。
●社会的信用を得られる可能性がある
●屋号で銀行口座を開設できる(後述)
●法人カードの申し込みができる
●青色申告ができる
関連記事 開業届の必要書類とは?書き方や提出方法をわかりやすく解説3:銀行口座の開設
開業の際は、屋号名義の銀行口座を開設しておきましょう。口座名義に事業用の名称(店名など)が入ることで、事業と口座名義が直結し、取引先からの信頼を得られやすくなります。
また、事業収支と個人収支を分けて管理することで、会計処理が明確になり、納税申告などの手続きも簡単になります。確定申告時の書類作成もスムーズに行えるでしょう。
なお、屋号名義の口座を開設するには開業届の提出が必要です。4:青色申告の申請
青色申告とは、税金面で有利になる特典がついた確定申告制度のことです。最大65万円の特別控除が受けられたり、赤字を3年間繰り越せたりと、さまざまなメリットがあります。
青色申告で確定申告をするためには、期日内に「青色申告申請承認書」と「開業届」の提出が必要です。赤字が生まれやすい事業初年度こそ青色申告のメリットが役立つ可能性があるため、積極的に青色申告を行うことをおすすめします。開業に必要な資金はいくら?
日本政策金融公庫総合研究所のデータによると、2023年度の開業費用の平均値は約1,000万円となっています。しかし、500万円未満で開業している人が全体の4割以上を占めており、開業に必要な費用の相場は一概には言えません。
開業時に必要な費用項目の一例は以下の通りです。
●物件取得費
●内外装工事費
●機材費
●備品費
●販促費
この中でもとくに大きな割合を占めるのが、物件取得費。店舗や事務所を賃貸する場合は内外装の工事費がかかる場合が多く、開業費用は事業内容や店舗の有無によって大きく変動すると言えます。
参考 日本政策金融公庫総合研究所「2023年度新規開業実態調査」開業時に利用できる補助金・助成金はある?
開業にはまとまった資金が必要なため、自己資金で足りない時は融資のほかに補助金や助成金を活用する方法もあります。個人事業主が開業時に利用できる主な補助金・助成金は以下の通りです。
名称 対象者・条件 補助上限額 参考 創業助成金(東京都) 都内で創業を予定している方、または創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方 400万円 https://www.tokyo-sogyo-net.metro.tokyo.lg.jp/finance/sogyo_josei.html 商店街起業・承継支援事業(東京都) 都内商店街で、新たに店舗を開業しようとする方 694万円 https://wakajo-shotengai.com/concept/ 地方創生起業支援事業 東京圏以外の道府県又は東京圏内の 条件不利地域において社会的事業の起業を行うこと 200万円 https://www.chisou.go.jp/sousei/kigyou_shienkin.html
関連記事 【2025年最新】飲食店開業時に使える助成金・補助金は?開業をするべきタイミングはいつ?
残念ながら開業を決意するのに“旬”と言える時期はありません。自分の生活の中で、ベストなタイミングを見極めることが大切です。そのためには、前項で解説した「事業計画書」が重要になります。あらゆる課題をクリアにしたうえで「このビジネスプランで収益が得られる」と確信を持てるまで、入念にプランを練り直しましょう。
canaeruでは、開業についての情報収集をされる方に向けて開業セミナーを開催しています。
オンライン配信が中心で、無料で参加いただけます。日本政策金融公庫による事業計画書の書き方セミナーや業種別の開業方法など、さまざまなテーマで発信していますので開業準備にぜひお役立てください。
開催中の開業支援セミナー一覧
開業する業種選びのポイントは?
やみくもに開業しても成功は難しいもの。開業を成功に導くためには、業種選びにこだわることも大切です。業種を検討する際は、以下のポイントを参考にしてみてください。
経験のある業種
開業を成功に導く鍵となる要素は、経験のある業種を選ぶことです。業界の専門知識と実践的なノウハウは、最大の強みとなります。加えて、不測の事態が起きた際の対処の仕方も分かっているからです。また、築いた人脈を活かすことで、ビジネスの安定性を高めることができます。
経験がなくても知見を得られる環境が整っている業種
未経験の業種に挑戦する場合、積極的に学びの場を求めることが不可欠です。セミナーや勉強会など、知識を共有し合えるプラットフォームが整っているかを確認しておきましょう。事前に関連する資格を取得しておけば、経験不足をカバーすることができます。
失敗のリスクを可能な限り抑えられる業種
開業において、失敗を回避するための対策を立てることや、失敗しても損失を最小限に抑えるための準備を行うことは非常に重要です。飲食業界の場合、需要が高く確実な集客が見込める業種や、競合が少ない業種を選ぶことがポイントの一つになります。また、どの業種であっても、原価や人件費、設備費を抑え、収支のバランスが取りやすいかどうかは、成功の可能性を高める要素となりえます。
開業におすすめの業種とは?
開業に向いている業種の特徴として、以下の2点が挙げられます。
低資金で開業できる
低資金で開業できる業種には、以下のようなものがあります。
・ライター
・デザイナー
・動画クリエイター
・ネットショップ経営など
これらは自宅を拠点に活動することができ、PCひとつあれば大抵の作業が可能なため、最低限の初期費用で開業することができます。資格取得の必要のない業種は新規参入の障壁が低く、開業を志す方にとって人気の業種となっています。リスクを抑えて開業できる
リスクを抑えた開業方法として、副業から徐々に本業へシフトしていくやり方があります。たとえば以下のような職業が挙げられます。
・講師業
・マッサージ師/セラピスト
・ハンドメイド作家
・YouTuber/ブロガーなど
これらの仕事は、本業をこなしながら合間を縫って着手できることが特徴です。講師業で言えば、最初は週に一回程度のペースで教室を開き、生徒が増えてきたり、慣れてきたタイミングで徐々に回数を増やしていけば、ローリスクで本業へ移行することができるでしょう。
YouTuberやブロガーなども、収入が安定してきたタイミングで本業と切り替えることができれば、失敗のリスクを抑えることができます。よくある質問と回答
ひとりでも開業はできますか?
一人でも開業は十分可能です。実際、多くの個人事業主は一人で事業をスタートさせています。ただし、開業には税務、法務、マーケティングなど専門的な知識が必要な分野が多く含まれています。これらの分野に詳しい専門家や経験者のアドバイスを得ながら進めることで、効率的に準備を進められるでしょう。
また、一人だけの判断ではなく、第三者の客観的な意見を取り入れることで、ビジネスプランの盲点を発見したり、より良いアイデアが生まれたりする可能性も高まります。成功確率を上げるためにも、必要に応じて専門家の力を借りることをお勧めします。資格を持っていなくても開業できますか?
資格を持っていなくても多くの業種で開業は可能です。例えば、飲食店の場合、調理師免許がなくても店舗を開業することができます。ただし、業種によって必要な手続きや届出は異なります。飲食店では防火管理者の設置や食品衛生責任者の配置が必要になりますし、保健所への営業許可申請も欠かせません。
美容院なら美容師免許、建設業なら建設業許可など、特定の業種では資格が必須となるケースもあります。開業を考えている業種について、事前に必要な許認可や資格要件を調査し、適切に対応することが重要です。不明点は各自治体の窓口に相談しましょう。起業・開業のお悩み相談はcanaeruへ
開業したいけど「開業準備をどう進めればよいかわからない」「何から始めればいいかわからない」など、なかなか一歩が踏み出せないという方は、ぜひ『canaeru(カナエル)』の無料開業相談をご利用ください。
『canaeru』では銀行出身者や元飲食店経営者など、さまざまな経歴を持った開業プランナーが在籍。開業に関するあらゆる悩みにアドバイスします。サポート料は無料なので、お気軽にご相談ください。
canaeru開業サポート利用者の声
明凛堂 中目黒本店 岡部様
急な資金調達が必要になったためサポートをお願いしました。
資金調達以外にも市場のトレンドや、他の開業者がどのような手順を踏んでいるかなど、僕たちの事業について客観的な立場で意見をいただけたのでありがたかったです。出店自体は会社員時代に数多くやってきましたが、自分で資金調達をすることは未経験だったので、山下さんから意見をいただきながら進められてよかったです。
まとめ
この記事では、開業に関する知識とノウハウを詳しく解説しました。開業のメリットとデメリットをしっかり理解し、自分に合った開業スタイルを見極めることが大切です。
開業を決意したら、必要な手続きを一つひとつ着実にこなしましょう。開業する業種の選定では、自分の経歴や長所を活かせる業種を選ぶことをおすすめします。
着実な開業準備を行い、自分の強みを活かした開業スタイルを選べば、夢の第一歩を踏み出すことができるでしょう。この記事の監修

USEN開業プランナー
長原雄一
株式会社USEN 開業サポートチームに所属。日本政策金融公庫のほか、地方銀行や都市銀行など複数の金融機関にて融資業務を担当。資金調達の豊富なノウハウを活かし、店舗開業者のサポートを行っている。
【主なサポート内容】
・開業資金にまつわる相談受付
・事業計画書の作成サポート
・資金調達時の面談アドバイス
株式会社USEN/canaeru 開業プランナーの詳細はこちら- NEW最新記事
-
-
2025/08/29
-
2025/08/29
-
2025/08/27
-
- 人気記事
-
-
2020/05/20
-
2025/05/19
-
2020/03/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
先輩開業者の声

「絶対にやる!」準備期間は20年超。念願の独立開業から3年で…
-
セミナー情報

【飲食店開業資金】不動産担保ローンによる資金調達と融資成功の…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数12,352件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数57件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数452件
-