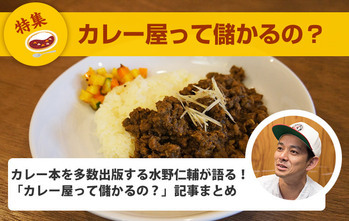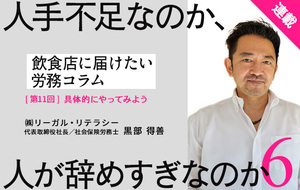- Tweet

空き時間やアイドルタイムなどを利用し、事業者が代金を取って別の事業者に店舗を貸し出す飲食店の間貸し。間貸しを利用した、間借り営業、シェアレストランといった営業形態が、近年注目を浴びています。
その需要は、貸したい側・借りたい側の双方ともコロナ禍を背景に増加傾向にあり、間貸しをサポートするマッチングサービスなども誕生しています。
この記事では、間貸しのメリットとデメリットに触れつつ、間貸しをはじめる基礎知識についてご紹介していきます。
目次
ニーズが高まる、飲食店の「間貸し」
ヒトサラ(USEN Media)が飲食店舗のオーナーを対象に実施したアンケートによると、「店舗の遊休時間(アイドルタイムまたは休店期間)を企業や個人に貸し出し、収益化をしたいと思いますか?」という質問に対して、
・内容次第では提供したい……約36%
・提供したい……約7%
・既に提供している……約3%
という調査結果が出ており、店舗を別の事業者に貸し出したいという意向を持つオーナーが約半数にのぼることがわかりました。
この背景には、コロナ禍で多くの飲食店が営業形態の見直しを迫られていたり、店舗を維持する賃料・光熱費などの固定費が重い負担になっていることが挙げられます。
一方で、飲食店を開業したいけれど物件を借りるリスクや、設備や内装、賃料の負担を軽減したいという開業希望者も増えています。
コロナ禍以前は、本格的な開業前の試験運用や週末の副業としてのニーズが強かった間借り営業ですが、「低コストで開業したい」「複数の土地でデリバリーのテストマーケティングをしたい」「ケータリングの仕込み場所を探している」など、ニーズが多岐に渡るようになってきました。間貸し・間借りの、メリットとデメリット
空き時間や店休期間を有効利用できる「間貸し」「間借り」ですが、具体的にどのようなメリットとデメリットが双方にあるのでしょうか。
間貸し側のメリットとデメリット
店舗を貸す側のメリットとデメリットを整理します。
【メリット】アイドルタイムに副収入を得て、固定費の負担を軽減できる
店舗を営業していない時間や期間も、賃料や光熱費などの固定費は発生しています。そこで、空き時間に店舗を貸し出すことで、副収入を得ることができ、店舗を有効活用できます。
また、副次的なメリットとして、別の事業者と共有することでそれぞれの顧客に対して店舗を認知してもらう機会も生まれます。借り手とコミュニケーションをとり、新たな顧客の創出に取り組むのもよいでしょう。
【デメリット】ルールを明確化しないと、トラブルが起きる可能性も
水光熱費の負担や、共有スペースの使用ルール、食材や消耗品の管理方法など、店舗を共有するにあたってルールを決めておかないとトラブルに繋がりやすくなります。特に、衛生管理については細かなルールまで設定し、順守しているかを定期的に確認したほうがよいでしょう。
後述しますが、万が一借り手の店舗で食中毒が発生した場合、その責任を負うのは貸し手になる可能性があります。間借り側のメリットとデメリット
店舗を借りる側のメリットとデメリットを整理します。
【メリット】リスクやコストを抑えて、短時間で開業が可能
いちから店舗を借り、飲食店を開業する場合、物件取得費や内装・設備・調理器具・什器などの投入費用に多額の資金が必要になります。間借り営業は、内装や備品が揃っている店舗を借りるため、設備投資のコストを抑えて、短期間で開業することができます。
また、店舗の運営と間借りした場所が合わない、複数の土地でテストマーケティングしたいなどの希望がある場合、店舗の移動や撤退もしやすいというメリットがあります。
【デメリット】内装・設備・営業時間など、さまざまな制約がある
店舗を間借りする場合、設備や什器の使い方などさまざまな独自ルールが設けられます。内装や店構えを自由に変更することができないため、イメージと異なる場合もあるでしょう。基本的に食材は別管理になるので、限られたスペースでどうやって食材を保管するかも検討しなければなりません。
また、貸し手の営業時間にあわせて営業を終了し、引き渡す必要があるので時間のやりくりも必要です。間貸しするための基礎知識
実際に間貸しをしてみたい場合、どのようなことを準備しなければならないのでしょうか。気を付けなければならない注意点も含め、基礎知識をお伝えします。
1.物件オーナーの許可を得る
賃貸物件の場合、物件を所有するオーナーに許可をとらねばなりません。
民法第612条で、「賃貸人の承諾を得なければ転貸できない。もし、違反した場合には賃貸人は、契約の解除をすることができる」と定められており、許可を得ない場合は自身が立ち退きを求められたり、トラブルに発展する可能性があります。
間貸しをはじめたい場合は、まず物件のオーナーに相談しましょう。なお、物件を自身が所有する場合は、自由に間貸しを行えます。2.間貸しの賃料を決める
次に、間貸しの賃料を決定します。水光熱費のほか、共有スペースの維持費などがかかる場合、どのくらいの比率で借り手に負担してもらうかを算出しましょう。
賃料に含めず、別途請求したり都度算出して請求する方法もありますが、固定の金額にして賃料に含めるほうが貸し手の手間はかかりません。3.共通ルールを決める
共有スペースの使用ルールや食材・備品の管理、ゴミ出しの方法など、店舗を共有するにあたっての細かいルール設定は非常に重要になります。もし、使用しないで欲しい設備や什器などがあれば、事前に伝えておく必要があります。
特に、衛生面のルールについては大きなトラブルに発展しかねないため、双方しっかり確認する必要があります。貸し手・借り手とも気持ちよく店舗を営業するために、コミュニケーションをはかりながらお互いの希望をすり合わせましょう。4.保健所の営業許可、食品衛生責任者の資格等の有無は?
飲食店を営業する際、保健所に申請し、飲食店営業許可を取得する必要があります。原則、貸し手側の店舗が取得していれば営業は可能ですが、万が一食中毒などの事故が起きてしまった場合、貸し手側も連帯責任を取る必要が出てくるため、借り手側も許可を得ておく方がよいでしょう。
なお、借り手側の目的が飲食店ではなく喫茶営業だった場合や、販売業・製造業で利用したいという場合は、必要な営業許可も異なってきます。使途に応じた営業許可を借り手が取得しているかどうかも確認が必要です。
また、食品衛生責任者の資格は、貸し手・借り手の双方の代表者が必ず取得しなければなりません。貸し手側は、飲食店開業を希望する借り手側が食品衛生責任者の資格を有しているか、しっかり確認しましょう。「間貸し」する際に活用例を提示してみよう
間貸しを行う際には、想像力を刺激する一手間が求められます。例えば、間借りする側に対して、その場所がどのように活用できるか具体的なイメージを提供することが効果的と言えます。
そのためには、間借り営業の活用例をいくつか知っておくことが大切です。以下で特徴的な間借り営業の実例を紹介します。元祖カジュアルラーメンバル『大気軒』
「宇宙×昭和ロマン」をユニークなテーマに掲げるラーメン店・大気軒は、居酒屋を間借りして平日の深夜24時から営業を展開しています。物件取得費や厨房設備費の節約により、驚くべきコストパフォーマンスを実現。看板メニューであるユーフォー醤油ラーメンは、わずか500円(税別)で提供されています。
さらに、深夜営業という特徴を最大限に活用し、セレクトされたカクテルも提供。ラーメンをつまみにお酒を楽しむという新しい食文化を確立し、革新的かつエコノミカルなスタイルで注目を浴びています。鮨カゲロウプロジェクト
鮨カゲロウプロジェクトは、六本木の高級寿司店を間借りし、本格的な江戸前寿司を破格の安さで提供する、株式会社クリエイティブプレイスが打ち出したプロジェクトです。六本木駅から徒歩1分以内という好立地にもかかわらず、間借りという方法を採用することでコストを大幅に削減し、お手頃な価格での提供を可能にしました。
本格赤酢寿司コース15貫コースは税込3,800円という価格で、高級寿司が1貫あたり約250円で食べられると話題に。わずか3日間で2000名の予約が入るという爆発的な反響を見せました。YOLO Spice
間借り営業と言えばカレー。“間借りカレー”というジャンルも確立されているほど、間借り店舗でカレー屋を経営しているケースは多いです。
YOLO Spiceは、夜は居酒屋営業している店舗を間借りし、オープンはお昼のみという営業スタイルをとっています。店主はアーティストという肩書で、開業当初からアーティスト活動の傍らでカレー屋を経営していたといいます。
人気も出て経営が軌道に乗ってきたことで、ゆくゆくは自分で店舗を立ち上げることを検討中とのこと。開業コストを抑えつつ、自分の料理の腕を試すことができる機会を創出できるのは、間借り営業のメリットと言えるでしょう。間貸しする際の使用料の相場は?
間貸し・間借りの使用料の相場は、物件の家賃に基づいて決まるケースが多いです。家賃をベースに、使用する面積の割合や時間によって算出されます。
一般的には家賃の1/3程度と言われており、家賃が30万円の場合、使用料の相場は10~15万円となります。
ただし、重要なのは貸主と借主がお互いに納得することです。お互いの意見を尊重しながら、双方が納得する条件で使用料を決定するのが理想のかたちです。
トラブルが起きたときの対処
明確なルールを取り決めてもトラブルが起こる可能性はあります。間貸しによってどのようなトラブルが起こるのか、対処法とあわせて具体例をご紹介します。
間借り側が、食中毒を起こしてしまったら?
借り手が食中毒を起こしてしまった場合、その責任は借り手側に発生します。立入調査を受けたり、営業停止などの行政処分を受けるのも借り手側になります。
しかし、貸し手が借り手に業務委託をして飲食店を営業している場合は、貸し手側に責任が発生します。また、貸し手側の飲食店営業許可を用いて借り手が営業している場合も、連帯責任として双方が処分を受けることになります。
借り手のみに責任が発生した場合でも、顧客の心証を害することは確かです。衛生面の管理は、双方とも徹底するようにしましょう。設備や共有スペースを破損してしまった場合は?
賃貸物件を間貸ししている場合、物件のオーナーと賃貸借契約を結んでいるのは貸し手側のみとなっている場合がほとんどです。
物件オーナーに間貸しの承諾を得ていたとしても、事故が発生した場合は物件を契約している側に責任が発生することがあります。
責任の所在をはっきりするためにも、事前に賠償の方法や金額などを取り決めておくほうがよいでしょう。ガイドラインの作成と、借り手の見極めが大切
お互いが気持ちよく営業を継続するためにはガイドラインやルールの作成が必須となります。状況に応じて、フレキシブルに内容を見直す柔軟さも必要かもしれません。
また、貸し手は間貸しする条件が合っているかどうか、ルールを順守してくれる事業者かどうか、店舗と事業はマッチしているかなどの見極めも大切です。
短期の貸し出しであれば不要ですが、中長期の貸し出しをする場合は、借り手側の事業計画はしっかりしているか、土地とターゲット層は合っているかなども確認したほうがよいでしょう。安定した副収入を得るためには、中長期の貸し出しがベストです。どのような事業を展開する見込みなのか、話し合いの場を持つことも重要でしょう。間貸しをはじめるには?
自身が所有する物件であったり、物件オーナーの承諾を得た場合は、好きなタイミングで間貸しをはじめることができます。借り手を募るにあたり、張り紙で宣伝したり、SNSを使ったり、人づてで探すといった方法が挙げられます。
昨今のニーズの高まりにより、貸したい側・借りたい側をマッチングするWEBサービスなども立ち上がっており、そういったサービスを利用するのもよいでしょう。
店舗の空き時間を有効利用し、副収入を得る間貸し。貸し手・借り手の双方がストレスなく、円滑に営業できることを目標に、間貸しを検討してみるのはいかがでしょうか。
この記事の執筆

株式会社USEN canaeru編集部
飲食店をはじめ、小売店や美容室などの開業を支援する『canaeru』の運営を行う。店舗開業や経営に役立つ情報を日々提供し、開業者と経営者に向けた無料セミナーの企画・運営も担当。
- NEW最新記事
-
-
2024/10/23
-
2024/10/18
-
2024/10/11
-
- おすすめ記事
-
-
2016/12/06
-
2023/04/24
-
2021/11/26
-
2018/08/20
-
2018/05/18
-
2020/03/12
-
- 人気記事
-
-
2022/01/28
-
2024/07/23
-
2024/06/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
開業・経営に関する記事

飲食店を開業するには?必要な準備の4ステップをわかりやすく解…
-
先輩開業者の声

シェアキッチン型飲食店『shitagoya』がオープン!新た…
-
セミナー情報

【第8回】月刊食堂・通山編集長の外食経営塾|スペシャル対談(…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数192件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数128件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数506件
-