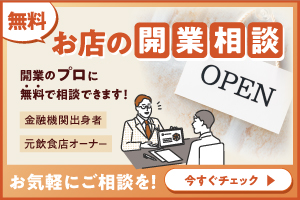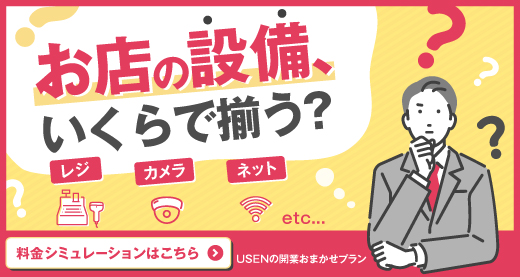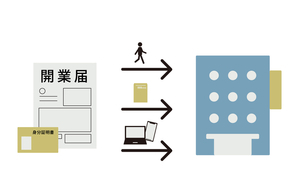更新日:
独立開業しやすい業種は?独立開業までに必要な基礎知識を解説!

- Tweet
-
働く際の選択肢には、会社員として勤務する以外に「独立開業する」という方法もあります。
独立開業を目指す際にやるべきことはたくさんあり、資金の調達や書類の提出など、さまざまな準備を行わなくてはなりません。
また、独立開業には不安がつきものなので、これまで培った経験を活かして独立開業したいと考えていても、なかなか行動に移せていない方もいるでしょう。
この記事では、独立開業のための方法や手段、流れを詳しく解説します。独立開業を検討している方、今とは違う働き方で仕事をしたい方はぜひご一読ください。
目次
独立開業とは何か
独立開業とは、雇用関係から離れて自分自身のビジネスを始めることです。既存の業種やサービスの枠組みの中で、自らの技術や経験を活かして事業を展開します。
個人事業主としての開業が一般的ですが、小規模な法人設立の形態もあります。特徴は比較的低リスクで始められ、自分のペースや価値観で仕事を進められることです。
参考記事 開業とは?起業・独立との違いは?必要な準備についてもわかりやすく解説
独立開業しやすい職種
開業する職種がまだ決まっていない方は、「初期費用の少なさ」と「利益率の高さ」に注目して選ぶことがおすすめです。
開業時の初期費用としては、主に以下のようなコストがかかります。
費用 内容 開業資金 物件取得費や設備導入費、開業手続きに必要な諸費用など 運転資金 光熱費や仕入代金などの固定費 当面の生活費 事業が安定するまでの生活費
どんな事業を始めるかによって初期費用の規模は大きく異なります。費用の中で大きく金額を占める物件取得費は、自宅で開業すれば抑えられます。物件を借りて開業する場合は居抜き物件にしたり中古の設備を手配することが有効でしょう。
また、場所を問わずオンラインで完結する仕事など、初期費用を低予算に抑えられる職種は資金を確保する手間と時間がかからないため、開業準備もスムーズに行えます。初期費用がかからない分、仮に事業に失敗した際に負うリスクも少ないです。
さらに事業の継続性と収益確保を重視して、利益率の高い業種を選ぶことも戦略上は大切です。コンサルタントやオンライン講師など、人的資本だけで完結できるサービスは初期投資や原価がかからないため利益率が高いといえるでしょう。
また、在庫管理が必要ないデジタルコンテンツの販売や、専門知識が必要ですがアプリ開発なども利益率を重視したい場合にはおすすめです。
以降は、数ある職種の中から初期費用が低く利益率の高い職種を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。インターネット関連のクリエイター
インターネット上のコンテンツを制作するクリエイターは、最低限パソコンが1台あれば仕事を行えるため、初期費用が少なく始めやすい職種です。
具体的な職種として、以下のものがあります。
●WEBデザイナー
●エンジニア
● ライター
●動画編集者
元々クリエイターとして働いていた方であれば、そのときに習得したスキルや知識をそのまま仕事に活かせるため、スムーズに事業を進められるでしょう。
事業に必要な情報を集めやすい点も、インターネット関連のクリエイターの魅力です。クリエイターとしての活動内容やノウハウを発信している個人事業主が多いため、仕事の不明点や疑問点の多くは、インターネットで検索すれば解決できます。講師
専門的な知識がある方は、講師業に挑戦するのもおすすめです。たとえば、下記のような職種が挙げられます。
●楽器の講師
● 英会話の講師
● プログラミングの講師
●パソコンの講師
これらの職種は特別な資格は不要のため、スキルや経験があれば開業はスムーズです。また、教室のように物理的なスペースで行うだけでなく、会議アプリなどを用いてオンラインで講師業を始めることも可能です。オンラインの講師業はスペースの確保が不要な分、初期費用も抑えられます。コンサルタント
専門的なスキルや資格を持っていれば、下記のような職種のコンサルタントとして活躍できます。
●経営コンサルタント
● WEBコンサルタント
●ITコンサルタント
コンサルタントの仕事の幅は広いため上記の職種はあくまで例であり、近年では恋愛やSNSの領域で活躍するコンサルタントもいます。
なお、コンサルタントは何よりも信用が重要となる仕事です。自分自身の信用性を高めるためにも、事前にホームページやブログで活躍したい領域の情報を発信しておくとよいでしょう。飲食店オーナー
飲食店オーナーとして飲食店を経営することは費用がかかると思われがちですが、条件によっては初期費用を抑えて開業できるケースもあります。
たとえば、業務に必要な設備が整っている「居抜き物件」を活用すれば、0から物件を借りて設備を導入するときと比べて初期費用を大きく抑えることが可能です。回転率が高い、または利益率が高い業種を選んで始めれば、開業後の生活も安定しやすいでしょう。
また、飲食店はフランチャイズ展開が多い職種でもあります。フランチャイズであれば本部のサポートを受けつつ開業できるため、経営に不安がある方にとって心強い方法です。サロン系のビジネス
美容に関するスキルがある方は、サロン系のビジネスに挑戦してもよいかもしれません。サロン系のビジネスにはさまざまなジャンルがありますが、具体的には下記のような職種が挙げられます。
● ネイルサロン
●リラクゼーションサロン
●まつ毛エクステサロン
サロン系のビジネスはオンラインではサービスを提供できませんが、出張型で行う、店舗を借りる、または自宅で開業することができます。レンタル・代行業
下記のようなレンタル・代行業も挑戦しやすい職種のひとつです。
● 家事代行
● 衣料品のレンタル業
家事代行は常に一定のニーズがある職種なので、安定して働き続けやすい職種と言えるでしょう。隙間時間に取り組めることから、副業として始めるのもおすすめです。
衣料品のレンタル業は、衣料品を仕入れる初期費用がかかりますが、同じ商品を複数回貸し出すことで利益を上げるため、在庫を多く抱える必要がありません。マッチング業
マッチング業とは、売り手と買い手を仲介する仕事のことです。例としては、下記のような職種が挙げられます。
●塗装会社のマッチング
● リフォーム会社のマッチング
●人材のマッチング
売り手と買い手さえいれば、どんなジャンルでも事業が成立するため、ニッチなジャンルでも始められるところがマッチング業の魅力です。専門業種の営業職などの経験があれば、これまで培ってきたノウハウを活かすことができるでしょう。
ただし、売り手と買い手を集めなければいけない以上、インターネットなどで強い集客力を構築しなくてはなりません。YouTuberやブロガー
YouTuberやブロガーは、近年インフルエンサーとして若い人を中心に大きな影響力を与える存在です。YouTuberは広告の付いた動画の再生数に応じて、ブロガーはブログ内に掲載された広告の閲覧や記事で紹介したサービスの申し込みなどにより、利益を上げるビジネスモデルとなっています。
パソコン1台で始めれば初期費用はほとんどかかりませんが、クオリティを上げるには機材費用が別途かかってきます。収入は人によって大きく異なり、上手くいけば月に数百万円のお金を稼ぐことも可能です。
ただし、YouTuberやブロガーは短期的に利益を上げにくいので、コツコツと努力を続けられる方向けの職種です。
参考記事 独立開業しやすい仕事ランキング|成功させるポイント・必要なスキルを解説
参考記事 一人で開業できる仕事25選!テーマ別におすすめの仕事をご紹介独立開業するまでの主な流れ
次は独立開業までの流れを確認しましょう。大まかな流れは以下の通りです。
Step1.計画・資金繰り
Step2.法的手続き
Step3.実務準備
Step4.営業開始1.計画・資金繰り
●事業計画書の作成(目標、市場分析、収支計画など)
●必要な資格・スキルの取得
●資金計画(自己資金、融資、助成金の検討)
●競合分析と差別化戦略の検討
始めにすることは、事業の根幹となる計画づくりです。市場ニーズを見極め、実現可能な収益モデルを検討します。必要な準備期間と資金を具体的に算出することが成功への鍵となります。
開業資金の調達方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事 開業資金の融資審査は厳しい?落ちる理由や通るためのポイントについて解説2.法的手続き
●事業形態の決定(個人事業主、法人など)
●開業届の提出(個人事業主の場合)
●法人設立登記(会社設立の場合)
●業種別の許認可取得
●税務署への届出(青色申告承認申請書など)
次は開業に必要な法的手続きを行う段階です。事業形態によって必要な手続きは異なりますが、税務・法務面での不備は後々大きな問題となるため、専門家の助言を得ながら慎重に進めましょう。3.実務準備
●事業拠点の確保(オフィス・店舗の契約)
●必要な設備・備品の調達
●取引先・協力業者との関係構築
●銀行口座開設(事業用)
●各種保険の加入(事業保険、社会保険など)
実際の事業運営に必要な環境を整えます。コスト管理を意識しつつも、事業が円滑に進むために必要な設備や人的ネットワークの構築に投資することが重要です。法的手続きと並行して進めることができればスムーズです。4.営業開始
●マーケティング戦略の実行(広告、ウェブサイト作成など)
●運営体制の構築と改善
●売上・収支管理の開始
●事業の評価と戦略の見直し
計画を実行に移す最後の段階です。初期段階では想定外の課題が生じることも多いため、柔軟な対応力と改善姿勢を持ち、PDCAサイクルを回しながら事業を軌道に乗せていきましょう。独立開業に必要な準備や手続き
独立開業には様々な準備と手続きが必要です。まず事業計画書を作成し、事業内容や市場分析、収支計画、差別化戦略を明確にしましょう。必要資金を算出し、自己資金や融資などの調達方法を検討します。
次に法的手続きとして、個人事業主か法人かの事業形態を決定します。個人事業主なら開業届の提出、法人なら定款作成から登記までの手続きが必要です。業種によっては各種許認可も取得しなければなりません。税務署への届出も忘れずに行いましょう。
開業届の記載方法については詳しくは以下の記事で解説しています。
関連記事 個人事業主に開業届は必要?手続き・流れを解説
実務準備としては、事業用銀行口座の開設、事業所の確保、設備・備品の購入、取引先との関係構築が重要です。また、事業保険への加入や、従業員を雇用する場合は社会保険・労働保険の手続きも必要になります。
最後にマーケティング準備として、ウェブサイト作成、販促ツールの準備を行い、集客活動の基盤を整えます。これらの準備を計画的に進めることで、スムーズな開業と事業の安定的な発展につながります。
独立開業のメリット
独立開業のメリットは、働く自由度が高いことです。好きな仕事を好きなペースで進められ、自分の判断で業務内容や方法を決められる柔軟なワークスタイルが魅力です。
その他にもメリットはさまざまあり、主なものは以下の4つが挙げられます。
●自由に働ける
●仕事にやりがいを感じられる
●高収入を目指せる
● スキルが向上しやすい
● 定年がなく働き続けられる
それぞれのメリットについて、詳しい内容を順番に説明します。自由に働ける
一般的な会社員は決まった時間に出勤や退勤をしますが、独立開業すれば働く時間は自由。会社のルールに縛られることなく都合のよいときに働けます。組織に属していないため、同僚や上司との人間関係に悩むことも少なくなるでしょう。
また、パソコン1台でできる仕事であれば、コワーキングスペースや近所のカフェなど、好きな場所で仕事に取り組めます。仕事にやりがいを感じられる
会社員の場合、1から10まで自分の思い通りにできる仕事はなかなかありません。割り振られた仕事内容によっては、窮屈に感じてしまうこともあるでしょう。
しかし、独立開業をすれば自分の好きなように仕事を進められます。好きな業種を選んで働けるだけでなく、自分で生み出したアイデアを形にできるため、仕事に対するやりがいも増えるかもしれません。高収入を目指せる
独立開業すると、月々の収入は自分の頑張りや工夫によって変化します。事業が上手くいけば、高収入を得ることもできるでしょう。
もちろん、会社員でも高収入は目指せますが、もらえる給料には上限があるケースが多く、どこかで限界が来る場合がほとんどです。
その点、独立開業する場合は収入に上限がないため、より高収入を目指せると言えます。スキルが向上しやすい
独立開業をする場合、会社員とは違って指示を出す上司がいないため、仕事について自分で考える機会が増えます。
同僚や上司がいない環境では、自分で行わなければならない仕事も増えますが、それだけ仕事に関するスキルも向上しやすいでしょう。
また、自分で考え行動することで得られる多くの成功・失敗体験を通じて、人としても成長できる機会も増えるでしょう。定年がなく働き続けられる
サラリーマンは定年を迎えると、収入が減少するリスクがあります。再雇用や嘱託になった場合でも、以前の給与水準を下回ることがほとんどです。
一方で、自営業には定年がありません。定年後も事業を続けられるため、確実な収入源を維持できます。これは独立開業の大きなメリットと言えるでしょう。実際、定年退職を機に開業を目指す人も少なくありません。
自営業なら、好きな仕事に没頭し、自らのペースで働くことができます。さらに、生きがいを持ち続けられるため、心身の健康維持にも好影響があると期待されています。独立開業のデメリット
独立開業はメリットが多い反面、下記のようなデメリットもあります。
●経済的な負担や不安がある
● 失敗やミスをしたときに責任を背負う範囲が広い
● 健康管理を徹底する必要がある
事前にメリットだけでなくデメリットも把握することで、リスクを回避しやすくなるでしょう。ここからは、それぞれのデメリットについて紹介します。経済的な負担や不安がある
どんな事業でも開業当初は顧客を確保するのが難しく、収入が安定するまでに時間がかかります。開業後しばらくは収入はほとんどなし、場合によっては赤字も覚悟しておかなければなりません。
十分な貯蓄があっても、開業資金に大半を費やしてしまうことも想定されます。独立開業する際は、融資や補助金・助成金をしっかり活用し、経済的負担を少しでも減らす工夫をしましょう。また、会社に勤めながら徐々に個人事業を大きくしていく方法もあります。失敗やミスをしたときに責任を負う範囲が広い
会社に所属しており、損害賠償などが発生するような重大なケースにおいては、会社が責任を負ってくれるのが一般的です。
一方、独立開業する場合には、事業を行ううえで発生したトラブルの責任は全て自分が負わなければなりません。ミスやトラブルを防ぐためにも、スケジュールや品質管理を徹底する必要があります。健康管理を徹底する必要がある
会社員として勤務している場合、身体に不調があった際には仕事を休むことができます。休んだ分の仕事は、同僚や上司が自分の代わりにカバーしてくれて、仕事に大きな影響が出ないケースも多いでしょう。
しかし、独立開業をすると自分の代わりがいないため、体に不調をきたしても自分で何とかするしかありません。作業の進み具合に影響を出さないためにも、今まで以上に健康に気を遣う必要があります。フランチャイズを活用して独立開業する方法
独立開業をする際には、自身で0から事業を立ち上げるのではなく、「フランチャイズを活用する」という選択肢もあります。
フランチャイズとは、ロイヤリティを支払う代わりに企業が提供する商品やサービスを販売できる権利を得られるビジネスモデルのことです。権利を与える企業を「本部(フランチャイザー)」、権利を与えられた側を「加盟店(フランチャイジー)」と呼びます。
フランチャイズを活用すれば、本部のブランド名を借りたうえで同じ商品を提供できるので、0から事業を始めるよりも軌道に乗せやすくなります。開業に不安がある方は、フランチャイズの活用も選択肢に入れるとよいでしょう。
フランチャイズを活用するメリット・デメリットについて詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。フランチャイズを活用するメリット
フランチャイズを活用するメリットは、大まかに以下の3点が挙げられます。
●未経験でも挑戦できる
● 成功する可能性が高まる
● 従業員の研修を行う手間が減る
多くのフランチャイズ本部では、開業や経営、業務に関するサポートを行なっており、バックアップ体制が充実していることから、未経験の方でも開業に挑戦しやすくなっています。
また、フランチャイズを活用する際は本部のブランド力に頼れる分、集客力や認知度が高い状態で事業をスタートすることが可能です。0から事業を行うよりも、成功する可能性はより高まるでしょう。
さらに、従業員の研修を行う手間が省ける点も大きなメリットです。雇った従業員の研修サポートを行なっているフランチャイズ本部であれば、自分が従業員の研修に費やす時間をほかの業務に使えます。フランチャイズを活用するデメリット
フランチャイズは魅力的な制度ですが、いくつかデメリットもあります。とくに注意したいのが、下記の3点です。
●個人のアイデアを活かせない
●ロイヤリティを支払う必要がある
● 解約が難しい
フランチャイズを活用して経営を行う場合、店舗や商品のイメージは基本的に本部の方針に従う必要があります。自分のアイデアを形にしにくいため、個性のある店舗や商品を作りたい方には向いていないかもしれません。
また、本部が提供する商品やサービスを販売できる権利を得られる分、毎月ロイヤリティの支払いが発生します。自分一人で開業する場合と比べると、収入が減る可能性もあるでしょう。
多くの場合は、契約期間中に解約すると違約金の支払いが義務付けられている ため、容易に解約ができないケースもあります。
関連記事 フランチャイズ契約書でチェックすべき注意点とは?デメリットや開業の流れをわかりやすく解説開業資金が足りないときはどうすればいい?
職種によっては、独立開業をするためには多額の資金が必要なため、自己資金だけでは足りない場合もあるでしょう。そんなときには、下記の方法で資金の調達を検討してみてください。
● 金融機関の融資制度を利用する
●自治体の補助金を活用する
● クラウドファンディングで資金を集める
公的な機関である日本政策金融公庫や民間の金融機関では、新規開業のための融資制度を設けています。 融資制度を活用すれば、不足している設備資金や運転資金などの借り入れが可能です。
返済に不安がある方は、補助金の活用も検討しましょう。補助金を受け取るには事務局に申請をして審査に通る必要がありますが、基本的には返済不要となっているため、経済的な負担を背負わずに資金を調達できます。
インターネット上でのクラウドファンディングを活用すれば、自分が発信した内容に賛同した方々から資金を集めることも可能です。リターン不要の「寄付型」、または支援者にリターンを示すことで資金を募る「購入型」などの方法で、開業資金を集められます。
紹介した方法以外にも資金を調達する手段は複数あり、開業資金の全てを自分だけで用意するのは難しいため、不足している資金は何らかの手段で外部から調達するのが一般的です。
「開業したい職種は決まっているけど、初期費用を用意できない」と困っている方でも、資金を調達すれば開業できる可能性は高まるので、お金が足りないからといって開業を諦めずに資金調達の方法を検討してください。ただし、自己資金はある程度用意する必要があります。全くのゼロではどの金融機関も話を聞くだけで終わってしまうでしょう。
開業資金については詳しくは以下の記事で解説しています。
関連記事 開業資金にかかるお金はいくら?資金調達の方法や融資の審査ポイントも解説独立開業して自分の理想の人生を歩もう!
独立開業は敷居が高いと思われがちですが、挑戦しやすい職種もあります。興味がある方は、自分の理想の人生の第一歩として、この機会に開業に向けて取り組んでみましょう。
もちろん、開業にはさまざまなリスクも伴い、準備すべき事柄も多岐にわたるため、不安を感じる方もいるでしょう。
そんなときには、「canaeru」の無料開業相談をご利用ください。canaeruは国から経営革新等支援機関(認定支援機関)と認められた株式会社USENが運営するサービスです。税務、金融および企業財務に関する専門的知識や支援にかかる実務経験が一定レベル以上ある支援機関として国に認められています。
これから独立開業を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な開業コンサルタントによるが誠心誠意アドバイスいたします。
無料開業相談
この記事の監修

USEN開業プランナー
松村俊治
株式会社USEN 開業サポートチームに所属。飲食店経営歴8年。その経験を活かし、開業に関するあらゆる支援を行う。開業に必要なサービスや設備、業者などの紹介のほか、店舗のコンセプト設計、事業計画書の作成サポートにも精通。
【主なサポート内容】
・開業手続きの支援
・開業に必要なサービス、設備、業者を紹介
・創業計画書の作成サポート
・事業計画書の作成サポート
株式会社USEN/canaeru 開業プランナーの詳細はこちら- NEW最新記事
-
-
2025/08/29
-
2025/07/17
-
2025/07/17
-
- 人気記事
-
-
2023/10/02
-
2020/06/30
-
2021/06/29
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
先輩開業者の声

「絶対にやる!」準備期間は20年超。念願の独立開業から3年で…
-
セミナー情報

【飲食店開業資金】不動産担保ローンによる資金調達と融資成功の…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数12,401件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数57件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数452件
-