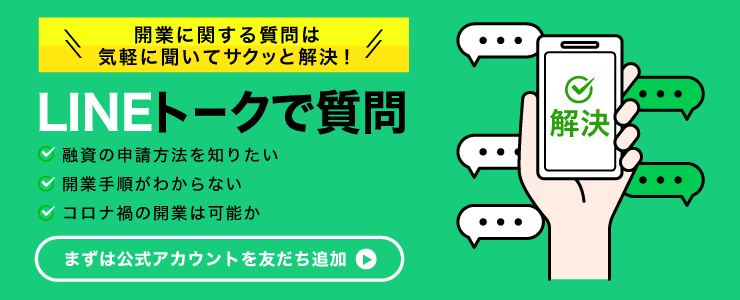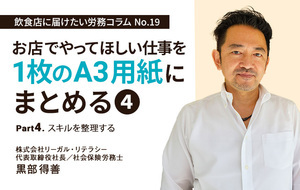炒飯を「れんげ」で食べるのは難しい・・・
誰もが一度は感じたことがあると思います。
特に難しいのが、「最後の一口」ではないでしょうか。
ほんの数十粒残ったお米を、こんなに大きな「受け」でどうやってすくえと言うのか。
形状上、ほぼすくうのが不可能なのに、永久に「れんげ」側の仕様は変わることなく、「残ったお米」と「受け」側のミスマッチのまま、令和の時代になっても、やはり炒飯には「れんげ」がついてくる。
そこまでして「れんげ」で食べさせようとする炒飯には、何か秘密があるのか?
「炒飯れんげ」なる「れんげ」もあるのですが、「炒飯れんげ」が出てくる店の方が少ないですよね。
なかなか頑固な「れんげ」。
その歴史から、炒飯にれんげが付いてくる理由を探りました。
■ 回答 ■
ラーメンなど麺類を出す中華料理店が、そのスープを飲む用の「れんげ」をそのまま出したのが始まり。
「れんげ」が日本にやってきたと言われているのが平安時代。
中国から日本に伝来したれんげは散った蓮の花びらに形が似ていることから、その名前が付けられたそうです。
日本人に定着したのはそのずっと先のことで、ラーメンなど、麺類を出す店が一般化したことで日本でも需要が増えました。
なお、本家の中国では、この大きなの「れんげ」で米類を食べることは無いそうです。