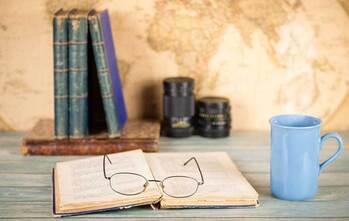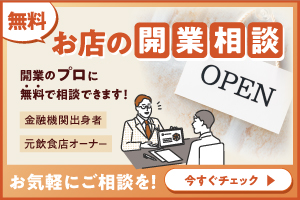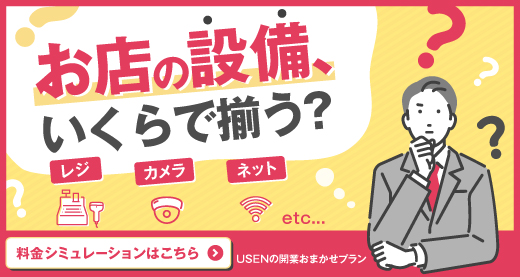更新日:
副業で個人事業主とサラリーマンを同時にできる?メリット・デメリットや節税、収入アップの方法も解説
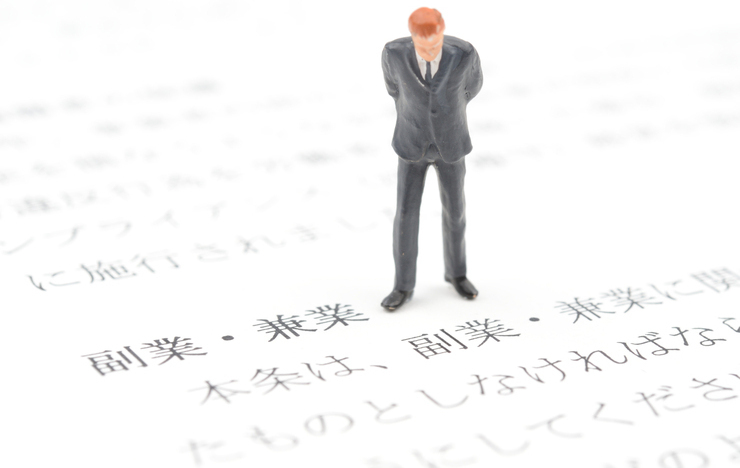
- Tweet
-
サラリーマンとして働きながら、副業を通じて個人事業主としての活動を始めてみませんか?
この記事では、個人事業主としての副業に関する知識を深め、税金や保険の節約方法、収入アップの秘訣をお伝えします。特に、飲食店での開業を考えている方には、独立や起業の準備として役立つ情報が満載です。
青色申告や確定申告、経費の計上など、必要書類の管理方法も詳しく解説します。
また、会社にバレずに副業を続けるためのコツや、社会保険との関係についても触れます。インボイス制度を含めた最新の税制情報を活用し、賢く節税しながら収入を増やす方法を学びましょう。この記事を通じて、個人事業主としての副業がどのようにあなたの将来に役立つかを考え、実際に行動に移すきっかけにしてみてください。
目次
サラリーマンの個人事業主副業とは?
サラリーマンとして働きながら、個人事業主として副業を始めることは多くの人にとって魅力的な選択肢です。個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を行う形態を指します。
サラリーマンが副業として個人事業主を選ぶ理由は、収入源の多様化やスキルの活用、さらには将来的な独立や起業の準備としてのメリットがあるためです。
また、副業を通じて得られる事業所得は、その事業に必要な経費を差し引くことで、課税対象となる所得を減らすことができ、所得税の節税にもつながる可能性があります。
詳細は以下のリンクをご参照ください。
No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) - 国税庁給与所得と事業所得の両立
給与所得と事業所得を両立させることにより、税務上のメリットを享受することができます。
給与所得者が事業所得を得ることで、経費を計上しやすくなり、青色申告を行うことで最大65万円の特別控除を受けることができます。また、事業所得が赤字の場合でも、損益通算により本業の給与所得と相殺できるため、税負担を軽減することが可能です。
この制度についての詳細は、以下のリンクをご参照ください。
No.2250 損益通算 - 国税庁
事業所得を得ることで、所得の多様化が図れ、将来的な独立や起業の基盤を築くことができます。個人事業主の副業と自営業は何が違う?
個人事業主として副業を行う場合と、独立して自営業を営む場合とでは、いくつかの違いがあります。
まず、所得・税務の処理について、個人事業主の副業は、給与所得と事業所得を合わせて確定申告を行う必要があります。一方、自営業は事業所得のみとなり、所得の種類による税務処理の違いが生じます。
次に、経営のリスクについて、個人事業主副業は本業があるため、収入が途絶えるリスクは比較的低いと言えます。しかし、自営業は収入が事業の成否に直結するため、リスクは高くなります。
また、時間や労力の面でも違いがあります。個人事業主副業は、本業と副業の両立が必要となるため、時間管理が重要になります。自営業は事業に専念できる分、自由な時間が増える可能性がありますが、その分責任も大きくなります。個人事業主の副業として認められない場合
個人事業主として副業を行う場合でも、全ての事業が認められるわけではありません。
まず、公務員は、法律で副業が原則禁止されています。ただし、一部例外として、許可を得れば副業が認められる場合があります。
また、会社の就業規則で副業が禁止されている場合は、副業を行うことができません。副業を行う場合は、事前に会社の許可を得る必要があります。
さらに、本業に支障をきたすような副業は、認められない場合があります。例えば、長時間労働や過度な疲労により、本業の業務に集中できない場合は、副業を制限されることがあります。
その他、特定の資格が必要な業務を、資格を持たずに副業として行うことは違法となります。例えば、医師や弁護士などの業務は、資格を持つ者でなければ行うことができません。個人事業主の副業が向いているタイプ
個人事業主として副業を行うのに向いているのは、自分のスキルや専門知識を活かしたいと考える人です。特に、デザイナーや動画編集者といったクリエイター、エンジニアなどが挙げられます。
また、飲食店での勤務経験を持ち、独立を目指す方には、業界の知識を活かして新しいビジネスのアイデアを試す良い機会となります。スキルセット以外では時間管理が得意で、自己管理能力が高い人も適しています。マーケティングや会計の基礎知識も持っていると、事業の運営がスムーズに進むでしょう。人気の副業3選
個人事業主として人気の副業には、フリマアプリやECサイトにおける物販、Webライター、そして動画編集が挙げられます。
ECサイトは、初期投資が少なく、自宅で始められるため、スタートしやすいのが特徴です。
Webライターは、文章力を活かし、自由な時間に働けるのが魅力です。
動画編集はYouTuberなどのインフルエンサーや企業のPR動画の編集業務です。Adobe Premiere Proなどの編集ソフトが必要ですが、高単価案件も多く、副業から本業化する人が多いことが特徴です。
各副業の収入目安や必要な準備については、以下の通りです。
業種 利益の目安
(月あたり)必要な準備 こんな人におすすめ フリマアプリ・ECサイト運営 フリマアプリ:数千〜3万円
自社ECサイト:5万〜20万円
・パソコンや梱包材の準備
・メルカリやBASEなどでショップの開設
・商品の仕入れ
在庫管理や仕入れに抵抗がなく、売るのが好きな人 Webライター 初心者
月1〜3万円
(相場は1文字0.5〜1円)
中級者
(専門性やSEOに強い)
月5〜10万円
・パソコンの準備
・クラウドソーシングサイトへの登録
・基礎的な文章力の習得
・SEO知識などの習得
文章を書くのが得意な人、コツコツ取り組める人 動画編集 初心者
(カット編集中心)
月3〜5万円
中級者
(テロップ・効果音・サムネなど含む)
月5〜15万円
上級者(法人案件や撮影含む)
月20万円以上
・高スペックPCの準備
・編集ソフト
・外付けHDD
・素材
(BGMや効果音など)
・クラウドソーシングサイトへの登録
・編集スキルの習得
クリエイティブな作業が好きで、パソコン操作が得意な人 個人事業主の副業で得られるメリット・デメリット
個人事業主の副業は、収入増加や節税のメリットがありますが、手続きや時間管理、社会保険、税金の負担も考慮が必要です。
この記事では、サラリーマンが副業で所得を増やし、起業準備を進める方法を探ります。経費計上や収入源の確保についても触れますので、参考にしてください。
経費計上で節税できる
副業を行う際、経費を適切に計上することで節税効果を得ることができます。経費とは、事業を行う上で必要な支出のことで、例えば通信費や交通費、事務用品費などが含まれます。これらを正確に記録し、確定申告時に必要書類を提出することで、所得から経費を差し引くことができ、課税対象となる所得を減らすことが可能です。特に青色申告を行うと、さらに特別控除が受けられるため、大きな節税効果が期待できます。
詳細な条件や手続きについては、以下のリンクをご参照ください。
No.2072 青色申告特別控除 - 国税庁
経費計上は、個人事業主としての副業において非常に重要なポイントです。適切に経費を計上することで、所得税の負担を軽減し、より多くの収入を手元に残すことができます。
副業を始める際には、どのような支出が経費として認められるかをしっかりと把握し、日々の記録を怠らないようにしましょう。独立準備と収入源の確保
副業を通じて、独立に向けた準備を進めることができます。副業は、収入源を多様化し、本業以外の収入を得る手段として非常に有効です。これにより、独立後の経済的リスクを軽減し、安定した収入基盤を築くことが可能になります。
また、副業を通じて得たスキルや人脈は、将来的な起業において大きなアドバンテージとなります。
さらに、副業を行うことで市場のニーズを把握し、自身のビジネスアイデアを試すことができます。これにより、独立後の事業計画をより現実的なものにし、成功の可能性を高めることができます。
副業は、単なる収入源としてだけでなく、将来的な独立に向けた準備の一環としても非常に価値があります。
手続きと時間管理の負担
個人事業主として副業を行う際には、さまざまな手続きや時間管理が求められます。開業届の提出や青色申告の申請、確定申告の準備など、必要な手続きは多岐にわたります。これらを怠ると、税金や保険の面で不利益を被る可能性があるため、計画的に進めることが重要です。
また、副業と本業の時間管理も大きな課題です。効率的に時間を使うためには、優先順位を明確にし、スケジュールをしっかりと管理することが求められます。特に、サラリーマンとしての本業を持ちながら副業を行う場合、時間の使い方が収入や事業の成功に直結しますので、計画的な時間管理が欠かせません。
社会保険料と税金の影響
副業を始めると、社会保険料や税金にどのような影響があるかを理解しておくことが重要です。副業による所得が増えると、所得税や住民税が増加する可能性があります。これにより、手取り額が減少することも考えられますので、事前にシミュレーションを行い、対策を練ることが求められます。
また、所得が一定額を超えると、健康保険や厚生年金の保険料も増加することがあります。副業を行う前に、これらの影響をしっかりと理解し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。インボイス制度の導入など、税制の変化にも注意を払い、適切な対応を心掛けましょう。
個人事業主として副業を始める手続きガイド
副業を始める手続きは初めての方には複雑に感じるかもしれませんが、適切に行えば収入を補完し節税も可能です。
開業届や青色申告、屋号の決め方、マイナンバーカードを使った電子申請について解説します。これらを理解すれば、安心して個人事業を始められます。
開業届の書き方と提出のポイント
開業届は、個人事業を始める際に税務署へ提出する必要がある重要な書類です。まず、開業届には氏名、住所、屋号、事業内容、開業日などを記載します。屋号は必ずしも必要ではありませんが、事業の顔となるため、慎重に選びましょう。提出先は管轄の税務署で、開業日から1ヶ月以内に提出することが望ましいです。必要書類を揃え、正確に記入することで、スムーズな開業手続きが可能になります。
開業届の書き方については以下の記事で詳細に説明しています。
開業届に必要なものは?提出するメリットや書き方を解説!青色申告の申請手順と注意点
青色申告は、税制上の優遇を受けられる申告方法で、特に65万円の特別控除が魅力です。申請手順としては、まず「青色申告承認申請書」を開業届と同時に提出することが一般的です。申請書には、事業の概要や会計方法を記載します。注意点としては、会計帳簿を正確に記録し、確定申告時に提出できるようにしておくことが必要です。また、期限内に申請を行わないと青色申告が適用されないため、早めの対応を心掛けましょう。
青色申告承認申請書の書き方や提出方法については以下の記事で詳細に説明しています。
青色申告承認申請書とは?2か月以内に提出しなければならない?書き方や提出期限を解説屋号と事業内容の決め方
屋号は事業のイメージを決定づける重要な要素です。特に飲食店を開業する場合、店舗のコンセプトやターゲット客層に合わせた名前を選ぶと良いでしょう。事業内容については、具体的なサービスや商品の提供内容を明確にすることが大切です。これにより、開業届や青色申告の際にスムーズに手続きが進みます。また、屋号は商標登録も考慮し、他の事業者と重複しないよう注意が必要です。
その他認可の申請
個人事業主として特定の事業を始める場合、事業内容によっては、税務署への開業届だけでなく、その他の認可や許可、届出が必要になる場合があります。これらの手続きを怠ると、法律違反となるだけでなく、事業の継続が困難になる可能性もあります。
例えば、飲食店を経営する場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。また、建設業を営む場合は、建設業法に基づく建設業許可が必要です。中古品を販売する場合は、古物営業法に基づく古物商許可が必要です。有料職業紹介事業を行う場合は、職業安定法に基づく有料職業紹介事業許可が必要です。
これらの認可や許可、届出は、事業の種類や規模、地域によって異なる場合があります。事前に管轄の行政機関に確認し、必要な手続きを行うようにしましょう。手続きには、申請書類の作成や提出、審査、手数料の支払いなどが必要となる場合があります。マイナンバーカードでの電子申請方法
マイナンバーカードを活用することで、開業届や青色申告の申請をオンラインで行うことが可能です。
スマホでマイナンバーカードを読み取ってアプリの指示に従いながら入力するだけなので操作も簡単です。マイナンバーカードを取得したら国税庁のe-Taxサイトにアクセスし、マイナポータルなど必要なアプリをインストールし、アプリの指示にしたがって必要な情報を入力します。最後に、紙の申請と同様に必要書類をデータ形式で提出します。
電子申請のメリットは、手続きが迅速に行えることと、郵送の手間が省ける点です。正確なデータ入力とセキュリティ対策を講じることで、安心して電子申請を進めることができます。
個人事業主が活用できる賢い節税方法
個人事業主が節税を効果的に行うことは、利益を最大化し、将来の独立や起業資金を蓄えるために重要です。
この文章では、個人事業主が利用できる節税方法を解説し、具体的な手法を学ぶことで、所得を守りつつ事業を進めるヒントを提供します。
青色申告特別控除の活用法
青色申告特別控除は、個人事業主が所得税を減らすための強力な手段です。この控除を受けるには、帳簿を正しく記帳し、必要書類を揃えることが求められます。青色申告を行うことで、最大65万円の控除が可能となり、節税効果が高まります。青色申告に伴って複式簿記を導入すると控除額が増えるため、事業や店舗を運営する際の経費管理にも役立ちます。
また、青色申告を行うもう一つのメリットとして、損失の繰越控除が可能となります。赤字が発生した年の損失を翌年以降に繰り越して税金を軽減することができます。このように、青色申告特別控除を活用することで、個人事業主としての税負担を大幅に減らすことができ、経営の安定化に寄与します。
経費計上できる項目一覧
個人事業主が経費として計上できる項目は多岐にわたります。代表的なものとしては、事業に直接関連する仕入れ費、広告宣伝費、通信費、そして水道光熱費などがあります。これらは、事業運営に必要不可欠なものであり、適切に計上することで、所得税の負担を軽減することができます。
さらに、飲食店を経営する場合には、食材の仕入れや店舗の賃借料、従業員の給与も経費として認められます。これに加えて、事業に関連する交通費や、業務上必要な保険料も経費に含めることが可能です。これらの項目を正確に把握し、確定申告時に適切に計上することが、節税の鍵となります。
損益通算と繰越控除の使い方
損益通算とは、複数の所得区分で発生した損失を他の所得と相殺することで、税負担を軽減する方法です。例えば、事業所得で赤字が出た場合、その損失を給与所得などと相殺することで、課税所得を減らすことが可能です。これにより、所得税の負担を軽減し、経営の安定化に役立ちます。
また、繰越控除は、赤字が発生した年の損失を翌年以降に繰り越して控除する制度です。最大3年間の繰り越しが可能で、翌年の黒字と相殺することで、税金の支払いを抑えることができます。これらの制度を活用することで、個人事業主としての経営をより安定させることができ、長期的な事業の成功につなげることができます。
会社にバレずに副業を続けるコツ
個人事業主として副業を始めたいけれど、会社にバレるのが怖いという方も多いのではないでしょうか。この見出しは、サラリーマンが副業を行う際に会社にバレないための具体的なコツを紹介します。会社の規則や税金の管理方法をしっかりと把握し、安心して副業を続けるための知識を得ることができます。
就業規則と副業規定を確認する
副業を始める前に、まずは自分の会社の就業規則や副業規定を確認することが重要です。就業規則は、会社が社員に対して求める行動やルールを記載したもので、副業に関する規定も含まれていることが多いです。まず、会社のイントラネットや総務部に問い合わせて、最新の就業規則を入手しましょう。
就業規則の中で注目すべきは、副業禁止規定や副業の許可条件です。これらの内容を理解することで、会社にバレずに副業を行うための第一歩を踏み出せます。副業が許可されている場合でも、事前に申請が必要なケースがあるため、必要書類の準備も忘れずに行いましょう。
確定申告時の情報管理術
副業を行う際、確定申告は避けて通れない手続きです。情報管理をしっかりと行うことで、スムーズに確定申告を進めることができます。まず、収入や経費に関する領収書や請求書は、月ごとにファイルやデジタルデータとして整理しておくと良いでしょう。
また、青色申告を行う場合は、複式簿記の記帳が求められます。これにより、最大65万円の控除を受けることができ、節税につながります。クラウド会計ソフトを利用すると、所得や経費の管理が簡単になり、税金の計算も自動化されるのでおすすめです。
副業禁止規定への対応策
副業禁止規定がある場合でも、完全に副業が不可能というわけではありません。まずは、会社の人事担当者に相談し、特定の条件下での副業が可能かどうか確認してみましょう。場合によっては、許可を得られることもあります。
また、おすすめはしませんが会社にバレないようにするためには、報酬の受け取り方法にも工夫が必要です。例えば、個人名義ではなく屋号を利用して報酬を受け取ることで、会社に知られるリスクを軽減できます。さらに、インボイス制度を利用して、取引先と正式な契約を結ぶことで、信頼性を高めることも可能です。
しかし、万が一会社にバレてしまった場合、懲戒処分や信頼関係の悪化といったリスクが伴います。したがって、会社に知らせず副業を行うことは慎重に判断することが重要です。
個人事業主の副業と社会保険の関係
個人事業主として副業を始める際、多くの方が気になるのが社会保険の取り扱いです。特にサラリーマンとして働きながら副業を行う場合、健康保険や厚生年金などの社会保険制度がどのように適用されるのかは重要なポイントです。この見出しは、個人事業主の副業における社会保険の取り扱いについて詳しく説明し、必要書類や手続きの流れを理解することで、安心して副業を進めるための知識を提供します。
健康保険・厚生年金の扱い方
サラリーマンが個人事業主として副業を始めると、健康保険や厚生年金の取り扱いが気になるところです。通常、サラリーマンとしての本業では会社が社会保険に加入しているため、副業を始めてもそのまま会社の健康保険や厚生年金を利用することが一般的です。しかし、所得が増えると保険料が上がる可能性がありますので、給与所得と事業所得の合計に基づいて計算されることを理解しておくことが大切です。
また、個人事業主としての所得が増え、青色申告を行う場合には、確定申告時に所得を正確に申告する必要があります。これにより、税金や社会保険料の計算が適切に行われ、将来的なトラブルを避けることができます。副業を行う際は、保険や年金の仕組みをしっかりと把握しておくことが重要です。
雇用保険の適用条件
副業を行う際の雇用保険についても理解しておく必要があります。通常、雇用保険は雇用契約に基づく働き方に適用されるため、個人事業主としての副業には適用されません。しかし、サラリーマンとしての本業で雇用保険に加入している場合は、そのまま継続されます。副業が本業に影響を与えないよう、就業規則に違反しない範囲で活動することが求められます。
また、起業や独立を考えている場合、雇用保険の失業給付を受けるためには、退職後の手続きが必要です。副業を通じて収入を得ていたとしても、失業給付の対象となるためには、必要書類を揃え、適切な申請を行うことが重要です。インボイス制度の導入も視野に入れ、事業収入の管理をしっかりと行いましょう。
サラリーマン×個人事業主を成功させる秘訣
サラリーマンとしての本業を持ちながら、個人事業主として副業を成功させることは、多くの人にとって夢のような話です。しかし、実際には時間管理や労力のバランスを取ることが重要です。この見出しは、サラリーマンが個人事業主として副業を成功させるための秘訣を紹介します。効果的な時間の使い方や、健康管理を通じて長期的に持続可能な働き方を実現する方法を詳しく解説します。
時間の優先順位付け術
時間の優先順位付けは、サラリーマンと個人事業主の両立において重要なスキルです。まず、自分の1日のスケジュールを見直し、重要なタスクに優先順位を付けることから始めましょう。タスクを「緊急かつ重要」「重要だが緊急ではない」「緊急だが重要ではない」「緊急でも重要でもない」の4つに分類する方法が効果的です。
また、時間を効率的に使うためには、集中力を高める環境作りも大切です。例えば、スマートフォンの通知をオフにする、静かな場所で作業するなどの工夫を取り入れましょう。これにより、限られた時間を最大限に活用することが可能になります。
本業と副業の両立テクニック
本業と副業を両立させるためには、計画的なスケジュール管理が不可欠です。まずは、週単位での目標設定を行い、それに基づいて毎日のタスクを設定することがポイントです。これにより、無理なく効率的に作業を進めることができます。
また、タスクを細分化して小さな目標を達成することで、達成感を得ながらモチベーションを維持することができます。さらに、オンラインツールを活用してタスクを管理することで、進捗状況を常に把握しやすくなります。このようなテクニックを活用することで、サラリーマンとしての本業と個人事業主としての副業をうまく両立させることができます。
健康管理の方法
副業を行う上で健康管理は非常に重要です。長時間労働にならないようにタスク管理をすることはもちろんですが、定期的な運動を取り入れることで、体力を維持し、ストレスを軽減することができます。例えば、週に数回、30分程度のウォーキングやストレッチを行う習慣をつけると良いでしょう。
また、食生活の改善も健康管理には欠かせません。バランスの取れた食事を心掛け、特にビタミンやミネラルを豊富に含む食品を積極的に摂取しましょう。さらに、十分な睡眠を確保することも重要です。これにより、日々のパフォーマンスを最大限に引き出し、副業を長期的に続けるための基盤を築くことができます。
よくある質問と回答
この見出しは、副業を考えている方々が抱えるよくある疑問について、具体的な回答を提供します。特に、サラリーマンとして働きながら副業を始めたいと考えている方にとって、収入の制限や税金、必要書類などの情報は重要です。疑問を解消し、安心して副業に取り組むための知識を得ることができるでしょう。
副業の収入制限について
副業を行う際に気になるのは、収入に関する制限です。サラリーマンが副業をする場合、まず確認すべきは会社の就業規則における副業規定です。多くの企業では、副業が許可されているかどうか、収入の上限が設定されているかが異なります。法律上は、年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
また、個人事業主として副業を行う場合、青色申告を活用することで、最大65万円の特別控除を受けられます。これは、節税効果を高めるための重要なポイントです。副業収入が一定額を超えると、健康保険や厚生年金の保険料負担が増える可能性もあるため、収入管理は慎重に行いましょう。副業で得た収入を効率よく管理し、税金や保険料の負担を最小限に抑えることが、成功の鍵となります。
インボイスへの対応
個人事業主として副業を行う場合、インボイス制度への対応は、取引先との関係や売上高によって異なります。
課税事業者の場合、インボイス(適格請求書)の発行事業者として登録する必要があります。登録することで、取引先(主に課税事業者)は仕入税額控除を受けることができ、取引を継続してもらえる可能性が高まります。
一方、免税事業者の場合、インボイスを発行することはできません。しかし、免税事業者のままでいると、取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引を敬遠される可能性があります。
副業の売上高や取引先の状況を考慮し、インボイス発行事業者として登録するかどうかを検討する必要があります。登録しない場合は、取引先との関係を維持するために、価格交渉や他の対策を講じる必要があるかもしれません。開業に関するお悩みは「canaeru」にご相談ください
副業で飲食店の開業を考えているけれど、何から始めればいいのかわからない。そんなお悩みを抱える方におすすめなのが「canaeru」です。「canaeru」は、開業を目指す個人事業主や起業家のためのサポートサイトで、特に飲食店の開業に関する情報が豊富に揃っています。起業に必要な知識や手続き、経費の管理、青色申告や確定申告など、具体的なアドバイスを得られるのが魅力です。
また、インボイス制度や所得に関する情報も取り扱っており、税金や保険に関する疑問を解消する手助けをしてくれます。さらに、必要書類の準備や手続きの流れも分かりやすく解説されているため、初めての方でも安心して準備を進めることができます。開業に関するお悩みを抱えている方は、ぜひ「canaeru」を訪れてみてください。あなたの夢を現実にするための一歩を踏み出しましょう。
まとめ
この記事では、サラリーマンが個人事業主として副業を始める際の知識や手続き、節税方法について詳しく解説しました。副業を通じて得られるメリットとしては、経費計上による節税、独立準備の一環としての収入源確保があります。一方で、時間管理や社会保険料、税金の負担などのデメリットも考慮する必要があります。
開業届の提出や青色申告の申請など、具体的な手続きについても触れました。これらの手続きをしっかりと行うことで、節税効果を最大化できます。また、副業を会社にバレずに続けるためのコツや、健康保険や厚生年金の取り扱いについても解説しました。これらの知識を活用し、サラリーマンとしての本業と個人事業主としての副業を両立させることが、成功の鍵となります。
起業を考えている飲食店従事者の方々には、この記事を参考にして、夢の実現に向けた一歩を踏み出していただきたいと思います。具体的な疑問や不安がある方は、「canaeru」に相談することもお勧めです。これを機に、ぜひ自分の可能性を広げてください。
- NEW最新記事
-
-
2025/08/29
-
2025/08/29
-
2025/08/27
-
- 人気記事
-
-
2020/05/20
-
2025/05/19
-
2020/03/24
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
先輩開業者の声

「絶対にやる!」準備期間は20年超。念願の独立開業から3年で…
-
セミナー情報

ロイヤルHD菊地会長は2026年の経済と外食業界をどう見る?…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数13,197件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数60件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数430件
-