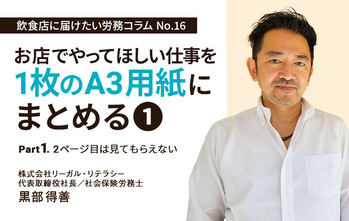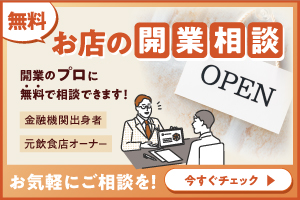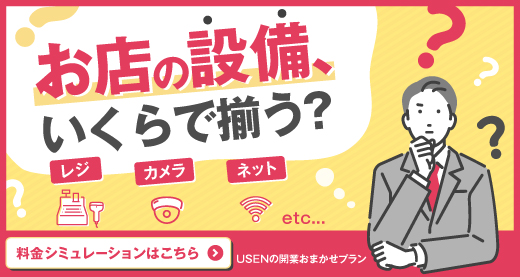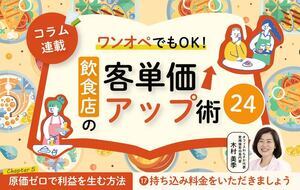更新日:
【連載】飲食店に届けたい労務コラム|第5回 勤怠データは宝の山

- Tweet
-
社会保険労務士で(株)リーガル・リテラシー代表取締役社長の黒部得善氏がお届けする、飲食店経営にフォーカスした労務コラム連載。
スタッフを雇用する店舗経営に欠かせない業務のひとつである労務管理。
特にコロナ禍以降の外食業界は深刻な人材不足に悩まされ、「せっかく採用したのにすぐに辞めてしまう」「そもそも応募が来ない」といった悩みのほかに、アルバイトがSNSを使ったトラブルを起こす事例もたびたび耳にするようになり、安定経営とリスク回避という二つの側面で労務管理の重要性が高まっています。
第5回は、感覚的な労務を脱却するための勤怠データ活用についてお届けします。みなさんのお店には、勤怠システムは導入済みですか?
私は勤怠システムの導入を強く進めています。勤怠データは「何時に出勤/退勤しました」という事実が記録されているデータです。
コロナ以降、出勤頻度が少ないスタッフが増えている中で感覚的なものを可視化してくれる勤怠データは、コミュニケーションのきっかけを与えてくれる情報としても活用できる時代なのです。
勤怠打刻をすることへの大きな誤解
最近では減ってきましたが、「正確に勤怠打刻をすると残業代を払わなくてはならなくなるから打刻をさせていない」という会社も存在します。しかし、これは大きな誤解です。
勤怠打刻がなければむしろ言われっぱなしで支払いをしなくてはならなくなる可能性のほうが高いのです。なぜかと言うと、スタッフから残業代を請求された時にお店側が「彼は残業していない」ということを証明する材料を持っていない、ということになるからです。その請求事実に対して反論する材料がないのです。
また、複数店舗になればスタッフと毎日顔を合わすわけではありません。
シフト通りに働いているだろうと思っていても、人手不足によりずっと休みが取れずに20連勤してしまっていたり、特定の優秀なスタッフにシフトが集中したりと業務の負荷に気づくことができず、いきなり退職されてしまう可能性が高まります。退職で済めばよいですが、それが過労死であったとしたら、会社の過失責任はとても重いものになってしまいます。
一昔前と違い、昨今の勤怠システムはかなり安く手に入ります。この先の人手不足の時代、データを活かしながらお店をよくしていくためには大切な情報です。つまり、勤怠システムのデータは宝の山と言えるのです。
データ化で感覚だけの労務からの脱却を
勤怠システムを使ってデータ化することの最大のメリットは「感覚だけ」からの脱却があげられます。労務という分野はもともと数値化することが難しく感覚に頼る分野でした。感覚だけの労務だと、以下の状況に陥ります。
□店長しかできない業務になってしまう
×店長の経験で処理
×複数店舗の場合、店舗ごとにバラバラな労務
×店長が異動するとすべてリセットされる
□問題の原因がわからない
×指導できない
×ノウハウとして蓄積されない
その結果、「気合と根性で乗り切る」ということにつながっていました。人手不足が進む飲食業において、この先「気合と根性で乗り切る」という解決策に賛同する人は減っていきます。だからこそ、データをよりよいお店作りに活かす必要があるのです。
労務AIでみえたコロナ後の飲食労務
データ活用の一例を紹介します。私は15年以上前から勤怠データを解析するという技術を作ってきました。25万人以上の飲食店で働く人のデータ解析を行った結果、現在は”労務AI“という技術になり飲食店で起きる問題を数値化することに成功しています。その取り組みの中で、特にコロナ前後で大きく変わった事実があります。
2019年の新人アルバイトの週平均シフト日数・・・2.9日
2023年の新人アルバイトの週平均シフト日数・・・2.0日
コロナ後の課題は人手不足、と言われていますが、実態としては一人当たりのシフトに入る回数が少なくなっているのです。そして、週2日のアルバイトを複数個所掛け持ちしているという事実もあります。
一昔前までは「最低でも週3日、週4日入れない人は採用しない」という方針が普通でした。しかし、“ダブルワークはかっこいい”という採用広告とともにシフトに入る回数が減り始めたのです。コロナ前まではギリギリ週3日が平均値でしたが、今は週2日が普通に。
気づけばスタッフの所属人数は多くなっているけど、シフトに入ってもらえない、という状況が生まれていたのです。
データで変化を把握し行動を変える
新人アルバイトのシフト日数が減るということは、当然今まで通りの新人育成と同じではダメです。「1カ月たったのにまだこれだけしかできないの?」と思っても、実際にシフトに入っている回数、一緒に働いている回数、会話をした回数はコロナ前と全く違うのです。
経験と勘だけではわからないことも、データとして見てみると違いが判ります。そしてその違いを現実として受け止めて、今までの経験と勘を活かしてこの先につながる新しい取り組みに挑戦、そして進化していくことが大切なのです。
感覚だと後回しにしていたことも数値化されると目標設定が可能になるので、労務は一気に進化します。
次回は、勤怠データから見えた人手不足についていろいろと考えてみましょう。
今回のキーワード:勤怠データを活用して労務を数値化しよう
- NEW最新記事
-
-
2026/02/02
-
2026/01/19
-
2026/01/05
-
- 人気記事
-
-
2025/04/04
-
2020/02/27
-
2017/12/28
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
先輩開業者の声

「絶対にやる!」準備期間は20年超。念願の独立開業から3年で…
-
セミナー情報

【大阪会場開催】今日からできる!「Googleビジネスプロ…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数12,311件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数57件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数437件
-