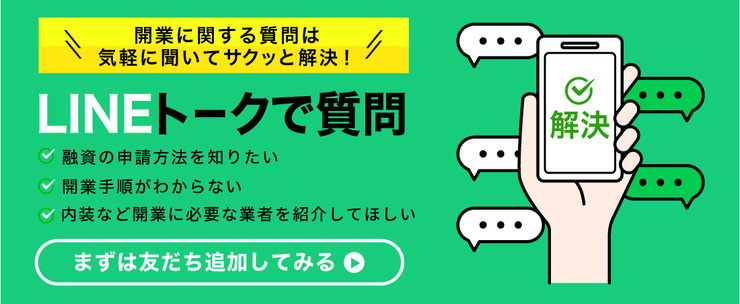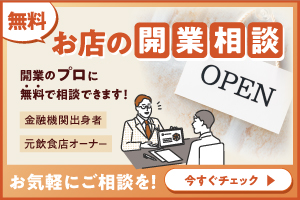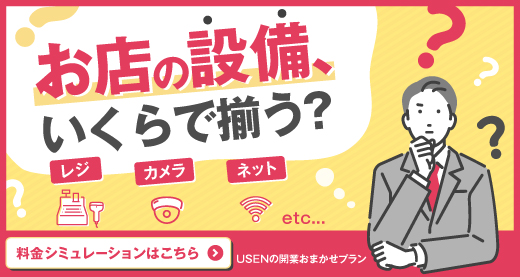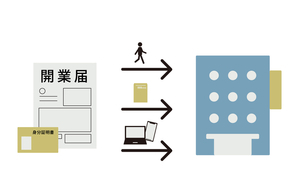更新日:
なぜ飲食店の開業で失敗する?失敗する原因やオーナーの特徴について解説

- Tweet
-
「開店3年目で廃業」というケースが多くみられる飲食業界。中には1年ももたずに閉店してしまった……という例も珍しくありません。
飲食店は特に競争が激しい世界。そこで今回は、「失敗こそ最大の師」という名言にならい、失敗例から飲食店を成功させるコツを学んでいきましょう。目次
なぜ飲食店開業・経営は失敗が多いのか?
中小企業庁による「2024年版小規模企業白書」によると、「宿泊業・飲食サービス業」の廃業率は5.0%と、すべての業種の中で最も廃業率が高い業種であることがわかりました。
全業種の平均が3.3%であることを考えると、飲食店の経営の難しさが浮き彫りになった形といえるでしょう。開業数以上に廃業数が高いのが飲食業界。失敗パターンをもとに廃業しやすい飲食店の特徴をみてみましょう。資金不足
飲食店が閉店に至る原因の一つとして、開業直後に資金がなくなってしまうケースが少なくありません。飲食店経営では、毎月の支払いとしてテナントの家賃や仕入れ代、人件費(アルバイトを雇用している場合)などの固定費がかかります。
また、融資を受けている場合は返済するお金も計算に入れる必要がありますそのため、安定した利益を維持しなければ経営が行き詰まるのは避けられません。資金に苦しむ経営者は、売上の金額にだけ気を取られて経費をしっかり計算できていないことが多いです。マーケティング不足
飲食店が廃業に至る理由の一つに、経営の基本であるマーケティングが不足していることが挙げられます。飲食業界は参入障壁が低い反面、競争が激しく、長く続けるのが難しい業界です。その中を生き抜く上で、もちろん料理の味は重要ですが、それ以上にマーケティングが成功の鍵となります。
例えば、商圏調査をはじめ、開店後は他店との差別化戦略や店舗の認知度を高めるための宣伝方法、さらに回転率を上げるための工夫が求められます。
自分の店に最適なマーケティング戦略をしっかりと見極め、実行に移すことが成功への近道です。人手不足
飲食店の運営において、人件費は大きな割合を占めており、一般的には売上の約30%が適正だと言われています。この点をきちんと把握していないと、必要な従業員数や採用にかかるコストを正確に計算することができません。
さらに、飲食業界は人手が不足しており、その影響で採用コスト自体もかなりかかっております。このため、採算が取れず、閉店に追い込み店舗が増えているのが現状です。
参考記事 人手不足で飲食店が回らない…!原因と解決法について徹底解説そもそも独立・開業・起業の業界に飲食業界が選ばれやすい理由は?
飲食店は身近な存在であるため、自分なりのビジネスモデルを描きやすく、多くの人が参入しやすい業界です。その中で料理の技術だけではなく、「経営者の視点」が圧倒的に不足しているケースが目立ちます。この視点は非常に重要であり、経営知識を学んでいないと、厳しい業界で成功するのは難しいです。
飲食業界で成功するには料理やメニューに対する「商品開発力」が大切ですが、それ以上に顧客へ魅力を伝える「商売力」も必要です。 新しいメニューが完成しても、接客や宣伝が伴っていなければ話題にもなりません。 「このメニューを大いに売りたい!」と思うなら、売る力を身につけるべきです。
参考記事 独立開業ビジネスは3年が勝負…儲けるために知っておきたい基本情報まとめ飲食店開業で失敗しないために抑えておきたいポイント
飲食店において「儲かっている」と感じる基準は経営者ごとに異なるものです。ここでは「全国平均年収所得並みの収入を得て、さらに貯蓄ができる状態」を「儲かっている」と定義し、その実現方法を考えていきます。
一般的に会社員の平均年収所得は約400万円と言われていますが、小規模な飲食店オーナーの多くは、それを下回る所得を想定することが現実的です。もちろん、それ以上の所得がある経営者もいますが、この違いはどこで出てくるのでしょうか。
熟知すべきは「商圏」
飲食業界では、自分がやりたい業態の店が商圏内で他店と重ならないことが理想です。 成功している経営者は、客層や繁盛する時間帯などのデータ収集に長けており、これらをうまく活用して他店と差別化できる独自の商品やサービスを提供しています。
お客様に覚えてもらえる「強み」を持つ
成功している飲食店は、お客様に「あの店に行くなら」と覚えてもらえるような強みを持っています。
例えば、アジアン料理店はよく見かけますが、もしそれが「パクチーをたっぷりしたアジアン料理店」として差別化されていたとしたら…。パクチーは女性に人気が高いため、このアプローチは効果的と言えるでしょう。
つまり、儲かっている店は、個別の強みを具体的に打ち出し、それを武器にしているのです。職人こそ「経営」視点を持つ
「飲食店は味がすべて」と考える職人気質の経営者は多いですが、その中に「経営者」としての視点が欠けている場合も少なくありません。
例えば、「美味しいコーヒー」をアピールするカフェはよく見かけますが、「個室でプライベート空間の予約席がある」というような特徴を打ち出すカフェは少ないものです。
経営者として、味以外にどんな価値を提供できるかを考えることが非常に重要です。
数字を徹底して追う
成功している飲食店ほど、「売上」や「原価」、「客数」などのデータ分析を徹底しています。
例えば、ランチタイムの客の流れに変化があった場合、その背景に「常連のお客様がいる企業が移転した」という予想外の要因が隠れていることもあります。
継続したデータ分析を行っていれば、メニューを調整するなど、迅速な対応が可能です。飲食店経営を成功させるための必要準備
では、飲食店開業から経営までを成功させるためには、どんな準備が必要なのでしょうか。
商圏リサーチをおこなう
飲食店を開業したいという動機はさまざまです。例えば、料理が好きでそれを仕事にしたい、あるいは人とコミュニケーションをとることが好きで、顧客や従業員だけでなく近隣の地域や仕入取引先まで、飲食店を取り巻く環境との結びつきを得たいというものです。
これらの目的や希望を持って飲食店を開業すること自体は悪くありませんが、安易な考えで経営を始めるのは避けるべきです。
お客様のニーズをしっかり把握するためには、やはり商圏リサーチが肝心です。 リサーチの方法は、出店予定のエリアでどのような人が集まり、どんな飲食店があるのか、そして他の店を実際に訪れて、客層や提供されているメニュー、使用されている資料、サービス内容などを調査することが大切です。お店のコンセプトを決定する
先述の商圏リサーチ・市場調査を行うことで、目標とすべきお客様が明確になり、その結果をベースに飲食店のコンセプトを決定します。コンセプトをしっかり決めることで、店舗設計やメニューの種類、従業員の教育に継続的な一貫性を持つことができます。
お客様にとって、一貫性のあるお店は安心感や良い印象を与えやすく、記憶に残りやすいものです。印象に残ることで、また店に行きたいと思わせることができ、リピート客の獲得にも繋がります。
さらに、特定のコンセプトを持ったお店には、熱狂的な固定客が付きやすい傾向もあります。コンセプトを決める際には、特に以下のポイントを現実現することが重要です。
・なぜ飲食店経営を始めるのか
・いつ頃にオープンするのか
・どのエリアでオープンするのか
・誰をターゲットにするのか
・何を提供するのか
とくに、なぜ飲食店経営を始めるのかについては、最も重要なポイントになります。最適な物件を選ぶ
多くのお客様に足を運んでもらうためには、出店場所の立地が非常に重要です。 どれだけ店の雰囲気が良く、魅力的なメニューを提供していても、アクセスが悪い場所に出店すると、集客に苦戦してしまうでしょう。
駅前や繁華街など、人通りの多いエリアは理想的ですが、通常は賃料が高いことが多いため、予算を考慮しながら物件を選ぶことが必要です。
商圏リサーチでどのようなお客様が集まりやすいのかよく理解した上で、物件選びを行うことがポイントです。例えば、駅近のエリアではお酒を提供する事がメインの飲食店へのニーズが高いことがあり、ビジネス街などでは企業で働く人々がターゲットになります。
経営したい店のコンセプトと、エリアのニーズがマッチしていることを確認し、物件選びを進めるために成功への自分の鍵となります。魅力的なメニューを開発する
飲食店の利用目的は様々ですが、やはり「おいしい料理」は必要不可欠です。
そのための魅力的なメニュー開発の方法ですが、例えば、こだわりを持ったメニュー一本で勝負する一つの方法があります。特定のジャンルや独自の料理を深掘りすることで、他店との差別化が図れます。
反対に幅広いニーズに対応できるよう、豊富なメニューを提供するスタイルも繁華街では有効です。顧客の選択肢を増やすことにつながります。
ただし、自店のコンセプトに合致したメニューであることや、メニューを考える際には、味だけでなく「原価」を意識することも重要です。人材確保と育成をおこなう
飲食店を経営し規模を大きくしていく際、人材の採用は重要な要素です。 特に、優秀な人材を見極めて採用することが成功に直結します。
採用時のポイントとして、まず飲食店での勤務経験の前職での勤務期間が長いかどうかも重要ですし、コミュニケーション能力の高さも重要です。ただ技術が優秀なだけではなく、トラブルを起こさない人物であること、短期に辞めてしまう人や実力を鼻にかけてお店に悪影響を及ぼす人など、「採用してはいけない人」の見極めが重要です。
採用後は、責任と権限を与える事で人材育成での成功へつながることも多いです。報奨制度などの従業員の努力が報われるインセンティブ制度を設けることも一つの方法です。失敗する飲食店経営者に共通する特徴とは?
これまで飲食店経営を成功するために求められる考え方についてお伝えをしてきました。この項目では、飲食店経営に失敗してしまう経営者に共通する特徴をまとめていきます。
経営視点が欠如している
料理の腕前や接客スキルばかりに目を向け、収益構造や市場分析などの経営全体を見る視点が欠けている方も少なくありません。感覚や思い込みだけで意思決定せず、客観的なデータに基づいた経営判断が重要となります。
人材管理が不十分
適切な採用基準がなく、従業員の能力や適性を見極められていない経営者も多く見られます。そういった環境では、モチベーション管理や適材適所の配置ができず、離職率が高い傾向に。チームワークも醸成しづらく、結果として顧客満足度も下がってしまうかもしれません。
マーケティング戦略が不十分
「良い料理を出せば客は来る」という思い込みから脱却できていない経営者は、ターゲット顧客の明確化や競合分析を怠りがちです。SNSやクーポン戦略も場当たり的で一貫性がなく、顧客ニーズの把握もできていません。効果的なプロモーションができなければ、集客に苦戦する悪循環に陥ってしまいます。
資金管理が甘い
開業時の資金計画が甘く、十分な運転資金を確保しないまま開店するケースが少なくありません。日々の仕入れコスト管理や人件費の適正化もできておらず、収支バランスが崩れがちです。突発的な設備故障や客数減少にも対応できる資金的余裕がなく、開業後1年以内に資金ショートしてしまう店舗が多いのが現状です。
柔軟性がない
市場環境やトレンドの変化に対応できない経営者は失敗しやすいといえます。自分の理想やこだわりを優先するあまり、顧客からのフィードバックを受け入れられず、メニューや営業形態の見直しができません。コロナ禍でも柔軟に業態転換できた店舗が生き残る中、変化を拒む姿勢は致命的な弱点となります。
自分ひとりで全てをこなそうとする
小規模な飲食店では、特に経営者が多くの業務を自分一人で行おうとする傾向があります。その結果、経営者としての視点を見失ったり、忙しさからお店を継続する体力や気力を失ったりすることも多いです。
コミュニケーションが不足している
スタッフとの日常的な対話や情報共有を軽視する経営者の店舗では、現場の問題点や改善案が経営に反映されません。また、顧客の声も吸い上げられず、サービス改善の機会を逃してしまうことも。コミュニケーション不足はチーム内の連携も悪化させ、顧客に対する一貫したサービス提供を困難にしています。
従業員教育における「怒る」と「叱る」の違いを理解していない
感情的に怒りをぶつけるだけの指導では、スタッフの成長は望めません。「怒る」ことでスタッフは萎縮し、創意工夫や主体性が失われます。一方、「叱る」とは目標や理想を示した上で、改善点を具体的に伝えること。この違いを理解せず感情任せの指導を行う経営者の店舗では、人材が育たず長期的な発展が見込めないのです。
関連記事 起業の成功率は80%!失敗する理由と成功の秘訣失敗する飲食店の共通点
あるデータによると、利益を出している飲食店は全体の3割程度。つまり、飲食店の7割が赤字だというのです。こうした赤字店にはある共通点がみられるのです。
リピート率・回転率が低い
飲食店の経営において、リピート率と回転率は非常に重要な指標です。
開店当初、珍しさから足を運んでくれるお客様も、その後リピートしなくなったり、回転率が低くてなかなか新しいお客様を迎えられなかったりすることはよくあります。リピート率が低い飲食店には、以下のような原因が考えられます。
印象に残らない:食事が美味しくなかったり、接客が淡泊だったりして、特に印象に残らなかった場合、顧客は再訪問を検討しない事が多いです。
料理やサービスの品質が安定してない:何度行っても料理やサービスの品質が安定しないことは、再訪問の動機が生まれません。どんな時でも期待通りの体験ができることが大切です。
メニューが無造作に多い
売上が減少している場合、つい料理メニューを増やしてみようとする経営者がいますが、この戦略には危険が伴います。
メニューが増えれば、それに伴って必要となる食材や作業工程が増加します。特に異なる料理に使用する食材が重複しない場合、必要な量を調達しても使い切れずに食材が残ってしまう場合があります。 これが食材のロスとなり、無駄に廃棄されることになります。飲食店の開業に失敗した場合のその後は
もし、飲食店の開業や経営に失敗した場合、その後の生活はどうなるのでしょうか?以下で一般的な選択肢を3つ解説します。
事業の再構築
メニューや店内装飾の見直し、ターゲット顧客の再検討などを行い、同じ場所で新たなコンセプトとして再出発します。地域のニーズや市場調査を徹底し、失敗した要因を明確にした上で改善策を講じます。成功するには適切な資金計画と実行力が必要です。
店舗売却または譲渡
投資した設備や立地を生かすため、店舗を他の経営者に売却・譲渡する方法です。後継者が見つかれば、一部の投資を回収できる可能性があります。店舗の評価や顧客データベースなど、無形資産も含めた価値を適切に査定することが重要です。
完全撤退と再就職
累積した負債や精神的な負担を考慮し、飲食業界から完全に撤退する選択です。これまでの経験を活かして関連業界に再就職するか、全く新しい分野にチャレンジします。重要なのは失敗を教訓として受け止め、次のステップに活かすことです。
「料理がおいしいこと」と「売上」は比例しない
ここまで読んで、気づいた人は気づいたと思いますが、飲食店経営の失敗談に、「料理」についての話は出てきません。飲食店経営が失敗するのに、提供する料理はほぼ関係ないのです。
「あのラーメン屋、おいしくないから潰れた…」「あの焼肉屋は、肉が安っぽかったから潰れた」というような噂話、よく聞きますよね。しかし、飲食店はおいしくないから潰れるのではなく、経営者が「経営」をできないから潰れるのです。
これから飲食店を開業するならば、「料理」ではなく「経営」を学ぶべきなのでは、先人を見ても明確と言えるでしょう。
関連記事 カフェ開業で失敗する原因!成功するための準備やリスクを回避する方法を解説この記事の監修

USEN開業プランナー
加納健雄
株式会社USEN 開業サポートチームに所属。銀行で融資審査を担当していたキャリアを生かした事業計画書の作成サポートが強み。そのほかにも開業や経営の資金計画の立て方に関するアドバイスを行っている。
【主なサポート内容】
・開業資金にまつわる相談受付
・事業計画書の作成サポート
・資金調達時の面談アドバイス
株式会社USEN/canaeru 開業プランナーの詳細はこちら- NEW最新記事
-
-
2025/08/29
-
2025/07/17
-
2025/07/17
-
- 人気記事
-
-
2023/10/02
-
2020/06/30
-
2021/06/29
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
先輩開業者の声

「絶対にやる!」準備期間は20年超。念願の独立開業から3年で…
-
セミナー情報

【飲食店開業資金】不動産担保ローンによる資金調達と融資成功の…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数12,352件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数57件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数452件
-