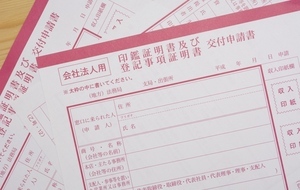全国・海外から約1,500社が参加する「ワクワク系マーケティング実践会」を主宰する小阪裕司が商売成功のヒントを毎週お届けします。
スーパーの定休日を週休3日にした理由
昨年末、ワクワク系マーケティング実践会(このコラムでお伝えしている商売の理論と実践手法を実践する企業とビジネスパーソンの会)会員の食品スーパーから、驚くべき報告が届いた。この報告が大変示唆に富んでおり、今日のお客さんが何を望んでいるかがよく分かる事例ゆえ、年始に早速分かち合いたいと思う。
同店は地方の人口減少が著しい地域にある50坪ほどの小さなスーパーだ。その店がこの10年余り過去最高の売上・利益を更新し続けているのだから、それだけでも驚くべきことなのだが、今回の報告は年間の総営業時間についてだった。
2011年以前には年中無休だった同店。その頃は、1日の営業時間も12・5時間だったという。それが2011年に月1回の定休日を設け、1日の営業時間も11時間と少し短くし、その後も徐々に店休日を増やし、営業時間も短くしてきた。2022年には完全週休2日を実現。そしてついに昨年、同店は週休3日となり、1日の営業時間は8時間に。2011年と比較すると、年間の総営業時間は約33%になるだろうというのである。
もう一度言うが、それでいて同店の売上・利益は2011年の頃より良く、過去最高なのだ。しかも同店の業種は食品スーパー。立地と営業時間で売上・利益が左右されるとされている業種だが、その常識を根底から覆している。また、近隣の人たちが買い物難民になって同店に来店が集中しているのでもない。同店から車で4分のところに、同店の10倍規模のスーパーはあるのだ。
もっとも、同店の営業時間短縮の経緯は、それ自体が目的だったのではない。店主は言う。「お客さん、スタッフ、取引先(生産者)にフォーカスして、みんなからもっと喜んでもらうには何が必要か?と考え続けて、それを実践するには営業時間を減らす必要があったからです」。
お客さんにもっと喜んでもらうには準備の時間も必要
ここがカギだ。先ほども言ったように、近くに10倍の規模のスーパーがある以上、近隣の人々は食品の買い物には困らない。これはおよその地域に言えることだと思うが、ネット通販もある現代のお客さんは、単に「モノ」を買うのに困ることはないのだ。では、同店がお客さんに提供できているものは何だろうか。
ちなみに同店、現在は週休3日だが、3日間みんなで休んでいるわけではない。休息を取っているのは1日だけで、2日間は出社し、その後の4日間のための準備をしている。そこでは何が行われているのか。それが「もっと喜んでもらう」こととどうつながるのか。この続きは次回に。