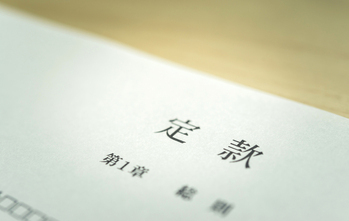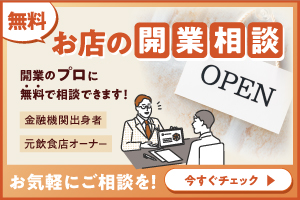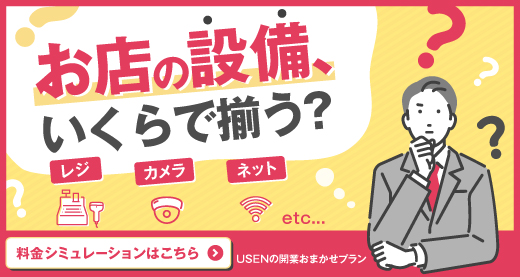更新日:
【連載】飲食店に届けたい労務コラム|第1回 飲食店では“仕事ができる”と“仕事をやっている”はちがう。

- Tweet
-
社会保険労務士で(株)リーガル・リテラシー代表取締役社長の黒部得善氏による、労務コラムの連載がスタート!
スタッフを雇用する店舗経営に欠かせない業務のひとつである労務管理。
特にコロナ禍以降の外食業界は深刻な人材不足に悩まされ、「せっかく採用したのにすぐに辞めてしまう」「そもそも応募が来ない」といった悩みのほかに、アルバイトがSNSを使ったトラブルを起こす事例もたびたび耳にするようになり、安定経営とリスク回避という二つの側面で労務管理の重要性が高まっています。
本連載では、社会保険労務士の黒部氏が考える、飲食店経営にフォーカスした労務のポイントについてお届けします。はじめに
飲食店の労務について、1年間の予定で連載をさせていただきます。社会保険労務士で㈱リーガル・リテラシーの代表を務めている黒部得善です。
飲食業界は未曽有の人手不足と言われていますが、人が辞めすぎなのも事実です。飲食店は人がいなくてはシャッタ-を開けることはできません。人がすべてです。しかし、一方で、お店にダメージを与える問題を起こすのも人です。身内であるはずのスタッフが起こしてしまうバイトテロや、パワハラをはじめとしたハラスメントが起こりやすい職場だというイメージを拭いきれない飲食店。これらの問題は、すべて労務で解決することができます。
「労務は難しい」「労務は面倒くさい」と言われていますが、労務は日々皆さんのお店で常に実行していることです。労務の運用という視点を身に付けるだけで、お店の多くの問題を解決できます。
労務の大前提
私は、労務を一言で表現しろと言われたら、
「①会社が指揮命令する権利を買い、②対価として給与を払う」
と答えます。
まず①の会社が指揮命令する権利を買うというのがどういう意味なのか、新人スタッフの入社初日を想像してみましょう。
店長:「契約も済んだから、今日から君はうちのお店のスタッフだね。頑張ってください」
新人:「はい、じゃあ今から仕事がんばってきます」と勝手に仕事を始める…
などというシーンはありませんよね。
最初に店長から何らかの具体的指示があり、それをスタッフが実行する、というのが一般的な流れです。
飲食店においては「やってほしい仕事があるから人を雇う」のです。会社や上司からの指揮命令(指示命令)があってはじめて仕事がはじまるのです。そして、仕事をしてもらうのであれば当然に給料を支払わなくてはなりません。給料とは②仕事の対価として支払われるものです。飲食未経験の18歳に時給5,000円と言ったら、何となく高く感じると思います。
また、飲食経験30年の料理人に時給1,000円と言ったら安く感じると思います。それはどちらも見合っていない給与だからです。やってもらう仕事に見合った給与を支払う、ということです。この例からもお分かりの通り、皆さんはあたりまえに労務を行っているのです。それくらい、飲食店にとっては空気のように労務を行っているのです。
飲食店は、なぜ人を雇うのか
飲食店では人がいなくては何もできない、と冒頭に書きました。それでは、なぜ皆さんは人を雇うのでしょうか? あたりまえのことですが、「やってほしい仕事があるから」人を雇うのです。そして「やってほしい仕事」をやってくれる人がいないから人手不足だと悩むのです。労務の大前提にあてはめるとこんな図式になります。
お店でやってほしい仕事がある(指揮命令する)
↓
できなければ教えてできるようにする(教育)
↓
できるようになったら見合った給与を払う(対価としての給与=評価)
誰かが指揮命令しなくては何も動き始めないのが飲食店の仕事。その指揮命令を会社(法人)が行うというよりも、お店の店長が行います。みんな好き勝手やりたいように仕事をしていくというのではなく、お店のコンセプトに合った仕事をしてもらう、ということにつながります。指揮命令という難しい言葉を使いましたが、これこそコミュニケーションの量です。「3卓バッシングしてきてください」「そこのお皿を取ってください」のように、人と人の大量のコミュニケーションによってお店は回っているのです。
“できる人”が欲しいけど
やってほしい仕事があって新たに人を採用する時、当然ながら“できる人”がほしい、というのが大半の思いでしょう。では、できる人が採用できたら本当にいいお店になるのでしょうか?できる人がお店にいたとしても、その人にお店がやってほしい仕事をしてもらわない限り、できる人を活かしたことにはなりません。そこには指揮命令が必要になってきます。お店で生かすための能力の見方について混同している飲食店の方が多いので簡単に解説します。
保有能力・・・●●ができる
発揮能力・・・●●をしている
「保有能力」と「発揮能力」のふたつの能力定義の仕方があり、飲食店では「発揮能力」しかお金を生まない、ということを覚えておいてください。
仕事ができる人であっても、指揮命令で具体的にやらせていないとお店の戦力にはなり得ません。極端な話「できるけどやっていない」「できるのにやらせていない」となれば、お店の役には立ちません。きちんとお店のために“やってくれて”はじめてお店の一員になるのです。
そのためには、指揮命令をきちんとして、できなければできるように教えて、そして、成長にともなって見合った給与を支払うという労務のサイクルに乗せていくことが大切です。できるかできないかではなく、やっているかどうか、やらせているかどうかで判断していくことが労務のスタートとなります。
この見方は後々、理念の活かし方や評価の仕方などへと発展していくものになりますが、それはまた後日。
今回のキーワード:きちんとちゃんと指揮命令をしよう
- NEW最新記事
- 人気記事
-
-
2025/04/04
-
2020/02/27
-
2017/12/28
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
先輩開業者の声

「絶対にやる!」準備期間は20年超。念願の独立開業から3年で…
-
セミナー情報

【飲食店開業資金】不動産担保ローンによる資金調達と融資成功の…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数12,401件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数57件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数452件
-