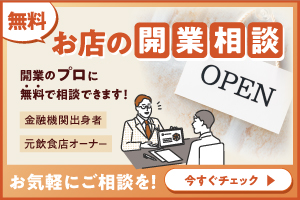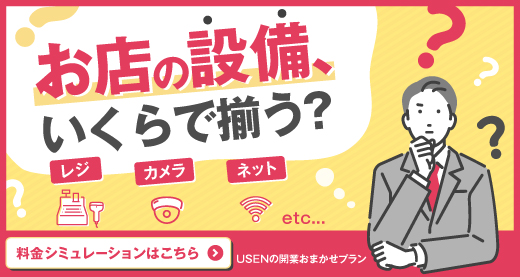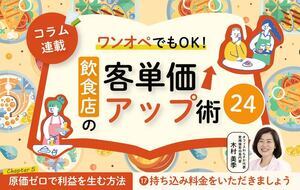更新日:
【連載】飲食店に届けたい労務コラム|第2回 スタッフに法律を守らせようとしても、お店は動かない

- Tweet
-
社会保険労務士で(株)リーガル・リテラシー代表取締役社長の黒部得善氏がお届けする、飲食店経営にフォーカスした労務コラム連載。
スタッフを雇用する店舗経営に欠かせない業務のひとつである労務管理。
特にコロナ禍以降の外食業界は深刻な人材不足に悩まされ、「せっかく採用したのにすぐに辞めてしまう」「そもそも応募が来ない」といった悩みのほかに、アルバイトがSNSを使ったトラブルを起こす事例もたびたび耳にするようになり、安定経営とリスク回避という二つの側面で労務管理の重要性が高まっています。
第2回は、時代の変化に対応した就業規則のあるべき姿をテーマにお届けします。前回、労務とは「会社が指揮命令する権利を買って対価として給与を支払う」という話をしました。今回は、お店のルールと法律についてお話します。
時代は確実に変わっている
私は、飲食労務という分野に20年ほど携わっています。
労務について経営者と話すと、「社員に訴えられたらどうしよう」「監督署ににらまれたくない」など、ネガティブな話ばかり出てきます。たしかに、コンプライアンス意識が高まっている今の時代において「バイトには有給なんてないんだよ」という、昔は何となく通っていた考えもアウトですし、「愛のムチで俺は育ってきたから俺も愛のムチで人を育てる」なんて方針にすると「パワハラ職場だ」と大騒ぎになることでしょう。
そういった時代の変化から、人を使いづらいと感じているオーナーさんや店長さんも多くいらっしゃると思います。実際にそのような相談をいただくことが多いのですが、多くの場合「まずは就業規則を見直しましょう」という話をしています。100社あったら100通りの労務がある
私は常々、「100社あったら100通りの労務がある」と言っています。しかし、多くの経営者は労務を「労働基準法をはじめとした労働法に基づいた就業規則をつくること」だと考えてしまい、結果、労務は楽しくないとネガティブにとらえてしまいます。それはなぜでしょうか。
昨今は、SNSのひろがりや、それによる身内のバイトテロ、さらにはコロナをきっかけとした関係性の希薄化など問題を起こす社員の質も種類も大きく変わってきています。また、社会が規模を問わず会社に求めるコンプライアンス意識も高まっています。そのような背景から、昨今はリスクヘッジを意識してより厳粛な就業規則をつくる傾向が多く見られます。
本章のはじめに述べた通り、私は「100社あったら100通りの労務」があると考えていますが、100社以上の就業規則に目を通しても大同小異。実によく似ています。なぜそうなるのか。1つは就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければならないから、つまり義務として作成しているからです。
もう一つの理由は、問題を起こす社員から会社を守るために就業規則を使おうという考えを持っているからです。もちろん、労使トラブルのリスクを回避するというのは就業規則の大きな役割であり、とても大切な考え方です。
しかし、それだけが突出すると、就業規則はまるで「社員やスタッフは黙っていると、何をしでかすかわからない敵」と言わんばかりの文言が並ぶことになります。結果、「人に期待しない飲食店」へとなっていってしまいます。本当にこれでよいのでしょうか?これで、ちゃんと運用できるのでしょうか?
会社には成長ステージがある。自社の“労務のKKD”を知る
飲食店には成長ステージがあります。人の使い方も成長ステージで変わります。
① 根性(K)!根性(K)!ど根性(D)! →とにかくみんな一丸で!この時期に組織風土“らしさ”ができあがる
② 経験(K)と勘(K)と度胸(D) →なんとなく暗黙知で労務が回り、急成長していく
③ 結果(K)と根拠(K)とDoing(D:実行) →ある程度成長して人が多くなり、振り返り検証しながら労務を行う
みなさんのお店はどのステージでしょうか。それぞれのステージで一番大切なお店の成長にあった労務を行わなければならない中、杓子定規な就業規則だけで労務はできるでしょうか。それぞれのステージで起こりそうな問題に対してどのようにリスクヘッジをしていくか、身の丈に合った労務の運用をしなくてはなりません。逆に言うと、ステージが変わっていてもそれに気づかず、今までと同じやり方で進めていくと会社がトラブルに巻き込まれていく、ということになります。
成長ステージが違うので、創業したての個人店が大企業の労務を参考にするには無理があります。労務に完成形はないのです。
飲食業はちゃんと時代に合わせて進化できています
長く飲食業に携わっている方、ちょっと思い出してください。
10年以上前など月300時間以上労働なんて当たり前でしたが、今はどうでしょう。昔と比べ物にならないほど労働時間は減りました。気が付けば多くの飲食店は時代の空気に合わせて少しずつ進化しています。
誰もトラブルに巻き込まれたくないし、時代に合わせていかなくては人が採用できない、ということも影響していると思われますが、飲食店の労務環境は確実に進化しているのです。この進化の裏には涙ぐましい努力があったことは否定できませんが、飲食店の方々が将来を見越して、人を巻き込んでより良いお店にし、人ときちんと向き合える、対話ができる関係をつくりより良い労務を創っていくという思いがなしえた成果です。
法律を守ることは当然大切ですが「わからないから、とりあえず形だけ守る」という向き合い方だけはせず、ぜひお店の将来につながるように向き合ってください。
今回のキーワード:自社のKKDが今どこなのか知ってから労務を行う
- NEW最新記事
-
-
2026/02/02
-
2026/01/19
-
2026/01/05
-
- 人気記事
-
-
2025/04/04
-
2020/02/27
-
2017/12/28
-
- canaeru編集部おすすめセミナー
- お役立ちコンテンツ
-
-
先輩開業者の声

「絶対にやる!」準備期間は20年超。念願の独立開業から3年で…
-
セミナー情報

【大阪会場開催】今日からできる!「Googleビジネスプロ…
-
セミナー動画

開業までの課題を解決する無料セミナーを動画で配信中!
-
店舗物件検索(首都圏)

ただいまの登録件数12,382件
-
店舗物件検索(大阪)

ただいまの登録件数654件
-
店舗物件検索(北海道)

ただいまの登録件数57件
-
店舗物件検索(東海)

ただいまの登録件数437件
-