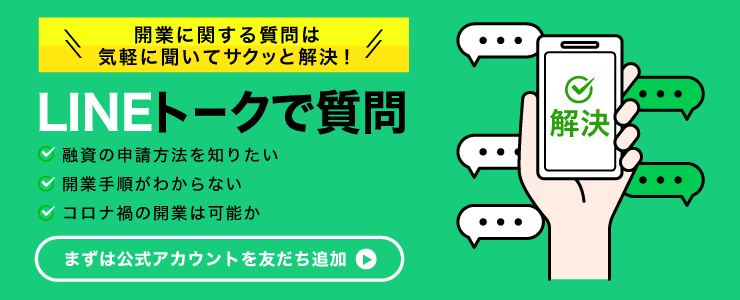開業すると決めたものの、資金の調達方法をどうするかお考えの方は多いのではないでしょうか?
資金調達が上手くいかなければ、その後の動きまで失敗するおそれがあります。良いスタートダッシュを切るためにも、今回は自己資金とその他6つの資金調達方法をご紹介。資金調達にお悩みの方はぜひ参考にしてくださいね!
自己資金はどれくらい貯めれば良い?
開業に充てる自己資金は「○○万円あれば安心!」と明確に決められておらず、多ければ多いほど良いとされています。自己資金が多ければ融資を最低限で済み、融資を受けなければ事業の制約を受けられます。
開業向けの融資制度を利用する場合には、自己資金額の基準が設けられていることもあるのでご注意を。
国の融資制度の一部では、開業資金の10分の1の自己資金が必要です。開業資金が1000万円なら、自己資金は100万円必要になりますね。
これはあくまで基準なので、融資を受けられるようにするには10分の1以上の自己資金を用意しなくてはいけません。
融資の審査において自己資金は開業者の意欲を測るものさしになるため、自己資金が多いほど有利になります。
親族からの援助は含まれる?
親族からの援助は自己資金に含められます。出資と借入という集め方がこれに当たります。
融資を申請する際には、援助の資金は銀行口座に入れましょう。札束での用意では、その出処がわからず不信感を抱かれてしまいます。
出資は贈与税の発生に注意する
出資の場合は贈与にあたります。1年で110万円を超えると贈与税が発生するので、多額の援助は難しくなります。
出資による課税を避けるためには、この金額以下におさめなければなりません。
借入時には契約書の作成と利息の支払いが必要
借入は契約書の作成を経てから行ないます。多額の借入を契約書なしで行なう場合と、利息を払わない場合は、贈与税が発生する可能性があります。
課税を避けるためには返済期間などの条件を契約書に記し、数%程度の利息支払いの履行が求められます。返済できない場合も贈与に当たりますので注意しましょう。
融資の種類も様々!開業の準備資金に活用しましょう
融資は日本政策金融公庫、メガバンク、信用金庫などが主に行なっています。また、自治体による制度融資というシステムも含まれます。
それぞれの融資には担保や保証人が不要であったり、協会による保証書が必要という特徴があります。

日本政策金融公庫の開業向け融資は柔軟に行なっている
日本政策金融公庫は政府が全額出資しており、融資は柔軟に行なっています。
取り扱っているのは「新創業融資制度」や「中小企業経営力強化資金」という開業向けの融資制度です。
新創業融資制度では担保や保証人が原則不要であり、中小企業経営力強化資金では相談の上で決まり、審査から融資までが1ヵ月ほどと短期間です。
中小企業経営力強化資金は金利が1.16〜2.85%と低いものの、融資申請時には経営革新等支援機関から指導を受けるという条件が設けられています。
日本政策金融公庫の審査では、他の金融機関と比べて事業計画の明確さや自己資金の多さがポイントです。
メガバンクは低金利でも審査は厳しい
メガバンクから融資を受けるには、開業したら採算が取れて確実に返済できる価値があると認可されることが必要不可欠。
巨大銀行は資金が豊富なので、2.5%前後ほどの低金利で借りられますが、審査は非常にシビアです。融資の際には事業計画は綿密に立てておきましょう。
信用金庫からの融資は時間的コストがかかる
公的機関の信用保証協会が発行する「信用保証書」によって、信用金庫からの融資を後押しする形になります。
地域に根ざしている信用金庫は、メガバンクと同様に融資を受けることが難しいと言われています。
保証書を発行してもらうには、面接、必要書類や資料を提出するなどの諸手続きの他、提出審査を受ける必要があります。
信用保証協会という第三者が介入するので、融資までの流れは3ヵ月ほどと時間的コストのかかる方法です。
制度融資は各自治体が仲介して融資を行なっている
制度融資とは、地方自治体が指定の金融機関と連携して融資をする仕組みです。こちらも実際の融資までには3ヵ月ほどかかります。
この制度での融資の保証人は「信用保証協会」という機関です。そのため、事業者が返済不可能となった場合には協会が代位弁済します。これにより開業者へのスムーズな融資が可能になるのです。
制度融資は金利が比較的安いという利点がありますが、都道府県または市区町村によって融資条件や融資限度額が異なります。
例を挙げると、東京都の「創業融資」では融資利率は「固定1.9〜2.5%以内(又は変動)」で、神奈川県の「創業支援融資」の融資利率は「年2.0%以内」となっています。
各都道府県や市区町村の制度融資に関する情報はホームページ上で公開されています。実際に目を通して、自分に合う制度を利用しましょう。
また、融資を受けるには、融資をする自治体内に開業をしなければなりません。融資を申し込む前にどのような条件であるか確認することも欠かさないようにしてくださいね。
事業計画をきちんと立てることが大切です
きちんとした事業計画を立てれば、融資や出資の実現性に繋がります。
融資や出資を実現するには、まず綿密に計画の構成を立て、その妥当性を明確に裏付けましょう。

事業のテーマ・必要性・規模を立てる
事業のテーマ、必要性、規模という3つの大原則には、説得力があり明確にすることがポイントです。
事業テーマでは、例えば「○○県の特産品を使用したアンテナレストラン」などと、開業する事業の内容を簡潔に表すことが大切です。
事業の必要性としては、「最近話題の△△や✕✕は、○○県が名産地として全国的に知られており、『○○産』というフレーズにはブランド力がある」などと裏付けします。融資担当者を納得させるために、共働き世帯の増加を表すグラフや、その地域の共働き世帯数を引用するといいでしょう。
事業規模では、「東京に○○産の食材を売りにしている飲食店は□□店存在する」などの具体的な情報を根拠に、顧客を獲得できる確率を算出しましょう。
必ず採算が取れるような具体的な説明を加えて説得力を持たせる
事前に市場調査を行ない、需要の存在を計画書に加えることが必須です。その後から収益予想を細かく展開していきます。
例えば、「客単価○○円を1ヵ月で目指すと、売り上げは△△円になる。売り上げから人件費と仕入れ料を引くと□□円の最終利益が出る」と踏み込んだ予想をしましょう。
収益性の他にも、事業の競合優位性や経営方法、リスクとその対処法、資金計画などを加えると説得力が増します。
計画書を立てる際には、様々なシミュレーションが必要。融資審査の担当者から重箱の隅をつつくような質問をされても対処できますよ。
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。