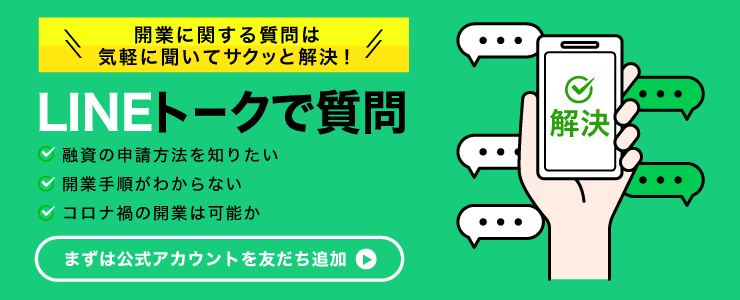黒字(利益は出ている)にも関わらず倒産・廃業してしまうことを「黒字倒産」と言います。
近年、起業した会社やお店の中には、経営者が会計上のお金の流れを理解していないために、黒字倒産を起こす例が増えているのです。黒字なのに組織が倒産してしまうのは疑問に思えますが、お金が流れる仕組みを知っていれば、「なぜ黒字倒産が起こるのか」を理解することができます。せっかく開業したお店を倒さないためにも、お金の流れを知っておきましょう。
まず、黒字倒産が起こる理由を知る
これは会計上の記録ではなく、実際のお金の動きが関係しています。例えば、商品を仕入れる場合、まずそこで支払いのお金が生じます。しかし、その商品を売ったとしてもクレジット決済であった場合は実際の入金は1ヶ月ほど後になります。
このように、実際のお金の入金と出金が一致せず経費の支払いなどで資金繰りが困難になることがあります。
帳簿上と実際のキャッシュフローにズレが生じるため、キャッシュがない会社の場合は、帳簿上黒字でも運営がショートしてしまうのです。
利益を出してはいるものの、キャッシュバランスがマイナスになっている企業には、銀行も運転資金の融資をしませんので、結果としてキャッシュが追いつかず、黒字倒産という現象が起きるのです。
「損益計算書」を理解する
損益計算書上の利益や損失と、実際のお金の動きは、一致しているわけではありません。実際に「お金が入ってきた金額」、「出ていった金額」という収支に注意を払いましょう。
損益計算書において利益が出ていたとしても、実際のお金の流れである収支を正しく管理する為に、キャッシュフロー計算書を作成することがポイントです。この収支を表すキャッシュフローが赤字になっている時は、収入以上に支出してしまっていることを意味しているので、注意が必要になることを、覚えておきましょう。
>>利益と支出を知るために損益計算書を作成!
「貸借対照表」を理解する
事業資金の状態を見るのが、「貸借対照表」です。ここでは、現状の事業資金のうち、自己資本は何パーセントなのか、出資や借入は何パーセントなのかを把握できます。自己資本比率(自己資本÷総資本(自己資本+他人資本))が高いほど倒産の確率は低くなり、負債(他人資本)が少ないと認識する事ができます。飲食店などの個人事業でも、自己資本率が20%以下であればかなり低い状態です。資金もつねにウォッチする必要があります。
>>貸借対照表から資産と負債のバランスを知る!
まとめ:まずは「常時把握しておく」ことが大事
忙しい中で後回しになりがちな帳簿マネジメント。しかし、上場しているような大企業でも、個人商店でも、ビジネスであることに変わりはありません。家計簿のように、「続かない」では済まされないことを、強く意識する必要があるのです。
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。