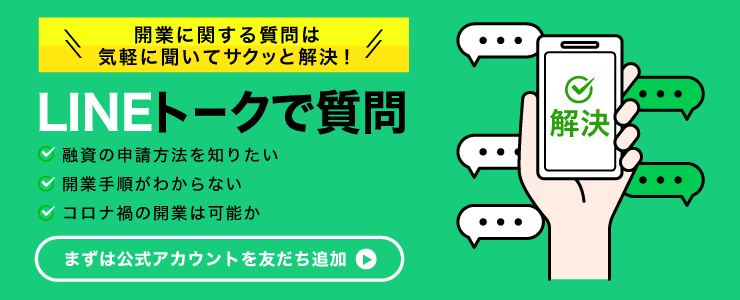会計が合わない、ということは経営に関わる大きな問題です。
なぜ現金は合わなくなるのでしょうか。
その原因から対策を探ります。
目次
意外にもあるのが「着服」
ほとんどのお店では、開店時に一定の金額を入れて、閉店時に清算するという流れをとっています。
そのような流れをとっている際に、会計が合わなくなる理由としては以下の4つが考えられます。
元金の計算ミス
レジ対応のミス
小口現金管理が煩雑
着服
「この店では現金管理はそれほど大切ではない」と思われてはいけない
最も大切なことは経営者の意識であるということを自覚しましょう。
お店のお金とプライベートのお金を混同してしまうなどの姿勢を見せると、それはスタッフに必ず伝わり、現金管理の姿勢に影響します。
「この店では現金管理はそれほど大切ではない」と認識されてしまうのです。
もうひとつ気を付けたいのがスタッフへの不信を態度にあらわすこと。
例えば、あなたが働いていたとして、雇い主から身に覚えのない不正を疑われたらどう感じますか?
現金管理における厳格さは大切ですが、それはあくまで「店の運営上」でのこと。
基本的に、経営者はスタッフを信用するスタンスを崩してはいけません。
また、店長とスタッフの関係が良好なら、小さなミスが発覚してもスタッフはすぐに店長に報告・相談できます。
ところが、小さなミスでもすぐに怒鳴ったりするようでは、委縮してしまい問題が埋もれたまま発覚の遅れに繋がるおそれがあります。
経営者側からスタッフに対して信頼関係を築く姿勢をしっかりと見せることが、健全な現金管理への第一歩だと肝に銘じておきましょう。
現金管理ミスを防ぐ方法4点
店長の意識だけが高くても、現金管理ミスは完全に防げる訳ではありません。
それぞれのパターンに応じて、ミスを防ぐ方法を決めておくことが重要です。
レジ元金の投入ミス
大体のお店では、元金(5万~10万くらいが一般的。必ず毎日同じ金額に統一するようにしましょう)をレジに入れるというシステム。
ここは、複数人でのチェックを入れることが大事。ふたり、3人と、役割の違うスタッフが多重チェックすることにより、入れ間違いを防ぎましょう。
金銭授受の間違い
比較的頻度が高いのが会計時の金銭授受ミス。
特に、ランチタイムなどの忙しい時間帯だと、お札の種類やおつりの金額を間違えやすいです。
ここは、金銭授受フローを策定、徹底教育を施しましょう。
会計が完全に終わるまではお札をレジに入れない。お札の数枚は必ずお客様と確認する、1万円札が入った場合は「1万円札はいりました」と周囲に声がけするなど、「指差し」確認の手順を踏むことが効果を発揮します。
小口現金管理のキモ
例えば、お店の備品などをレジから支払うという対応を繰り返すと、最終的に計算が合わないという事態が発生します。
レジ内のお金の流れを極力単純化することで、清算時に計算が合わない事態を防げます。
備品などの購入費用は別途保管しておき、レジ内の現金と区別しましょう。
スタッフによる着服
実は、意外と珍しくないのがこのケース。
これはスタッフ個人のモラルの問題で、教育で回避することは難しいかもしれません。
そして、こちは立派な犯罪なので、経営者としても厳しい対処を取らざるを得ないのが現状です。
スタッフの採用時に見極める、あるいは、スタッフの普段の働きぶりからレジ係を決めるなどの対策が必要です。
また、時間帯によってレジを扱うスタッフを決める、交代時にはレジ内の現金を確認する、レジの後ろに監視カメラを設置するなど、着服や横領が発生しづらい環境を整えることが重要です。
清算時に現金が合わなかったら?
どれだけ気を付けていても、ヒューマンエラーというのは必ず起こるもの。
飲食店を経営していれば、閉店後の計算時に現金が合わないという事態は必ず起こると考えましょう。
そのようなとき、どう対処すればよいでしょうか?
計算のし直しは、複数人で
1日の仕事を終えてからの計算ですから、単純な計算ミスが予想されます。
しかも、人間は意外と自分のミスには気付かず、同じ人が計算し直すと同じミスを繰り返す恐れがあります。
まずは、別のスタッフに計算し直してもらうなど、ダブルチェックをしてみましょう。
伝票ミスの確認
オーダーの伝票への書き込みミスが考えられます。
実際には売上額は合っているのに、手書きの伝票上で計算が合わない場合に多いパターンです。
伝票を再度見直すと意外とミスが見つかることがあります。
「ミスしたスタッフなどに補填させる」は絶対NG
「雑損」という費目は、お店経営にももちろん必要です。
雑損を皆無で経営することは困難ですから、少額の損失に対して補てんする金額をプールしておきましょう。
そして、絶対にしてはならないは「ミスしたスタッフなどに補填させる」ということ。
実はこれ、個人事業などではやってしまいがちなことなのです。
例えば、スタッフ側から、「自分が間違えたから補てんしておいた」などの報告があっても、必ず正しましょう。
この点を疎かにしていると労働基準法第24条で大きな問題に発展してしまうので注意が必要です。
労働基準法第24条(賃金の支払)
1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
従業員への罰金は法律上禁止
上記のように労働基準法第24条は、スタッフに対して給与の全てを支払うことが義務付けられています。
そのため、ミスしたスタッフに対する罰金で給与の一部から徴収した場合は、労働基準法に違反していることになります。
明らかに抜いていることが発覚した場合でも、後々のトラブルを防止するために、給料の一部から徴収することは避け、すぐに警察に相談しましょう。
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。