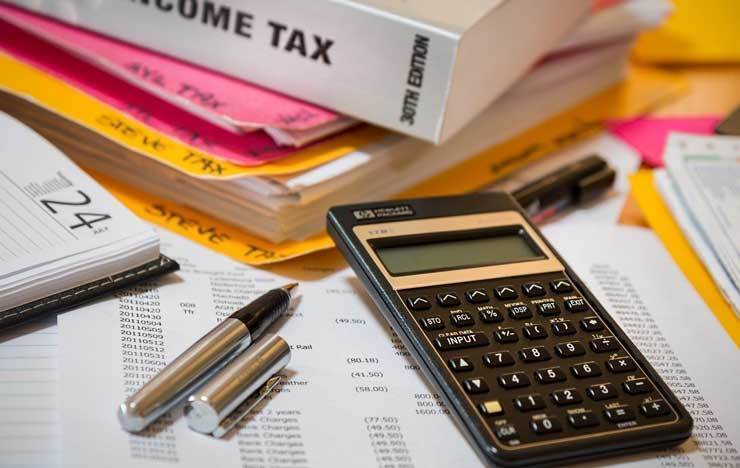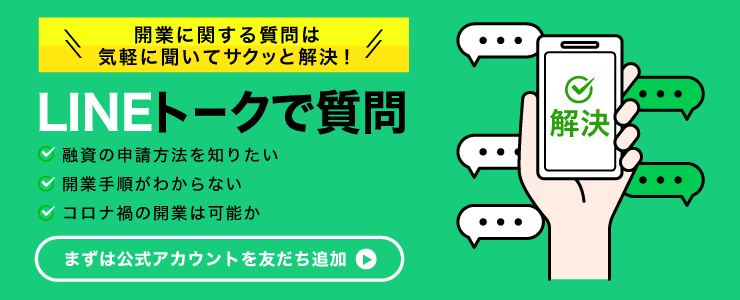一般的に消費税は商品やサービスを購入した時に発生します。そして発生した消費税は消費者から受け取った事業者に納税義務があります。ただし、中には消費税の納付が不要な事業者もいます。そこでどのような個人事業主に消費税の納税義務があるのか、また納める消費税の計算はどのように行うのか、などの基礎的な知識をご紹介。個人事業主の方で消費税を納める必要があるのかわからない方はぜひ参考にしてみてください。
目次
個人事業主が消費税を納める条件
課税売上高が1,000万円を超えると納税義務が発生
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた際には必要な消費税を支払いましょう。
この場合の基準期間とは「2年前」です。2年前(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、その翌々年に消費税を納税しなければなりません。
納税義務は「課税売上高が1,000万円を超えた場合」に発生するため、1,000万円に満たなければ消費税の納税は免除されます。
課税売上高とは、消費税の課税対象となる取引の売上金のこと。土地の売却収入や家賃収入、社会保険診療報酬などを除いてほとんどの取引が課税売上高に該当します。課税売上高は、納税義務や簡易課税の判定材料になるため、日々の収支をチェックし、課税事業者となったときに焦らないよう準備しておくことが大切です。
課税事業者と免税事業者
次に、課税事業者と免税事業者の違いを解説します。
| 課税事業者 | ・基準期間の課税売上高が,000万円以上 ・特定期間(個人事業主は1年前の1~6月)の課税売上高または給与等支払額が1,000万円以上 上記いずれかの条件を満たす |
|---|---|
| 免税事業者 | ・開業1年目 ・基準期間の課税売上高が1,000万円以下 ・特定期間の給与等支払額が1,000万円を超えない 上記いずれかの条件を満たす |
条件に当てはまり「課税事業者」になった場合には、「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出する必要があります。
課税事業者になっても、課税の条件から外れた場合には「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を税務署に提出することで免税事業者になります。
参照 国税庁|消費税の仕組み
要チェック!消費税の計算方法
消費税の計算方法は、「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2つがあります。
元々は原則課税方式のみでしたが、中小企業の納税に関する事務負担軽減を目的として「簡易課税方式」が後から導入されました。事業者はどちらかを選択して消費税額を計算します。
ここからは、2つの計算方法をわかりやすく解説します。
原則課税方式
原則課税方式は、年間を通じて受け取った消費税から仕入などで支払った消費税を差し引いた金額で納付額を算出します。
【原則課税方式の計算方法】
課税売上高にかかる消費税額ー課税仕入高にかかる消費税額=消費税の納付額
軽減税率制度によって、消費税は8%と10%の複数税率となっている点には注意しましょう。消費税額は税率ごとに区分して計算する必要があります。
【原則課税方式のシミュレーション】
※課税売上高1,000万円、課税仕入200万円を想定
※税率10%を想定
100万円ー20万円=80万円
上記の場合、原則課税額は80万円となります。
※中小事業者の税額計算の特例
原則課税方式では、軽減税率制度の導入に伴い消費税額の計算が複雑になっています。中小事業者にとって負担が大きいことを考慮し、売上または仕入の一定割合を軽減税率の対象売上または仕入として税額を計算できる「中小事業者の税率計算の特例」が2019年10月1日〜2023年9月30日までの限定措置として取られています。消費税を税率ごとに区分して計算するのが困難な中小事業者は活用してみましょう。
参照 国税庁|中小事業者の税額計算の特例
簡易課税方式
簡易課税方式は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に選択可能な計算方法です。
仕入などで支払った消費税を「みなし仕入率」で計算できる点、事業区分に応じて「みなし仕入率」が変わる点が特徴です。すべての仕入にかかった消費税を個別に計算する必要がなく、計算を簡素化できます。
【簡易課税方式の計算方法】
課税売上高にかかる消費税額ー課税売上高にかかる消費税額×みなし仕入率=消費税の納付額
【事業区分ごとのみなし仕入率】
- 第1種事業(卸売業)…90%
- 第2種事業(小売業)…80%
- 第3種事業(製造業)農林・漁業、建築業、製造業など…70%
- 第4種事業(その他)飲食店業など…60%
- 第5種事業(サービス業等)運輸・通信、金融・保険業、サービス業…50%
- 第6種事業(不動産業)…40%
【簡易課税方式のシミュレーション】
※売上高1,000万円を想定
※税率10%を想定
※第5種事業を適用
100万円ー(100万円×50%)=50万円
上記の場合、簡易課税額は50万円となります。
参照 国税庁|簡易課税制度
個人事業主に影響大!インボイス制度と消費税の関係

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、適格請求書(インボイス)を使って消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。
適格請求書は、正確な適用税率や消費税額等を伝えるために用いられます。適格請求書として認められるためには、区分記載請求書に対して新たに「適格請求書発行事業者登録番号」「税率ごと(8%または10%)に区分して合計した税込対価の額」「税率ごとに区分した消費税額等」などを記載しなければなりません。
インボイスを交付できるのは、税務署長に申請して登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみです。
参照 国税庁|適格請求書保存方式の概要
インボイス制度と消費税の関係
ここからは、インボイス制度が導入されると「なぜ個人事業主の消費税に影響が出るのか」を解説していきましょう。
インボイス制度が導入された後に事業者が「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」になると、事業者は「課税事業者」となります。課税事業者になると、 1,000万円以下の売上でも納税義務が発生するのです。
これまで支払わなくて済んだ消費税を支払うことになるため、「インボイス発行事業者にならず免税事業者のままでいるほうがよいのでは?」と考えられがちですが、多くの場合、個人事業主にとってデメリットになる可能性があります。
インボイス制度導入以前、発注側は請求書がなくても一定の条件を満たすことで仕入税額控除が受けられました。しかし、導入後は適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」が認められません。
そのため、インボイス発行事業者に登録していない個人事業主との取引は仕入税額を控除できず、発注側は登録していない個人事業主との取引を避けることが予想されます。インボイス発行事業者となった事業主と取引をする方が発注側にとってはメリットがあるのです。
もし、インボイス発行事業者への登録に迷う場合は、現在の取引先にどのような方針か確認してから判断するとよいでしょう。
【一挙紹介】個人事業主に関係する消費税まわりの届け出一覧
個人事業主が消費税関係で届け出が必要な書類は、下記4点です。条件や期日を確認し、該当する場合は速やかに届出を提出しましょう。
| 書類 | 提出タイミング |
|---|---|
| 消費税課税事業者届出書 | 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えることとなったとき速やかに提出 |
| 消費税課税事業者選択(不適用)届出書 | 免税事業者が課税事業者を選択するとき(又は選択を取りやめるとき)課税期間の初日の前日までに提出 |
| 消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書 | 3簡易課税制度を選択するとき(又は選択を取りやめるとき)に課税期間の初日の前日までに提出 |
| 消費税課税期間特例選択・変更(不適用)届出書 | 課税期間の特例を選択又は変更するとき(又は選択を取りやめるとき)に課税期間の初日の前日までに提出 |
「消費税課税事業者選択」「消費税簡易課税制度選択」「消費税課税期間特例選択・変更」の届出書を提出した場合は、原則2年間選択を取り下げられません。届出を提出する場合は2年後までのことを考慮しておきましょう。
参照 国税庁|消費税の仕組み
各届出書類のフォーマット(雛形)はこちら
消費税課税事業者届出書
消費税課税事業者選択(不適用)届出書
消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書
消費税課税期間特例選択・変更(不適用)届出書
【Q&A】個人事業主の消費税に関する細かい疑問に回答

免税事業者でも消費税を請求できる?
免税事業者であっても、消費税の請求は可能です。免税事業者が請求する消費税は「益税」とも言われており、純粋に売上の一部、利益となります。
消費税法に「免税事業者が消費税を請求できない」との記載はなく、国税庁からも請求を不可とする通達は今のところ出されていません。
しかし、消費税を請求する場合は、消費税の区分を明確にしなければならない点に注意が必要です。2019年10月に「区分記載請求書保存方式」が導入されているため、請求書では税率8%の品目と税率10%の品目を分けて記載しましょう。
受け取った消費税は売上高として処理して問題ありません。
消費税が支払えない場合はどうなる?
納付期限を超えても消費税が支払えない場合は、延滞税が課されます。延滞税の期間と税率は下記表のとおりです。
| 期間 | 延滞税率 |
|---|---|
| 納付期限の翌日から2か月が経過するまで | 年7.3% |
| 2か月以降 | 年14.6% |
期限から2か月を超えても納付をしなければ、延滞税率が14.6%まで上がります。加えて、意図的に支払いを避け続けた場合には、重加算税の課税対象となる可能性がある点には留意しておきましょう。
新型コロナウイルス感染症の影響など、特別な事情がある場合には「納税猶予」が適用されます。国税庁のホームページを参考に、要件などを確認しておきましょう。
参照 国税庁|新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
消費税の支払いは経費になる?
消費税の支払いは経費として計上できます。処理方法は「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つですが、経費とできるのは税込経理方式での処理の場合です。
【消費税の処理方法】
- 税込処理方式:
租税公課として計上、取引の総額で処理 - 税抜処理方式:
仮受消費税と仮払消費税を相殺して処理。差額は未払消費税または見収消費税として処理
消費税を経費として計上したい場合には、税込経理方式を選ぶようにしましょう。
簡易課税と原則課税はどちらを選択するべき?
簡易課税と原則課税のどちらを選択すべきかは、一概に結論は出せません。
仕入れ額によっても消費税額が変わってくるため、実際にシミュレーションをしてお得な方法に決めるとよいでしょう。もし計算が面倒な場合は、処理方法が簡単な簡易課税を選ぶと事務作業がスムーズに進みます。
消費税の納付時期、納付方法は?
個人事業主は、確定申告で消費税納税額の申請と納付を行います。確定申告の時期は、毎年2月16日〜3月15日にかけてです。
確定申告に加えて、直前の課税期間の消費税額が48万円を超える事業者は中間申告・納付が必要です。中間申告・納付の回数は、直前の課税期間の消費税額によって異なります。
【直前の課税期間の消費税額|中間申告・納付回数】
- 48万円超400万円以下|年1回(直前の課税期間の消費税の2分の1)
- 400万円以上4,800万円以下|年3回(直前の課税期間の消費税の4分の1ずつ)
- 4,800万円超|年11回(直前の課税期間の消費税の12分の1ずつ)
中間報告・納付に該当しない個人事業主であっても、事前に「任意の中間報告書を提出する旨の届出書」を提出した場合、自主的に年1回の中間申告・納付が可能です。
消費税の納付方法は、下記のとおりです。
- 電子納税(e-Tax)
- 振替納税
- クレジットカード納付
- コンビニ納付
- 窓口納付
e-Taxによる電子納税やクレジットカード納付であれば比較的手間なく納付できるため、おすすめの方法です。ただし、クレジットカード納付は決済手数料がかかるため注意しましょう。
正しい知識を身につけて消費税の納付に備えましょう
事業者が消費者から受け取る消費税はあくまで預かっているお金です。基準期間、特定期間のどちらかで売上高が1,000万円を超えたら課税事業者としてしっかりと消費税を納税しましょう。消費税の納税額の計算は簡易課税方式の方が簡単ですが、還付を受けるには原則課税方式での計算が必要なことも。個人事業主に関する消費税の基礎知識を把握して、消費税の納税で損をしないで済むように気をつけましょう。
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。