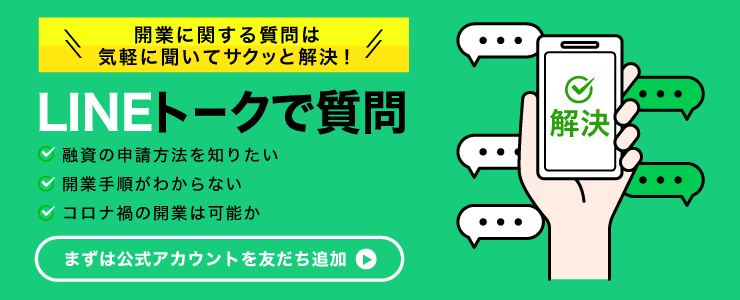新型コロナウィルスの感染拡大防止のための外出自粛要請により、飲食店におけるテイクアウトの業態は急激に浸透しました。
緊急事態宣言の延長や複数人での会食の制限などによって厳しい営業を強いられている飲食店にとって、テイクアウトを行うことはもはや必須と言ってもよいかもしれません。
しかし、もともと「テイクアウトできるメニュー」を扱っていればそこまで難しくないものの、急に「テイクアウトできるメニュー」を考案するとなると大変です。
何の許可もなしにいきなりテイクアウトで食事などの販売を行ってよいのかどうかも分かりませんし、どのようなことに注意すべきか、ほぼ手探りの状態でしょう。
この記事では、飲食店でテイクアウトを始めるには許可が必要なのか、許可を得ること以外にはどのような注意点があるのかなどについて、解説します。
目次
飲食店テイクアウトの許可は必要か?
最初に結論からお伝えしておくと、すでに飲食店を営業している場合、追加で特別な許可は必要ありません。
新規にテイクアウトの専門店としてオープンする場合は、通常の飲食店開業と同じく保健所からの営業許可と食品衛生責任者資格が必要になります。
すでに飲食店を経営している方にとって、これは大きな安心材料と言えるでしょう。
ただし、テイクアウトの商品すべてに対して許可が不要というわけではなく、許可が必要なものもいくつかあるので、これから挙げるような商品のテイクアウトを考えている場合には注意が必要です。
お酒のテイクアウトは許可が必要
店内でお酒・アルコール類を提供している場合、お酒のテイクアウトには注意が必要です。
簡単に言えば、飲食店で提供しているお酒は、簡単にテイクアウト販売することができません。
お酒を販売する場合、「酒類販売業免許」という免許が必要になります。
この酒類販売業免許は、個人の飲食店が開業の際に取得しているケースはなかなかありません。
なぜなら、取得するのがなかなか困難な免許のため、飲食店では取得しないのが通例です。
飲食店は酒類販売業免許を持っていないですが、お酒を店内飲食のメニューとして提供すること自体は問題ありません。
ポイントは、封を切っていないボトルやビンを販売することです。
封を切らずに提供すると「お酒の販売」となり、違反をすれば1年以下の懲役または「50万以下の罰金」を課せられることになります。
もちろん、どうしてもテイクアウト販売をしたい場合は、これからでもその免許を取得すれば販売できます。
今後、飲食のテイクアウトが定着していけば、持っていれば損になることはないでしょう。
「飲食店お酒テイクアウト|できる?できない?お酒の販売免許「酒類販売免許」まとめ」
テイクアウトに許可が必要な食品
お酒以外にテイクアウトで販売するために許可が必要な食品としては、主に以下のようなものが挙げられます。
・アイスクリーム(乳類販売業)
・お菓子やパン(菓子販売業)
・ハムやローストビーフ(食肉製品製造業)
・刺身(魚介類加工業)
・仕入れをしてそのまま販売する食品(食料品等販売業)
これらのテイクアウトを考えている場合は、事前に保健所に届け出を行って、該当する営業許可を取得しなければなりません。
飲食店テイクアウトで許可以外に必要なこと
飲食店でテイクアウトを始めようと思う場合、最初に意識がいくのは「許可が必要かどうか」ということですが、ほかにも必要なこと・注意しておくべきことはいくつかあります。
飲食店テイクアウトで許可以外に必要なことを、以下で説明します。
衛生管理
お店で料理を提供する場合、空調などの管理は行き届いていますし、料理はテーブルに届けたらすぐ食べてもらえます。
しかしテイクアウトで料理を提供する場合は、提供した料理がいつどのような環境で食べられるかは分からないので、お店で料理を提供する場合と比べて、食中毒などが起きるリスクが非常に高くなっています。
そのため衛生管理をしっかりすることが、お店で料理を提供するとき以上に求められます。
料理の提供方法を工夫したり、腐りやすいような食材を使わないようにしたりする配慮が重要です。
テイクアウト用の容器やカトラリー・レジ袋の準備
テイクアウトで料理を提供するにあたっては、料理を入れる容器やカトラリー・レジ袋などが必要不可欠です。
料理はあるのに提供できなくなってしまうので、常に十分な量を確保するよう心がけて、少なくなってきたなと感じたらなるべく早く補充しましょう。
収益性の把握
店内で料理を提供する場合と比べると、テイクアウトでの客単価はどうしても下がってしまいがちです。
また、新たにテイクアウトを始める場合は、容器やカトラリーなどを購入しなければならないため、その分だけ費用がかかります。
そういった点も踏まえたうえでテイクアウトでの収益性を把握して、商品の単価設定を行うようにしなければ、売れ行きはいいものの、その分が赤字になってしまうことも考えられます。
飲食店でテイクアウトを始める前に許可がいるものを把握しておこう!
飲食店が新たにテイクアウトを始める場合、そのために特別な許可を取る必要はありませんが、取り扱う商品によっては別途許可がいる場合もあります。
代表的なところではパンやローストビーフ・アイスクリームなどは、それぞれの商品に該当する営業許可を取得しなければなりませんし、お酒のテイクアウトも許可が必要です。
許可を取得すること以外にも、衛生管理に注意して料理を提供することや、収益性を把握したうえで商品の単価設定を行うことなども、テイクアウトを始めるうえでは注意しておかなければなりません。
このように飲食店でテイクアウトを始めるにあたっては、注意すべきことや意識しておくべきことがいくつもあります。そういった点をすべてクリアにしたうえで、テイクアウトを始めることを心がけましょう。
この記事の監修
株式会社USEN/canaeru 開業コンサルタント
○会社事業内容
IoTプラットフォーム事業・音楽配信事業・エネルギー事業・保険事業・店舗開業支援事業・店舗運用支援事業・店舗通販事業。
○canaeru 開業コンサルタント
銀行出身者、日本政策金融公庫出身者、不動産業界出身者、元飲食店オーナーを中心に構成された店舗開業のプロフェッショナル集団。
開業資金に関する相談、物件探し、事業計画書の作成やその他の店舗開業における課題の解決に取り組む。
■合わせて読みたい記事